宮崎県農業会議2000.1 やまめの里 秋本 治
テーマ
『住民参加のまちづくりと都市農山漁村の交流促進』
会場 新潟県高柳町
主催 財団法人 ふるさと活性化センター
日程 平成12年11月8日(水)
14:30 開会
主催者挨拶 財団法人ふるさと情報センター
専務理事 赤木 壮氏
歓迎挨拶 高柳町
町長 樋口昭一郎氏
来賓挨拶 農林水産省構造改善局地域振興課
中山間地域振興室
調査係長 佐藤 実氏
14:45 基調講演
『住民参加のまちづくりと都市農山漁村の交流促進』
講師 江戸川大学助教授 鈴木輝隆氏
16:30 事例発表
『じょんのびが都市に語りかけたいこと』
高柳町地域振興課長 春日俊雄氏
18:30 情報交換会 じょんのび村「萬歳楽」
平成12年11月9日(木)
現地視察 8:30〜11:30
〇越後富士黒姫・棚田見学
〇岡田ひょうたん会館
〇環状茅葺集落 荻の島
〇門出ふるさと組合 茅葺き、和紙
講師 江戸川大学助教授 鈴木輝隆氏
講演要旨
〇行政が普通の人に戻る時代
―住民参加から住民主体の町づくりへ―
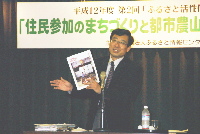 近年、農山村は荒れてきております。私は、このような中で高柳町は割合うまくいっているのではないかと思っています。高柳町には、5年以上通っておりますので、皆さんにこんな視点で高柳町を見ていただきたということを、これからお話したいと思います。それから、この夏に、全国やイギリスを2ヶ月くらい歩いておりました。私なりに感じたことをお話してみたいと思います。
近年、農山村は荒れてきております。私は、このような中で高柳町は割合うまくいっているのではないかと思っています。高柳町には、5年以上通っておりますので、皆さんにこんな視点で高柳町を見ていただきたということを、これからお話したいと思います。それから、この夏に、全国やイギリスを2ヶ月くらい歩いておりました。私なりに感じたことをお話してみたいと思います。
現在、住民参加のまちづくりというより、住民主体のまちづくりになっていると感じております。全国のまちづくりで先頭を走っていたチーム、例えば、大山町や湯布院町、小国町など、農山村でかつてトップランナーで走っていた町に行きますと、いろんな問題がでてきています。こうした中で、まちづくりで大切なことは何だろうと思ったのです。それは、真に持続性のあるまちづくりが必要だと感じたのです。持続性ということは大変に難しいということにも気がついたのです。農山村で活性化に成功したという地域でも、これを永く持続していくということが難しい時代になっているなと思っています。
よりよい地域社会を実現するのに、一般的に言えば行政の公共事業が主役のように言われてきました。しかし、地域のビジネスはグローバル経済の中で、ほとんどのモノを地域外から仕入れたり買ってきたりしているので、せっかく手に入れたお金なのに、大都市中心に地域外へ流れてしまう。ですから、地域の経済がなかなか潤わないのです。どんどん地域の経済は貧しくなっています。これをどうしたらいいかという問題があります。このことに住民は気づき始め、中心市街地も、農山村地域も、どうしたら地域の経済を良くしたり、暮らしを良くすることができるんだろうと、住民が主体となって動き出さざるを得なくなってきたのだと思います。
まちづくりは、住民からいろんなサービスが欲しいので公共施設などを作ってくれということで、住民の声を聞くということから住民参加のまちづくりとなったのです。なぜ住民の参加が必要なのかといいますと、行政は住民の声をバックにすればどんどん国からお金がもらえるので、これも作ってもらおう、あれも作ってもらおうという形で要求を先に聞いておこうとしたのです。住民の盛りだくさんの要望を活かして、地域の身の丈を超えたオーバー・オーダー(過剰な要求)とかオーバー・スペック(高すぎる仕様)の施設を実現してきたのです。例えば、今の時代ですから、使うかどうかは別にしても全自動のハイテクの映像設備や音響装置をつけてもらったり、それからどの部屋にも空調をつけようとか立派な施設を作ってきたのです。どんどん事業は大きく贅沢になるというような時代が続いています。
自分たちが自分のお金で作るならば、決してそんな豪華なものは作らないというような贅沢なものが出来上がってしまいました。地域の人にとっては悲鳴が出そうな難しい近代的な設備類は上手く使いこなせないことが多いのです。ですから、住民の人が本当に使いたいものや、自分たちが本当に必要なもの以上に要求が大きくなっている事実を何とかしていかねばならない。
行政にとっても、住民の声を入れた結果、こうなったという話になりますので誰も文句は言えないのです。優秀な行政の職員は、国や県から大きなお金を取ってくるから優秀だと思ってしまう。本当は、自分の金だったら、そこまではやらないよ、ということを本音で言わなきゃいけないのです。素晴らしい自然の中に作るなら、空調は使わなくて、外の風をいれるようなものでいいじゃないかっていうようなことが、言えるような時代ではなかったと思うのです。まだ、もらえるものはもらえということが続いています。
これまでは一生懸命、行政の方もがんばって無理をしてきてしまったのです。よく考えてみると、どうもすべてがオーバーになっていたのじゃないかなというような反省があるのです。ですから、行政はいろんな施設を作ってきたことが原因で、赤字になったり、施設経営に非常に困っている。先進的といわれた町に行ってみても、こうしたことが続いて行われていて、かつての状況と違ってきています。
これからは、行政の人が普通の人になっていかないと、どうにもならないし、ますます駄目になっていくということなのです。これからの時代は、企画した人の自己責任という意味でも、住民参加というより住民主体だと思います。住んでいる人や言った人が責任とらなければいけないのです。行政は金を使わない町、あるいは上手に行政の金を使ってもらいたいまちづくりっていう手法をとらないと、地域社会は良くならないと思います。今までのように行政の金をどこまでも当てにするのではなくて、住民主体で責任ある事業をしていくという視点が必要なのです。
〇地域の中で通用するお金
―種子島の事例―
種子島は人口約3万6000くらいが住んでいる島です。その島に、10年位前から、国土庁の地方振興アドバイザーなどで伺っています。地域の中心市街地の商店街の問題や、農産物や加工品もなかなか新しい注目を浴びるような商品が生まれてこない、若者が島を出ていって帰ってこないなどの問題があります。種子島といいますとさつまいも(地元ではカライモといいます)なのですが(日本で一番はじめに伝わってきた伝統的な農産物で、種子島ゴールドなどの新品種も生まれている)、収穫したさつまいもの50パーセントくらいは商品として市場に出せない。それから、パッションフルーツやモンキーバナナなどの農産物もあるのですが数が揃わない。漁業もナガラメなどの特産品が捕れなくなって市場に出せるほどの量がない。イセエビやアサヒガニが捕れても数が揃わない。市場に出すには、形や量が揃わないなどの問題があってうまくいかない。その出荷できない産物を活かそうと思い始めたのです。
行政にも住民にも情熱があって、面白い人が結構います。なかでも異業種交流の会、「いちごの会」(一期一会)という元気の良い会があります。変人が多いのです。歯医者、行政書士、種子島の鉄砲鍛冶からはじまった鍛冶屋さんで包丁を作っている人、日本で一番フリージアの球根を作っている人、民宿を始めた人、焼酎を作っている人とか、いろんな人が集まっては島の活性化を考えています。ホームページで種子島を見てもらいますとわかりますが、その人たちが商工会で数年前から新しい事業として取り組んでいます。IT革命っていうのは地方にとって有利な社会なのです。どんな地方にいてもインターネットを活かして自分の情報を自分で作れ、しかもそのまま直ぐに情報発信できる。そして、全国何処からでもアクセスできるし、さまざまな情報も居ながらにして得られるのです。
でも、島に暮らしている3人に1人が高齢者ということでなかなかそうした新しい技術を使いこなすことができない。そこでは、「インターネットはどうやったらいいんだ、ホームページはどうやって作ったらいいんだ」と、自分達の町のいいところを宣伝したいという思いがあっても、なかなか実現しないのです。そして、美しい海岸にゴミが散らかり汚れていても、それを片付ける人や拾う人がいないなど、地域はいろんな問題が重なって疲弊していくのです。また一方では、日本製のロケットの方がなかなか成功しないということもあり、元気が出ないのです。
先週、そうした状況の中で、種子島の人たちと話をしていたら、地域のお金を考えてみようということになったのです。エコロジーだ、コミュニティだ、地域の産業起こしだ、こういった話の中で、地域の中でしか通用しないお金を作ろうという話がでて、そのメンバーが興奮状態で議論したのです。
その時に一緒に行った学生も加わって、例えば、海岸に行ってボランティアとしてゴミを拾ってくる。こうしたボランティア活動を1時間すれば、1種子島もらえるとかですね。地域の中でしか通用しないお金「種子島」を作ったらどうかということになりました。そのお金で、市場には出せないサツマイモが買える、新鮮な魚が買える、病院に行きたい年寄りを車に乗せていく、魚の料理方法を教えるとか、自分が出来ること、自分がして欲しいことを公開しよう。地域社会を支える地域マネーを考えようという話になったのです。
地域の中には自分たちが助け合っていく仕組みが昔はあったのです。これを地域の中でしか使えないようなお金「地域マネー」でやっていこうと、現在、全国で30くらいの地域でしています。これはもともとアメリカで、1929年に起こった世界大恐慌の中で、疲弊した地域や経済を復興しようとして地域通貨ブームが起こったことがありました。当時は、分権的意志決定を前提としていたこうした取り組みは終焉させられましたが、地域ごとに、自分たちが働いて自分たちが食べていくために、地域だけで通用するお金を発行したわけです。
1997年には、タイのバーツが切り下げになって国の経済が駄目になりました。この反省もあり、カナダ政府の資金援助により、現在、地域通貨の実験が始まっています。カナダは、現在、世界的に巻き起こっている地域通貨ブームのきっかけを作った国です。そして、この地域通貨は国の通貨との交換さえ可能なシステムになっています。
世界の経済が変わると地域の生活を無視して、経済が勝手に動いていってしまう。そして地域を駄目にしてしまう場合さえ出てきます。地域がなければ国も地球もないわけですから、世界各国で2000以上の地域において、世界の経済とは別に自分たちが地域の助け合う仕組みとしての経済を生み出しています。
地域の中で必要なサービスを提供しあっていくシステムを作っているところは、日本では、滋賀県草津市の「おうみマネー」や北海道栗山町の「クリンマネー」など30以上の地域で実験が始まっています。福祉であるとか、まちづくりであるとか、それから環境活動などもありますし、雪かきをしてほしいとか、年寄りのところへ行って面倒を見るなど、そうした地域のサービスを地域マネーを媒介させて、お互いに支え合っていこうとしているのです。
自分は何が出来ますか?栗山町の例ですが、人口15000人の町で553人が参加しています。自分がして欲しい・して上げられるサービスが5479メニューにもなったのです。こういうことしたい、こういうことできます、こういうことしてほしい、こうした地域の情報を公開していくことによって、今まで捨てていたものが蘇り、海岸に捨ててあったゴミを拾ってくることによって、自分たちが必要としている他からのサービスが受けられるのです。こうしたことを種子島でもやっていこうという話になりました。
ホームページは地域の民宿の人や農家の人が作れるようにしようということになりましたが、やってみると簡単には作れない、お金もかかる。そしてサーバーも必要になってくる。サーバーがなければプロバイダーに契約しなきゃいけない。プロバイダーに契約すると1月で1500円くらいだけど10ページくらいしかつくれない。それで、サーバーをもってみんなで立ち上げて、みんなで注文とったり、お客さんにも情報を発信することができるようにしようと考えました。みな自分が出せるものから出そうということで、ホームページを立ち上げたい人は海岸に行って5時間ゴミ拾いをする、海に行って魚を捕る、畑のさつまいもやバナナを持ってくる。それを地域のお金としてホームページの作成費に充てるのです。
実際、珊瑚礁という民宿がホームページを作りたいが自分ではできないし、ビジネスとして頼むほどのお金はないので何とかしたいという話がでました。そこで、私の知り合いに、大阪大学の情報センターで優れた技術を持っていて、旅が好きな人がいるので、携帯電話を使って、その場でお願いしました。(後日談、みなでできることをしようという話で、島を案内するやら、食べ物はみなが畑や海などで集めて持ってきてその場で料理して、あるものでもてなしました。ホームページはすぐに実現しました。下記は「珊瑚礁」のホームページのアドレスです。まだまだ、試作品ですが、とりあえず、ご覧になってください。ただ、1枚しか出来ていません。http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/2947/)
いずれは、みなができるサービスと自分たちがして欲しい活動を交換しようということ自体も、ホームページに載せようということになりました。前から実現できなかった商工会のインターネットをこの際だから、立ち上げて、みなでホームページを作ろうという話にまで発展しました。自分の考えているものがヒットし、アクセスする人が増えたらいい。そうすると行政でもいいホームページ作ってもらわないといけないということになり、商工会の会長さんも商工会もホームページを作ろうよっていうような動きになったのです。お金があまりかからず直ぐに自分たち自身でできることから始めたからです。行政のお金だけに頼ってはいません。
このように、いろいろして欲しいことをお金を使わないでやろうと考えているのです。それは行政のお金というよりは、むしろ自分たちができることを地域の中でしてこそ、ホームページが立ち上がるという仕組みさえできるじゃないかということを住民の人たちと話し始めています。
こうした動きは日本だけではなくていろんな国でも起きています。例えばフランスです。フランスの制度は地域の経済、日本と同じように農村部が経済的に苦しいのです。現在、フランスでは地域通貨が発行される際に、政府がコストの20%を負担しています。イギリスのドレア首相も地域の経済を良くしていくことと世界の経済とはまた別と、助け合っていく地域マネーを考えているようです。オックスフォード方式というのもあるのだそうです。
ニュージーランド、オーストラリアでも政府機関が積極的に支援しています。世界中が取り組み始めている。地域を良くしていかないと駄目なのです。地域が振興してこそ国があり、地球があるのです。こうしたことから、島の環境を良くしていき島が持続する仕組みづくりを島の中の動きを通してお話ししたかったのです。
〇じょんのび循環経済学
―10億円も地域で3回廻せば30億円になる―
実は、今年から高柳町のじょんのび経済学をやろうということになりました。先程お話があったと思うのですが、高柳町では28万人の人が訪れて約10億円の観光の消費額があります。外貨が10億円獲得できる。ところがこれすべてを地域外から買ってきたものを売っていたとすると、10億円のお金がそのまま外へ流れ出してします。このお金をもう1回、地域の中で廻していけば20億円になります。地域の中の経済を良くするために、みんなが幸せになるために、じょんのび循環経済学をやろうということになったのです。
町の人から相談があるたびに、問題を一緒に考えているのですが、この地域で作っている農産物の販売する朝市があります。みなさんが泊まられると、翌朝には朝市があるかと思います。その野菜などを買って、みなさんの食事に出しますと、農家の人達にお金が、10億円の何分の一かは地域の中でお金が廻ります。10億円を地域で3回まわせば30億円になるから、これをみなで考えようと言うことになりました。
そのための調査を丸投げ委託はするようなことはしないと決めたのです。ただ報告書を作ってもらってもしょうがないじゃないかと、住民自らが、じょんのび研究センターという場を使って考え始めています。もっとじょんのびな町を作るために、自分たち自らがじょんのび力をつけるために、住民主体で意識改革しながら、まちを作っていこうという人たちが、今日もこの会場にも参加しています。
どのような話がされているかと言いますと、じょんのびの根っこを深くしようとか、自分が変わらないと地域のお金は動いていかないということです。報告書がいくら立派にできてもじょんのび循環経済学は成り立たない。ですから商工会の人にも入ってもらおう。農家の人にも入ってもらおう。一人ひとりがそうした気持ちになって、地域の経済を動かしていくようしていこう、住民主体でやっていこうということで少しずつ動いています。
じょんのび研究センターの理事長は町長さんではなく、これから、ゆっくり町民自身が考えていこうと理事長は今不在です。行政はリーダーシップを発揮するより、むしろプロデューサーとなってその地域の人たちの中から、一生懸命にするやる気のある人をひっぱり出し、新しい職業さえを作っていこう。一人ひとりの意識改革ができるような仕組みにしていこうということを話し合っています。
〇地域の人たちが活躍できる場面を作る
―地域の人たちが作った日本一のポスター―
このポスターですが、(じょんのびのポスターを指して)日本観光ポスターコンクールで銀賞を受賞した作品なのです。この写真は、高柳町荻ノ島の暮らしに感動した米山孝志さんというアマチュアカメラマンが、生活の内側に入り、長年かかってこの写真を撮った中の1枚です。プロではないから売るために撮ったものではないのです。ですから使用に当たって版権はいらないというのです。「じょんのび」という意味は、芯からのびやかで心身ともに心地良い、気持ち良いの最大級を表すこの地方の方言なのです。このポスターは、このことを実にうまく表現していると思いませんか。
わたしも大学で学生から教わったのですが、今時の学生はいわゆる超高級ホテルや旅館など豪華な建物を喜ばないのです。むしろ、素朴な茅葺の家に泊まりたいなど地域の個性を求めています。住民の生活文化や住民自らが作っている風景こそ本物であるということを、学生たち、若い人達や都会の人達は感じていて、観光客用に作られたものでないものを求めているのです。
観光地に行くと正面に大きな駐車場があり、大きなおみやげ品の売店があります。いかにも観光地らしい表情があるわけですが、こうしたものを求めてはいないのです。新たに作るのではなく、既にそこにあるものを活かす時代なのです。既にあるものやそこにしかない生活の風景を活かす。生活文化、普通の生活そのものに人々の心を惹かれるのです。
高柳町のパンフレットが皆さんの資料の中に入っているかと思いますが、このパンフレットの写真やコピーは地元のアマチュア写真家の人たちが作っているのだそうです。地元には必ず写真の愛好家がいる。地元に写真好きな人がいるのです。こうした人たちに集まってもらってパンフレットを作るのです。
印刷会社や広告会社に頼むと、プロの写真家が来てその日だけ来て、急いで撮って帰ってしまうわけです。それに比べるとこのパンフレットは、ここに住んでいる地域の人たちや地域住民といつも交流をしているアマチュア写真家の人たちが撮っている写真ですから、住民の顔が非常に生き生きしているし、自然流の生活を撮っているのです。
以外と、こうした地域の人をうまく使ったパンフレットの作り方をしていないのです。すべてプロにまかしてしまう。プロはコストが高いですから、毎日写真を撮りに来ることができない。地域のアマチュア写真家はその点、ごく自然に風景も人物も撮れる。そして、パンフレットは地元アマチュア写真家の発表の場でもあるわけです。多くの人に見られることによって、もっと腕をあげていこうということになり、もっとセンスのいいパンフレットを作っていこうということにつながっていきます。
コピーライターは受ける言葉を考えますが、地元の人たちは自分たちが普通の言葉で語ろうとしますから、これもそこにあるものを活かしていくということのひとつです。地域の人たちが活躍できる場面を作ることが活かすことなのです。それは、前に話しましたリーダーとプロデューサーとの違いということなのです。
地域の人をおだてて、舞台に載せて活躍していただくということがあるわけです。今、このパンフレットを持ってきて下さった大橋勝彦さんは、「じょんのび便り」という地域の情報誌の編集長をしています。彼は、もとはこの町の住民ではないのですが、以前、農文協に勤めておられ、本の編集に携わっておられたそうです。今では貴重なここ高柳の住民です。
住民を対象にした「源シリーズ」で、詩人で哲学者の宗左近さんに「じょんのびと縄文を考える」と題して来ていただいた時です、宗さんの話に感動した大橋さんは本を紹介して欲しいと言ったのです。その時、宗さんは手元に持っていた本を「あなたにあげます」とサインもして下さったのです。それをみていた役場の人が、大橋さんに「まちの雑誌の編集長をしてくれませんか」ということになり、「じょんのび便り」を編集することになったのです。宗左近さんの文章はもう3回も、ただで書いていただいております。大橋さんも凄いですが、役場の人も凄い、宗さんも凄いのです。本の内容はレベルが高いのですが、こうした理由でお金はかかっていないのです。
地元の方を上手に活用して生きがいを作る。役割を作る。今度も載せたいからと宗左近さんと綿密な連絡をして、門をたたく。そうした中から地域づくりや日本人の精神、人間が生きるということ、人間の成長ということを住民自らが学んでいるのです。そうしたことが、今後のじょんのび高柳の中に生きてくると思うのです。
また、その情報誌には、住民の一人ひとりの声が描かれております。小林勝美さん、町の施設で働いていた人ですが、現在、70歳を過ぎても、毎日のように4時間かけて山菜を煮込んだ佃煮パックを100円でじょんのびの施設で売っています。その地域の中にあるもの、暮らす人をしっかりと取材しています。普通の住民の声をとりあげて描いている本なのです。小林さんは、家で遊んでいるより体の運動にはこれがいいんだと、体の運動が目的ということで汗をかきつつ、なべをかき回しながら、じっくり何時間も山菜の煮込み続けています。こうした高齢者の活躍が、今いわれているコミュニティビジネスだと思います。
地域の中で新しい創業というか、70歳を過ぎたおじいちゃんが地域の中の産業を支えたり、こうした丁寧な暮らし方が地域の魅力になっています。それを地域の情報誌で取り上げる。新たに作るということではなくて既にあるものを、上手に活かしていくということが、実は、これまで地域の中であまり行われてこなかったと思うのです。
〇既にそこにあるものを活かす時代
―農地を歩くイギリスの事例―
10月1日から8日間、イギリスへ行ってきました。農山村部、いわゆる条件不利地域において、地域にあるものをそのまま活かして地域振興ができるということを聞いたのです。ほとんど作らないで、あるものを活かして地域振興ができるとは、これは最高ではないかと思いまして体験してきました。何にも作らなくて、その風景を利用しただけで地域振興になっていました。日本でいうようなにぎやかな活性化ではありません。
実際、行ってみますと、本物の農村や農地があり、ただその中を歩くということなのです。イギリス人というのは、歩くことが好きな国民だそうです。そして、イギリスは国土の80%が農地なのです。農村を歩くということが観光になり、交流になっているのです。
駐車場もトイレも新たに作ったものはないのです。歩道さえも作ってはいません。牧場の中を、畠の真ん中を、ここが道だという道はありません。普通の道は車が通りますが、人間が通る道は新たに作るのではなくて、道はこちらですと矢印で示した15cmくらいの小さなステッカーだけが牧場の柱に貼ってあるだけです。道に沿っていくと、牧場があり、その牧場の柵を乗り越えるために小さな木で作った台があるだけです。あるいは、牛や羊が出ていかないように一人だけが通ることのできるゲートが設置されているだけなのです。柵をくぐるか、乗り越えて行き、そして、道のない牧場の真中を歩いている自分が気持ちよいのです。
駐車場や売店はないので、人は何処から歩くかと言えば、町の中の駐車場に車を置いて歩き出す。町の中心から農場まで歩いて行くか、タクシーを利用するかです。タクシーを利用する人は20%いるのです。そうすると、牧場に駐車場を作らなくてよいから、環境を大きく変えなくて良いわけです。我々も大きな駐車場がある農村を好んではいないのです。道にしても、コンクリートとかでしっかりと舗装されていない道や牧場や農地の方が気持ちがいいのです。
トイレも作っていません。その代わり、昔から営業している地域のパブやレストランなどの店があって、そこで、コーヒーを飲んだり、紅茶を飲んだり、ビールを飲んだりして、その店のトイレを借りるのです。昔からある地域の生活圏の活性化につながるのです。町の中に車を停めているから、町の中の店ににも買い物に行きます。
キャベツ畑などの真中を歩いて行くその気持ち良さは実際歩いてみないと分からないと思います。新たなものはほとんど作っていないのです。農場の柵のそのままに、一人ずつ出入り出来るようになっているだけです。そして、看板を新たに設置するのではなく、方向を示すステッカー1枚だけです。道も舗装されていませんから、靴がグチャグチャに汚れるところもあるわけです。タクシーには迷惑だろうと思いましたが、運転手はビニール袋を用意していて、その袋の中に靴ごと履いて乗ればいいのです。
舗装がしてないのでグチャグチャであったり、牛のフンもありますが、人間が気をつけて歩けばいいのです。歩道の維持管理費はいらない。人間が歩くために作った人工の道より普通に歩いた方が気持ちいいのでこれでいいのです。あるものをそのまま活かしているわけです。みんなあるものを生かしているから、そんなに大きなお金もかけることはないし、維持管理費も少ない。なおかつ地域の経済にも貢献し、歩いている人もこの方が気持ちがいいのです。
でも、日本の中ではこうはいかないのです。観光客の方から注文やクレームが出るからです。こんなグチャグチャな所を歩かせるのか。確かに靴は汚れます。農村や農地の中を歩けば、汚れて当たり前なのです。造っていない自然の中を歩くから、我々は気持ちよく実は歩けるということを発見するわけです。
ですから、我々は何をするにも、少々贅沢に作り過ぎているではないか。もっとあるものを活かしていくということが実は重要じゃないかなと思ったのです。こうした例のように、イギリスの作り過ぎない手法からは学ぶことがたくさんあります。
〇地域の魅力は多様な文化の融合
―少しは都会の匂いがする自前の文化を育てる―
次に需要の拡大ということなのですが、今までは都市や農村は、その土地の文化というものを1つだけ、それしかないよって言っていたわけです。実は、文化というのは、その地域にいろんな文化があってもいいんのではないかというお話をしたいと思います。
例ですが、かつて出稼ぎや集団就職したりして、東京圏に暮らしているこの町の出身者が集まって、「東京の高柳会」を作っています。年に何回か、原宿にある新潟県の迎賓館「ネスパス」でその人たちとの交流会が開かれます。種子島で、お会いした人たちに聞いた話です。種子島でも島出身者に集まってもらって地域の活性化を求めて、コンタクトとったりしています。どこの町でもしていることです。
面白い話を聞いたのです。その町の出身で東京や大阪、名古屋に住んだりしている人たちの意見を聞くと、故郷は変わって欲しくないと言うのです。昔のままであって欲しいとか。しかし、現実は違うのです。
種子島の中心市街地の商店街が駄目になっているからなんとかしたい。中心商店街を活性化させる為には、中心に人が多く住んでいなければ活性化はできない。どんどん人が街の中心から人は減っているのです。そこで、都市に出ていった人たちに帰って住んでもらおうよということで、「種子島に帰って来たいですか?」と聞きました。就職先があるかななどの要望がありました。それでも帰ってきたいという人は、25%くらいいました。
そうした人たちに、「条件が整えば帰って来ますか、何処へ帰って来たいですか?」と聞いたのです。そうしたら、昔の農村に帰って来たいじゃなくて、町の中心にマンション作ってくれって言うのです。そう言いながらも、すべてが都会になってしまったのでは嫌だと言うのです。ちょっとでもいいから、少しは都会の匂いが欲しいと話すのです。少しおしゃれなカフェで、おいしいコーヒーを飲んでみたい、ケーキも食べたいと言うのです。
高柳町にパン屋さんが出来て2年になるのですが、バクバクといい、麦麦と書くのですが、美味しいパン屋さんができました。毎日買いに来る人もいて、予約をしている地元の人も多いのです。作っているのは乗岡さんで、大阪の人から高柳にあこがれて来た人です。町の施設で働いていた人なのです。もともとパン屋さんではないのですが、町にさまざまな新価値を作ろうとする空気の中で、朝早くから長岡まで通って学んで来て、今では地域の穀物も入れた天然酵母のパンを作っています。若い人だけでなくて、田舎にいてもおいしいパンは食べたい人がいることで繁盛しているのです。こうした都会の空気も少しは欲しいという人は普通にいるのです。いろいろな地元の文化の中に、都市の多様な文化や文明を田舎にも入れて行くことが求められている時代なのです。
都会から田舎に住みませんかという本も出ておりますが、田舎暮らしで失敗する人はどのような人かと言いますと、高柳でも、全国的にみても同じなのですが、都会の価値観しか認めない人、そうした価値観の人は移住に失敗しています。
町すべてが田舎では嫌だと田舎の人も考えている。都会の人も、実は嫌なのです。ですから、多様な文化を地域の中で認めていくことが求められるのです。都会の文化や香りが少しは欲しいのです。地元の文化と新たな都会の文化が上手に向き合っていく時代だと思います。
イギリスの田舎に行ったときにも、美味しいコーヒーが飲めたり、おしゃれなレストランもあります。それでいて田舎だぞという雰囲気はあります。じょんのびの茅葺屋根だけが田舎の文化ではない。そこには美味しい豆腐もあり、美味しいパン屋さんもあり、美味しい魚屋さんもある。そして、今も、おいしいイタリア料理、地の野菜や山菜を使ったパスタ料理やピザなどもできればいいなと、そんな話をしているのです。少しは都会の匂いがする自前の文化を育てていく時代なのです。
〇個性を引き立たせる交流を
―違った文化でかき混ぜて、新しい文化を造り出す―
山梨県須玉町に「おいしい学校」という町で作った施設があります。地元の人と公募で集まってきた全国の人が一緒になって運営している施設です。今年の5月にできました。3ヶ月間で10675人が利用しています。地元の小学校が廃校になって、明治、大正、昭和の校舎が同じ敷地にある珍しい処で、全国に一つだけでした。どんどんぼろぼろになってくるので、これを活かして地域の活性化を図ろうと、「おいしい学校」を作ったのです。そこでピザを、パスタ料理を食べさせようということになり、東京代官山の「カノビアーノ」の植村隆政シェフに来ていただいて指導してもらっています。この町の気候は北イタリアとよく似ているのです。地元の新鮮な食材を使って、パスタの料理を地元の食材を使って「ほのボーノ」というレストランを経営しています。
パン工房も、地元で無農薬・有機農法で栽培している小麦粉を使い、四季の地元の食材を入れたパンを焼いています。監修は筑波第一ホテルの山下雅一さんに指導してもらっています。地元の農家の主婦たちが作る「新武田御膳」は、料理研究家の小林カツ代さんが監修しています。
この例は、地域の個性を引き立てるとか、個性を際立たせる交流です。それはどういうことかといいますと、交流する事によって、お話ししましたような駐車場を作れ、トイレを作れ、というような個性を壊す交流ではなくて、自分たちの個性を引き立たせる為にどのような交流をするかということなのです。地元の素材を引き立たせる交流をどうするかということ、地元の個性をもっと引き立たせる為に交流を積極的にしていくことが必要なのです。
高柳町もいろんな形で自分たちの個性を引き立たせる為に交流をしています。これまで各地を歩きますと、都市住民と交流をすると媚びてしまって、相手の懐のお金が欲しい故に、先程の駐車場を作れといったら駐車場を作ってしまう。何々を作れと言ったら、お客様は神様ですと言って作ってしまう。そういったことをしていくと地域の個性がなくなってしまう。個性を引き立たせる交流のめざしていかないと駄目なのです。
それは、外からの英知を積極的に吸収するということが一番大事なことです。交流の仕方が上手になりますと、春日俊雄課長さんがお話して下さるか分かりませんが、いろいろなカルチャーショックを受けながらも、自分は屈しないで、決して媚びず挫けず、いい影響を受けて育ってきたことで、今の高柳町を作り上げてきたのです。この町の人は上手に交流することの大切さを、身を以て体験し、体で覚えてきたと思います。
山梨県早川町にあります日本上流文化圏研究所での話ですが、住民に個性があるといっても同じ文化の中ですから、住民だけでは議論が進まないことがあります。先程の地域マネーの話もそうなんですけれど、自分で自分をかき混ぜるということは難しいのです。外の人に少しかき混ぜてもらわないと、違った文化によってかき混ぜてもらわないとできないこともあるのです。それを上手に使って、自分たちの文化を掘り下げていくことを発見することがあります。交流上手な人たちは自分たちの力をつけていきたい、いい話を聞きたいといつも思っているわけです。そうした心構えで交流をしませんと地域の個性も育ちません。今までは、都会の価値観そのものを押しつけられたり、自分の価値観を相手に押し付けるという一方的なやり方が多かったように思います。
このポスターのデザインしている人は高知県の梅原真さんです。高知の海の文化の人に、山の文化の個性を引き立たせてもらおうとする交流の一つなのです。海の人は、もっと山の文化がこうあったらいいなぁ、こんな所は素敵だなぁという所を見つけたりする。逆に、海の人は、山の人に見てもらうといいのです。そうした中でそれぞれ自分をかき混ぜていく。かき混ぜていく中から新しい文化を作りだしていくことです。はじめは、この写真を見て、地元の人は貧しいから嫌だなと思ったのです。
〇若者の3分の1は東京圏に暮らす
―癖が個性、地域社会は個性を失った―
皆さん方の手元に、世代別東京首都圏集中率という資料がお渡ししてあるかと思います。どう見るかといいますと、例えば、1946年(昭和21年)から1950年(昭和25年)は戦後のベビーブームで、1年に220万人が生まれています。現在ではどうかというと、1年間120万人から100万人しか生まれませんので、5年間に600万人くらい生まれたということなのです。
一番上の欄、1916年(大正5年)から1920年(大正9年)最初の5年間に東京圏で生まれた人は13.1%です。東京圏とは東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県で、生まれた人が13.1%ということです。ベビーブームの時は、東京圏で生まれた人は15.1パーセントです。それから一番下の欄を見ていただくと24.9%になっている。全国の子ども、今は東京圏で生まれる人が4分の1になっているのです。実に、4人に1人は東京圏で生まれている。ですから、私の大学で学生に東京圏生まれの人って言ったら7割くらいいます。そして、その後、10代後半から20代前半になると、まだ全国から集まってきて、若者は3人に1人は東京圏に住んでいるのです。日本はここまで極端に大都市に人口を集中させてしまったのです。学生に田舎の話をしても分からないのは無理ないのです。
学生をじょんのびへ連れてきます、アメリカの学生も来て研修していますが、茅葺の家にびっくりするのです。それだけではなくて、農村部に来ただけでびっくりします。というのは、自分の故郷は、親がいるところ、生まれたところですから、4人に1人は東京圏で生まれているので、故郷さえ東京なわけです。なおかつ、その後10パーセント以上の人が上ってきたりして3人に1人が東京圏という非常に異常な形をなっているのです。ところがです。法政大学の2部ですが4年生で就職が決まっていない人が半分以上いるのです。自分で就職を決めない。今はフリーターが流行っていますけれど、行きたいところが分からない。就職しても3年以内に会社を辞める人が32%もいる。
その学生たちを静岡のサトウキビ刈りとか、種子島などに連れて行きました。アルバイトやって夜も昼も働いて、ボランティアにいくのです。学生たちは実は感動を求めているのです。今は若い人たちは東京意外の所を知らない。で、地域に出かけるきっかけが欲しいと思っているのです。種子島へ行って、今、ジャガイモを植え付けて、3月に収穫するのです。学生たちはびっくりしてそれを手伝ったのです。パッションフルーツ、マンゴー、バナナもあるです。モンキーバナナは少し酸味があって美味しいです。それらは、お土産としては売っていないのですね。自分達が楽しんで食べている。それを学生が手伝いたい、それを食べたい。今度10日間ボランティアで行きたいっていうのです。
京都市は人口が140万人、うち14万人が学生なのです。大学は54校あるのです。学生たちに人気があるのは、インターンシップ制度なのです。学生がいろいろ地域に行って体験したいって言うのです。3つのコースがあり行政コース、企業コース、そしてNPOコースというのがあるのです。
1番人気があるのがNPOなのです。人の役に立ちたい。阪神大震災の時も自分の親をほっといても、人を助けに行ったりすることがうれしいと話すのです。人に感謝されたい、そうした感動を求めに行くのです。社会のことを知らないからそうした所に体験しに行きたいと思っているのです。社会に出ても自分のしたい仕事と違うから、3人に1人が失望して3年以内に辞めてしまうというようなことがでている。
昔は、学生たちは田舎や農村と交流していたのです。お盆になったら帰る。正月になったら自分の親のところに帰るということがあった。今は、親が都会にいるわけですね。ですから、田舎のことも知らない、交流もしていない。ですから、いろんな所へ行っても世の中のことを知りたい。そこには感動があるが、企業社会へ入っても楽しみや生きがいを見出せないと言うのです。
学生を農村に連れて行く。一つのイベントや交流学習ということなのですが、そうすると、その土地の人の癖とか地域の癖とかが見えるのです。その癖が実は個性だったのです。癖を上手く繋いでいけば実はもっと個性豊かなるのですが、地域社会がいつの間にか、その癖をみんななくしてしまって、みんな同じことをやろうとしたのです。学生はその地域社会の癖を見て、面白そうだというのです。自分の個性は伸ばしてたいというのに、地域社会の個性は大事にしなかったのです。
〇風景は地域のメディア・イベントは地域の学習装置
―手作りではじめた「狐の夜祭り」―
地域社会の個性を見つけるためにイベントをするのです。高柳では、狐の夜祭というのを11年前から始めました。夕方、狐の格好をして、畳1畳敷きのあぶらげを揚げたりします。狐のお面をつけ、白い装束を着て、狐の踊りや音楽もあるのです。地元の人たち自身で工夫したイベントです。「ゆめおいびと」という人たちがしているのです。和紙職人の小林康生さんの漉いている和紙を利用して、型絵染めの村田仙三さんが作った洒落たデザインのちょうちんを持って、その中にロウソクを灯して山から下りていくのです。
夕焼けの時に、山から峠を越えて降りて行くのです。みんながちょうちんを持って、お爺さんやお孫さんが手をつなぎ、地域の人やよそから来た人たちが300人以上の人が歩いていくのです。下から見れば、山の上から下のほうまで明かりが続いて見えるのです。それだけで感動しちゃうのですね。何ともいえず、懐かしく自分の住んでいる集落の灯りが風景として現われるのです。
風景というのは地域のメディアとして大切なのです。車社会になって暮らしている地域を村人が歩かなくなってしまった。そこで、こうしたかたちで地域の良さを見せる。そんなイベントやっているのです。
イベントは一つの学習装置なのです。地域の風景を見直させるという学習装置です。そして、その村の風景を美しくしていくという為に、風景の作り方を自分たちで学習する。町が汚ければ感動しないのです。ですから、イベントはただ客を呼ぶだけじゃなくて、自分たちが勉強したい、あるいは、それに参加する人にこうしたことを学習させたいというのをやっているです。このように地域の癖(風景)を学習していったり、地域の中のいろいな人の癖を繋いでいく。まあ、人間の生態としての癖をもっと活用していくということが必要だと思います。
〇懐かしさと珍しさが求められる時代
―結論が先にある公共事業―
まちづくりで、町を良くすること考えようと人を集めたりしてもなかなか人は集まってこないのです。ところが、種子島で料理を勉強しようと企画したら、300人も集まってきました。総論では駄目なのです。各論が大切なのです。各論からやっていかなきゃいけないのです。どんなテーマだったら出席したいですか?ってことから始めることです。
ある団体が寄付を集める。寄付してくださいっていったら寄付が集まらないのです。どんな条件であれば寄付をしますか?っていう聞き方もあるわけです。先程、言いましたように自分がして欲しいこと、自分がしたいことというのは、住民にとって興味があるのです。こうした智恵が実はものすごく大切なのです。
今までの、いろいろなところでしていた地域づくりは、コンサルタントなどに計画を作ってもらってプロジェクトを進めていたことが多いのです。どうしても国の予算の関係で、期限がありますから半年の間に作ってくれ、今年度中に作ってくれということになります。効率をよく進めるためにコンサルタントはこういう風に作りませんか、と最初に完成案を出すわけです。
皆さんが、何が欲しいと言えば、じゃあこういう風に作ったらいいでしょうと提案してくれます。それからアンケートをとってどういうものを作りますかって進めていくのです。結論が先にあるわけなのです。本当は皆が何をしたいかというところから入っていけばいいんですが、結論から先に作っていくものですから、作ることが目的化しているために無理が出てくるのです。
できるもののイメージが最初だから、効率的には推進しやすいわけです。結論に理由をつけて、利用者はこれだけだ、これだけ儲かるっていう風に作ってしまう。本当は、地域の中でいろいろ各論をやって、どういった条件でどのようなことがしたいのかということから始めていくような、余裕をもって、地域の中で日ごろから話し合っていかないといけないのです。結論から作ることは非常に無理があるのです。
今はどのようなものを求めている時代かと言いますと、「懐かしさと珍しさ」を求めている時代だと思います。先程言いましたように個性を際立たせるということは、自分は自分であるということに他ならないのです。珍しさと懐かしさというのは、例えば、若者は茅葺のことを珍しいと言い、年寄りはこれを懐かしいと言います。歴史的のなかで地域が持ち続けてきた地域遺伝子や地域の持ってきたものは懐かしさです。それから新しいもの、変わったものが珍しいもの。地域はこの2つの側面から見ていかなくてはいけないのです。
個性を引き立たせるためには懐かしさだけでなく、まったく新しいものばかりでも駄目。ノスタルジー、古いものに浸っているだけでは駄目で、その中に新しいデザインを入れていろんな形で展開していくことが必要なのです。このポスターを作る時にも、実は、デザインで新しさをいれています。こうしたことによって新たな命や魂を入れているのです。
〇オタクが21世紀の文化を創る
―オタク文化・珍しい局面から町を編集する―
もう1つは町を編集していくという事です。いろんな形で珍しい局面からその町を編集していくことも必要なのです。パンフレットなどを作りますと1回作ったら、おしまいです。この「じょんのび便り」は、一歩の家にはおばあちゃんもいる、というような形で編集しているわけです。地域に本当にいる子どもの名前です。子供からも編集しているのです。人の顔からも、農産物からも編集は出来るのです。
これは、この町の勉強会に来られた雑誌の編集の人が言ったのです。ゴッホ、セザンヌなどを美術手帳で特集するとします。ゴッホを特集するときに、3年前もゴッホの特集をしたが、また特集をしなくてはいけない。そうしますと、ゴッホの周辺の人々、ゴッホの青春時代、ゴッホとセザンヌとか、いろいろな切り口から編集していくことによって、読者に新たな興味を持たせることができる。同じように絶えず違った局面で、町を編集していくことによって、地域の個性を見つけることができるのです。違った交流ができるのです。
写真が好きな人、農産物が好きな人、それから山を歩くことが好きな人、山野草採りが好きな人がいて、違った局面から町を編集していく。今、「じょんのび便り」は、特集欄でこのことをしている思います。今までは、地域の情報は観光パンフレットか、施設紹介のパンフレットだけだったのですが、地域の情報紙を使って、自分たちの町をさまざまな視点から編集できるのです。
海のあるところでは、珊瑚礁の便りであるとか、珊瑚の好きな人、海を渡る人、海の中へ潜りたい人など、いろいろなかたちで地域は編集できるのです。これまでは町の編集をしなかったのです。それは何故か。山のことを書けば、まだ農業もあると言われ、農業のことを書けば、商業もあるとか、何かだけを書けば、これもあるだろうと言われてしまう。行政はクレームには非常に弱いものですから、すぐすみません、すべて載せますか、止めますとなる。いつの間にか編集がなくなり、癖がなくなってしまうのです。本当は、農業ばかり載せててもいいじゃないか、商業だけ載せてもいいじゃないかと自分以外のことにも応援しなくてはいけない。毎回、違ったテーマで町を編集していくことが必要なのです。そのテーマが好きな人が、それを見て来るわけです。オタクがいるのです。
オタクという言葉がですが、例えば、写真オタクもあるでしょうし、いろいろなオタクがあります。テーマに対するマニアなのです。昨年、日本とフランスを結んで議論されたテーマが、「世界文化首都の新世紀〜オタク文化の活力と新世界〜」だったのです。その報告書を読みますと、オタクというのは、「私には私の、自分の文化があります」ということがまず基本にあり、自分という存在を自ら確かめるための努力をすることが、オタク文化の出発点であると言っています。
「オタク」は、自分を探すために、相手とのつながりを求めて世界を飛び歩き、「あなたは」と質問するところから情報がつながり始めるというのが、オタク文化の基本になっているのだそうです。オタクは悪く言われがちですが、自分の周りに壁を作って閉鎖的になると駄目なのですが、今は仲間を探してネットワークして、オタク文化を生み出しているのです。先程のアマチュア写真家というのは、写真のオタクの集まりなのです。それから、薬膳料理なら薬膳料理のオタクであったり、いろいろなオタクがいるのです。好きだから、そればかりやっている。
私もまあ、地域づくりオタクだと思います。世の中にはいろいろなオタクがいて、そのオタクが21世紀の文化を創っていくだろうといわれているのです。ですから、大学の先生でも及ばないような一芸に秀でた人は結構でてきているのです。オタク方が大学の先生より一点においては詳しいのです。
東京の神田神保町で古書店の調査をしているのですが、神田の古書店が1軒も地上げにならなかったことを知りました。1軒も地上げにあってないのです。また、こうした不景気な時代、本離れの時代にも、神田の古書店は倒産していないのです。
聞いてみたら、古書店1軒に300人のオタクがいれば、本屋は成立するのだそうです。考古学であれば考古学、宗教、アニメ、地図であれば地図の専門書、それくらいオタク化しているのだそうです。ですから、自分の文化をもっていない人は、ひょっとすると、21世紀になってあなたは何の文化も持っていないのですね、と言われてしまうかもしれません。オタク文化的に町の編集をしていかなくては、文化がないと言われる時代になってきたということなのです。
農山村は顔の見える小さな社会です。さまざまなオタクを育てていくと交流する時に地域の魅力になっている。オタク同士が交流して、ネットワークして新しい地域社会を創り出すことになるかもしれません。地域の精神も深まっていくと思います。
意識改革は人間の成長そのものなのです。オタクによって意識改革を迫られるのです。自分が自分を受け入れてくれる町をお互いが作っていく、オタクが町に住む条件として、それぞれが居心地がよい、自分が暮らしていける環境を作っていく時代が来ると思います。そうしたことから、これからの都市と農村の交流となって、さまざまに繋がっていく時代になると思うのです。コミュニティビジネスも、そういったオタク文化の中から生まれてくるものだと思います。
〇まちづくりは人づくりのベンチャービジネス
―1人1芸の個性と活きた言葉・行政は1人1人と夢を見る―
もともとまちづくりというのは、人づくりのベンチャービジネスと思うのです。こういうことをやってみよう、こういうことに挑戦しよう、それが固まってくるとベンチャーでなくなり守りに入ってしまうのです。例えば、大分県大山町の一村一品をご存知だと思うのですが、梅や栗を植えて一村一品をしていますが、その梅は農協なんかが扱っていたわけです。ところが全国各地がマネをしてどうもうまくいかない。
そこで、全国梅干コンクールを実施したのです。地元の人の梅干しは、最初の大会では、審査員から無惨な評価をされました。「梅の産地がこんな梅干しをつくっていいのか」と思ったそうです。みんな意識の中で、「たかが梅干し」と思っていたのです。
最初の時に、600点近い梅干しが集まってきたのですが、その梅干しを見て、町の人はびっくりしました。「梅干しがこんなにきれいなものなのか」と。これは勉強せんといかんと。それから、4年経って、第2回の梅干しコンクールがありました。最初の予選で上位30点を選んだのですが、そのうちの18点に大山町の梅干しが入りました。すると、日本一の情報の凄さです。びっくりです。次の日から、何も言わないのにどんどん電話がかかってくるのです。今、25軒の農家が今までは農協に出荷していたものを、保健所の許可をもらって自分たちでデパートに梅干しを直接おろしています。
個人の名前の方が売れるのです。ベンチャーというのは一人ひとりが生き生きすることです。人口も減ってくる中で一人一人が生き生きと暮らしていくにはどうしていくかというのがテーマです。ベンチャー精神そのものなのです。一人ひとり違った個性や癖がないと駄目なわけです。地域で個性を一つにしていく、自分を一つにしてしまうことがむしろ、ベンチャーを育てなくなってきたのです。これからのインターネットの時代は、違いがなくてはいけないのです。
こうやって同じモノを作れと言ってすべての住民と行政が一緒になってやってきたのがこれまでのあり方です。これをを変えていかなきゃいけない。住民一人ひとりが行政と夢を見ていく時代です。全体で同じ夢を見ていく時代ではなくなったのです。
今の話は、これまでの工業製品に対して一人ひとりの工芸製品ということです。今までは、農村も漁村も工業製品を作っていたのです。これを工芸製品にしていくことが必要になったのです。要するに一人一芸で一人ひとりの個性、そういうものが集まらないと地域の魅力がないのです。
大山町では、商品は素材の梅ではなく、工芸製品となった高い値段の梅干が売れる。梅の実のままだったら1kgで100円です。100円には個性がないわけですね。梅を工芸製品、梅干にしてしまう。自分の名前のついた工芸製品の方が人気はあるのです。
各地を歩くと、最近は生き生きした言葉で地場産品を売っていますね。○○おばあちゃんの饅頭、○○さんの蒸しパンなど、今までは、こうした産物は地域の名前でした。じょんのび饅頭は、じょんのびという言葉そのものが生き生きしている地域の名前なのでしょうけれど、最近は、じょんのびにおいても、一人ひとりの個性的で生き生きした言葉の方に向かいつつあります。
交流とか住民参加という一般的な言葉より、個別の言葉の方がもっと生き生きしているのです。人の心をつなぐ言葉として、「じょんのび」という風に言ったのです。住民参加というのをじょんのびという言葉で言っていると思うのです。ですから一人ひとりの住民と行政が一緒に夢を見るには、「生きた言葉」が必要なわけです。
こうした講演会でもフォーマルな姿でするのと、インフォーマルな姿でするのとでは大きな違いが出ます。建前に対して、まず本音が出てくる。本音には実に面白いものがあることがみんな分かってきたのです。非公式の方が生きた言葉が出てくる。生きた言葉っていうのは、一人ひとり違うわけですから、住民一人ひとりと行政が一緒に夢を見ていくことができるのです。そのことによってのみ、自分の特徴を知ることになるわけです。
〇遊び心で新たな発想を
―けなし合うより誉め合って前向きに楽しむ―
遊び心は次の仕事の発見ということなのです。仕事から次の仕事を考えるのはなかなか難しいものです。新しい発想は、遊び心の中から出てくるということが多いのです。昨日もコンサルタントの人が来て、学生に町の総合計画の作り方を話してくれたのです。そしたら学生が、今、何の話しをしてるんですかということを言ったのです。それは何かと言ったら、新しい楽しさになってなってないじゃないかと、ただの仕事じゃないかっていう学生がいたのです。その時に、ああ、そうだろうなと思いました。学生は地域社会の中で感動したり、遊んでみたり、楽しみたいということを若い人は思ってるということに気がついたのです。
高齢化社会にどのような高齢者対策をするか、教育の問題はどうするかなど、もっと楽しく考えられるような方法はないか、もっと楽しさの中から地域社会のあり方を考えていくってことは出来ないのですかっていうのです。その時、面白かったのは、高齢化社会ということをマイナスと考えない、けなし合う社会より誉めあう社会と捉えていることでした。前向きにとらえている。学生の方がですね。もっと攻めのスタイルで、それを楽しんでしまおうとさえしているのです。世の中を面白くしてこうということを学生は考えているのです。
早川町にある日本上流文化研究所ですが、山のある上流圏から21世紀の新しい文化を作っていこうとしているのです。私はそこのお手伝いをしています。集落内の道のあり方っていうのを学生たちが調査したのです。皆が声を掛け合い励まし合うための歩く道を、皆の普請で手作りでしたらどうか、というようなプランをたてたんのです。歳を取ると車に乗らない。人の歩く道を楽しく作っていこうというプランを立てたのです。
その時に、学生たちがそれを発表した時、「君たちそこに住むのかい」って言ったら、学生たちは住まないって言うのです。年寄りの町だから、自分が住むわけではない。町をどう作っていくかを考えるときに、世代別プランがあってもいいのではないか、若い人たちが住むならば、年寄りのことを考えないで、こういう町であってほしいなどを作ってみてもいいのかもしれないと思ったのです。
このように考えると、今まで同じ条件で、真面目に取り組みすぎていた。年寄りの人たちは年寄りで楽しんだり、若い人は若い人で、また若い人と年寄りと一緒に楽しむまちづくりもあってもいいのではないか。そんな風景を想像すると、けなし合うのではなく、お互いに誉めあって前向きにとらえて楽しんでいるプランになる。高齢化社会と関係なく、若い人が勝手なことを言ってプランを作っていく。そうしたことが遊び心になっていく。仕事として考えずに、楽しく作っていくことが重要じゃないかなと思うのです。
プランを考える時に、もっと遊ぶような心を我々は持っていかなくてはいけないのではないかなと思うのです。問題や課題をなんとかしなきゃいけない、なんとかしなきゃいけないと先の心配してばかりしていては生き生きしたことはできないのです。高齢社会を見てみますと、おじいさんたちは経済的にも豊かで、孫にこづかいやって楽しんでいる元気な人も多い。少子高齢社会になれば、孫は少なくなって自分のこづかいが増えていいなあと思えば、まあ、そんなことも考えられるわけです。年寄りで若い子の世話になっている人よりも、若い子どもの面倒を見ている人の方が多いと思うのです。前向きにものごとを考えていくようなことも必要かなと思います。
〇リーダーシップよりプロデュースシップを
― 一人ひとりの発想をどんどん言えるような環境づくり―
最後に活動領域を広げるコミュニケーション作りについてですが、先程少しお話したようにリーダーシップ型というのは、ある意味では閉鎖的なところがあるのです。ある方向にもっていこうとする。これから大切なのは、むしろプロデューサー型だと思うのです。プロデューサーやコーディネーターのように、住民の活動にチャンスを作ってあげることが重要な時代なのだと思います。
石原慎太郎知事の元で、今、都庁でどのようなことが起きているのかなと、友人に聞いてみたのです。都庁はいろいろと新しい政策を打ち出しています。ディーゼルエンジンの規制などいろいろなアイディアを出して続けています。聞いていて面白かったのは、職員に向けて、「お前たちが今まで考えてやろうと思ったけどやれない事ってあるだろう。言ったって無駄だ思ったことがあるだろう。それを俺と一緒に実現しよう。」と言う言葉でした。
俺を利用して自分たちの夢を実現すればいい、作ればいい、だからこれを機会にみんな言いたいことを言えと。俺はそういう事をすると。都知事は何を言うか分からないひとですから、今までやりたかった事も言ったらひょっとして、実現できるかもしれないと思わせたことは大きいです。そうした環境を作ったということを聞いたのです。
以外だったのは、石原都知事はリーダーシップをとって自分がこういうことをやりたいと言っているようだけれど、一人ひとりが自由に発想すること、どんどん言えるような環境を作っているのだなあと思い感心しました。全部の案件がリーダーシップ型のトップダウンで出ているわけではないのです。変なことを考えたり、遊ぶ心で考えたりしたことを、この際だから言っちまえと。俺だったら実行するぞと思わせるのがプロデューサーなのです。
これは活動領域を広げるコミュニケーションの手法です。リーダーシップというのはコミュニケーションが少ない世界なのです。一方通行で命令ばっかりしている。そうしたこととは反対に、考えていること、やりたいことをどんどん発言しよう、コミュニケーションしようと。これはプロデューサーシップです。こうしたことが新しい社会の実現につながっていくのではないでしょうか。
〇知恵は地域の中に転がっている
―地域の中の違った文化の交流が新しいものを生みだす―
他にもいろいろなコミュニケーションが作られています。九州の阿蘇地域でもそうなのです。地域の活性化っていうのはどういうことかという話をしている時に、新しい知恵は、地域の中、住民の中にしか、転がっていないということを教わったのです。
阿蘇地域では牛を飼っている。でも牛を食べる文化はないので、自分の町では牛を食べないのです。みんな商品として出しているのです。この前行ったら、牛を自分たちでおいしく食べる文化を創ろうと動き出しいたのです。農家の人たちが今の牛の飼い方が自然や時代に反していると言い出したのです。食べる段階になって逆だと言い出したのです。面白かったのですが、霜降り肉は脂肪が入っているわけですね。あれは健康な牛ではないわけです。農家の人は、健康ではない牛を美味しい牛として作っているんだけど、時代から言えば逆ではないかと。霜降りが美味しいから高いって言っているのは、時代から言えば逆だと作ってる人に分かったのです。脂がもっと少なくって、もっと健康な牛を、赤身を食べようといって自分たちで肉屋を始めたのです。
その次には、その赤肉を使って料理を作ろうということになってのです。町のホテルや旅館で働いているシェフの所に行ったのです。すると、実は俺もね、お客が喜ぶから霜降りとかそういうの使っていたのだけど、その肉を使ってみたいということになったのです。自分がしてみると、大量にもつがでるから、もつの料理もやってみたいという風に広がっていったのです。
それまで、観光客のために作っていた料理というのは、地域の人が楽しむ料理ではなかったのです。農家が肉屋さんになり、そして地域住民が肉を食べる。レストランを新しい料理人と立ち上げていくということに発展したのです。活動領域を広げるというのは、違った職業とか違った人たちを結び合わせていく。そうしたコミュニケーションや交流というものを作っていくということによって、遊びから次の仕事の発見になっているということなのです。
これには、コーディネートを具体的にしてくれる人がいないと駄目なのです。人と人を繋いでくれる人、違った人と違った人を出会わせていく。そこから新しいものが生まれてくる。そのことが実は交流なのです。地域内の交流も実はあまりされていなかったと思うのです。地域の中で違った文化の交流をさせていくということで新しいものやことが生まれてくる。自分たちが本当にやりたいことに近づいていくということなのです。
〇都会には、頭脳を持った暇な人が多い
―都会の暇な人を引き寄せる個性を持とう―
住民自体が、自分がしたいことや自分の文化を持って、自分が主体となって参加していくことによって、行政もコストが安くなってくる。本当に必要なもの、作りたいものになってくるのです。そして、農村漁村の交流促進を考えますと、都会には暇な連中がたくさんいると思うのです。その暇な連中を引き寄せるような魅力的な癖をもつこと。都会には同じような癖を持っている暇人が多いのです。これがインターネットなどで繋がっていくから面白い時代になりました。そして、地域の中でも違った個性がどんどん結び合わさっていく。そして、地域の経済というものは、市場の経済だけでなくて、いろいろな地域経済があるっていうことも分かっていただけたと思います。
皆さん、今日は遠くから来られて、何か新しいことが一つでも感じていただければと思い、お話しました。高柳の人たちとこれからインフォーマルな場所で、懇親会が開かれます。是非、この会場に扱かれています、大橋さん、村田さん、小林さんなどのオタクとつながっていって下さい。こうした人、一人ひとりが実は大切な時代が来ています。そのことが住民参加から住民主体へとなっていきます。
私のところに、この町の誰と誰が結婚するよという情報さえ流してくれるようになりました。私も身内になったよう気持ちで、交流が楽しくなっています。同じようなことを観光客の人たちも、願っている時代がきていると思います。せっかく来られたのですから、地域の人と出会わないじゃなくて、出会って頂きたいと思います。
最後に学生が言った言葉で締めたいのですが、北九州から来ている学生が北九州まで自転車で帰りたいと言いだし、私の知っている町を訪ね歩きました。帰ってきたら、一期一会という名刺を作ってきて、皆さんにご迷惑をかけましたが、それで終わる男ではありませんという言葉が印刷してありました。そんな風に、学生たちも自分を受け入れてくれる地域を求めていますので、是非、そうした学生に夢を与えることができる地域を作っていただけたらありがたいと思っております。最後まで、ご静聴、有難うございました。