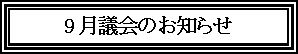
�@9���c��͌��Z�c��ł��B�����͒�ė��R�̐����A2���ڂ͑������^�A3���ڈ�ʎ���A�ŏI�����̌��̗\��ł��B����T���ɗ��Ă��������B�T���҂�����ƊԈႢ�Ȃ��c��͊��������܂��B
9�� 6���@���c����@14������
9�� 9���@�{��c2���ځ@10������
9��18���@�{��c3���ځ@10������
9��25���@�{��c�ŏI���@14������
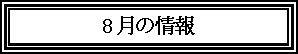
�@���k�t�H���X�g�s�A���s�ψ���������A����䒬���R�x�{���Ǘ��Z���^�[�ŊJ�Â���܂����B
�@���̎��s�ψ���ɂ��ẮA�{���̍�N8��15�����ɂ��ڂ����f�ڂ��܂������A�ēx���グ�Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�{���Ƃ́A�{�茧�����a61�N�x���肵����3���{�茧���������v��ɐ����ڕW�Ƃ��Đ��荞�݁A���a62�N�Ɍ��k�̓��V�e�A�����A�܃P���A�ŗt�A���˂̌ܒ��������f������Ƃ��Ďw��B��63�N�Ɂu���k�t�H���X�g�s�A������{�v��v�����肵�āu�t�H���X�g�s�A�{��\�z�v�̋���Ɍ����đS���I�Ȏ��g�݂��s�Ȃ��Ă������̂ł��B
�@����䒬��������ۂ̓y���ے��i��̂��ƂŊJ���܂����B
����A�i����䒬��t�����j�v�|
�E���a63�N����{�茧�m���̐���ɂ��X�щ��Љ��ڎw�����t�H���X�g�s�A�\�z�̋���ɓw�͂��Ă���B
�E�ߑa�A����A�ыƕs�U�̉ߑa�n��ɗE�C��^�������̃v���W�F�N�g��13�N�̍Ό����}�������ӂ������B
�E���Ƃ̒��j�ƂȂ�l�������ł́A�t�H���X�g�v���f���[�T�[��t�H���X�g�C���X�g���N�^�[��������B������i�ޒ��ŐV�������z��s���͂����߂��Ă���B
�E5���̑���Ńt�H���X�g�v���f���[�T�[����ƃt�H���X�g�C���X�g���N�^�[����������āu�t�H���X�g�s�[�A�C�G�[�o�h�`�v�Ƃ����g�D�ōĔ��������B
�E�A���U�v�^���ł͂��s�͂������������ƂɊ��ӂ������B���ʂƂ��Ă͎c�O�ł��������A����17�N5���̈����T�Ԃł͖쒹�̏W�����Ƃ��ē��������B
�E����Ƃ���2����{�v��̐��i�Ɍ����ēw�͂��Ē��������B
�������c��c�����A�v�|
�E�R���̌���́A�ߑa�A����A�؍މ��i�̒���ȂǂŌ������B
�E�\�Z���������ɂ��邪�A�p�m�����W���Đ����邽�߂̓w�͂����Ăق����B
�E������t�͒n���Ɍ������B�����̓W�]���ǂ���J�����A�n��̂��Ƃ͒n��ōl���p�m�����W���Ď�g��Œ��������B
���R�������������A�v�|
�E�{���Ƃ́A�R���̓Ǝ��Ȑ��������A�V�����R���Љ�̍\�z�ɂ���B
�E�V�X�їыƊ�{�@����N���肳��A�{���̍��y�ۑS���㐧�x���F�߂�ꂽ�B
�E�{���Ƃ���N�����2���v��ƂȂ邪�o�ώ���͑�ό������B�V���Ȏ��_�Ŏ�g��Œ��������B
�E�u�t�H���X�g�s�[�A�C�G�[�o�h�`�v�̑g�D���ݒu���ꂽ�B�����Ɋ��҂������B
�����Ď����ǂ���̐���������܂����B
13�N�x�̎�Ȏ��Ɣ�́A
�E�t�H���X�g�s�A�n�惊�[�_�[�W�c�g�D�������Ɓ@443��~
�E�t�H���X�g�s�A����w�K�̐��m�����Ɓ@1.529��~
�E�X�Ƃނ當����i���Ɓ@492��~
�E�R���s�s�𗬊������i���Ɓ@3.796��~
�E�t�H���X�g�s�A���Y�i�J���x�����Ɓ@421��~
�E�t�H���X�g�s�A���Y�i�̔����i���Ɓ@3.258��~
���A�����njo��܂߂�12.579��~�̎��Ƃł��B
�@���k�R���̊������ɂƂ��Đ�D�I�Ȑ���\�z�Ɗ��҂���Ă��܂������A���̎��Ƃ̐��ڂ�����ƁA���͂₱��܂ł��Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
�@���\�́A���̎��Ɣ�̐��ڂł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʐ�~�j
| 5�������S | �����S�� | ���@�v | |
| 12�N�x���� | 22,872 | 16,289 | 39,161 |
| 13�N�x���� | 11,218 | 3,080 | 14,298 |
| 14�N�x�\�Z | 10,146 | 1,171 | 11,317 |
���̕\������ƌ����S�����ɒ[�Ɍ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@���̌��ɂ��ẮA�{���̍�N8��15�����ɂ��f�ڂ��܂������A��N�̎��s�ψ���ŁA�����S���ɂ��Ď��₵���Ƃ���u���ꂩ��͕⏕�����肫����̃X�^�[�g�ł͂Ȃ��āA�ʂ̎��Ƃ��ᖡ���Đ��ʂ��グ��ꂻ���Ȃ��̂ɂ��Ă͕⏕�������������B�T�ˑO�N���80�����x��ڕW�ɂ��Ă���B�v�Ƃ������ق��������̂ł��B
�@���̂��Ƃ��画�f�����16.289��~��80���A13.031��~������łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A���т͑O�N��18.9����3,080��~�Ƃ������̂ł����B
�����ŁA�M�҂͎��₵�܂����B
�����v�|
�@1.����ɂ��Ă��q�˂��܂��B��N�x�̒莞����ŁA����ɂ��ė\�Z�Ăł̓[���ƂȂ��Ă���̂Ŏ��₵�܂����Ƃ���O�N��80�����x�͍l���Ă���Ƃ����������ł���܂��������Z���������3.080��~�ƂȂ��Ă��܂��B
����́A10���p�[�Z���g�ɂ����Ȃ�܂���B���ƌv���5�����̃��[�L���O����ŋN�Ă����낤�Ǝv���܂����A���Ƃ��ẮA�\�Z�����Ă��悢�Ǝv����悤�Ȍv�悪�オ���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤���B����Ƃ����̕����炱�̘g�ł��Ȃ����Ƃ����ӂ��ɍl�������ς����̂ł��傤���B
2.���ʂ̏オ�肻���Ȋ�悪�Ȃ������Ƃ������Ƃł���A���Ԃ̒m�b���W���邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�������̂��߂̎��Ƃ́A�s���哱�̊���_�ł͎��Ƃ��}���l�������Ă��ėǂ��A�C�f�B�A���łĂ��Ȃ��ł��傤�B�Z������A�C�f�B�A������W���ėǂ����ɂ͗\�Z�����āu���Ԃł��Ȃ����A�s�����x�����܂��v�B�Ƃ��čL���m�b���W�߂����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@������̓��ق��Ȃ��A�����ǂ���̐����͒��ۓI�ł����B�܊p���ꂾ���̑����̃����o�[���M�d�Ȏ��Ԃ������ĎQ�W���Ă���킯�ł�����A�����Ƌc�_���Ȃ���B����҂��M�҈�l�݂̂Ŏ₵���t�H���X�g�s�A���s�ψ���ł����B
�@�V�N�x�̗\�Z������͍X�ɗ��Ƃ���đO�N��38���ł��B���������̊��Ҋ���ӋC���݂͂ǂ��ւ��B�u����Ⴂ����Ȃ��v�B
�@����ҕی������E���ی����ƌv�����ψ�������1��c���ŊJ���܂����B�͂��߂Ẳ�ł��B
�@�`���A�������Ϗ��n����܂����B�Ϗ����Ԃ́A����14�N8��1�����瓯16�N3��31���܂łł��B
�ψ��̃����o�[�́A���\�̂Ƃ���11���ł��B
| ��ی��ґ�\ | �����r�s |
| �V | �����`�H |
| �c���\ | �b��[�T |
| �V | �H�{ �� |
| �����ψ���\ | �{���v |
| �V | �ŗt�O�q |
| �{�����e�B�A��\ | �e�n���Îq |
| �������� | �b���q |
| �����a�@ | �쑺���@ |
| �Љ�����c�� | ���g�t |
| ������ | �A�ؗE�� |
�@���ی����Ƃ́A3�N���Ƃ�5�N��1���Ƃ��Ē�߂�Ƃ������ی��@�̒�߂�Ƃ���ɂ��{�N�x���ɕ���15�N�x����19�N�x�܂ł�5���N�v������肷��K�v������Ƃ������Ƃł��B
�@��o���ꂽ�v��Ă����ꂼ��̗��ꂩ��`�F�b�N���Ă����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
�@�{���ɂ����镽��14�N7�������݂̉��ی����x�̎��{�́A
1.��ی���
�E��1����ی��� 1,549�l
�E��2����ی���1,647�l�i40�`64�j
2.�v�x���E�v���F��Ґ��@195�l
3.�T�[�r�X�̗��p�i14�N5�����j
�Z�ݑ���T�[�r�X�@ 105�l
�Z�{�݃T�[�r�X
�E���ʗ{��V�l�z�[���@38�l
�E���V�l�ی��{�݁@�@ 4�l
�E�×{�^�a���@�@�@�@�@ 8�l
4.�ݑ���T�[�r�X���Ǝ�
�i��ی��҂����p���Ă��鎖�Ə��j
| �T�[�r�X�̎�� | ���Ə��� |
| �K���� | ���Љ�����c�� |
| �K�������� | �T�����[����B |
| �K��n�r�� | �܃P�������a�@ |
| �K��Ō� | �܃P�������a�@ |
| �h�z�K��Ō�r�s | |
| �f�B�T�[�r�X | ���Љ�����c�� |
| �V���[�g�X�e�B | �������� |
| �h�]�� | |
| �s��Ή��^���� | �Ђ܂��i���a�@�j |
| ������� | ���݂�i���˕a�@�j |
| ���x���v��쐬 | ���Љ�����c�� |
| �h�z�₷�炬�� |
5.���ی����@�i����13�N�x�j
| �l�� | ���ۑ��z | |
| ���ʒ��� | 1,344 | 27,610,191 |
| ���ʒ��� | 208 | 4,340,376 |
| ���@�v | 1,552 | 31,950,567 |
�u�킪���̏��������l���鎋�_�ŁA�n��ɂ�����A����ׂ����t�ƕ��S�̐�������������v�Ƃ���܂��B�d�g�݂����G�ŕa�@���Ƃ��W���Ă��܂��B�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���P�n3���c��c�����C�����䒬������c���ł���܂����B�u�t�́A���{���Y���őS�������c��c����c���������������Ƃ��������������̐搶�ł��B�c���ɂȂ�Ɓu�c���K�g�v�Ƃ����c����̃}�j���A���I�Ȗ{��n�����̂ł����A���̖{�����M�������Ƃ������Ƃł��B�܂��A�u�n���c��l�v�Ƃ��������E�c�����C���ɂ����M����Ă�����{�s���w��E���{�����w�����ł��B
�@���C�e�[�}�́A�u��������̂܂��Â���Ɋ��҂����c��E�c���̊���v�ŁA�ߌ�2��30������5���܂ōu�`���܂����B
�@���e�́A�M�҂������v���Ă������Ƃ����b���ꂽ�̂Ŋ������Ȃ�܂����B�u�`�̃��W�����͂��̂Ƃ���ł��B
1.��1���������v�̐���
�@�n���������i�ψ���̊���
�E�n���c��̊�����
�A�n�������ꊇ�@�̎{�s
�E�@�ֈϔC�����̔p�~
�B�n���������v���i��c�̔���
2.��2���������v�̉ۑ�
(1)�����E���Ƃ݂̍���Ɋւ��钆�ԕ�
�E�ō����̈ڏ�
(2)��27���n�����x������̓���
�E����̘_�_
�A�E��b�I�����̂̂�����ɂ���
�C�E��s�s�̂�����ɂ���
�E�E�s���{���̂�����ɂ���
�G�E�n���ō����̂�����ɂ���
�I�E���̑�
3.�ŋ߂̒n�������@���̉���
(1)����������̖@����
(2�j�c���h���̖@����
(3�j�����҂ɑ��A�c��R�c�̏�ł̈ӌ��q�@��̕ۏ�
(4)�������c��ݒu�ɏZ�����[���x����
(5)�Z���č������E�Z���i�א��x�̉���
4.�s���������Ƌc��̑Ή�
(1)�N�̂��߁E���̂��߂̍�����
(2)������̎����̂̂�����͂ǂ���
(3)�u�n�������̖{�|�v�ƍ���
(4)�ŏI�I�Ɍ��߂�̂͋c��
5.�����c��̌����
(1)�c��E�c���͏Z���ɂǂ��F������Ă��邩
�@�{��c�A�ψ���̖T����
�A��c�^�̉{����
�B�c����A�s�u���p�A�z�[���y�[�W��
�C�c���萔�A�c����V�͑�����
�D��p�ُ��A�c���N����
�E����������A�c���h����
�F�c���o�b�W��
�G�s�����@�A�\�t�g�{�[���A�싅����
(2)�c��ƒ��̊W�͓K��
�@���ƒn���̈Ⴂ��
�A�@�\�o�����X��
�B�^��}�W�ɂ͂Ȃ��͂�
6.�n���i�����j�c�������������ɂ�
(1)�n���c��̎��含����������
�@�c���萔�̎���I��
�E�c���萔�͑S�ď�ቻ���ׂ��ł�
�A����̉�����P�p����B
�E�S���ꗥ�Ɂu�N�l��ȓ��v�łȂ��Ă��悢�̂ł�
�B�Վ��c��̏��W�v�����ɘa����
�E�c���ɂ����W����F�߂�ׂ��ł�
�C��C�ψ��̏���������P�p����
�E���ꂼ��̋c��Ō��߂�悢�̂ł�
(2�j�c���͈͂��g�傷��
�@�u��{�v��v���c���̑Ώۂ��ׂ�
�E�u��{�\�z�v�����ł͒����̏����v�}���킩��Ȃ��̂ł�
�A�ʌv��̃}�X�^�[�v�������c���̑Ώۂɂ���
�E�Ⴆ�A�S�[���h�v����21�A�V�G���[���v�����Ɋ�Â��e��ʌv��E��ʔp���������v��E���ی����ƌv��Ȃǂ́A���K�̋c��ŐR�c���ׂ��ł�
�B���@��̌_����c���̑Ώۂɂ���
�E�����̖��Ԉϑ����A�d�v�Ȃ��̂͋c�����ׂ��ł�
�C�n�����ЁE�O�Z�N�ւ��ϋɓI�Ɋ֗^����
�E�o���A�⏕�����̎g�r�͂��Ƃ��A�g�D�^�c�S�̂ւ̋c��̃`�F�b�N���K�v�ł�
�i3�j�c�������g�傷��
�@�_��c���̐������ɘa����
�E�����̂̔��f�ɂ���Č��߂Ă悢�̂ł�
�A�\�Z�R�c�����g�傷��
�E�c���̑Ώۂ��u���E���v�݂̂ł͐����_�c���ł��Ȃ��̂ł�
�B���Z���d������
�E���s�ς݁u������߁v�R�c�ł͂Ȃ��A���̗\�Z�R�c�ɂȂ���ׂ��ł�
�C�ꌈ�����𐧌�����
�E�ꌈ�̗��R�Ɂu�c������W����ɂ��Ȃ��v���A���ՂɎg��ꂷ���ł�
(4)�������āE�R�c�\�͂����コ����
�@�c�ē���o�v���̊ɘa
�E�c���ł���Ȃ����l�ł͋c�Ă��o���Ȃ��̂͂ǂ���
�A����E���^�̂���������P����
�A�E�c��͋c�_�̏�̂͂��ł�
�C�E�c��̌^���s���R�ł�
�E�E�����Ɋւ��鎩��K�����Ȃ��̂ł�
�G�E����̒ʍ�������߂Ă݂���
�I�E1��1�������������̂ł�
�B�c����ǂ��[������
�E���s���ɔ�ׂ��܂�ɂ����Ȃ��̂ł�
�E�u�̗p�v�l�����x�ɖ�肪����̂ł�
�C���C���[������
�E�A���ԁA���e�����܂�ɂ��c
�D�c��}����������
�E�c��}�����́u�K�u�v�`��������
�E�����������K�Ɋ��p����
(5)�ΏZ���W�����P����
�@���J�ւ̎��g�݂͋c��̃��[�_�[�V�b�v��
�E�ψ�������J���ׂ��ł�
�E�{��c�������I�Ɍ��J����
�\�x���E��ԁ\
�A�c�����[������
�E���m�点�L��l����L��[��������
�B�C���^�[�l�b�g�̊��p�A�z�[���y�[�W���J�݂���
�C�Q�l�l���x�����p����
�E�c��ւ̏Z���Q���𑣂�
�D�Z�����b������{����
�E�c���Z���̒��֏o������
�E��c�\�蓙�����O�L��
�F�T���Ȃɋc�Ă������
������
�u�n���c��ς�Γ��{���ς�v
�i�_�]�j�u���̒��Łu�c���͋c���ɐӔC�������ƁA�^���E�����E���̋c�������c���^�Ɏc�����Ƃ��K�v�v�Ƃ̂��b������7���c��i�{��19���j�̂��Ƃ��v���܂����B
�@�܂��A�u�c����ϋɓI�ɏ��̋c�Ă��o���邱�ƁB�ʌv��̃}�X�^�[�v�������c���̑Ώۂɂ���B�v�Ȃǂ́A�܂��ɉ�ӂ���ł��B
�@�n�������@��96����2���u���ʒn�������c�̂́A���ŕ��ʒn�������c�̂Ɋւ��鎖���i�@���������ɌW����̂������j�ɂ��c��̋c�����ׂ����̂��߂邱�Ƃ��ł���v�̊��p�𑣂���܂����B
�@����܂ŁA���̎��ƌv��͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩����Ȃ��܂ܗ\�Z������Ă���Ă��܂����B�u���̗\�Z���c�����Ȃ���������������߂ɂȂ�܂���B�v�Ƃ������Ƃŋc��͒ǂ����܂�Ă����̂ł��B
�@���̂悤�Ȏ���6.(2�j�́u�c���͈͂��g�傷��v�͑�ϕ��ɂȂ�܂����B
�@�܂��A�u�c��͋c�_�̏�łȂ���Ȃ�Ȃ��B1��1���������悢�v�Ȃǂ͂܂��ɂ��̂Ƃ���ł��B
�@���C�̐��ʂ��������ɋc����Ɋ������Ă��������Ǝv���܂��B
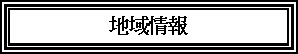
�@���̂Ƃ���A�^�J�ƊԈႤ�悤�ȑ�^�̒����{����ɏo�v���Ă��܂��B���̑�^�̒��́A�����قɖ⍇�������ʁA�u�~�T�S�v�Ƃ������ŋ�B�R�n�Ő������Ă���̂͑�ϒ������Ƃ������Ƃł��B��܂߂̗��̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���L����]�ڂ��܂��B
�@2002�N8��22���i�j
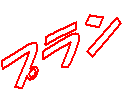 �������₦���݂܂����B5���ɎԂŎ������Ɍ����܂������Ԃ̉��x�v�͍���ɑ���12���ł����B��N�͋C����12���ɉ��������̂�9��19���ł��̂ňꌎ���炢���������ł��B��邩�獡���ɂ����ăh���}������܂����B
�������₦���݂܂����B5���ɎԂŎ������Ɍ����܂������Ԃ̉��x�v�͍���ɑ���12���ł����B��N�͋C����12���ɉ��������̂�9��19���ł��̂ňꌎ���炢���������ł��B��邩�獡���ɂ����ăh���}������܂����B�@��[�U���ɗ{����֍s���܂�����A���}���̒r�̉��ɑ傫�Ȓ����Ƃ܂��Ă��܂����B�Tm�ʂ̎��ߋ����Ŏԑ����炵�炭���߂Ă��܂������A�������Ƃ����Ɣ�ї����ē�����̂ł����A����͎���������Ȃ��炱���������Ă��ĂȂ��Ȃ������܂���B�h�A���J�����瓦���邾�낤�ƎԂ̃h�A�������J���܂������A����ł������܂���B�����ŎԂ���~��Ă����Ƌ߂Â����Ƃ���傫�ȉH���J���Ēr�̔��Α��ɔ�шڂ�܂����B�ړ��������։��2���ʂɋ߂Â��܂����������܂���B�����ŁA�����Ƃ��̏�𗣂�đq�ɂ֍s���A���}�����������Ԃ������čĂт����Ƌ߂Â��܂����B���͓������E�ɐU��Ȃ��炶���Ǝ��̍s�������߂��ɂ悤�ɂ��Ă��܂��B�����ŁA�����ƖԂ����Ԃ��܂������A�\��邱�ƂȂ��Ԃ̒��ł����Ƃ��Ă��ē����܂���B�����ŁA���}����~�p����J�S�̒��ɓ���܂����B�����܂����Ă��܂��B����̓N�}�^�J���낤���A�T�V�o���낤���B�����쒹�͏ڂ�������܂���B�T�C�Y�͌v�����܂���ł������H���L�����2���߂����肻���ł��B
�@30cm�قǂ̃��}���e�����^���C�Ɉ�C����ĉj�����Ԃ̒��ɓ���Ă��܂����B�R���N���[�g�̏�ł́A�����܂̂��ߗ����ɂ������Ɍ������̂ŁA�~�܂�ƂȂ�悤�Ȋۑ������܂����B�������̎ʐ^��쒹�̏ڂ����l�ɑ����ĊӒ肵�Ă��炨���Ƃ��̏�𗣂�܂����B����������A��ۂɂ����Ƃ̂����Ă݂܂�����A��قǍ������ꂽ���}�������܂���B�����������y���ɂȂ����悤�ł��B�S�Ă͖������Ǝv���ċA��܂����B
�@���̖���R�Ƀe���r�̃J�������܂킵�Ă��鉄���̓c�肳��d�b������܂����B������̈ꌏ����������Ƃ���ނ͖쒹�̒����������Ă���Ƃ������ƂŁu�܂ɋC�����Ȃ���|�J���X�G�b�g�����܂���悤�Ɂv�Ǝw�����܂����B
�@�����āA�����������̒������̂Ƃ���ɍs���Ĕ`�����݂܂����B���܂���B�J�S�̒��͋���ۂł��B��������ƃJ�S�̖Ԃ͂܂�Őn���Ő������悤�ɔj���Ă��܂��B�u���܂����B�쌢���e���̎d�Ƃ��낤���v�B�J�S�̂܂����悭�ώ@���Ă݂܂����A�H�������Ă��܂���B�쌢��e���ł͓��R���̂悤�ȖԂ������������Ƃ͂ł��Ȃ����ł��B�u�c�O�A���Ă��ꂽ�v������̂܂�ł��B�쐫�̐�������������ꂽ�����ł��B���̉s���܂Ńi�C�����̖Ԃ���������Ɛ���悤�ł��B�������Ƃ��킵���ώ@���Ă����悩�����B����ɂ��Ă����͂Ȃ����̂悤�ɂ��ƂȂ��������̂��B�s�v�c�ł��B
�@�W���ɂȂ�{����̃X�^�b�t���o�Ђ��Ă��܂����B�u�В��A����͍���[���T�����������钹���r�̒��ł��ڂ�Ă���̂ŏ����Ēr�̉��ɂƂ܂点�Ă����̂ł��B�v�Ƃ����B�ǂ���烄�}�����l��ɐ����ւ������Ă��ڂꂽ�炵���B�����ł͂Ȃ����Ƃ�Y�ꂽ�̂��B�����Ė锼�悤�₭���C�ɂȂ��ē����o�����̂��B�������A�܂��A���̍������ꂵ�����}���e�������������H�ׂĂ���̂ł��B����Ō��C���ł��̂ł��悤���B�u�~�p�J�S��j���č����͎d���ɂȂ�Ȃ��v�Ɠ{���邵�A����͂�A��ςȃh���}�ł����B�ǂȂ������̒��̖��O�������Ă��������B
�@�NjL�F�����ɂȂ�܂����B�������̏ォ��s�[���s�[���ƒ��̖��������������̂ŊO�֏o�Ă݂܂�����A���̒������������̓d���ɂƂ܂��Ă���ł͂���܂��B���A�ɗ����̂��ȁB����Ƃ����̎����̌��ꌟ�Ȃ̂��A�͂��܂��A���̒��̑��_�Ȃ̂��A�������ł͂���܂����Ƃ�ɂ��܂藈�Ă����邵�A���Ȃ���Ύ₵�����Ƃ������Ƃ���ł��B�i���j
�@�\�\8��22���t�̒����ł����A�����ق��V����������Ӓ茋�ʂ̕ւ肪�͂��܂����B
------------------
�@���āA���₢���킹�̒��ł����~�T�S�Ƃ������ł�
�ǂ��炩�Ƃ����Ɖ��ݕ��ɑ������ŁA�[�R�ł̏��͎��͏��߂Ăł��B�O�̂��߁A�쒹�̉�̒m�l�ɂ��Ɖ�܂����������͓����ł����B�c���Ƃ���܂����A�H�͂��������H�ƂȂ��Ă���悤�ł��B�ߊl�̏A���̎�̒��̖ڌ����Ȃǂ��̒��i��j�ɂ��Ă̏������������ڂ������m�点���������B���̂��Ƃ����܂��ƁA���̒��̔ɐB������ł͂قƂ�ǂȂ��̂������ł���낵�����肢���܂��B
------------------
�Ƃ������ƂŁA�~�T�S�Ƃ������������ł��B���}�����l���Ă��Ⴍ�ł����A��Ɍ����܂��傤�B
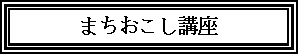
�@������18���i7��1���j�Ōf�ڂ����u�S�������̂ނ��c�v�̑����͑O�������c����W�Ōf�ڂł��Ȃ������̂Ŗ{���Ɍf�ڂ��܂��B������ƃ{�����[��������܂����A�܂��Â���̃q���g����t����܂��̂ł��ɂ̎��ɂ���育���������B
**********************************
�R�����s���ʂ����߂̌𗬉�c
�u�S�������̂ނ��c�v
���C���e�[�}
�u������̏z�o�ς��l����v
2002�N2��15���i���j�`
�@�@�@ 2��16���i�y�j
�ꏊ�@���R���p�c�S�����q��
�@�@�@�����h�ɂ��킭�瑑
��Á@�S�������̂ނ�𗬉�c���s�ψ���
�u���Z�b�V�����v
��G�@���͂悤�������܂��B�Q�X�g�̕��́A�����猵���̎ᐙ���n��"�����c�A�["�ɎQ�����ċC�������̂��Ă��܂��B�܂��A����A����������Ȃ���������������Ǝv���̂ł����A���̑��ɁA"���̐�"�������Ղ蒍����Ă���Ƃ������Ƃ͊����ł��B����͊O���̃~�l�����E�I�[�^�[���u����Ă��܂������A���̒n�̐�"���̐�"�����������Ƃ����̂ɂȂ��A"�O���̐�"�Ȃ̂��A�Ȃ�Ęb���������킯�ł��B�l�Ԃƌ������̂́A���ꂾ���Ŋ������킯�Ȃ̂ł��B�n���̐����u���Ă����ƁA����܂ł̓��[���b�p�̐����u���Ă���������ǂƂ����悤�Ȏ��ł��ˁB
�����̒��A�����X���Ă��܂��ƁA����̖�̘b�Ƃ��A�����Ȑ����������Ă��܂��B�����֗����炱�����������������̂��H�ׂ���̂��ƁA�����h�ɂɔ������炱���������������������H�ׂ���Ȃ痈�Ă݂����Ƃ��A"�����c�A�["�ɂ��q����A��āA�Ƒ���n��̒��Ԃ���ė��Ă݂����Ƃ����悤�Ȏ��������Ă����܂����B�n���̕��������̎ᐙ���n�т�������̂͏��߂Ă��ƌ����Ă����܂����B
�匴���Ò�����������ɂł��ˁA�����ɏZ��ł���������A��������ė]�����痈��ꂽ���ƕ����̂��T�O�N�Ԃ肾�Ƃ����悤�Ȏ�������ꂽ�肵�Ă��܂����B�n��ɕ�炷�l���A���͑����ɖڂ������Ȃ������Ƃ����b���������܂����B�����Ƃ悭���߂��肷��ƁA�������������ł���̂���Ȃ����Ȃ�Ă��Ƃ����߂Ċ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ŁA�����́A�����̃p�l���ɂ���܂��悤�ɁA�u�R���������������߂̌𗬉�c�v�Ƃ������Ƃł��B���ꂩ��R�����{���ɐ��������Ă����ƌ������͑�ςȎ����Ƃ������Ƃł��B���̒n��ɂ�����̂������Ȏ��_���猩����_������A�]������m�b�Ƃ̌𗬂̒�����l���悤�Ƃ������Ƃł��B���������ׂ̌𗬉�c�A���̂��߂Ɍ�����̏z�o�ς��l�������Ǝv���܂��B
�n��ɐl�����āA�����𗎂Ƃ��Ă������ɂ��ꂪ��s��ɗ���Ă����Ă��܂��B�n��̒��ɏz�o�ς��Ȃ��A�������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����Đ��E�̒��Œ����Ȃǂ̊C�O�̃R�X�g�������Ƃ������ƂŁA�ǂ�ǂ���{�͋����Ă����Ă��܂��B
�����������ŎR�������������Ă����Ƃ������ƂŁA�c�_��i�߂čs�������Ǝv���܂��B����̃Z�b�V�����̃R�[�f�B�l�[�^�[��3�l�̕��A�R�[�f�B�l�[�^�[�̕��Ɏ����̂���Ă����鎖�Ƃ��A�����̍l�����Ƃ������Ă����܂���̂ŁA�����͂��̂�������b���Ē��������B
���ꂩ��A��قǓ��㑺��������A�e���r�ǂ̃C���^�r���[���āA�u�������炱���܂����H�v�ƌ���ꂽ�ʂł�����A�ǂ����e�����������̂ł͂Ȃ��̂���Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂩ��A�����q���o�g�̉��R�s������ɂ�������Ă��������A���܂łƂ͈�����ڂŁA�����������߂Ƃ������ŁA���R�s�Ƃ�����s�s����㗬�ɁA�̋��ɋA�����ƌ������ŁA�����̑�������ł����Ƃ����邭�炢�̋C�����ō����͘b�����Ē��������Ǝv���܂��B
����ł́A��ԍŏ��̃Z�b�V�����̏H�{����̕�����B�H�{����́A�{�茧�̌܃������ŁA���}���̗{�B����{�ōŏ��ɂ������ł��B�H�{����͗ыƂ�����Ă����āA����ł͂����H�ׂĂ����Ȃ��ƌ������Ƃ����a30�N��ɋC�t�����킯�ł��B�ыƂł͐H���čs���Ȃ��A�l���ǂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B�����������ŁA���}����{�B�ł�����ƁA���ꂪ�������Ă��A���}��������Ȃ��B�ꐶ�������}��������Ă����Ă��炨���A���v�����߂悤�Ƃ������Ƃ������B
����ƁA���}�����Ă��A�n�悩��l���ǂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B���x�́A���}����H�ׂĂ��炤�悤�ȓX����낤�B�����Ă��炨���A�����ăX�L�[��܂ō���Ă����ƌ����������Ă��܂����B���̎��ɂ���āA�u�i�т��J���āA�����ؕԂ����Ă��܂����B���̒�����u�����z�v�Ƃ����X�уc�A�[�����o�����̂ł��B�l�������Ȃ������R�̒�������Ă���A�Ƃ������������ꂾ���̎���5000�l�̐l�����Ă��܂��B���̒��ŐV�����A�����������Ă����B
���������čs���ƌ������́A���͑����̒������J����Č����Ă����B�����ȑ��̒��ň�̎����n�߂�ƌ������͐F��Ȏ����A�������I�ɏz���Ă����܂��B��������̈�ь����������{�Ŏn�߂��̂́A�܃������Ȃ̂ł��B���{�̒��̒��������ς����̂ł��B�������ꂪ���͎Ƃ����悤�ȕ����ɂ����Ă��܂����A�{���͒n��̒��Ő����Ă����q���B����ĂĂ����w�Z���ق����A�s��̎q���B����������悤�Ȋw�Z�����グ�Ă����̂ł��B�H�{����̕�����R���̐��������m�b�Ƃ������̂����b���Ă��������B
�H�{�G�@�͂��A�H�{�ł������܂��B����獡�A���낢��Љ�Ă��������܂������A���́A�R���̕�炵�͖{���̐��E�ł����āA�����Ǝ��R�����߂Ă���ƐF��Ȃ��̂������Ă��鐢�E�ł�����Ǝv���̂ł��B�����̎R�ɏZ�ށA�v����ɐ�l�A�R�ɐl�����Đ�l�Ƃ����킯�ŁA���E�̎҂͂Ȃɂ�����̂��Ƃ����悤�ȋC�����ŁA�����ȊԈႢ�������Ă���Ƃ�����������܂��B
�@�F�l�̂��茳�ɐV���̃R�s�[���͂��Ă���Ǝv���܂����A�u�����ׂ̈Ɂv�Ƃ����A����͖^�V���̃��[�J���łł����A��1�{�Ƃ������ō������Â��Ă��܂��B����́A������8���f�ڂ̕��Ȃ�ł��B�����̋^��������Ă��܂��B
�@������ɂ��k�����̃A�}�S���������Ă��܂��B���}���Ɠ����悤�ȋ��ł����A��������y���ɂȂ����킯�ł��B����������ƌ��߂Ă��܂��ƁA�����Ƃ������̂��������܂��B10���ɂȂ�ƎY�����܂��A������P�O����������ɂ��܂��傤�B�����ė��N3��1���ɂȂ�������ւɂ��܂��傤�B�Ƃ������Ƃł��B
�@�ł��A����������ƁB�Y�����ɂȂ��Đ��n�������͉a��H�ׂȂ��B�a��H�ׂȂ����͂ǂ�����Ēނ�̂Ƃ����^��ł��B���ꂩ��3���ɂȂ��ē~�̗₽�������悤�₭����ł����̂ʼna��H�n�߂�����̃��}�����ł��ˁA���̎��ɉ��ւ����̂ň�C�ɒނ��Ă��܂��B�������ނꂽ���́A�Y�����̃T�r�����Ă��Ȃ��̂ŐH�ׂĂ��܂����B
�@���������1���������Ă܂�܂�삦�Ă��ă��}���̏{�ɂȂ��Ă�����ւ�����������̂���Ȃ����B�Y�����͉a��H�ׂȂ��̂ɋ����ɂ��Ă��d�����Ȃ��̂ł��B����������ւ̎���������ōl����B
�@�����������b�͌���_�Ɗ���_�̈Ⴂ�ŁA�܂��Ɏ���ɍ���Ȃ�����_���܂���Ƃ����Ă���̂����̐����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�R���͂܂��Ɍ���_�̐��E���ƌ����Ӗ��ŁA�V���R�s�[��z��܂����B
���́u�����z�v���e�[�}�ɂ��ċ�B�u�i�ѕ������\�z�𐄐i���Ă��܂��B���b���Ă��킩��ɂ����Ǝv���܂��̂ŁAOHP�̕���p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA������Ȃ��炲�������čs�������Ǝv���܂��B
------------------ OHP�J�n-------------------
�@���ǂ��̃t�B�[���h�A��܂߂̗��A�{�B��A�h���{�݂ł��B��́u�n�L�v�ƌ����Ƃ���́A���h���ɂȂ�܂��B���̒n���т��A�����������h���ّ��ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̎R�͕W���P�U�O�O���̔����������Ă��܂��B���̕ӂ�́A��������čs���܂����悤�Ȍ����ђn�тł������܂��B�w�ǐl������Ȃ������悤�ȏ��ŁA���L�тȂ̂ł��B�����ŁA���}���̗{�B���n�߁A�s�s�ƎR���̌𗬂��l���āA�n��̑��������O���[�v�B�Ƃ��낢��Ȏ�g�݂�����悤�ɂȂ�܂����B
�@�X�L�[��́A�W���P�U�O�O���[�g���A���̎����ϐ��1���[�g�����Ă��܂��B���N�͗�N���ϐႪ�����āA���Ȃ�v��������q����̐��������Ă��܂��B
�́A�Ԏ���ȑO�Ƃ����͔̂����`����l�X�͕����Ă����̂ł��B�u�ʒ��t�����v�Ƃ����āA�W������������~��ČF�{���܂łȂ����Ă��܂��B
���̔����̓����u�����z�v�ł��B�X�Y�|�����Ēʂ�Ȃ������̂ł����A�͔̂n�������Ă������ł�����A�X�Y�^�P�����蕥�������ŗ��h�ȓ��ɂȂ����̂ł��B���������ɏo�����킯�ł��B���̃J�V�o�����܂ŎԂœo���킯�ł��B�R�����A��R�̎R�����オ���č~��čs���u�����z�v�̃��[�g�͊�{�I�ɂ́A40�L�����[�g�����炢�̓��̂�ł��B�����̗ǂ��������������Ƃ����̂����̃g���b�L���O���[�g��12�L����7���Ԃ��炢�ł��B
�����`���ł�����A�y�ɕ��������ł���̂ŁA80�Α䂭�炢�̕��ł����\�����܂��B�������ē��������ōō����88�ł����B�N��5000�l���炢�����Ă��܂��B���̃��C�����[�g���炢�낢��Ȃ��̂�����Ă��܂��B
���̌��̑ꂪ��������āA�Γ�ԃ��[�g���Ƃ����낢��ȃ��[�g������Ă��܂��B�u�����z�v�́A�����т̑f���炵���Ƃ���ŁA���ǂ��C���X�g���N�^�[�́A���R�̘b�A�A���̐����A�����̘b�����Ȃ���K�C�h���Ă����܂��B���500��ނ��炢���{�ؖ{�ނ������ł����A�قڑS�������o����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�����20�����炢���܂����A���̒��łQ�A�R���ʂ͎����ŐA���}�ӁA���̂��}�ӓ����Ă��āA���q����q�˂�ꂽ���ɐ����ł��Ȃ��̂͂��Ⴍ���ƕ����Ă��܂��B�R�̐N�B�����q�l�ɑ��Đ搶�ɂȂ��Ƃ������Ƃł��B����Ŕ��Ɏ��M�������Ă��āA�s���������ɂȂ��Ă��܂����B
�G�߂��ƂɐV�ƍg�t�ƐF�X�ς���čs���킯�ł������܂��B���N�̏o���������������Љ�����Ǝv���܂����A�u�����z�v������Ă���Ƃ��ɁA���i���Ȃ�Ȃ��������邱�ƂɋC�������̂ł��B����ŁA�A���ɏڂ����搶���ƕ����Ă���Ƃ��ɁA�u���̍��Ⴄ��Ȃ��ł��傤���ˁv�Ƃ����ƁA�u�]�˔ފ݂��낤�v�ƁB
�v����ɁA���̊�{��Ƃ����̂́A��̂X��ނ��炢�����Ȃ��̂ł��ˁB���S��ނƂ���̂́A��z�ō��o�������Ȃ̂ł��B�����тɂ���̂́A���̊�{��A����Ȃ킯�ŁA�V���|�W�E���ŐF�X�����������čs�����ɂȂ�̂ł��B�����͉ԍX�����ɒ����A��4�Z���`�قǂ���܂��B���邢�͂��̂߂��ׂ����ɓˏo���Ă���ƌ������ƁB�����͂��̃K�N���i�Ƃ��j�̌`���S�����̍��ƈႤ�ƌ������ƁB�ؕЂɔS���������ł����Ƃ˂˂��Ă���B�F�����ɂ��ꂢ�ȃs���N�̍��Ȃ̂ł��B
����ׂčs�������ɂ�͂�Ⴄ���A���̒n����L�̌ŗL�̍��ƌ������Ƃ�������܂����B�X�L�[��̗L��W���P�U�W4���[�g���̌���R���甒��R�t�߂Ɏ������Ă��邱�Ƃ�������܂����B69�{�A���݊m�F�o�^���Ă��܂����A�ォ�玟�X�����萔�S�{�ɂȂ邩���m��܂���B
���́A���ɑ傫�ȖƂȂ��Ă��܂��B�悭���͒��������Ȃ���Ƃ����܂����A����͐l�H�̃T�N���̃\���C���V�m�Ȃǂł����āA���̊�{��A����Ƃ����̂́A150�N200�N�ȏ�������Ă���B���a��50,60�Z���`�Ƃ����̂͂���ɂ���܂��B���O�����܂��āA�a���ł́u�L���^�`���}�U�N���v�Ƃ����܂��B
���́A���̖��O�������Ă��܂����̂ł����A�w���́u�Z���T�X�E�T�[�[���e�B�E�o�@�E�A�L���g�E�C�v�ƁB�Z���T�X�Ƃ����̂́A�����̎��ł����āA�T�[�[���e�B�Ƃ����̂́A��R���n�ŁA�A�L���g�E�C�Ƃ͏H�{���������������Ƃ������Ƃ������ł��B����͍��̉Ԃ����ɂ��ꂢ�ł��ˁA�����ɐA���悤�Ǝv���A�ږ�����������肵�Ă���̂ł��B�����ł����藦���ǂ��đ��₵�Ă���Ƃ���Ȃ�ł��B
����Ƃ����ЂƂʔ����̂��������܂��Ăł��ˁA���͒n�}�ɂ��Ȃ����̑���������Ƃ������Ƃł��B��̍�����150���[�g���A�O�i�ɂȂ��Ă���̂ł����A���ꂪ��ԏ�̑�ŁA������75���[�g������܂��B����������������Ȃ��A�������Ƃ��Ȃ��Ƃ����킯�Ȃ̂ł��B
�Ȃ����Ƃ����ƁA�R�̒��Ɉ͂܂�Ă����Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�B��̓`���������Ă��A��������������Ƃ��Ȃ������ƁB��������悤�Ƃ������ƂɂȂ������������́u�����z�v�ł��B��R�̎R���Ƀg���b�L���O�œo�������ł��B
�����ɂ͋G�߂ɂ��Ɛ��̉�����������Ƃ����\������̂ł��B�R�̒���Ő��̉�����������͂����Ȃ��B�������A���������\������̂́A���������Ƃ������ƂɂȂ�܂��āA�o�ዾ�Œ��ׂĂ݂���ł��ˁA��������ƁA�������������Ⴎ����ɂȂ��Ă��鏊������̂ł����A�������������ƌ������ƂɂȂ�܂����B������Ɣ������̂������A����͑�ɈႢ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA�T�������悤�ƌ������ɂȂ�܂����B
�@�T������g�D���ĒJ����o���Ă����āA���̖������̏����オ��܂����A������x�ƒʂ��ƒT�������F��Ȃ����������Ă܂��B������o���đ��˂��~�߂��킯�Ȃ�ł��ˁB���̎��͖����ŊR���悶�o���������������ɂ͓�x�ƍs�������Ȃ��Ƃ����قǕ|�������B������͂������A�A�鎖���o���Ȃ��̂ł��B
�@�R�̒������邮����Ȃ��疽���炪�����ƋA���Ă����̂ł��B�ォ��n�}�Ō��܂��ƁA�t�̕�����s���ƊȒP�ɍs���鎖���������̂ł��B�����A�l�������������Ȃ��������Ƃ���ŁA�n���̗t���������Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ŁA�s���Ȃ��̂ł��B����ŁA�v�l���낵�Ȃ��烋�[�g���J���܂����B
�@���NJR�̌��������͏b�������ǂ�Ηǂ��ƌ������Ƃ��킩�����̂ł��B���ł�30�����炢�ŕ����čs����悤�ɂȂ�����ł��ˁB�݂�Ȋ������܂��āA��J�������悤�ƌ������ɂȂ����̂ł��B
�@����͑�1��̑�J���ł��B�_�傳��ɏj���������Ă�����āA�e�[�v�J�b�g�����đ�J�������܂����B���̎��Ɂu��ɕ����鎌�i���Ƃj�v�Ƃ����̂�����ĊF�ŘN�ǂ����̂ł��B���̊�����Y�ꂸ�ɂ��悤�ƁB�ǂ�Ō��܂��B
�@�u��ɕ����鎌�i���Ƃj�@���Â̐̂��A�ŗt�R�����[���A�����i���������j�̊┧�ɓ{���Q�����e�z��A������W�߂ėV���錶�̑��B���Ȃ��́A�f�R��ǂ����ɂ������Ȃɐl�Ԃ̐N�������ݑ����āA���z���������悤�ɔ��������̎p���B���Ă��܂����B�l�m�ꂸ�A�b�����ƋY��Ȃ��玩�R�̉c�݂��c�X�Ƒ����A�I�v�̗��j�����X��B���Ȃ��́A���炩�Ȑ���₦�ԂȂ����������Ĕ����������݁A�J���Ƃ������̌��ɍr�p���������R������Ă���܂����B
�@���B�͂���܂ŁA��̓`�������p���ł��܂������A���̂��сA���Ȃ��ɋߕt�������Ƃ����肢������Ă���A�����琁i���������j���邱�Ƃ��ł��܂����B�_��I�Ȏp�ŏo�}���Ă��ꂽ�j�O�O��N�܌��\���������B�͏I���Y��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���B�́A�n���a���̃G�l���M�[���߂ĎW�R�i����j�ƋP�����Ȃ��̔������Ɏ䂩��A���Ȃ��ƌ������邱�Ƃ̊��т𑽂��̐l�����ɕ��������������Ɗ肢�A�{����J���������Ȃ��܂��B�����̐l�X���A���̐��n��K��A�I�v�̎��R���t�ł�G�l���M�[�ɁA�S�̔�������A������͂�h�点�邱�Ƃł��傤�B���B�́A���̎��R���������A�������A���R�Ƌ��ɐ����邱�Ƃ𐾂��܂��B��킭�A������K���l�X�Ɉ��S�Ƒ厩�R�̃p���[��^�������A�����邱�Ƃ̑f���炵��������������Ƃ��B�j�O�O��N������\����@�����z�̗��j�Ǝ��R���l�����v�ƁA�����I�ɏ����Ă��܂����킯�ł��B
�@�ʐ^�������V���̑S���ł̈�ʂɑ傫���ł܂����̂ŁA��ςȔ��������ŁA���ꂩ�炢�낢��Ȏ�ނ����肵�āA��u�[���ɂȂ�܂����B���R�����߂Ă���Ƃ������Ėʔ����������X�ƋN���Ă���Ƃ������Ƃł��B
----------------- OHP�I�� -------------
�@���R�������ƌ��߂Ă���ƌ����Ȃ����̂�����Ɍ����Ă���B�������A��̒�������Ȃ���A���̒J�Ԃɂǂ��������킪���邩�ȂƂ����v���ŕ����Ă����킯�ł��B
�@���������u�i�сA���t�L�t���т̐X�Ƃ����̂́A�J�Ԃɂ���̓N���~��V�I�W�������A����͐����Ȃ��ƈ炽�Ȃ����́B�����̐��̒��������c���ɂ������蒣���Ă���A����Ő����������Ǝ���Ă���Ă����킯�Ȃ̂ł��B
�@������l�H�т������Ă��܂�������삪�r�p�����B�k�������̐X�����̖{���̎p�ɖ߂��Ă������Ƃ��邱�ƁA���ꂪ���͑厖�Ȃ̂ł��B�R�S�����C�����鎖�͕s�\�ł������܂�����A���߂ĒJ�쉈�������ł������ɂ��鎩�R�̌��̎p�ɖ߂��Ă������Ƃ��鎖���厖�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�ƌ������Ƃ��A���[���ƌ��߂Ă���ƌ����Ă���킯�ł��B
��G�@�݂Ȃ����Ă��Ĕ��Ƀ}�j�A�b�N�Șb���Ǝv��ꂽ���ƂƎv���܂��B���̖؈�{�A���ɂ���Ȃɂ������̂��ƁB�������ł��ˁA�����������ɂ�����������Ƃ�����܂����B��邽�߂ɂ́A�X�L�[��̘b�ł��A10�N�ԁA�ϐ�ʒ���������ׂɖ���5���ԂƂ������Ē��������������ł��B��̖{������邽�߂ɂ́A���ɂ�������ώ@������ƌ������Ƃ��H�{����͂��Ă���B
�@���O�ɂ́A�V��������������킯�ł����A���̂܂��ɂ������ώ@�͂Ƃ������w�͂�����킯�ł��B�����ȏ��ɂ�������Ă���B�H�{����ɓ����Ē��������Ǝv���̂ł����A����A�؍H�̘b�ȂŊߋ�̘b�𐼎R���炵�Ă��������܂������A�H�{������Ƃł��ˁA���ɏ��ɉ��̐l���������ނ̂ł��B
�@�Q�l�ɘb�����Ă��������B���낢��Ȃ��Ƃ����鎞�ɕK���n��̐l����������ŘA��čs���B�������čs���A�F�����C�ɂ�����Ƃ��������������B�������Ȃ��ƁA���̏H�{����̔��Ƀ}�j�A�b�N�Șb�ŁA�����ǂ������ƌ������ɂȂ�̂ł����A���̍���{���݂�Ȃ�������ɂ��čs���A����F�ŒT�����Ƃ��Ȃ��ƁA�������Ȃ��B
�@����ŁA���낢��Ȃ��Ƃ����鎞�ɁA����̐l�ƈꏏ�ɕ��������Ă����Ƃ������Ƃ��ǂ�����Ă���̂��錍�������Ă��������B�ǂ�����ďZ���̐l�B�����̋C�ɂ����Ă��܂��̂ł��傤�H�Ⴆ���_�y�̘b�������Ȃ�ł��B���_�y�͉����Ԃ�����̂ł��������H�@�@
�H�{�G�[��8�����珉�߂Ė閾���܂łł��B
��G���_�y�A���X�Ƒ����Ă����������B�݂�ȂŒn���̐l���x��̂ł����A�Ȃ����̂悤�ɒn���̐l�����̋C�ɂȂ��āA�ꏏ�ɂ���čs����̂��Ƃ����悤�Ȏ��ɂ��Ă��b�ɂȂ��ĉ������B
�H�{�G���������́A�ЂƂA�X�L�[��ł��ˁB�X�L�[������Ȃ��Ƃ��̑��͂����Ȃ��Ȃ��Ƃ�����@������Ȃ�ł��B��B�ň�ԐႪ�����̂́A���͒n���̎����B�̏Z��ł���Ƃ���ŁA���̊O�ɂ͂Ȃ��Ƃ����������܂����B�s���͂Ȃ��Ȃ������Ă���܂���ł����B
�@���낢��Ȏ�g�݂��������ɂ킩�����̂ł����A�R�̐N�����Ƃ����̂́A�R���̍s���~�܂�Ƃ����̂͂���������]�������Ƃ��낾�ƊF�v��������Ă����ł��ˁB�����ŁA�Ȃɂ��������낢���Ƃ������Ȃ����ȂƂ������ƂŁA�݂�Ȉꏏ�ɂ��Ă��Ă���Ă��ꂽ�킯�ł��B
�@�X�L�[�ꂪ�����������ɂ���āA���̊F����̌��C���o�Ă��āA�����̒n���������ďЉ�o����悤�ɂȂ����킯�Ȃ�ł��ˁB��������A���������O���[�v���������o�Ă�����ł��B���A�u�����z�̗��j�Ǝ��R���l�����v���Ƃ��u��̌܃����������O���[�v�v���Ƃ��F��ȃO���[�v���ł��Ă��܂��āA�����łȂɂ���낤�Ƃ���ƁA�݂�Ȉ�ĂɃe�L�p�L�Ɠ����Ă����Ƃ����d�g�݂��o���܂����B���ꂪ�傫�Ȃ��������ł����B
�@�������A�X�L�[��J���ł�܂ߗ{�B�ꂪ�S�ł����ȂǁA���s������܂����B����ł�����Ƃ����N�w���K�v���Ƃ������ƂɂȂ�A�u��B�уu�i�������܃����\�z�v�Ȃ���̂��l���܂����B����ɂƂ肩����͂��߂Ă���v�����̂ł����A������������A�̂̔n�ŕ������Ƃ�������������Ȃ����Ȃƍl���Ă����Ƃ���A����푈�̎��ɐ��������������Ă���������q�˂Ă������������̂ŁA���n���ē�������ł���B
�@�����|�������킯�Ȃ���A���ɋ�J���āA�����A���Ă����Ƃ��͈Â��Ȃ��Ă����̂ł����A���̎��ɕ����������`���̓����ƂĂ��������������̂ŁA���߂Ă��̃��[�g����������������낢���낤�ȂƎv�����킯�Ȃ�ł��B
�@�A���Ă��Ĕӎނ��Ȃ���A���̓����F���s�N�j�b�N�p�ŕ����Ă���Ƃ�����ʂ��قɕ�����ł��Ă��܂��āA�n���̃O���[�v�̐N�����Ɂu���̓��͂�����v�Ƙb�����Ƃ���A����1�T�Ԃ�10���キ�炢�ɂ̓����o�[20�l���炢�������ɍs���Ă��܂����̂ł��B
�@����ŁA���ۂɌ��Ă��������o�[���u����͂�������v�u���낤����Ȃ����v�Ƃ����b�ɂȂ��āA�s���ɑ��k�ɍs�����̂ł����A�S�R���͂��Ă���܂���ł����B����Ȃ���������B�ł�낤�ƌ������ɂȂ�A�X�Y�^�P������Ƃ��ĕ�����悤�ɂ����B
�@�܂��V���|�W�E�����J�Â��悤�Ƃ��낢��Ȑl�ɐ��������܂�����A�n���̐V���Ђ̎В������A���̕��A�����̎R�̍D���ȕ��Ȃǂ��܂��܂ȕ��X�������������Ă���܂����B�����ŁA���R����^�C�~���O�����v����đ�1��̃V���|�W�E������悵�܂����B
�@���ꂩ�疈�N1��2��ÂV���|�W�E�����d�˂Ă����āA�����ɂ����Œn�����N�B�ƈꏏ�Ɋw��ł䂭�Ƃ����X�^���X���Ƃ�A������J��Ԃ��Ă��܂����B�̔��ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����A������ƋL�^�����ă��[�v���Ő������āA�F�̏��Ƃ��ċ��L��}���Ă䂭�B
�@���̎��ɂ���ؐ搶�ɉ��x�������b�ɂȂ�܂��āA�[�������V���|�W�E�����J�Âł����킯�ł����A���̎��X�Łu���̎��̃V���|�W�E���͂������납�����ˁv�u���������ǂ������ˁv�Ƃ����z�����������A�܂����������̂��y���݂ŃX�^�b�t���݂�ȓ����Ă�����ł��ˁB
�@������������{�I�ɖʔ����e�[�}�������āA�u�݂�Ȃǂ����H�v�ƒ�Ă���ƁA�F��Ȃł�[���Ƃ�����Ⴄ�B���������������ł́A�g�D���o���Ă����Ƃ����Ƃ��낪�ǂ��낤�Ǝv���܂��ˁB
��G�@�H�{����̂Ƃ���ł́A�{���ɂł��ˁA�S�C�����̗t���Ƃ��n���̕��ʂ̕�������V���|�W�E���Ɍ���Ă݂���A����b�ɏo���w�p�I�ȍ��̒����ȂǁA�����������n���Ȏ��������Ƃ���Ă����܂��B
�@�������������������Ƃ�n��̐l�B�ƈꏏ�ɂ���Ă䂭�B�Ⴆ�A��������Ă����������؍H�̂�������Â�����H�{����͖ʔ����ʔ����Ƃ���������Ă��āA������ǂ�����ĊF�ɍL�߂Ă������Ƃ�������₦���l���Ă����܂��B���������Ƃ��낪��q���g�ɂȂ邩�ȂƎv���܂��B
�����ŁA�~������ɘb���������������Ǝv���܂��B�~��������Ǝ��̎��_�ŏH�{����̂悤�ɍ��Ƃ���Ƃ��ʔ������̂�����킯�ł��B
����̐ԉ����̊ԏ邳��̘b�ɂ���������ł����A�Ⴆ�Α匴�̒��ʼn����������炻����ǂ�����ĊF�ɔ���₷���`������A���Ԃ��������肵�čs���̂��B���̂悤�ȁA�~������̍ޗ���������@�ƁA�R�~���j�P�[�V�����̑��x�Ȃ�Č��t�ɂȂ��ł����A�������ǂ�����ĊF�ɓ`���Ă䂫�A�ǂ��������ɖʔ����邩�Ƃ������Ƃ��������������ł��B
�����炭���̊�{�͂ł��ˁA�~�������{�̒���n�悪�����ʂ��Ă����ɂ́A���{���̂��̂��������낭�Ȃ邱�Ƃ��K�v�ŁA���̂��߂ɂ͎����̒����y���܂Ȃ�����A�܂�A�����̐l�����y���܂Ȃ�����A�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB�����̒����y����ł����A�~������I�Ɍ����Ȃ�Ζϑz�������悤�Ɋy����ł䂭�B
�����������ɔ�Ă䂯��悤�Ȏ��̃X�e�b�v������Ǝv����ł����B�Ⴆ�ΐԉ����Ƃ��A�l���\�h���}�Ƃ��ł��ˁA�n��̉ۑ�E��肪���邯�ǂ�����ǂ�ǂ��Ȃ�Ɋy����Ŕ������Ă������@��~������ɘb���Ă������������Ǝv���܂��B
�~���G�@������������ɂȂ�Ƃ͎v���Ă���܂���ł����̂ŁA�����������Ă��܂���ł������A�����炵����������̂��v���o���܂����̂ŁA������ƊF����S���ɂ͍s���n��܂��A���Ɉꖇ�Âz���Ă��������B
�@�����̂���Ă鎖�ɂ��Ď����ŕ��͂�����ł�����ǂ��A�����͓y���ɏZ��ł��܂��āA�y���̕��i�ł��ˁA�����̏Z��ł���Ƃ���̕��i�́A�������ƈႤ���A�X�ƈႤ���A�k�C���Ƃ��Ⴄ�킯�ł��ˁB����ȈႢ���������ق����o�ς�����������ł��傤���A�l�Ԃ̍��A���ꂪ�Ⴂ�܂��ˁB
�@�ł��X�s���Ă��ǂ���������ƁA�������Ă��v���܂��B�ʂɒÌy�O�������Ȃ���Ăւ�ȂƁB����������ƐႪ�~���Ă���ȂƂ��ꂭ�炢�������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂�����ł���ˁB
�@�����l���Ă݂�ƁA���̏Z��ł���y���ł́A���t����{�ނ�ł�����ނ��Ă܂����ǁA����͂ǂ�ǂ�p�Ƃ��Ă����Ă�킯�ł��ˁB������p�D�A�܂��{�ނ肷�镗�i���y���̕��i�Ȃ̂ɂ��ꂪ�ǂ�ǂ�Ȃ��Ȃ��Ă����Ă��܂��B
�@����ŁA���Ƃ��Ắu�Ȃ�Œm�b�g��ւ�v�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B�ǂ����������Ƃ����ƁA���̈�{�ނ�̕��i���ǂ�ǂ��Ȃ��Ă���A�D�����ǂ����ǂ������Ȃ��Ă��Ă���A�Ƃ����V�����L���ɂ��Ă���B�ǂ�ǂ�ǂ�ǂ�ʖڂȂ�����ł���A�ʖڂȂ�����ł�����Ė���������ł��ˁA�V���ɁB�Ȃ�őʖڂƂ����菑����A�l����������̂���A�Ƃ����ӂ��ɂ����Ǝv���Ă܂�����A���t������Ă�����ł��B�l�̂Ƃ���ɁB
�@�D���牺��Ă�����{�ނ�͂�����A��ň�{��{�ނ邩��ƌ����܂��āB����̘b��ɏo���u��d���v�ƈꏏ�ł���B�Ԃł��[���Ƃ�����߂��������ł����ǁA��{��{��d���ł��B��d���͑ʖڂɂȂ��Ă�Ƃ�������A�O�s�����ɂ����ƌ�̕��ŏ������悤��Ƃ������Ƃ��l�����̂ł��B
�@����͘m���g���Ƃ������Ƃł��B�m�Ƃ������͓̂c�ɂɈ�t����܂��B������m�ŏĂ����^�^�L�A�u��{�ނ�m�Ă��^�^�L�v�Ƃ������̂��f�U�C�����ď��i�ɂ��܂����B
�@���̋��t�͂͂��߂͉Ƒ�3�l�ł���Ă܂����B���ꂪ�S���ɔ������n�߂��肵�Ęb����Ă��8�N�Ԃقǂ�20���~�̊�ƂɂȂ��Ă��܂�����ł��B�܂�A������ނ��Ęm�ŏĂ��ă^�^�L�ɂ܂ʼn��H���ŏI�I�ɐ��i�ɂ��ē͂��悤�Ƃ������Ƃ���������Ȃ�������ł��ˁA���܂ł́B
�@�f�U�C�����Ƃ��p�b�P�[�W�̍��m�炵���Ƃ������������ɂ��Ă͖l�����͂�����ł��B���̎��ɖl�̓R�~���j�P�[�V�����Ƃ����̂͒Z�����������ǂ��ƍl���܂����B����ł��̏��i�ɂ͂������t�����܂����B�u���t���ނ��ċ��t���Ă����v�������܂��ƁA�ŒZ�����ŏ��i�̃R�~���j�P�[�V�������o���܂��B�u���t���ނ��ċ��t���Ă����v�ƁB
�@�����ނ��āA�����Ă������˂ƁA�킩��₷���ď��k�͂��Ȃ�Z���ς�ł��܂���ł��B�܂�A�p�b�P�[�W�����邾���Łu���Ȃ����Ђ���Ƃ��ċ��t����ł����H�v�u�����ł��v�u���Ȃ����Ă�����ł����H�v�u�����ł��v�u���ŏĂ�����ł����H�v�u�m�ł��v�Ƃ������Ƃ��S���킩���Ă��܂���ł��B�����������̂����i�̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ������Ƃ��Ǝv����ł��B
�@���Ȃ݂Ɂu���t���ނ��ċ��t���Ă����v�Ƃ������t�͂������m�ł͒蒅���Ă��܂��B���ꂾ���ŁA3�l�ŏĂ��n�߂������̃^�^�L�̏��i��8�N�Ԃ�20���~�ɂȂ��Ă����܂����B�����炻�̐l�̑D�͎c������ł��B�Z��5�l�ł����D��2�ǎ����Ă����ł��B���ʓI�ɁA�J�b�R�悭�����A�l�͂��̕��i����c�������ȂƂ������ƂɂȂ�܂��B�y���̈�{�ނ�̕��i���c������ł��B�ǂ������ȂƎv���܂��B
�@���āA���ɘb���܂��̂́A�������Ŕz���Ă���������������Ă������������Ǝv����ł����A����̂������t�̈�{�ނ�̊�n�A�y������`�ׂ̗ɑ劃���Ƃ�����������܂��B������4�L�����[�g���̍��l�Ə���������܂��āA���n�Łu���l���p�فv�Ƃ����̂��v���f���[�X���܂����B
�@���̎�����14��ڂƂ����Ă���܂�����A14�N�O�̎��ł��B14�N�O����n�߂���ł��B�����̓��]�[�g�@���A�n�R���m�s�����łƂĂ��o�u���[�Ȏ���ł����B�l�͂���Ȃ��̂Ɍ��C�������Ă܂����B�����ȏ����Ȓ��ɂ��ł������A�ςȌ��������݂���Ă��܂����B�����Z���Ƃ��ē{�邵������܂���ł����B
�@����ŁA����Ȃ����牽�ɂ�������������Ǝv���܂������ǁA����ʼn��ɂ�����̂�́A�{���ɉ��ɂ����Ȃ���ł���B����Ŏv�������Ă����̍��l��2�{�̍Y�𗧂ĂĂł��ˁA����Ƀ��[�v�Ő��������悤�ɂ��Ă����ɍ�i��݂邵�Ă����킯�ł��ˁB
�@����͂₪�āA���֖߂��܂��B�Y�ƃ��[�v����������猳�ɖ߂����ł��B�����Ă݂����͉��݂ł��B���ł��o���܂��B�ł������ɂ���͑傫�ȍ\�����ł������ł��B���ꏇ�Ԃɂ����ƕ��ׂĂ����ł�����ǂ��A500���[�g����܂ł���܂�����ˁB�����ł����\�����Ȃ�ł��B
�@�܂�A����"����"��������ł��B�����������Ƃō\��������������ł��ˁB�������A����͉���������ł��B����ōY�ƃ��[�v���Ă��܂��Ό��ɖ߂�܂��B
�@���̂Ƃ��ǂ������V�X�e������������Ƃ����܂��ƁA�u�S������G�������Ă��������B�ʐ^������đ����ĉ������B�G�������Ă��ꂽ��A�ʐ^������đ����Ă��ꂽ�肵����A�������v�����g���Ăs�V���c���쐬���ēW�����܂��B�����ēW�����I������炻��T�V���c����ċM���̌��ւ����肵�܂��B����͎��������̃I���W�i���s�V���c�ł��v�Ƃ������̂Ȃ̂ł��B
�@����͍����ł����B�������n�������킯�ł��Ȃ��S����������猳�ʂ�ɖ߂�܂��B�傫�ȍ\���������Ă������ʼn����Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���g�������Ă��������K�I�ɂ�������o���āA���ʂ�ɖ߂���V�X�e����l�͍������ł��ˁB�l�����̃v�����𗧂Ă��Ƃ��ɂ͒m��܂���ł������A�������̒��ɂ̓��]�[�g�@�̖��̌��ɊJ���Ǝ҂��ނ�̃v�����������Ă��Ă��������ł��B
�@����̌v��ɂ́A�S���t��A���]�[�g�z�e�����݂���A�猩����~�^�̃v�[��������A�T�C�N�����O���[�h��������Ƃ������Ƃ����������ł��B���̍��l�܂ł��ł��ˁA���������v�����ɂ���Ă��̕��i����������̂ɂ��悤�Ƃ��Ă�����ł����ǂ��A����4�L���̍��l�̕��i�͐l������Ă��ł��ЂA��������炱�̂܂܂ł������������ȁA�Ɩl�͎v�����̂ł��B
�@���������̂܂܂ł������Ƃ����������ƁA���������Ă��邾���̐l�Ԃ݂����ł�����A��������Ȃ��đO�����ɍl���āA���̌��ʁA�u���l�ɂЂ�Ђ炳����v�Ƃ����v�����𗧂āA�i�߂Ă������̂ł��B
�@�₪�Ď��オ�ς��o�u�����͂����܂����B���������Ƀ��]�[�g�v�������i�߂��Ă�����ǂ��Ȃ��Ă������낤���B14�N�O�Ƃ������̓����͑S���킩��Ȃ��ł���B������o�u���̎��Ƃ����̂́A�݂�ȋ��ׂ��Ă��鎞�ɂ������������Ă�ꍇ����Ȃ��Ƃ�������ł����B
�@�������A����1�S�A�T�N�ŕ������͋��炭������ɕς���Ă��܂����B����ɑS�����炱���������l�ς������Ă��鎩���́A���R�ɂ���Ă��鎩���̂Ȃǂɐl���W�܂�n�߁A�ߍ��̓G�R�~���[�W�A���Ƃ��A����͂���14�N�̊Ԃɍ��ꂽ���t�ł�����ǂ��A���l���p�قƂ����R���Z�v�g�ɋ߂����Ƃ�i�߂Ă���A����Ȏ���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
����܂ŁA2�̓y���̕��i���e�[�}�ɂ��Ă��b���܂������A���ɂ��`���`���d�ԕ҂Ƃ��A�l���\��҂Ƃ��A�q�m�L�̐X�҂Ƃ��A���낢��b�͂����ł��B
�ԉ��������̒���1�ł��B���̒��ł́A���C���ŊF�ʼn�c���Ă���ł����ǁA�~�ɂȂ�Ɗ�����������قɍs�����Ƃɂ�����ł��B�g�����A�V���ނŏo���������قł��B�ł��l�́A�����قŒ��̂��Ƃ���ׂ�̂͌���������ł��B���ԕ����s���[�s���[�����Ċ�����������ٍs������Ȃ��ɁA���̕��C���ł���Ă�˂�~�ł����[���Ƃ����Řb�����ƌ������ŁA�Δ�����������ł��n�߂܂����B
����ς�A�����̕��̍l�������f�U�C������Ƃ����̂͂����������Ƃ��ƌ����Ă���킯�ł��B������������������������Ȃ��Ȃ�ĒN�������܂��ǂˁA�l�͂����v���܂��B
���̃p���t���b�g�ɂ��鍻�l���p�قł����A����ɂ����͂�����܂��B�u���B�̒��ɂ͔��p�ق�����܂���B���������l�����p�قł��v�Ƃ���2�s�ł��B����̂����̃^�^�L�̌��́u���t���ނ��ċ��t���Ă����v��2�s�ł��B���̘b�ɂ��S���Z�����t�������āA����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�ɁA�����̒����ǂ��Ȃ肽�����A�����̉��̂��̂��y���݂����Ǝv���āA�l�͂����Ƃ����f�ނ�n���̋��t�ƈꏏ�Ɋy����ł��B�����Ă��̍��l�Ƃ������i���y���B���邢�̓`���`���d�Ԃ��y���B�܂�A�����̖ڂ̒��ɓ�����̂͂����������Ɋy����ł������Ǝv���Ȃ������Ă邾���ł��āA�{���͂���܂葺�������Ƃ����������Ƃ��v���ĂȂ���ł��ˁB
��G���̔~������́A�u���l���p�فv���ł��ˁAT�V���c��W�������ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��č��l���̂��̂���p�قɂ���A�Ƃ������ɔ��z���ǂ�ǂ�ǂ�ǂ�o�Ă����ł��B�C�Ɍ~���������A�ƂȂ�Ƃ��̌~�����p�ق���Ȃ����A�Ƃ������ɁB
�@����ƌ~�E�H�b�`���O�Ƃ������ƂŁA�c�A�[����悷��ƂȂ�܂���̐V�����Y�Ƃ��o�Ă���Ƃ����킯�ł��ˁB��������l���p�ق̍�i�����ɍs���Ƃ����킯�ł��B���ꂩ�獻�l�ł����烉�b�L���E������܂��̂ŁA���̃��b�L���E�����ɂ���ƌ~�Ɍ����Ȃ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł�����u�����������v���Ĕ����Ă��ł��ˁB�����ɉԂ��炢����Ԍ����y���ނƂ��A�����������������ǂ�ǂ����āA���A�����B���y����ł����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��d�v�Ȃ�ł��B
�~���G�@��̂��̂�^���̎��������ɂ���Ă����炢�낢��Ɩʔ��������o�Ă����ł��ˁB�Ⴆ�A�����̊C�݂ɂ̓S�~����t����Ă����ł��B�ȑO�͊F�ł��̃S�~���W�߂ďĂ��Ă���ł��B��������B�ł��悭����ƂƂĂ��������낢�̂��������Ă����ł���ˁB�����邽�тɂȂ�₱��A�Ȃ�₱����Ă����Ă���ł��ˁB����ŁA�ʔ������̂��W�߂ĕY�����W�Ƃ����̂����n�߂܂����B�R�₵����S�~�A���ׂ�Δ����قɂȂ�܂��B
�@����������\�N�ȏ㑱���Ă��܂��B���̒��̐E�����ł��ˁA�������A�����ŊC�݂ɍs���ăS�~�i�Y�����j���E���Ă邤���ɁA���̊Ԃɂ��Y�������m�ɂȂ����������ł��B�����\�Ȃ�N���E�������Ă܂�����ˁB����ŁA���N�ł��ˁA���ɓ��{�Y�����w��Ƃ����̂𗧂��グ�Ă��܂��܂����B�C���^�[�l�b�g�Ȃ����p���Ă��܂��B
�@�Ⴆ�ΐ�䂠���肩��ł��ˁA���̕Y�����Ȃ��낤�������ƂɂȂ�ƁA�Ȃ�Ƃ��̍���łƂ��A�w�p�I�ɂ͂ǂ��Ƃ��A���낢��Ƃ����ł��B�ʔ����̂́A����������ɂˁA���˓��C�̕Y�������������肷���ł���B�Y�����ɋ���������l�́A���{�Y�����w��̃z�[���y�[�W�J���Ă݂Ă��������B�Ȃ��낢��Ȏ�����Ă܂���B
�@�܂��A��������������܂������ǁA�C�݂̍��n�Ń��b�L���E��������܂��āA���b�L���E�̉Ԃ��H��11�����ɍ炫�܂��āA���ꂪ�ނ��Ⴍ���Ⴋ�ꂢ�Ȃ�ł���B���ʂ̉Ԍ��͏㌩�܂����ǂ��A���b�L���E�̏ꍇ�͉������ł����ǂˁB������u���b�L���E�̉Ԍ��v�Ƃ������������ŁA�{���Ƀ��b�L���E�̉Ԍ��ɂȂ��Ă��܂���ł��ˁB
�@����A�F�{�̔����������b�L���E��H���܂������ǁA���̃��b�L���E�����܂ł̂��̂Ǝv�킸�ɁA�u���A�Y��ȉԂ�A���x���_�[�̉Ԃ��������v�Ǝv�����v��̘b�ł����āA�v����������u���b�L���E�̉Ԍ��v�Ȃ�ł���B�����炱�̏����ȃR�[�X�^�[�݂����̂ŁA�u���b�L���E�̉Ԍ��v�Ƃ�����������邾���ł���Ȃ�̊��A�C�f�B�A�ɂȂ��Ă��܂��܂���ˁB���������̂́A���ɂ���t����܂��ˁB
�@�����炱�����̂͂ł��ˁA�������̖��ł��āA�l�͍ŏ��s�V���c��݂邳���Ăƌ�������₯�ǁA���̒��̖���̕��������ɂ́u�����̂Ƃ��ɍs���Đ������Ă����Ȃ�����A�l�炪�s�V���c�݂邳���Ă��Č����ւ�v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�l���������ɍs�����킯�ł��B����ŁA�������Œ��������O�ɂ��āu���݂܂��̂�����Ƃs�V���c���Ђ�Ђ炳���Ă��炦�܂��v�Ƃ����Ă�������A�����Ŗl�͎����������āA�Ƃ����Ɂu�~����i����Ȃ��ł����B�����āA���l���p�ق͓��̒��ɂł��鋐��Ȕ��p�قł���v�u���̒��S�̂��݂����ȑ傫�Ȕ����قȂ�ł���v�ƌ�������ł��B
�@����́A���̒��ɍ�邾���ł��B���������i�͉��ł��傤�B��������i�B���Ɍ����Ă�~����i�B������������i��B���b�L������i��B�Y��������i�ł���Ƃ������ƂɂȂ��ł��B
�@�����������ɁA�����̍l���������ĂA�v�������������̂��A�Ⴆ�S�~�Ƃ������v���Ă����A�Y�����w��ɂ܂łȂ��Ă��܂���ł��B
�@�����̂��̂̒��S�����߂�A���ꂾ���ł��Ă��܂��킯�ł��ˁB���S�������̂ɂ����ǂ����ɍs�����Ƃ��Ă���̂��n���̑��݂����ɖl�͎v���Ă��܂���ł����A�����Ƃ��Ă͂���Ȃ����ł���Ă��܂����B
��G�@�C���^�[�l�b�g�łȂ��Ė{���Ɍ���ɍs���Ă݂�Ɖ��ł��Ȃ��Ƃ���ɔ��ɔ��z���ł���킯�ł��B�匴�̌Ò�����̔��p�ق��ƌ������ɂ��l�����邵�A���낢��ȕ����ɖʔ������Ă����Ƃ������Ƃ���ł��B���ꂩ��A���������������тɂ��Ă���̔��p�قɗႦ�Ă������ł����A���܂��܂Ȃ��ƂŊy����ł䂭�B�������������Ƃ́A���Ќ��n�ɍs���Ă��炤�Ƃ��ʔ����b�����Ƃ��ł��邩�Ǝv���܂��B
���x�͎s������̕��Ɉڂ肽���Ǝv���܂��B�s������̏��z�{���Ƃ����̂́A��N��120���l���炢�̐l���K��ė��Ă��ł����A���ď\���N�O�͂ł��ˁA��l�����Ȃ��悤�ȂƂ��낾������ł��ˁB
�ł��A�s�����������낢�Ȃ��A���̐l���݂�ȂƂɂ����ʔ����B�܂�𗬏�肾���Ă������ƂŌ��݂̂悤�ɂȂ��Ă����ł��ˁB���̃p���t���b�g�ɂ��𗬉�c�Ə����Ă���܂����A�Ȃ��𗬂���Ƃ����������ɏd�v�Ȃ킯�ł��ˁB
�Ⴆ�A��X���Ò��̕��ɕ����ɍs���Ƃł��ˁA�����Ƃ���͓c������̂Ƃ���ƃg�C�����炢�����Ȃ��A��͂ǂ�������Ȃ��Ƃ����Ȃ�ł��ˁB����ł͐܊p�����ɖK�˂ɂ������肵�����ɂł��ˁA��X�Ƃ�����������V�����𗬂����邩�Ǝv���ė��Ă���̂ł����A���������ɂȂ�ɂ����B
�s������̂Ƃ���ł͂ł��ˁA�𗬂Ƃ������̂��A�𗬕����E�T���������ƌĂ�ł��܂��B���̂悤�Ȍ𗬂Ƃ������́A�����Ė��킢��ԂƂ����A�����H�ו�������Ƃ��������łȂ��A�l�Ƃ̌𗬂��ǂ��������������o���Ă������A�����Č𗬏��ɂȂ�ɂ͂ǂ����Ă�������悢�낤�A���̌��ʉ������܂��̂��A�Ƃ����悤�Ȏ��ɂ��ď����b���Ă������������Ǝv���܂��B
�܂��A������A�s������Ƃ��̏��z�{�Ƃ����u�����h�����Ε��������킯�Ȃ̂ł����A���̏��z�{�u�����h�Ƃ����悤�ȃ��[�J���u�����h�ƁA�S���ɒʂ���i�V���i���u�����h�ɂ��Ă����b���������������Ǝv���܂��B
�s���G�@������㐶�܂�ł�����A�����ĎЉ�ׂ̈ɂƂ����������������ɂ���Ă�킯�ł͂���܂���ŁA�v����Ɏ����ɂƂ��Ĉ�ԉ��K�Ȋ��͂ȂƂ���������S�Ĕ��z���Ă���܂��B
�@����ŁA�����݂ƌ������ł���܂�����ǂ��A��20�N�قǑO�Ɏ�g�ݎn�߂���ł����A����ƂĂł��ˁA�q���̍��܂��Ԃ����܂葖���ĂȂ����������̒����݂̕����ǂ������Ǝv���Ă��܂��B���ȁA���r���[�ȋߑ㉻�Ŗ��C�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ȂƎv����ł��B
�@���ꂶ��ǂ����悤���Ǝv���A�F�X�ȂƂ�������ĉ��܂����B�ł��A���z�{�Ƃ������́A�Ⴆ����̌Ò��̂悤�ɂ��Ȃ�Â����̂��c���Ă���Ƃ������ł͖��������킯�ł��ˁB�ł�����A���̔������̎c�������̖т��������ނ悤�ɂł��ˁA�������������̂�厖�ɂ��Ă������Ƃ������ɂȂ�܂����B
�@����ƁA�����݂Ƃ����Ă����{�̏ꍇ�ɂ́A�Â������݂��V�����r���X���ł��ˁA�l���Ă݂�Ƃ݂�Ȓʂ�ɒ�������悤�Ȍ��ĕ��ɂ��Ă���A�L��Ƃ������������Ȃ���ł��B����ł��͓̂��H���L���Ȃ�����ׂ��Ȃ����肵�������������āA���H�̕����L���Ƃ��낪���m�̒��ł����L��I�Ȗ��������Ă���Ȃ����Ǝv����ł��B
�@�������������H�����a30�N�ȍ~�A���̒��𑖂��Ă�����̂������łȂ����̂��݂�ȓ������ɂȂ��Ă��܂����肵�Ă���B����ŊF�����܂�ꏊ���O�ɂȂ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B
�@���ꂶ�Ⴀ�A�Ƃ������ƂŐ�����b���������݂Ȃǂ�厖�ɂ��邾���łȂ��āA���\���グ���l�����S�����킹�Ă���Ă������Ǝv�����̂ł��B
�@�Ⴆ�A�S��������ʂ�ɒ������̂ł͂Ȃ��āA��X�́u�����v�i�����ӂƂ���j�ƌ����Ă��܂�����ǂ��A������ƊO���̒ʂ肩������ɓ��肱�ނ悤�ȏꏊ���A�N�̏��L�Ƃ��N�̂����ł��Ƃ��l����O�ɂł��ˁA����������ԂƂ������̂��~�����Ǝv������ł��B
�@���������Ӗ��ł́A���̓s�s�̌v�戽���́A�s�s�̌��z�̂�������炢���A�ނ�����{�I�ł͂Ȃ���ł��ˁB���m�I�ȓs�s�v����v�������Ď����ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�����͂ł��ˁA�Â����̂��ɂ��邵�A�V���������̂��Â����̂ƒ��a�������̂ɂ��Ă䂭�Ƃ������Ƃ���낤�Ƃ����̂ł��B����𖼂Â���Ɓu���z�{�̒����ݏC�i���Ɓv�Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂��ˁB�����Č��݂�����𑱂��Ă���Ă���Ƃ��������Ǝv���܂��B
�@���̓��@�͉����Ƃ�������A����ς肻�������ꏊ�A�����A�i�ς��Y��Ȃ�Ή�X���g�A���C���o���Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤�ˁB�����̎��傫�Ȗ����̈�͂ł��ˁA�����ɏZ��ł�l���A������ʂ�l���A�F���C�ɂ��鎖�ł���͂����Ǝv���܂��B
�@���������l���̌��ɁA�n�[�h�ʂ̐��������܂����B�ł́A����������������Ηǂ��̂��ƌ����ƁA����ς�H�ו����������Ȃ���܂�����Ȃ��Ƃ������ŁA���������̂��o���邾���H�ׂ�悤�ɂ��邵�A���A���������̂���Ă����ɂ͂ǂ������炢�����Ƃ����悤�ȁA���ʓI�ɂ̓��X�g�����Ƃ��������������̂ɂȂ��ł�����ǂ��A���������̂��ꐶ�����撣���đn��o���Ă�������ł��B
�@�H�ׂ鎖�������������ƁA���x�͂��ꂾ�����Ⴈ�����낭�Ȃ��悤�Ȃ��Ǝv���o���܂����B�h���������Ă��Ȃ��ƑS�R�������낭�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����ŁA�h�����ĉ����낤�Ƃ�������A���ǁA�l���^��ł�����̂��낤�ȂƂ����Ƃ���ɍs�������܂����B�e���r�⊈���͂���͂���ŋM�d�Ȃ��̂ł����A�����������������������B
�@�������ł�������d�g�œ`�������A���ډ���Ęb��������Ƃ��������Ƃ����悤�Ȃ��̂��A�o���邾���������������̂Ƃ���ɓ����Ă��邤�ɂ���ɂ͂ǂ������炢�����ƍl������ł��B�����l���Ă䂭�Ƃł��ˁA�ό��q�������l�����Ƃ��A�����甄�オ�������Ƃ��A������������ǂ��čs���Ƃǂ����Ă��n�����Ȃ��āA���̒Ⴂ���̂ɂȂ��Ă����Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪�A�s���Ƃ���ƌo�c�ƌ����̂͑�̐�����ǂ���ł��ˁB��������ƌo�c�����Ă��ĕςȂ�ł����A�]�ƈ�������������������������ł�����A���₢�₻�ꂾ���ł͉�X�̎h���ɂȂ�Ȃ���Ƃ����b�������肵�܂����B����Ő��Ɏ��́A�Г��ł͐����̌����ȎВ��Ƃ������ɂȂ��Ă��܂�����ł��B���͌�������Ȃ��Ăł��ˁA�����Ƃ����͔̂��Ɍ�̕����i�ߋ��j�̎��ł���A���ۂɌ��N���Ă��鎖�ɔ�ׂ�Ɛ��N�x��̘b�ł�����A�����ɗ�������댯����Ƃ����Ӗ��Ȃ�ł�����ǂ��B
�@���b�ł��鎞�Ԃ��Z���̂ŁA���ۓI�Ɍ����܂�������ǂ��A���������悤�Ȏ�������Ă����킯�ł��ˁB�����͏�����ʂ��Ȃ���ł����邵�A���Â����Ђ�ʂ��Ȃ���ł�����܂��B
��G�@�{���͎��Ԃ�����Β��Â����Ђƌ������ɂ��Ă������b�����Ē���������ł��B������ƏЉ�܂��ƁA�u�A�����z�{�v�Ƃ������z�{���A���z�{���̒��Â����Ђ������Ăł��ˁA�����ł����ĂȂ������Ȃ��璬�̈ē���������A�S���ŏ��߂ăI�[�v���K�[�f�j���O�Ƃ����`�łǂ̉ƒ���i�ς���������Ă������Ƃ����A�ό��n�Â���ł͂Ȃ����������̐����������炵�������čs�����Ƃ�������������Ă��܂��B
�@�S���ŏ��߂Ď��̏��̓I�[�v���ɂ��Ă��܂���Ƃ����`�ŃK�[�f�j���O�̒�����Ă��炨���Ƃ��������ό��n�ł��Ȃ����ʂ̂Ƃ���ōs���Ă��܂��B�����50����������܂��B
�@���������Ă݂܂������ǁA�����Ă��邾���ŐF��Ȑl�ɉ�����肵�Ċy�������A�����ɐQ������̕��Ƃ������������āu�������炫���́H�v�Ȃ�ĉ�b���ł����肵�āA�����ɂ��𗧂��Ă���A����Ȏ����i�ς̒��ɓ����Ă����肷��킯�ł��ˁB�܂����̕ӂ���b���Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�@����������s������ɁA�u�Y�n���牤���v�Ƃ����b�������ł��ˁB���̉��R�����N���^�j�Ƃ����낢��Ȃ��������Y�����̂��킯�Ȃ�ł����A�P�Ȃ�Y�n�Ƃ������̂Ɖ����Ƃ̈Ⴂ�Ƃ������������b���Ă�����������Ǝv���܂��B
�s���G�@�V���E�e���r�̗p��Ō����Ή��ł�������ł����A���Y���������ƁA�Ⴆ�Ε����������ƕ��������Ƃ������܂��ˁB����������͉����ƌ����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv����ł��B�����P�ɎY�n�ɉ߂��Ȃ��āA���̎Y���̐��Y�����ʓI�ɑ����Ƃ�����������Ȃ����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��ˁB
�@�ł́A�{���ɖL���ɉ���������Ă�����炵�ɖL���Ɋ��������Ăǂ����������낤�Ƃ������Ƃ�F�X�l���܂����B����ʼnߋ��̎��Ȃǂ��l���Ă���܂�����A�ς��ƋC�t�������������ł��B
�@����́A�吳�����a�O�����炢�܂ł͑S���ǂ��������������Ǝv����ł����A�Ⴆ�Α卪���ɂ��܂��ƁA���낵�Ɏg�����낵��������A���ꂩ��ϕ��Ɏg���卪�A���邢�̓^�N�A���Ɏg����卪�A���ꂼ�ꂪ���̒n��̒��Ń^�N�A���p�ɂ͂���A���낵�ɂ͂������Ƃ����悤�Ɏ�ނ����낢�날�肻�ꂼ�ꂢ�낢�����Ă����킯�Ȃ�ł��ˁB
�@����ɔ�ׂĐ��A���ɃX�[�p�[�̔������l���܂��ƁA��X�͔���ʐς��x���ꂿ�Ⴄ��ł����A�������Y��ɐ���Ă���卪���͖̂L�����Ǝv������ł����̂ł����A�����ɂ�1��ނ̑卪���������Ă��炸�A���ꂾ���őS�Ă̗�����d���悤�Ȏ�������Ă���킯�Ȃ�ł��B
�@����͑卪�����Ɍ��炸�A������Y���������Ȃ�ł��B�悭�l�����炱��Ȃ��̂͑S�R�L������Ȃ��B
�@�Y�n�Ƃ��ĖL���Ȃ͉̂��Ȃ̂��Ƃ����ƁA��X�M�B�ł�����������܂����A��X���q�����������͂�����ƍl���Ă�5��ނ�10��ނ͂������Ƃ������Ƃ��Ǝv����ł��B���͖w�ǒÌy�Ƃ��x�m���Ƃ�����ނɌ����Ă��܂��܂������B�������͐��ŐH�ׂ鎖��z�肵�č���A�������֑����čs��������Ă܂��B
�@�Ƃ��낪�A��ƌ����َ͉̂q�ɂ��g���A�����ɂ��g���܂��B�W���[�X�ɂ�������1��ނ̂�������g������2���3��ނ̂�������č�����肷��Ɣ��ɂ��܂����̂��o����킯�Ȃ�ł��ˁB�Ƃ��낪�卪�Ɠ����ŁA���ʐςɑ�R�ł��āA��ʓI�ɍD�܂�镨�ɏW�����Ă����Ă��܂��B
�@�l���Ă݂���A�S�Ă̐H���������Ȃ���������Ȃ��Ƃ������ƂɋC���t���܂����B����͂Ȃ�Ƃ����Ȃ��������Ǝv�����̂ł��B���Y�҂ɐF�X�����Ă݂�ƁA�u���₢���X���Y�҂��F�X�����Ă��܂��v�ƌ����Ă��܂����B�m���ɐ��Y�Z�p�̎��ɂ��Ă͕����Ă��܂����B����ł́u����Ɋւ��Ă̏��͂����Ă��܂����H�v�Ƃ����Ƒ��͎����Ă���Ƃ�����ł����A�悭�����Ă݂�ƁA����͂����ǂ�����Ύs��Ŏ��������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ�ł��ˁB
�@����Ȃ��̂́A������ł��Ȃ�������ė��ʏ��Ȃ�ł��ˁB�ł́A�{���̏�����͂ǂ����Ē͂�łȂ����ƕ�������A�u��X�͍�邾��������v�Ƃ�����ł��ˁB�����������Ƃ��l���܂��ƁA�P�ɕ����R����đS���̃V�F�A���g�b�v�Ȃ�Ă������Ƃ́A�Ђ���Ƃ���19���I�̐A���n����Ɠ����������Ă��Ȃ����Ǝv���Ă����̂ł��B
�@20���I�A21���I�́A���Ȃ��Ƃ����������͐�i�����Ǝv���Ă������A���g����Ǝv���܂����ˁB
�@���ꂩ�������厖�Ȃ̂́A���낢��Ȏ�ނ̕i��̓����Ƃ������̂���͂萶�Y�Ҏ��g���͂܂Ȃ�����ȂƂ������Ƃł��B�u���������猋�ʓI�ɔ���܂����v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�u����������������y���݂�����܂��A�����������p������܂��v�Ƃ����̂Y�Ҏ��g�������Ă��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���ׂ̈ɂ͐��Y������ӂ̐l�B�ɏ�������Ă��炤�Ƃ������Ƃ��厖���ȂƎv����ł��B
�@�Ƃ������Ƃ͂ł��ˁA�����s��łǂ����������Ƃ������Ƃ�������E�p�������������Ƃ������Ƃł��B�n���}�[�P�b�g�A�����͎����ŐH�ׂĂ݂Ď����̕�炵�E�n��̒�����������͂ށB�����Ă��̏�����ɂ��������Y������Ă����Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B�����čX�ɉ��H�i����͂�~�����˂Ƃ������ƂɂȂ�܂��l����B
�@�Ⴆ�Ή��R�Ɏ�������ƁA�}�X�J�b�g���ȂƂ����ɃC���[�W���N���܂��B���H�p�ł��H�ׂ������A������������}�X�J�b�g�̃W�������Ăǂ��Ȃ��Ă�̂��ȂƂ��A�W���[�X���Ăǂ��Ȃ��Ă�̂��Ǝv���܂��B�����āA���̃W���[�X��W�����̃��x�����Ⴂ�ƃ}�X�J�b�g���̂�����܂�債�����Ȃ���Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��ˁB
�@�Ƃ��낪���܂ł̔��z�Ƃ����̂́A�u���₢��A�W���[�X���Ă���̂͑��Ǝ҂����A������Ȃ���v�Ƃ����悤�ɁA���Y�҂��݂�ȉ�����Ȃ�������Ȃ����Č����Ă����ł����A����҂Ƃ����̂͂������Z�b�g�ɂ��ăC���[�W��`����ł���ˁB�ł�����A�N�̐ӔC�Ƃ����킯����Ȃ���ł���B
�@�v����ɑS�����x���������Ȃ��Ă͉����Ƃ͌����Ȃ��B���Y�������i�킠���āA���ꂼ��̗ǂ��Y�Ҏ��g���͂�ł���A����ʼn��H�i�̎������ɍ����B�����Ă܂��n��������S�̂��ɍ̂����Ă���B���������̂�{���̉����ł���Ǝv����ł��B
�@����ς�21���I�͉�����ڎw���Ă䂩�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���Y�҂�����҂�"���{�l��20�N�A30�N���g���Ăǂ��������ɐ����ɖL���ɂ��邩"�Ƃ�������^���ɂ���Ă����̂��������Ǝv���܂��B
�@�Ԃ������ł��ˁB�m���ɐ��\���ǂ��Ă������������Ԃ���邯��ǂ��A���̎Ԃ��g�����ɂ���Ė{���ɖL���Ȑ����Ƃ����̂͂ǂ��������̂Ȃ̂��Ƃ������ƁA���́u�g���v�Ƃ�������������Ă��Ȃ������B���������Ӗ��ł́A���{�S�̂�������ڎw���Ă��Ȃ������ȂƂ����C�����Ă��ł��ˁB
��G�@�����Ƃ��̕ӂ���b�W�����Ă䂫������ł����A���R�̎s������ɂł��ˁA��قǘb�ɏo���悤�ɁA������_�����́A�L��̒n���ł���Ƃ����Ƃ���ɂ��Ă��b���������������̂ł��B
�@���̒n��ɂƂ��Ĉ�ԏd�v�Ȃ͎̂��͉��R�s��������܂���B���̉��R�s�̎s�������炵�Ă�킯�ł�����A���x�͂����̑�������ɂȂ�������ł��̎R���������c���čs�����߂ɂ͉��R�s���ǂ�"�g����"�������炢���̂��������������Ǝv���܂��B
�@�L��̒n�����g���Ȃ���A�܂��A�s������̂�������������[�J���u�����h�Ƃ������_������A���̒n�悪���R����肭���p���Ȃ���s���ʂ����@������̂Ȃ炻��������Ǝv���܂��B
�@���̂��߂ɉ��R�̎s������ɂȂ��Ă����������H�������ƂŁB�������ł��傤���H
�����G�@������O�̎����肨��������ł������낭�Ȃ��ȂƎv���Ă�����ł����B
��G�@�����ł����B����ł́A�ʔ����W�J���Ă���������B
�����G�@�����قǂ̎s������̘b�Ȃ͕����ĂĖʔ����Ȃ��Ȃ�ċC�����܂����ˁB�o���o���b���܂����ǂ��A�s������ƂƓ�����������ǂ��Ƃ����͎̂��͉R�ł��āA�s���͖w�ǐ�����ǂ������͂Ȃ��ł��ˁB
�@�܂��A�\�Z�̐����͒ǂ���������܂����A���т̐�����ǂ������͂Ȃ��ł�����B�悤�₭�s�������т̐�����ǂ��悤�ɂȂ��āA��Ƃ̃��x���ɋ߂Â��Ă������Ȃƌ������������܂�����ǂ��B�s���͏o����������������т̐�����ǂ��悤�ɂȂ���������ǂ����ȁA�Ƃ܂����̎����v���܂����ˁB
�@���ꂩ�炳�����̕��̘b���Ƃ����̂͂ƂĂ����ɂȂ�܂����ˁB���������Ă�������̘b���Ƃ����̂ł����A�l��������͎v���Ă��ł����A�s�������̎��̋�����Ȃ��Đ^���ɒu���Ď��Ƃ�����Ăق����ł��B���ꂪ�������̉��R�̘b���Ƃ����炭�ŏI�I�ɂ͗���ł���Ǝv���܂��B
�@����ς���F�ƌ������A�ق�܂���łȂ��Ɖ������N���Ȃ���ł���B�v����ɁA�����q�͐����q�ł���ׂ������A�����q�͓����q�Ƃ����̂͑傫�Ȍ���������ǂ��A���R�̐l�����s�ɍs���Ƃ������ɂł��ˁA�ǂ��ł��ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ă���ς萼���q�ɂ����ɂ͐����q�ɍs�����R���K�v�Ȃ�ł��ˁB���̉����ق�܂��Ƃ��������������肵�Ă��Ȃ��ƁA�P�Ȃ��̎R���̌����������ƌ��������ɂȂ��Ă��܂��B
�@���������ɂ�������X�́A�݂�Ȃ��̌����̒n��̐l�ԂȂ�ł��傤���A���ꂼ��̒��Ȃ����A���ł��ꂼ��̒��A���炵�����Ƃ��������肳�ꂽ��ł��������𗬉�c�Ƃ������ʂɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B�S���̎R���S��������Ȃ킯�ɂ͂����܂���ˁB
�@�S���Ɍ����͋��炭�Q�����R�������ł�����ǂ��A���̒��łق�̏����̐l���������肵����������Ă���Ƃ����̂������Ȃ�ł��ˁB��������������ďW�܂��Ă݂�ƁA�ǂ��ł��������ł��������肵�������������āA�������肵���l���撣���Ă�݂����ȊԈ�����C���[�W��������Ƃ����̂���Ԃ悭�Ȃ���ł��ˁB
�@���Ɋ撣���Ă�������X���A�F�X�Ƃ�����������ł��̌����Ƃ����̂������āA�����ɂق���̂̓��������Ă��邩��l�͍s���Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ�킯�ł��B������A���R�s���猩�Č����Ƃ����͎̂��͂����ς�����킯�Ȃ�ł��ˁB
�@���R�̐l�Ԃ��g���̌����̐����q�ɂȂ����邩�ƌ����ƁA�s���������q�o�g�����痈�Ă���B���낢��Ȑl�����Ă��āA�F�u�����Ƃ���ȁ[�v�ƌ����Ă���܂�����ǂ��A���������͎̂����s�����N�r�ɂȂ�����I���܂�����B��������ƁA��͂萼���q�I�ɗǂ����̂��čs���K�v������̂łȂ����ȂƎv���܂��B
�@�Ƃ���ŁA��قǂ̎s������̘b�̑����݂����Ȏ����A�o���o�����ƌ����܂�����ǂ��A���̊ԓ������傤��������Ƃ����āA�l�ԍ���̓�����������̑��q����̓��|�Ƃ̕��Ƙb���������Ƃ���A�q���g�������Ԃ�܂����B
�@�q�_�X�L�Ƃ����̂��������܂��ł���B����͘m���g���܂��B����ŁA�ǂ��m���ق�����Ȃ��Ƃ�������A�������m���ǂ��[���Ǝ����Ă��Ă��ꂽ�����ł��B����œ�������͉��Č������Ǝv���܂����H���́u����f���v�Ƃ������������ł��B�m�͘m�ł��q�_�X�L�p�̘m������̂�m��Ȃ��Ŏ����Ă����Ƃ�����ł��ˁB
�@�q�_�X�L�p�̘m�Ƃ����̂͐̂̕i��ŁA�s�̒����A�|��₷�������ĂĂ����c���肷������ł��B���̂��߂ɓ�������̂Ƃ���ł͂킴�킴�c��ڂ��ĉƑ��Ŗ��Ȏ����ɓc�A�������āA8���̂��鎞���ɊF�ɔl�|����Ȃ���ŏ��̐c��������Ă����Ƃ�����ł��ˁB���̐��m�������Ďg�p����Ƃ����̂���ԃq�_�X�L�̐F�ɗǂ������ł��B
�@�����������Ƃ����āA�܂�A�ނ�͂��̂������R�X�g�������Ă���Ă����ł��ˁB�����̎��Ԃ������č���Ă����ł��B�{���̂��̂Ƃ����̂͂��������������肪����ŏ��߂Đ������邻���ł��B�t�ɂ����ƁA�����������Ƃ��킩���Đ��Y����ƁA���������j�[�Y�Ƀ}�b�`�����Ⴄ�Ƃ����Ƃ��낪�����ł��ˁB
�@�Ƃ���ŁA���l�͉��R�s�ɏZ��ł��܂��B����Łu���т�H����v�Ƃ����̂I�ȗ��A�R�������Ă���킯�Ȃ�ł����A�F����A���тƂ����̂͂����m�ł��傤���H�����ʂ�A�P�ɂ��т̏�ɕ����̂��Ă�����̂Ȃ�ł����B���R�s���̐��c�n�т̐��̈����Ƃ��ň���������R���قǂ����ēD���������Ďg���̂ł����A���̕��т���邽�߂ɂP�����قǑO���珀�������ł��B
�@���т����H�킵�Ă����傤���Ȃ�����A���̎ϕ�������ł����A���̎ϕ��Ɏg�����ƕ��тɎg�����͈Ⴄ�Ƃ���ō̂�̂ł��B�����̕��������ō̂邩�Ƃ������A�����ĒN����������Ƃ��������v�����j���O���āA�S�����Ɛ��ō���ł��B�X�ł��̂ł͂Ȃ��A��ʂ̉Ƃł��̂őS���^�_�Ȃ�ł��B�����R��ڂȂ̂ŁA�R���ڂɂȂ�܂����A�������痈�����q����Ȃǂ����̉Ƃɏ��҂��ĐH�ׂĂ��炤��ł��B
�@���̑O�́A�_���Ȃ̓y�ؒS���҂����҂��ĐH�ׂĒ����āA�u���̂悤�Ȕ����������т�H���Â�����悤�Ȑ������ێ����Ă��炤���߂ɂ��Ȃ���������v�ƌ�������A���̂������N���A�ɕ������Ē������Ƃ��ł��܂����B
�@���̕��ɂ��Ă��ł��ˁA���������̂������l���āA�傫���≽���̐삩��Ƃ�̂���I��ł��Ȃ��ƁA�{���ɂ��������Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@���ꂩ��A�̂������H���̐������̂����������Ă܂��ˁB������܂����ɖ߂��Ƃ����̂��ƂĂ��ǂ����ƂȂ̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B
�@��قǂɂ������悤�Șb������܂������A�ʕ������Ɍ���܂����ˁB�l�����������̎����v���o���ƁA�E�Y���A�z�����A�O�C�~�i�O���~�j�A�i�c���ȂǁA�����������͉̂����ɂł��������킯�ł��B����͎��Ɏ��R�H��������ł��ˁB�����ɂ͂�������邽�߂ɔ엿��������A�_������Ȃ�Ă��Ȃ��킯�ł�����A�����������̂͐��藧�����炵�Ď��R�H�Ȃ�ł��ˁB���ƂȂ��Ă͂����������͔̂��ɑ�Ȃ�ł��B
�@�t�L�����Ă����ł���ˁB�t�L�����Ęn�����āA������엿��������_��܂����肵�܂����ˁB���ꂪ���ɂ̃I�[�K�j�b�N�A���S�Ȗ��_��ƌ�����Ǝv���܂��B�ł����ӂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂́A�����{�B����Ȃ�Ă����܂���B�������������̂́A���������ꏊ���ׂ���Ă���̂����ɖ߂��ƌ�������������ǂ��ł����ƌ������ł��B
�@�t�L���o����悤�ȏ�ۂ��Ă��A�����Ă����Ă��t�L�͏���ɏo����킯�ł�����B����͔��ɂ������A���ł�����ˁB���܂ʼn�X�̓t�L�Ȃǂ�����o���Ȃ��悤�ȏ�����Ă��܂��Ă������������������Ă��܂�����ł��B�����Ă����Ă���悤�ȏɖ߂��Ă�����A�t�L�͐����������ɐ�����킯�ł��B
�@���ꂩ�瓯���悤�Ȃ��̂Ƃ��āA�R������������܂����ˁB�F���R���Ƃ��ĐH�ׂĂ���̂͂X�W%�ȏ�͎R���Ƃ��������Ȃ̂ł��B�݂�ȖY��Ă��܂��Ă���B�����������̂��������葶�݂���悤�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ��̂��͎R�̖��Ȃ�ł��B�R���������肵�Ă���ΎR��������ɐ����Ă��܂��B���������̂������̌��_�ȂƎv���܂��B
�@�ł��A�����������̂蕨�ɂ��悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�H�ׂ����l���̂�ɗ�����H�ׂ����Ă��ƌ����X�^���X�ł�����ł���B���R�s�ł��Ⴆ�T�����ł́A�`�̎��n�O�ɂ́u�`����v�Ƃ����̂�����ł����A�`�����낻����n�Ƃ��������ɂȂ�����`�̖̉��ɍ����Ď��������ނ�ł��ˁA�ǂ��`���Ȃ��Ă܂��˂��Č����Ȃ���������ނ�ł��B�����֊F�����āA�`�̖����Ċy����ŏ�肢���̂�H���āA����ŋA���Ă����B���ꂾ���Ŋy����ł���B�����K�ɂ��悤�Ƃ���ƁA�_����������肢�낢�낵�Ă��܂��܂�����B�p���đK�ɂ��܂��Ƃ���Ƌt�ɑK�ɋ߂Â��l�ȋC�����܂��ˁB�������������y����ŁA�������Ă��܂�����ǂ����Ǝv���܂��B�ɂȐl�͈�t���܂�����B
�@���A�ʔ������Ƀz�[���Z���^�[�����ɗ��s���Ă���ƌ�����ł��ˁB�Ȃ����Ƃ����ƁA�ŋߎ��Ǝ҂������Ă��܂����A���������l���������Ƃ����牽�����邩�Ƃ����Ƒ�̓y������Ȃ����ł��B����Ńz�[���Z���^�[���ɐ����Ă�����Ă�����ł���ˁB
�@���������ɂȎ��ԂƂ����̂��A�Ȃ��R�ɂȂ���Ƃ��㐢�ɂȂ���Ƃ��A��������������Ƃ����y���݂ɕς��čs���Ɨǂ��̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂����A�������������s���ł������v���o������ȂƎv���܂����A���ꂪ���R���猩���p�Ƃ��āA�����q�Ɠ����q������҂���Ă��鎖����Ȃ����ȂƎv���܂��B
��G�@�����Ȓn�悪�s���ʂ��Ă������Ď��ɁA�傫�ȓs�s���o���Ȃ�������Â��낢��Ȉӌ����ĎQ�l�ɂ��Ă������炢���Ǝv���܂��B����̉�c���L��Ŏ�g�ނƂ������ŁA��������ɂ��낢�남���������Ƃ���A�O�̒����ł���������g�݂����܂肵�������Ȃ��Ƃ���������Ă����̂ł��B
�@�s���������Ȃǂ̖��ɁA�L��Ŏ�g�ގ��̑����A�������낳�Ƃ��A����̘b���Ă���Ȕ��������āA������Z���̐l�ƈꏏ�ɍl���Ă݂ĐF��Ȍo���̒����炱��Ș_�c�������炨�����낢���낤�ȂƂ����悤�ȃe�[�}������A���コ��A����A���b���������B
����G�@���A����̉�c�ɔ��Ɋ������Ă��܂��̂́A�����łQ���ڂƂ������ƂȂ�ł��B����A�Q���҂̕��X�͂P�����炢����U�����炢�܂ʼn��X�Ƙb�����Ƃ����̂ɁA�����܂����܂茸�炸�ɊF����̐^���Ȃ܂Ȃ���������Ƃ����������ɑf���炵���Ǝv���܂����B
�@���̂��������́A�R�{���玝���|���Ă�����������ł��ˁB�ǂ������́A�������������Ƃ�������͂Q�N�������Ȃ��̂ł�����A���ɍD��S�������Ăł��ˁA���ЎR���ɍs���Ă݂悤�ƌ������ɂȂ�A�����ŗ����ɂ��������ł��B
�@����ŁA�����̏Љ�ŁA�܃����������A���z�{�������A�W���������Ƃ������b���ǂ�ǂ����̂ł�����A���̂Ƃ���ɂ������ƕ����Ă݂���ł��B����Ȓ��ŁA�����b���Ă݂���A���ɑf���炵���Ǝv���܂����B�������悢��{���ł̌�肪����܂��B�F��������ɑf���炵�������������Ē�������Ȃ����ȂƎv���܂��B�����A���ɗǂ������ȂƂ����̂�����ۂł��ˁB���F��ȊF����Ƃ̏o��������āA�����Q�����Ă��������������������A���Ă������������Ǝv���܂��B
�@�n��Љ�̖��Ƃ����̂͘b���Δ��ɒ����Ȃ�܂����A�{���ɑ�ςȏł��ˁB�ł�����A�Ȃ�Ƃ����ɂႢ����ȂƂ����v�����F��������Ă��邩�炱���������Q��������Ƃ������Ƃł���ˁB�v����������Ȃɂ��ς��܂���A���Ȃ��Ă��S�������ĕς��悤�Ƃ�����������āA�����Ân�悪�ς���Ă����B���̐��̒��̓��������ɑ����ł�����A���Ⴂ���镔�������X����B
�@���X�c�ɂȂ�Ă����̂́A�č�肪�����āA�l�G�������āA���X�Ƃ��������`�Ԃ��Ƃ��Ă�����ł��ˁB���X�̕č���ʂ��Ă̔N�Ԃ̃X�^�C��������̂ɁA���̒��̓����������Ȃ������̂ł�����E���������Ċ��Ⴂ���Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�L��łƌ������ŁA�����q�͔��ɏ����ȑ��ł�����A�O�P�����Ŏ�g�B�O�P�����Ă݂�A���ꂼ�ꏭ���Â��邢�����̂������͑傫���Ȃ�܂��ˁB�ł�����A���ꂩ��͍L��I�Ȓ��ŕ����l����ƌ��������ƂĂ��K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�ԎЉ�ɂȂ��Ĕ��ɓ����������Ȃ�܂����̂ŁA��P���������ł��q����ɌJ��Ԃ��A�J��Ԃ����Ă��������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�܂����B���A�s������b���ɂ���܂����悤�ɁA�g���A�F���̌����Ɖ����̗���Ƃ������ł��B
�@�]���A�⏕����Ⴄ���߂ɍ\����������Ă����Ƃ����b�����������܂������A���X�͓c�ɂ炵�������点�邽�߂ɕ⏕���������Ď{�݂�������̂ɁA�ǂ�������Ă����̂��ȂƎv���܂��B
�@�����q�̃p���t���b�g�ɂ�����܂����A�u���̗��A�̑��A��̍��v�Ƃ����e�[�}�ʼn��\�N�����Ă��܂����A����~������̘b���ɂ�����܂������A���͂ǂ��Ȃ́H�Ƃ��A���̎{�݂̂ǂ��ɖ̍S�肪����̂��H�Ƃ������Ƃ��`����Ă��܂���ˁB
�@�����q�́A�W�U�p�[�Z���g���A�т����Ă���̂ŁA�ɂ���Ĕ��Ɍb�܂�Ă�������������Ȃ���A�ǂ��������≪�R�s�̃��m�}�l�����Ă��Ă��܂����B�������A�܂��܂��Ԃɍ����Ǝv���܂��B
�@���R�s��萼���q�͏㉺�����P�O�O�p�[�Z���g�����ł����琶�������͂����[���オ���Ă܂�����A���̐���������ۂ��Ȃ��炱�̒n��̐����l����������@��N�����Ă����ƌ��������A���Ԃ͂�����Ǝv���܂����ߓ��Ȃ̂��ȂƎv���܂��B
�@���낢��Ȏv���������Â���Ƃ����������̉�c�̖ړI�Ƃ������Ƃł����A���̐��̒��ł́A�L��I�ɍl���Ă����Ƃ������͂ǂ����Ă���ɂȂ邩�ȂƎv���܂��B
��G�@�܂������̒��ɂ��āA���t���܂Ƃ܂��ĂȂ��Ƃ���������ł��B�[�ׂ��A�Z���̕��R�O�l���S�O�l���炢�Ɉ͂܂�Ă��낢��Șb�������Ă����킯�ł����A�����Ńe�[�}�ɂ����Ƃ����R�g�o������܂��̂ŁA���̉\���Ƃ��A�����̂���͂����Ƃ��A��������Ă䂯�Ζʔ����̂ł́H�Ƃ��A�܂��͂����̏Z���̒��Ɋ��������̂�Z���̕��Ƙb���Ă݂����ł��������������̏����ȉ\���ȂǁA�Ƃɂ�������͖ʔ����Ȃ肻�����Ƃ����悤�Ȃ���������L�[���[�h�Ȃǂ́A�~������A�����������܂��H
�~���G�@��������Ǝv���o������ł�����ǂ��A�㗬�������ŁA���R�s������܂���ˁB�s�s�̐l���������Ђ˂�Ɛ����o�Ă���B�����āA�P�O�N���炢�O�����������Ƃ��F�������n�߂܂��āA���������̂��Ƃɂ��ď����l����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�ƒ�Ŏg����܂͂��ꂪ�����Ƃ��B�v����ɁA�������r���������������ɍs���̂��ȁH�ƌ������_���������鎞��ɂȂ��Ă����킯�ł��ˁB�ł��A���������܂ŗ���A���̌����l���������Ȃ��ł��ˁB���̐��͂ǂ��������Ă���̂��ȁH�Ƃ������_�ł��B
�@����N�������Ă��܂�������ǁA�C�̐������������肵�ċ�ɉ_���ł��A�J���~��A�R�̕��ɐ�������������A�X�т������܂�ł��̒����琅����H�o�Ă���Ƃ��ꂪ�����ƂȂ�A���ꂪ���܂��Ă������̂��ǂ�ǂ�āA���R�s�̐l��������g�����Ă�Ƃ����킯�ł��ˁB
�@�������A�����g�����Ă鉪�R�̐l�͌����̎��͂���܂킩��Ȃ��ł���A�܂��B��������������܂����悤�ɁA���������̎��͍l���鎞��ɂȂ��Ă����B���ꂩ��́A�ǂ����Ă������̎����l���Ȃ�����̂��Ⴄ���ȁA����Ƃ��ẮB
�@����ƁA���R�s�̐l�ɎR�̕��ɗ��Ă��炤�Ƃ������Ƃ��K�v�ł��ˁB�X�����ĂȂ��̂ɁA�����������ƁA���������Ȃ��ł���ˁB
�@������A����̂����c�A�[����Ȃ��ł�����ǁA���̂����c�A�[�ɗ���Ƃ������Ƃ́A�X�����Ă��炦��B���ۂɐX�̒��ɓ����ł��B����ŁA�����ǂ����畦���o�Ă�̂��A�Ƃ����悤�Ȏ����l���Ă��炦��悤�Ȃ����������Z�b�g�ł���Ⴄ���ȂƁB�s����������������������Ȋ炵�Ă܂�����ǂ��A�ǂ��ł����B
�s���G�@����̖�̃Z�b�V�����ŁA�匴���ɍ��J��Ƃ����f���炵���삪����Ƃ����܂����B���̍��J�������Ƃ����̂����邻���ł��āA���͍���̃p�l���[�̓c������Ȃ�ł�����ǂ��A�����o�[����t���炵�Ă܂����B����͌����ł���Ƃ���������N�����ۑ��ōʼn����̋g���̐��厛�ɑ���ꂽ�����Ȃ�ł����A���̐��厛�ɓ͂���ꂽ�ۑ��̏��Ɏs�����������[���Č����ɉ^��ł�����āA���̔�����Ă������ł��B
�����G�@����͎����Ă܂��ĂˁA�ŏ��̓A�T�q��Ŏn�߂���ł��B�A�T�q�삪�������������̂ŁA�l�͐��܂ꂪ�g���̕��Ȃ̂Ō��ݏȂɗ���ŁA�g������낤��Ƃ������ƂɂȂ�A���N�����q����n�߂Ď��͐����q�A�����đ匴�ɂƂ����i���Ői�߂���ł��B�����ӎ��Ƃ����͉̂��R�͂ƂĂ�������ł��ˁB
�@�����A�T�q��͎R�{���u�A�T�q��v�Ƃ����̂�������܂������A�u�g���v�Ƃ����̂͂���܂���ˁB������A���R�̐l�̃A�T�q��ւ̌����ӎ��̕���������ł��ˁB�ł������Ƃ����Ă���������̂ŁA�K���ꍇ�A�ǂ��ɍs�������Ȃ邩�Ƌ��������ɂȂ��ł��ˁB
�@�ȑO�A���R�s�Ɛ����ǂ́A�M�Ɏ����ѐE���Ƃ��Ĕh�����ꂽ��ł��ˁB�N���Ƃ��P���L��A���邽�߂ɁB�������܂�����A�n���ł݂͂�ȗ܂𗬂��Ċ��ł��ꂽ��ł���B�e���r���������w���B�́A�s������B���l�B�̏����̂��߂ɖ�A���Ă��ꂽ��ł��˂ƌ����Ă��ꂽ�肵�āA�ӎ��Ƃ��Ă͐�����������ł��B������A�����̑��Ƃ����Ă����ꂼ��̑��̌��Ƃ������̂��ǂ�ǂ�o���Ă����Ȃ��Ă͂������낳��������ƌ����������������Ǝv���܂��B
�s���G�@���́A���R�͐i��ł����ł����āA�S���I�ɂ͉����ƌ������q�����Ă���Ƃ����ӎ��͓���Ȃ��Ǝv����ł��ˁB���ɉ�X�̒��쌧���l���Ă݂܂��ƁA�S���������ŏ㗬�Ȃ�ł���B�����͑��̌��ɂȂ��Ă��܂���ł��B�삪�����܂���������Ă����ł��ˁB�ł�����]�v�Ɍ������牺������ł���Ƃ����ӎ����Ȃ���ł��B�t�ɂ����Ɖ��R�͑S���������牺���܂Ō����ɂ���܂�����A���ꂼ�ꂪ�W���Ă����ł��ˁB���ꎩ�̂͑�ςȏ��i�ɂȂ�\��������A��ςȍ߂�����\������������Ǝv����ł��ˁB
�����G�@��̐��E�ł͉��R�͗L���Ȃ�ł���B�S���̐�D���ɂ���P��������Ƃ����͉̂��R�s�ł������ł�����B���R�̂悤�Ɍ����Ő삪�������Ă���Ƃ���͏��Ȃ��̂ŁA�s���̈ӎ��������Ƃ������͊ԈႢ�Ȃ��ł��B����͌��ݏȂ̐l�������Ă��܂����B
�s���G�@���łɂ��������Ă����ł����H���͎��A�����ł��āA���O��ނ̓��̂P�́A�A�J�C���łȂ��āA���厛�̔��O���܂����g���Ă��ł��B
�����G�@���肪�Ƃ��������܂��B
�s���G�@���͂���Ȏ���������邯�ǁA14�A5�N�O�ɔ����ɗ����Ƃ��́A�t�Ɏ���̕������肢���܂��Ɠ��������Ă��肢���܂����B���̍��͏��ʐ��Y�ł�������B
��G�@�������ł����H���̉\���Ƃ������ŁA����͂����Ɨǂ��Ƃ���������������܂��H�H�{����͍��Z���̕��Ƃ��b�����āA�����̂Ƃ���͂��������������������ǂ���ł͂Ȃ����ƌ������͂��肹�H
�H�{�G�@���́A�����D���Ȃ̂ŁA���낢��Ȉ��ݕ���H�ו������Ă����ł��B������Ԃ��̗��ɔ��߂Ă��������āA�A�}�S���������y���ɂȂ�����ł����A�����͂��Ԃ�����R�炭�Ƃ����̂ŁA�u���Ԃ��̉Ԃ̗����͂���܂����H�v�ƕ����Ɓu�����������̂͂Ȃ��v�Ƃ�����ł��ˁB���́A�������Ԃ��̉Ԃ̗���������Ă݂����Ƃ������ł����ǁA����������ł���B�����Ƃ����������点�đ�̂Q�����炢���ɂ��炵�Ă����܂��ƁA��������������ǂ��āA���Ђ����Ƃ��O�t�|�ŐH�ׂ܂��Ɣ��ɂ��������̂ł��B
�@�����͂��Ԃ��̉Ԃ��炭���͂킴�킴���̉Ԃ��̂�ɍs����ł����ǂ��A�܊p���̂��Ԃ��̗��ɂ��Ԃ��������Ȃ�A���Ԃ��̉ԗ����𖼕������ɂ��ꂽ�炢����Ȃ����ȂƎv�����Ƃ���ł��B
�@�C���i�����ʔ����ł��B�Ē��̒��M���̓������y��̒��Ɋ������C���i�����o���ĕ��肱�ނ̂ł��B�Ē��̒��ł���܂����₪�Đg���͂����Ĕ����ۂ��G�L�X���łĂ��܂��B�����|�̂Ђ��Ⴍ�Ȃł������Ĉ��ނƔ��������̂ł��B�����Ĉ��������܂���B
�@����ƁA�u�i�т��ƓV�R�̃~�c�o�`�����܂���ˁB���̃~�c�o�`�ł����������������ݕ�����������ł��B�V�R�̃~�c�o�`�Ƃ����̂͑����c�ɃJ�[�e���̂悤�ɂ����āA���̗����ɑ������J���Ă��Ă����ɖ������߂Ă��ł����A���ʁA�I���Ƃ����͉̂��S�����@�ɂ����Ă��̒��̖����������o����ł��B�������A���͂��̑����̂�H�ׂ�̂����ɂ���������ł��B
�@������̂܂܂ł͐H�ׂ��܂����B�܂��Ē��ɑ����Ɠ���āA���x���X�O�x�߂��܂ŏグ���Ⴄ��ł��B��������ƁA�͂��̑����S���n��������āA���̖̔�Ƃ��J�X�����������Ă���̂ŁA��������菜���Ĉ��ނ�ł��B���ꂪ�ƂĂ�����������ł���B�������A���������������͊炪�c���c���ɂȂ��Ă����ł��B���C�����[���[�Ȃ�Ĕ�ו��ɂȂ�Ȃ��ł��ˁB�V�R�̃~�c�o�`�𑃂��Ǝ�ɓ��ꂽ��A�I���������ނȂ�Ĕ��ɂ��������Ȃ��B���̑��������������A���N�ɂ����B�������������낢��Ȃ��Ƃ��l���Ă���Ă݂���ʔ����Ǝv���܂��B
��G�@���Ԃ��̉Ԃ̃G�L�X���X�e�[�L�ɓ��ꂽ��A�V���[�x�b�g�ɂ��Ă݂���ƁA�H�{����̏��ł͂��Ԃ����������낢��o���ł��B���̕ӂ́A����H�{����̏��ɍs���ĐH�ׂĂ݂�Ƃ����ł��ˁB���ɂ����}���̃X�[�v���o����ƁA�������Ⴄ��ł��ˁB�ŏ��̂��Ԃ��̉Ԃ̐�[���̂�͔̂��ɑ�ςȂ����ł���B�����Ȃ����肵�āB�ł��A���Ԃ��̉Ԃ������������ɗ����o����Ƃ������́A���Ԃ��̗��̕��X�ɂ͊���q���g�������Ȃ����Ǝv���܂��ˁB
�����G�@���Ԃ��̗����͂����炭�炢�����ł����H�n�E�}�b�`�H
�H�{�G�@�����͂����ł������܂�����K���Ȓl�i�Ō��\�B�ŏ��͂��Ԃ��̉Ԃʂ̏�ԂŐH�ׂĂ݂���ł�����ǂ��A����͂��������Ȃ��ȂƂ������ƂɂȂ�A���N���̂܂܂ق����炩���Ă������̂ł��B����ŗ����H�ׂĂ݂��炱�ꂪ��������������ł���B����͂�����ƁB�I�̑������Ĉ��ނ̂��ł��ˁA�I�����Ē��ɓ���Ĉ��ނƂ������Ƃ͂悭��鎖�ł����A���������Ƃ��ɂ�������̂܂Ē��ɓ���Ă݂Ă��n���Ȃ�������ł��B����œd�q�����W�ɓ���ă`�����Ă݂���n��������Ă��ł���B����͂������������Ǝv���܂����B����ŁA�y��ɓ���Ă�����Ɖ��o���Ȃ�����Ƃ��ꂪ�ƂĂ�������ł��ˁB
��G�@�~������͉�������܂��H
�~���G�@���̒����ǂ������炢�����������Ƃł����H����Ƃ������A�C�f�B�A�Ȃ����A�Ƃ������Ƃł����H
��G�@�����ł��A�����ł��B
�~���G�@���[��B
�����G�@���A�傫�Ȃ��˂�ɂȂ��Ă���̂��A�_�Ɨp���̎��R���ł��B�͍����R���N���[�g�ɂ��Ă��܂����̂ŁA����Ȃ��Đ����������������Ȃ��Ă��܂��Ă��ł��B
�@���R�s�Ŗ��ɂȂ��Ă���̂́A�����t�߂ɓ��{�ł͉��R���암�A���N�����̈ꕔ�ɂ����Z��ł��Ȃ��Ƃ�����Ŋ뜜�킪�����āA���R���ł��ꂪ���߂ɂȂ�Ɛ��E�I�ɑ�ςȂ�ł��B�ڗ����Ȃ����ł����A�������M�d�Ȏ킪�����ł��B�������邽�߂ɂ́A���H�̍������l���Ȃ��Ⴂ����ł���ˁB�����Ԃ������̂ł����A�v�͐̂ɖ߂��Ηǂ��Ƃ��������̎��Ȃ̂ł��B
�@����ŁA�R���N���[�g�ł͂Ȃ��ۑ����g���Ƃ����肪�����ł��B���x���̂ł����A����͎R�̐��E�Ɣ��ɖ��ڂɊW���Ă��܂��āA�_�Ɠy������Ă���l���炷��Ɣ��ɍ������������邻���ł��B���̊ۑ��̑ϗp�N�����P�O�N�����Ȃ��Ƃ���������ł��B���i�͌���̂��̂̂R�O���̂P�Ȃ��̂ł�����A���炭�S����薳���Ǝv����ł����B
�@�����������ƂŁA�����������R�ی�I�Ȑ��H��C�ƌ��������l����ƁA�R�̐��E�ƒ��̐��E�A�����ēc��ڂ̐��E�����ɂ��ꂢ�Ɍ��т��Ă����悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B���������^��������Ă��܂����B�������A���R�s�̊ۑ��̂�̓o�^�Ǝ҂��������P�Ђ����Ȃ���ł��B�����q���X�ёg���̓o�^�����Ȃ��������̂ł�����A���ʂ�������S���������甃���܂����A����L���Ă����A���������ɂȂ�Ǝv���܂��B
�s���G�@���̃Z�b�V�����ł��i�ς̕���������������b���o����ł���B����ς莩�R�f�ނƂ����̂͂Ȃ��݂�������ł��ˁB����܂ł͂�����Ƃ��������ł��R���N���[�g���g���߂��܂����ˁB���ꂩ��͊ۑ��Ȃǂ̎��R�f�ނł����ׂ��ł��B
�@���̊ۑ����A���R�X�g�������Ȃ��悤�ɉ��R�������炢�ŋ������s���n��Ƃ����̂����z�ł���ˁB���̕ӂŕK�v�Ȃ̂͂��̕ӂ̎R�ō̂�Ƃ������Ƃɂ��āA�ׂ̈��쐅�n�͈��쐅�n�̎R�̊ۑ����g���Ƃ����悤�ɂ��Ă䂯�Αf���炵���Ǝv���܂��B
��G�@�ǂ��ł����A���ɉ�������܂����H
����G�@���A�͐�̐�����ۑ��̘b���������̂ł����A�������T�O�N���X�o�߂����Ƃ������ɂȂ�܂��B���̂Q�O�`�R�O�N���炢�ʼn͐삪���ɏ���ł��܂����Ǝv����ł��ˁB��X�͍��A�����̗�����Ȃ�ƂȂ����Ă��܂��B�n��̏Z���ł���Ȃ��猹���̌ւ�����������Ɋ����Ȃ��łȂ�ƂȂ����Ă��܂��ˁB
�@�s��̕��͐����q�̂�����݂͂Ȑ������ƌ����Ă�����ł����A��Ƌ��Ɉ���������炵�Ă݂�ƁA���̐�͂����������Ă��܂��Ă����ł��ˁB�����قƂ�Ǖ������鋛�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂�����ł��B���͔��Ɋ�@���������Ă��܂��B
�@��������ɖ߂��Ƃ����̂́A�R�сA�Ԕ��A�A�сA�_��̖��ȂǁA�F�X��X�̐������̂��l���A�n��ɍS������Ă�悤�Ȃ��Ƃ��K�v�ł��B���Ԃ͂�����Ǝv���܂����A�����������ɂ�������ƖڕW�ݒ�����čs���Ƃ����̂���X�̒n��̖������S�Ƃ������ɂȂ�ł��傤�B�����ĉ��R�s�̃}�l�͂��܂��Ƃ������ɂ����Ȃ����ȂƎv���܂��B
��G�@���R�f�ނɂ���Đ���C�����Ĕ����������߂����Ƃ�������ł��Ȃݐ�Ƃ����͐삪�����ł��B�����́A�{���̓V�R�f�ނ��g���ĕ�����������ł��B�����������i������Ă���Ƃ��ɁA����̐��̖��ɂ��Ă���قǂ̐F�X�Șb���ɂ��Ă��A�n��̂��̂��������Ă����Ƃ����������܂肵�Ă��Ȃ������Ƃ������ɋC�t������ł��ˁB������i�ςɎg���Ă��Ȃ������B
�@���i�J�������܂�n��ɂ�����̂����p���Ă��Ȃ������B�~������|�����Ă���l���\��ŁA���̒n��ɂ���ؔꖇ�Ƀq�m�L�̍�������āu�l���\�̃q�m�L���C�v�Ƃ����ĂP���~�ʎ��v��ꂽ�Ƃ������Ⴊ�����ł��B
�@���̂悤�ɁA�n��ɂ��鎩�R�f�ށA�V�R�f�ނ����p���ď��i�J��������ۂ̍l�����ɂ́A��̉�����Ȃ̂ł��傤���B��قǔ~����������������A�R�~���j�P�[�V�����̑��x�𑁂�����Ƃ������ɂ��W���邩�Ǝv���܂����A��́A�F�������̂Ƃ���ɂ�����̂��������Ă����Ƃ����Ƃ��A���ɏ��i�J���Ƃ����_�ł͉�����Ȃ̂ł��傤���H
�~���G�@�l���\��̎d�������Ă���Ƃ������ƂŁA��R�Z�N�^�[���ݗ����ꂽ�Ƃ��ɂ����ɍs������ł��B����3�Z�N�Ƃ����̂́A�l���\�여��̂R�������ō������Ђł��B������Ўl���\�h���}�Ƃ�����Ђł����B�����́A�قƂ�ǂ��̂�����̎Y���邽�߂ɂ�������Ђł��B
�@����ŁA�܂���{�͔_�Y�����Ǝv������ł����A�l���\�여��ɂ͕��n���Ȃ��̂ł����݂͂�Ȕ_��Ђ��Ȃ�ł���ˁB�����͑S�Ďl���\��ɗ���Ă����Ă��܂��܂��B���Y�҂͎����̍앨�͂�葽�����n���Ď����ɂ���������A�قƂ�ǃI�[�K�j�b�N�Ȃ�ĊW�Ȃ��ł��ˁB�F���l���\��Ō�̐����ƌ����Ă��邾���ŁA�����̎��ӂ̔_�Ƃ͔_��Ђ��Ȃ�ł��ˁB
�@��������ƁA����Ƃ��Ɂu�l���\�삩�痈�܂����_��Ђ��̖�ł��v�ƌ��������āA�܂�����܂����ˁB����ł�����ƍl���܂��āA�R�̕���������q�m�L����������ł��B����͔_��Ђ��ł͂���܂���B�ł��n���ł͊F���������ւ�ւ��Ă��ł��ˁB�l���\�q�m�L�Ƃ������O�����Ă����ł����A����͔����ۂ��Ȃ��āA������ƃs���N�F�����Ă��Č��ނɎg���܂��B�����������ƌ����Ă܂����B
�@����݂�A�������̂̋��������ł����A�V�R�̂����܂��B���͖l�A�����̗���ɏZ��ł��āA�����Ŗԓ����ăA��������Ă����l�ԂȂ�ł��B���������ڂŎ��������ƁA�A���͗��ʂ��Ă��܂������̃A�����_�ƂŌ����Δ_��Ђ��̍앨�̂悤�ɖl����͌����Ă��܂��܂��B
�@���ꂩ��A�����̎����Ƃ̔r���������������̂܂ܐ�ɗ����Ă��܂��B����ł��Ȃ���̎��R���c�������Ƃ����ƁA�����l�����܂�Z��ł��Ȃ������Ƃ��������Ȃ�ł��B����ƁA��Ƃ̊ւ��������Đ������o���Ă����Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂�
�@�B�l�������ɏZ��ł����Ƃ��ɁA�܂��A�����̂邾���Ő������Ă���싙�t�̂��������܂�������B�싙�t���O�l�͂��܂����ˁB����������ł��B���̎��A�l�͔�����͉̂����Ȃ�����Ȃ����Ǝv������ł��B������A������͎̂����ō��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ǝv������ł��B����������͎��R�̂��̂ɋ߂����́A�l�C�`���[�̂��́A�I�[�K�j�b�N�Ȃ��̂łȂ��Ƃ����Ȃ��B����������ƍl���܂����B
�@�_�Y���͔_����g���Ƃ������i�ɂȂ�Ȃ��Ȃ邩��A���̎��A�R�ɐ����Ă�q�m�L������"�q�m�L���C"�Ǝv������ł��B�q�m�L���C���Ă����Ă��ق�܂��̂̃q�m�L���Ƃ��Ⴂ�܂���B���̎��Ɏv�����̂��A�s��Ń}���V�����ɏZ��ł�l�A���ꂩ��r�W�l�X�z�e���ɍs�������Ȃ́A���j�b�g�o�X�ɓ��邶��Ȃ��ł����B����Ȃ��̂��ƁA�����A�l�Ȃ��܂ł���Ȃ���ł���B�ł��A�����������C�ɂł��|���ƈꖇ�̃q�m�L�̔��ׂ���q�m�L�̂����C�ɂȂ��Ă��܂��B�������ł���B���������l���ŁA�P�O�Z���`�l���̔Ɂu�l���\�̃q�m�L���C�v�Ƃ����Ĉ���o�[���Ɖ�������ł��B
�@�q�m�L���܂��V�R�q�m�L�̃G�L�X���g���āA���̒��ɔ��P���ʐZ�������̂�܂ɋl�߂ĉ��M���������ł��B����́A����������ł���������ł����邱�Ƃ��o���܂��ˁB�߂���߂��Ⴭ�[�e�N�ł���ˁB�������ʂȋ@�B�Ȃ͂���Ȃ��ł��B�Ă��Ƒ܂Ɗ��M�V�[��������Ώo���Ă��܂��B
�@���ꂪ�s��ɏo����Ă���Ԃɒ��̔��q�m�L�̍�����ǂ�ǂ�ǂ�ǂ�z�������ł��B����ŁA���鍠�ɂ͓��������悭���ՂȂ��Ȃ��Ă��ł��B�������P�O�Z���`�l���̔���Ă�����ƍH�v���������Ńv�[���ƃq�m�L�̍���ɂȂ��Ă��܂���ł��ˁB�����"�q�m�L���C"�ƌ�������ł��ˁB������x���Ǝv���܂����ǂˁA�����Ɩ��Ȃ����Ԃɒʂ�����ł��ˁB�ی����ł͗��̌��ޗ��Ƃ��`�F�b�N���ꂽ��ł������̖������������ł��ˁB�т����肵�܂������ǁA���ꂪ�����ɂP�S�O�O���~�̏����ɂȂ�����ł��B
�@�n���̋�s��������̕��ɑe�i��i�悷�鎞�ɈȑO�͂قƂ�Ǔ���A�W�A�Ő��삵�Ă����v���X�e�B�b�N���i�������Ă���ł��ˁB���ꂪ�����͍l����悤�ɂȂ����̂��A����A�W�A�łۂ�ۂ��Ă������̂��������Ɍ����Ȃ��炨�q����ɂ���������A�O���łU�O�O�~�́u�l���\��̃q�m�L���C�v��i�悷�邱�Ƃɂ�����ł��B����łP�S�O�O���~�������Ă��ĂƂ������ƂɂȂ�����ł��ˁB
�@����ޒB���u������L��������܂����v�Ƒ�ʐ��Y�̂��̂�n���̂ł͂Ȃ��A�n���̕����g��Ȃ��������ȂƎv���n�߂���ł��ˁB���͂���Ȃ������ȂƎv���Ă���ł����A�Ȃɂ�������̂��Ȃ����玩�R�n�̍�����v�[���Ƃ����āA�M���̃��j�b�g�o�X���q�m�L���C�݂����Ȃ��Ƃ��l������ł��B���ꂪ���܂�������ł��ˁB
�@�l�̐헪�́A���̏��i�͐��̒��ɏo���ȁA�X�ɒu���ȁA�B���Ƃ��A�Ƃ��������ŁA�Ⴆ�Ήc�Ƃɓ��{�����֍s������A����Ȃ���M���̂Ƃ���ɂ����Ȃ��ł�����Č����Ȃ���A�^���̃q�m�L���C�̂Ƃ���ɓ��{�����ƏĈ�������������炢������Ȃ����ƌ����Ă���ł��B�Ă�����ăI���W�i���ł����ĂˁB
�@�܂��A�d�C��������_�ꂽ���ɂ͂ۂ�Ƃ��Ă���A�Ȃ�Ă����������ɓW�J���Ă�������A�R�N��ɕ�������т����肵�܂����B�ꉭ����܂������Č�����ł���ˁB���[�A���ꂪ�ꉭ�~�H�f�U�C���P�O���~�������̂ɂȂ����Ďv���܂����ˁB���C�����e�B�[������Č��������ǂ����x�������ł���B�����Ɏ���Ȃ����炠���܂ւ��āB
�@�܂��A�����������ɖl���m�b�g���Ă��Ƃ����̂͂����������Ȃ킯�ł��B�����āA�ɔ��������āA��������ă|�[���Ɣ����āB�������������̂��āA�l���\��Ɏv�������邩��o�Ă���킯�ł��B�{���ɉ��Ƃ��������Ǝv������A�C�f�B�A���o�Ă���킯�ł��B
�@���������炱�̑��Ȃ�Ƃ����Ă���Ƃ����Ă�₯�ǁA�����o�Ă��ւ�Ƃ������Ƃ͂��̑��Ȃ�Ƃ��������Ǝv���ĂȂ��A���Ȃ��Ƃ��܂��v���Ăւ�ƌ������ɂȂ�܂��ˁB
�@�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���̑��ɂ��������u�Ƃ������̂�������̂�����ǁA�Ⴆ�ŏ������Ƃ��ɗ�����������̉w�̌�����������ł����A����͂ȂႤ�ȂƎv����ł���B�����ǂ����Ō������̂�����̂ł���B��t���ł��É����ł�����Ȃ��Ă܂�����B���������̂�����ƁA�����̐l�͂����������l���Ă��Ȃ��A���������ǂ��ł������낤�Ȃ��Ďv���Ă��܂���ł���ˁB
�@�F�{�̏������ɍs������A�����͐��̗т̑��ł����珬���h�[���Ƃ����̈�قɂ͖��ꐶ�����g���Ă��ł���B������Z���X��������Ȃ���ł���B���������̃C���[�W��`���Ă����v�Ƃ͒N��Ƃ������Ƃ��l���āA�܂��A�S���ō��킯�ɂ͂����܂���̂ł����������Ƃ����낢��Ɛݒ肵�Ă���Ă����ł��B
�@���Ƃ����āA���̌����S���ɑ��Ăł͂Ȃ��A���ꂼ��̌��z�ɂ��ĒN�̐v����Ԃ������Ƃ������Ƃ܂Őݒ肵�āA�S�Ĉꏏ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ���ł��B�������͂�������܂�����B���̎��ɂ͂��̌��z�ƂƂ����悤�Ɏ��������ō�肽�����̂̃v���Z�X�����������ŃZ�b�g���Ă��肢����B
�@�ł��u�搶���肢���܂��v�ƌ����Ă��܂���������������܂����B�搶�����̂��ԈႢ�ł���A���z�ƂɁB�u���������̂���A�����������ɍ���Ă���v�ƌ����̂��v���Z�X�ł���B���������Ӗ��ł����A�����ǂ������o�����X�ŃZ�b�g���Ă����̂��Ƃ����̂��Z���X���Ǝv����ł��B���m������B���������v���Z�X��厖�ɂ��Ă���̂��ȂƂ��������܂߂āA���̑��ł͂���Ȃ��̂���܂芴���Ȃ�����A������ڂ��ڂ��l������ǂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�l�͐����Ɍ����Ă��܂��Ă܂������邩�ȁA�Ǝv���܂����ǂ��A���ꂪ�{���̏��ł��B
��G�@�ǂ��ł����A���̕��łł��ˁA���͎����͂��̓y�n�ɂ����������̂����邩�炱���������Ƃ�������ƕ����Ă݂����Ƃ������Ƃ͂���܂��H�ǂ��ł��傤���H
�Z���G�@���͐�قǂ̘b�̂悤�ɁA�@���Ɍ����̉͐����邩�ƌ���������X�̎g�����Ǝv����ł��B�����q�ł͏��a�R�W�N�̃M���j�ЊQ�����������Ɍ�Ճu���b�N���g���Đ������Ă��܂��A��ɂ�����Ȃ���Ԃł��邤���A�����p��������o�Ă��āA��X���q���̎��ɗV�삩�炷��Ɣ��ɍr�p�����ł���Ǝv���܂��B�����ɖ��A�������Ȃ�����ł���܂��B
�@�����������ŁA�g��������Ɏ����Q�����A��������A�S�~���E�����肵�Ă��܂��B����ł����ɗǂ����������ɗ������ƌ���������X�̎g���ƍl���Ă���܂��B���̂悤�Ȏ�����A�Ƃ�킯���R���̕�����ӂꂠ���̐��Ӎ��Ƃ������Ƃ��܂����B�V�R�ނ��g���A��������ł�����鐅�Ӎ��Ɍ����ĉ����A�h�o�C�X����������Ǝv���܂��B
��G�@���ɂ�����������ΐ������Ē��������Ǝv���܂��B��ŃQ�X�g�̕��ɂ��b���Ă��������܂��̂ŁB
�Z���G�@���͗��j���D���ŕ����̗��ɗ���̂Ɋy���݂ɂ��Ă�����ł����A������n�R���m�s���I�Ȃ��̂����������Ĕ��ɂ�������v���܂����B�Ⴆ�Ώ��z�{�ƌ������́A���j�w�i����肭�n�������Ă����ł��ˁB
�@�����͌����̑��Ƃ������ƂŎ��R�̎��̘b�����\�����Ăł��ˁA�u���҂͌o���Ɋw�сA�q�҂͗��j�Ɋw�ԁv�Ƃ����i��������܂����A���Ƃ��Ă̓������o�����߂ɂ������Ɨ��j�w�i���ɂ��Ăق����ȂƎv���܂����B
�Z���G�@�K�[�h���[�����ޖō��Ƃ��A�X�ɓd����n�ɐ��点��Ƃ����̂����Ƃ��Ă���܂��B
�Z���G�@�����̂Ƃ���̐�͂��ꂢ�ɂȂ������厖�Ȃ��̂������Ȃ�ƌ�����������܂��̂ŁA���������ؖڍׂ��Ȏ�����������ȂƎv���܂��B�傫�ȔL���������Đ�Ȃ��ŗ~�����Ƃ��肢�����̂ɁA�����Y��ɐ��Ă��܂��Ă��āA���̉Ԃ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă��������������̂ɂȂƎc�O�Ɏv�������Ƃ�����܂��B
�Z���G�@���́A�l�������Ȃ���ł��ˁA���̑��́B�R�R�p�[�Z���g�ȏオ����҂ł����āA�����������Ől�͂ǂ������邩�Ƃ����������������������Ǝv���܂��B
��G�@����ł͎��Ԃ����܂肠��܂���̂ŁA����܂ł̎���ɓ���������̂���������Q�X�g�̕��ɓ����Ă��������āA���̑��ɂ��ꂾ���͓`���Ă��������Ƃ�����������܂�����H�{����̕����珇�Ԃɂ��肢�������Ǝv���܂��B
�H�{�G�@����̉��s����̂��ꂩ��̔_�Ƃ̗L����Ƃ����b�̒��ŁA����҂̔_�Ƃ�s�s�Z���̔��̘b����������ł��B���͂����ЂƂA�_�R���̖����A�s�s�Z���ɑ�������Ƃ������̂�����Ǝv����ł��B
�@������ŏ��ɘb���܂������}������w�����Ȃ̂ł����A��������Ă����̂V�T�O�O�N���炢�O����ߍ��ȏ����̒��Ő����Ă���ׂɂ͂��̂������x���S���Ƃ��A�V�C��ǂޗ͂ł���Ƃ��A�����܂����쐫�I�Ȑ����͂�����킯�ł��ˁB
�@�������A�l�Ԃ��{�B�����邱�Ƃɂ���Ă������������̂������Ȃ��Ă����āA�����ŎY�����鎖���o���Ȃ��ĂȂ��Ă��܂����̂ł��B�l�Ԃ��������o���Ă��܂�����ł��ˁB�u�����A����ȋ��ɂȂ����́H�v�Ƃ����悤�Ȏv��������킯�ł��B�쐫�̋��Ɣ�ׂ�ƁB
�@���́A�[�ׂ����̒n��ɂ̓I�I�T���V���E�E�I���ƂĂ������Ă����Ƃ����b������܂����B�Ȃ������Ă�����ł����ƕ����ƁA��Ԃ͉a�ɂ����ł͂Ȃ����ƁB�A�}�S��������Ă���A�Ƃ�����ł��ˁB�̂̓A�}�S���I�I�T���V���E�E�I���l�낤�Ƃ���Ƒ�ςȎ��������ł��ˁB�����Ɠ������Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�{�B�A�}�S�͌x���S���Ȃ��̂�т�Ƃ��Ă�����̂ł�����A�ȒP�ɂς����Ɗl��Ă��܂��B������a���L�x�ł���������Ă�������q�������n�߂��̂ŁA�V�R�L�O���̃I�I�T���V���E�E�I�������n�߂č����Ă���Ƃ������ƂȂ�ł��B
�@�l�Ԑ��E���ł��ˁA�܂��Ɏ��R�E���炾��Ă������ɂ���Ė{���̐l�Ԑ��������Ă���Ƃ����Ƃ��낪����B��s�s�ŁA�Ⴆ�}���V�����̏\���K�ɏZ�ސl�B���ł��ˁA�q���A��Č����ɍs���ăo���̉Ԃ��炢�Ă���̂Ŏq���Ƀo���̉Ԃ̓����������悤�Ɓu�o���̉Ԃ���A�����k���ł����B�ǂ������ł��傤�v�ƌ����B����Ǝq���́u�͂��A�g�C���̓������ˁv�B����ł͉����{���Ȃ̂��킩��Ȃ��B�g�C���̖F���܂��ŏ��ɂ����āA�o���̓����������^���Ă�Ƃ����悤�Ɏv���B
�@�܂��Ɏ��R�E���痣��鎖�ɂ���Ęc�ɂȂ��Ă��Ă����ł��B���͒n��Ɠs�s�̍���҂Ƃ̌𗬂̕��������̂ł����A�{���͎��R�̎���S���m��Ȃ��q���B�ɂ��낢��Ȏ���̌�������Ƃ����Ƃ���ɁA���͔_�R���̑傫�Ȗ����������Ȃ����ȂƎv���܂��B
�@���ɂ̓s�s��������莩�R�E����u�����ꂽ�悤�ȏ��ŕ�炵���������܂���炿�̐l�Ԃ�����O�����炢�ɂȂ�Ƃ�����ł��ˁB���̐�ɖ����͂Ȃ��Ǝv����ł���B�������l�Ԃ̈�`�q�͌㐢�ɓ`�����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������ł��ˁB
�@��͂�R���Ő�����l�B���㐢�ɐ������l�Ԃ̈�`�q��`���Ă����Ǝv����ł��ˁB���������������R���ɂЂƂ���Ƃ������_�œs�s�ƎR���̌𗬂��l���Ă����ׂ��ł͂Ȃ����ȂƂ����C���v���܂��B
�~���G�@��قǎl���\��̔_�Ƃ͔_��Ђ��Ƃ����܂������A����C�����Ȃ�����ȂƎv���Ă��܂����B�{���ɑO�͂�����������ł����A���̂Q�C�R�N�قǑO���疳�_���Ƃ����̂��l���\�h���}�ł����n�߂Ăł��ˁA�X�[�p�[�̒��ɃR�[�i�[��݂��Ċ��S���_����n�߂܂����B
�@����������͎��͒n���̐l������Ă����Ȃ���ł��ˁB�h�^�[���҂ł��B�������痈�Ďl���\��ɗ��Ĕ_�Ƃ����n�߂��l�����ł��B���͂܂��I�[�K�j�b�N�Ƃ����̂͒n���̐l�̓��̒��ɂȂ��ł��B�ł����̂h�^�[���̕����ł��ˁA���̕�����ܐl���炢���l���\�여��ɏZ��Łu�l���\��Z��Ёv�Ƃ����̂�����Ăł��ˁA���̂����̌܂̔_�Ƃ̐��i������Ɩ��_���Ƃ�����悤�ɂȂ�����ł��B
�@����͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H�܂�A�����Ɍ��X����l�͋C�t���Ȃ��Ƃ������A�R���v���b�N�X������܂��ˁA�s�s�ɑ��āB�����獑�̌������Ƃ�����Ȃ̂��蕷���Ă��ł��B������A�킩��Ȃ���ł��B�ыƂ�_�Ƃ͍��ł������ł��B�������ςȂ��̂��Ƃ��Ă�����ł��B
�@���ꂪ�u�Ⴄ��Ȃ��H�v�ƁA�ŋ߂�����ƕς�肩���Ă��Ă��܂��B�܂�A�l�����������̂́A����ς�l���\��ɏZ��ł݂���C���[�W�Ⴂ�܂�������B��͂���̂܂܂ŖL���ł����B�ł������ɏZ��ł���l�������L�����ǂ����Ƃ����ƁA����͍l���Ă��܂��Ƃ��낪����܂����B�����Ɏ��یܔN�ԏZ��Ŏv������ł��B
�@�����A�l�͂����ɂ͎R�t�ɂ͎R�t�̐����������Ă��邶��������Ǝv���Ă܂����B�R�ɍs���O�ɂ��Ȃ��̎d�|�����āA�A���Ă݂Ă��Ȃ����������Ă�팾���āA��������Ăɂ��ĐH���āA������܂݂Ɏ�������ŁA�Ƃ������܂�Љ�̕ς��l�Ƃ͊W�Ȃ��ɐ����Ă�悤�ȁA����Ȑl������Ə���Ɏv������ł܂����B���������ۂɂ͂���܂肻�������l�͂��Ȃ��ł��B
�@�����玩���̃v���C�h�����B�R�̎d�������Ă�Ȃ�R�̎d���̃v���C�h�������Ă��A�C�̎d���Ȃ�C�̎d���̃v���C�h�������Ă��B���ꂪ��{�̐��������Ǝv���܂����ǂ��A�l���ǂ������邩�͖l�炪�T�W�F�X�`�����ł��܂���B���̕����������߂���̂��Ǝv���܂���B�����炱���̎R�̒��ŋM���͂ǂ����������������Ă����ł����Ƌt�ɖ₢�����B�M���̓v���C�h�������Đ����Ă��܂������ƕ��������B�ȏ�B
�s���G�@��قǂ̕����̎��₪����܂������A�����������Ǝv���܂��B������Ò��̒����݂��Â�����ƌ����Ă��A�����̂��������Ɍ����͖���������ł��B�������A����͒|�R�鉺�ł����A�|�R�鉺�����X�T���m�E�T���W���E�i�R���R��H�j�������̂ł́H�Ƃ����悤�Ȏ����������蒲�ׂė~�����ȂƎv���܂��B
�@���̒����畐���̎��������ƌq���肪�o�Ă����Ȃ����Ǝv���܂����A�����̃t�@���Ƃ��Ă����̕ӂ̔w�i��m�肽���B�P�ɕ����͂����̐_�Ђׂ̗Ő��܂�ĂP�U�̎��ɓ����čs����������Ƃ�����������A�҂������̂������Ȃ����ȂƎv���܂��ˁB
�@����ŁA���������̂��ꂾ���̑̈�ق������ł�����A�����̑S����������Ē��������ȂƎv���킯�ł��B�ł������ė��N�m�g�j���������Ă��邤���ɂƂ����悤�ɂ͍l���Ȃ��Œ��������Ǝv���܂��B
�����G �n���ٌ̕�Ƃ����킯���Ⴀ��܂��A�����͊X���̒��ł����Đl�̍s�����������������ƌ������A�퍑����ɗ̎傪�������ς�������ɂ���ė��j�̌֎����Ƃ������̂��Ⴂ��ł��ˁB������܂����j�Ȃ�ł��B
�@����ȋ����ʂ�ŁA�قƂ�nj�ʂ����Ȃ��悤�Ȓn�`�\�����Ƃ炴��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���ƌ���������A�ǂ��ɂł�����悤�ȕ��͋C�Ƃ������͎̂��͐����q�ɂƂ��Ă͗��j�I���Y�Ȃ�ł��ˁA����Ӗ��ł́B����͎d�����Ȃ���ł��B�X�����ɂ͊X�����̕��͋C�������Ă��܂����̂ł��B
�@�������A���ꂾ���ł͂������낭�Ȃ��̂ŁA�����q���X�����Ƃ��Ă̓�����O���������Ƃ����łȂ��āA�����ƍL��I�Ȏ��_�������Ƃ��K�v�Ȃ�Ȃ����ȂƎv���܂����B
����G�@�s���A������ƕt�������܂��ƁA�����͔��ɗ��������������ƌ������Ȃ�ł��ˁB������A�ȊO�Ɠ��Y�������̒n��Ɉ���Ă��Ȃ��Ƃ�����������܂��B�����A����������c�̂��������ǂ����Ă��������ȂƎv�������̂́A�n�������Ƃ����낢��Ȏ���w�i�̒��Œn�����ւ������Ă邩�Ȃƌ������Ȃ�ł��B
�@�������̂��낢��Șb�����f��������A�����т�������肵�āB�����������̌����т�������̂͏��߂Ăł��ĂˁA����ς茩�Ȃ������芴��������A�����������̐X�ɂT�O�N�����ď��߂Ċ��������Ƃ����̂͂ǂ����A���Ȏ��Ȃ�ł����A������V�����������ȂƎv���Ă��܂��B
�@�n��̎������ǂ�����Ċ������Č��点�čs�����Ƃ������́A���݂̂悤�ȃR�X�g�������ǂ����߂��Ă��鎞��ɑ������邩�ȂƎv���܂����A���ꂪ�n��̂������ȂƂ�������m�F���čs�������Ǝv���܂��B
�@�i���o�[��������I�����[������ڎw���Ƃ����̂́A�I�����[�����͂Ȃɂ��K�͂��g�債�Ȃ��Ă��o���鎖�ł�����A���������������ł��ˁB
�@���ꂩ��A���̂�����͖�Q�l�ɂP�l���U�T�Έȏ�̕��Ƃ����킯�ł�����A���C�ȃV���o�[�Ƃǂ̂悤�Ɋւ��������Ƃ��������d�v�ŁA�̗̂��j��`�����ēx�V�����n��Â���̒��ɑg�ݓ���Ē������Ă����Ȃ���Ƃ����v�������������Ă���܂��B
�@���Ƃ��Ă̎v�����S���`����ė��Ȃ��ȂƂ������͂��������ʂ�Ȃ�ł����A�������������Ƃ�����A���Ȃ��Ƃ��v���������Â��Čp�����Ă����A�{���Ɍq����B�{���ɂȂ�ΊF����̂悤�ɁA�p�����čs���ƌ������ł�����A���Ȃ��Ƃ��d�|�������Ă����Ȃ��Ă͂�����ȂƂ����v���͋��������܂����B
��G�@���肪�Ƃ������܂����B�����̃Z�b�V�����A����̃Z�b�V���������X���w��ōs���Ƃ����̂́A��͂�A���̐l�̐��������o�Ă���Ƃ����Ƃ��납��Ȃ̂��Ǝv���܂��B���ꂪ���́A��X�̐S�����ꂽ��A�ڂ̗��Ƃꂽ�肷��Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB
�@�ł�����A�����ƈقȂ镶���Ƃ������̂ɋ��ۂ����Ȃ��Ŏ����X���Ă݂�Ƃ����������͍���̃e�[�}��������Ȃ����ȂƎv���܂��B
�@�����ƈႤ�����Ƃ̌𗬂��y����ł����A�����Ă����Ŋy����ł���l�B������B���������������߂邱�Ƃ����͊��������߂�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�����犴����^���钬�Ɏ��͍s�������Ǝv���܂����A������^����l�ɉ���Ă݂����A�����Ď������o�����犴����^�������Ǝv���Ă���킯�ł��B
�@����͕��i�ł�������A�l�ł�������A�H�ו��ł������肷��Ǝv���܂��B�Ƃɂ��������������낢��Ȃ��̂Ɋւ��Ă������̔~������Ƃ��H�{�����s������A�����č�����炢�炵�Ă���Q�X�g�̕��B�����]�����Ȃ��A���҂𗠐�Ȃ��Ƃ������Ƃ��𗬂̒����琶�ݏo���čs���B���̂��߂ɂ���������c������Ǝv���܂��B
�@�S���������痈��ꂽ���A�n��̕����A������̑O�̔ӂ��炨�t�����������������������̒��Ŋ�������������A�ڂ̗���ꂽ�肻���ŐV�����������������肵����K�����Ǝv���܂��B
�@�܂��ڂ̗���ꂽ�r�[�ɂ܂����̖ڂ̗��o�Ă��Ėڂ̗��炯�ɂȂ��Ă��܂��̂���X�̐�������Ȃ����ȂƎv���܂��B�ق��R�[�f�B�l�[�^�[�ł������A�݂Ȃ���M�S�ɍŌ�܂ŕ����Ă��������Ăǂ������肪�Ƃ��������܂����B����ŏI���ɂ������Ǝv���܂��B
[��]
*******************************
�ҏW��L
�@�����̂ނ��c�̔��Z�b�V�����͂ǂ��������ł��傤���B�M�҂̘b�͂��悤���Ȃ��ł����A���z�{�̎s������A�l���̔~������Ȃǂ͎��X������܂����A�������ł��B���̂悤�Ȑl�ނ��������̒��ɂ�����Ȃ��ƑA�܂����v���܂��B���Â���̑傢�Ȃ�q���g�����邵�A�킪���̉ۑ���傫�����Ƃ����킩�肾�Ǝv���܂��B
�@����A���ʂ̋����ɂ͍��N�̖����z�V���|�W�E���̋L�^���f�ڗ\��ł��B
�@�����ɂ́A�ǎ҂̊F�l�ւ̃A���P�[�g�p����Y�t���Ă���܂��B�n��1�N�ڂ��}���A�X�ɂ��ǂ����ʂÂ���ɊF�l�̂��ӌ������������B��낵�������͂����肢���܂��B
�@���̂����Łu���v�́A�C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ��Ă���܂��B�A�h���X�͉��L�ł��̂Ńp�\�R�����������̕��̓A�N�Z�X���Ă������������B
http://www.miyazaki-nw.or.jp/yamame/kawarabanfm.html
�@���̎��݁u�����Łv��14�斯�̊F�l��Ώۂɔz�z���Ă���܂���14��ȊO�̕��ɂ�������ł��܂��̂ł��Љ�������B�X�����Ƃ��ĔN����~�̂����S�����肢���Ă��܂��B�i���j