�@2002�N8��1�����@����1��1�����s
�@���s�ҁ@��܂߂̗��@���ҏW�@�H�{ ���@�܃P�����Ɖ�4615�@�@�d�b0982-83-2326
�@�{���ł́A�����I�̂���6�����c�7���ɕύX�ɂȂ�܂����B���̂��ߍ����͋c����W���Ƃ��ĕҏW���邱�Ƃɂ��܂����B�ȉ��������ɉ����Čf�ڂ��܂��B
---------------------------
2002.7.5�@�S�����c��
�@8������̖{��c�J��ɐ旧���A�ߌ�ꎞ���c���T���őS�����c��J�Â���A7���c��̐R�c�\��ɂ��ċc�^����̕�����B
��8���̖{��c
�E���P�n�S�����ψ���̑I�C���ӂɂ���
�E�Œ莑�Y�]���R���ψ��̑I�C���ӂɂ���
�E�����̈ꕔ�����ɂ���
�E����14�N�x�܃P������ʉ�v�y�ѓ��ʉ�v��\�Z�ɂ��Ă̒�ė��R�̐����B
�E���ʂ̒̕��Œ����̏��M�\��������B
�E��ʎ���́A�����̏��M�\�����Ă��玿��ł���悤�ɒʍ�������9����17���܂łƂ���B
��17���̖{��c�B
�E��ʎ���Ɛl���Č��R�c�̌��B
��23���̖{��c�B
�E�����̈ꕔ�����ɂ���
�E����14�N�x�܃P������ʉ�v�y�ѓ��ʉ�v��\�Z�ɂ��ĐR�c�̌��B
�E���ɒ�Č����u�[���̗��ӂꂠ���𗬋�Ԑ������Ɛ��i���c��v�Ȃ�5������B
�E����̋c���^�����҂́A13�ԉ��{�N��c���A�P�ԋ����t�j�c���Ƃ���B
�������ď����Ɣ_�щے���胏�C�i���[�֘A���Ƃ̈Č��ɂ��Đ�������B
�����̗v�|���̂Ƃ���B
�@�_�Ƃ̊������̐V��������Ƃ��ČK����n��ɓs�s�Ƃ̌𗬎��Ƃ̑��i��}��A�_�Ƃ̌o�c����ƌ�����͂���{�݂Ƃ��āu�܃P�����C�i���[�v�̌��݂Ɏ��g�ށB
�{��̊T�v�́A
�E�܃P�����C�i���[�̐������i�B
�E�O���[���c�[���Y�����_�{�݂̐������i�B
�E���Y�i���Y���H�{�݂̐����Ƒg�D�琬�B
�E�_�ƂƂ̂ӂꂠ���̌��{�ݐ����B
�E���y���������y�H�����̊m���B
�E�ӂ邳�ƌ𗬎��Ƃ̑��i�A�Ȃǂł���B
�@��̓I�ɂ́A�o�c�\���ƂƂ��āA���ʐv��8,500��~�i�����\�Z�Ō���ρj�A�A����70,000��~�A�����p�n����15,000��~�A���C�i���[654,000��~�A�e�핪�͒�����3,000��~���őS�̂ł�748,000��~�ł���B���A����371,000��~�A����17,000��~���t���A�����S���̓�336,300��~�͋N��\�肵�Ă���B
�@���̓����N�x����79,000��~��\��A���@���̕t�ю��Ƃ��̑����܂߂�88,961��~��{�N�x��v�サ�Ă���B
�@�⏕����8��15����t�\���A8��30������������ށB
�@�^�c�́A���ꂩ���O�Z�N�^�[�̐V��Ђ�ݗ����āi���ߔ����o���ʼn_�C�A�i�`�A�n���Z������\��j���̎{�݂Ƃ��ĐV��Ђɉ^�c���ϑ�����B�܂��A���ꂩ��v�悷�郌�X�g�����i100�Ȓ��x�̋K�́j���̎{�o�c�������ĐV��Ђōs���\��B
�@���C���̐��Y�ʂ́A����21�N�x���߂ǂ�132,000�{�������݁A�S�ʒ����Y�Ԃǂ��Ń��C�����S�ʒ����Ŕ̔��\��B
�i�_�]�F���̎��Ƃ́A3���̒���̓��e��{��4��1�����ɂ������Ƃ����ʎ���ł��Ƃ肠���A�S�����c��̐ȏ�ł��A���ƌv��̖��_��˂��āA�����������Ԃ������ė��肠����ׂ����Ǝ咣�������A�x�点��ƈƉ��̒��R�Ԓn�����������Ƃ����߂ɂȂ�܂���Ƃ����Ďd���Ȃ����ӂ����o�܂�����B
�@3���Ɋ��Ƀ��[���͕~����Ă���킯�ł�����A���Ƃ͐��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A��O�Z�N�^�[�Ƃ̌_��A���Y�҂̕s���ɂȂ�Ȃ��悤�ȕ���A���̕��S�̌y���A�Ђ��Ă͎��Ƃ����܂��Ȃ��悤�Ȓm�b�̑n�o�ɂ��ċc�_���d�˂Č������Ă������Ƃ��d�v�B
�@�Ԃǂ����Y�҂���̔������ꉿ�i������܂�1kg����500�~�ł������̂����N�͌��z����Ƃ����̂ł��̌������ӂ��Č���肽���B
�@������ɂ��Ă��A���̎��Ƃ𐬌�������ɂ́A�X�L�[��ȏ�̗U�q���ʂ̂���m�b���o���Ȃ���ΐ������Ȃ��ł��낤�B���C�i���[���݂ɂ��܃P�����ɑ����̐l�X���K���Ƃ������z������Ă���l���ȊO�ɑ����B���Ƀ��X�N�̍����q���ł���B�j
�����ɗыƐU�����66,582��~�̒lj�����v�コ�ꂽ�Č��ɂ��Đ�������B�v�|���̂Ƃ���B
�@�X�ёg���̗a�����ɂ��Ė{�N�x��\�Z�ɁA�X�ёg���ݕt��10,000��~���v��B����́A�O����X�ёg������������������悤�Ɋe������10,000��~�ÂA�a���̒����A�����A���V�e��2���͊��ɕ�\�Z�Ɍv��ς݂ł���B�X�ёg���̎x���ׂ̈ɕK�v������B
�@�X�ђn�抈���x����t��42,890��~���v��B����́A���R�Ԓn�x���⏞���x�ɏ��������x�ŕ���14�N����18�N�܂�5���N�Ԃ̎��Ƃł���B
�@30ha�ȏ�̒c�n�ŋ��菑�������킵�A1ha������ꖜ�~��⏕����B��50���A��25���A��25����60�N�ȏ�̎��R�сA35�N�ȉ��̐l�H�ѐ����̎x���ł���B
�@���̑������y�яo�����Ƃ��Ė؍މ��H���ʎ{�ݐ����Ƃ���4,600��~�v�サ���B
�����Ɋ��ے�����X�ь������Ɣ��35,154��~��lj�����42,000��~�ɂ������Ƃɂ��Đ�������B�v�|���̂Ƃ���B
�@�X�L�[��ւ̈ϑ���20,000��~�̕�ɂ���
�E���̎����́A�X�L�[��̊Ǘ��^�c�ɕK�v�Ȏ����ł���B
�E�ʔN�ٗp��6������A�X�L�[�V�[�Y���ȊO�͉_�C�ɏo�����Čo��S���Ă�����Ă���B
�E�_�C�̊e�n�x�X�ŃX�L�[��̂o�q���������Ē����Ă���B
�E�I�t�V�[�Y���̉^�]�������K�v�A���̗��R�ɂ����̂ł���B
�@�H��������15,154��~�ɂ��ẮA��3���t�g�̏C���A�X�L�[�Z���^�[���̃g�C���r���C�U�Ȃǂł���B
�i�_�]�F�ϑ����ɂ��ẮA��{�_�����A���̏ꂻ�̏�Ō��肳��Ă���B���N�́A1���~�̒P�N�x�������łĂ���̂�����A�^�c�ϑ������o�������A�����Ǝ��v�̂����铊���A�Ⴆ�Βʏ̒n���J�Ƃ���R�[�X�̋��̕������i�������苷���Ċ���ɂ����A�����V�������Č��������Ă���댯�ł��邽�ߒi�����Ȃ����čL���铙�̕�C�Ƃ��A���т����Q�����f�ɂȂ��郌�X�g�������̃R�[�X�̐V�݂Ƃ��A�X�m�[�{�[�_�[�̂��߂̃R�[�X����������X�L�[��̎��v����ɂȂ�B�����v������͂��邱�Ƃňϑ����𗎂��ׂ����������B�j
�����ɐŖ��ۂ���A�l���Č��ɂ��Đ���������B
�������ĕ����ۂ���f�Ï���Ƃ���48,807��~����\�Z�Ɍv�コ��A���z57,167��~�ɂȂ������Ƃɂ��Đ�������B�v�|���̂Ƃ���B
�E���݂̎��Ȑf�Ï��́A26�N�o�߂��ĘV�������Ă���B
�E�~�n���ؒn�ƂȂ��Ă���B
�E���̂��߁A���a�@�ɗאڂ���120�u�A���Ɣ�25�C700��~�K�͂ŐV�z�������B
�����̌�A������Ђ����ݐꖱ��莖�ƊT���̐�������B�v�|���̂Ƃ���B
�E�����݂̐��i�́A���ݕ����A�k��B���ʂ𒆐S�ɋ�B�Ǔ��Ŕ̔���L���Ă���B
�E�������ނ́A�ڂ��܂��ċ��x������A�F���悢�A���ꂪ���Ȃ��Ȃǂō����]��������B
�E����́A�ƈ���̐��i����������Ō������Ă���B
�E���i���s�������B���A���A�����ƈ�����g�p�����{��ɑ��Đ��P�n3���̏��i��5��~���s����\��Ō������Ă���B
�@�{�ݐ����ɂ���
�@.�����{��
�����@3�������Ɣ�90.300��~�Őݒu�B����ɂ��A�����ނ̐��Y�ʂ͔N��6,202�����b�ƂȂ�B
�A.���i�ۊnjɁA���Ɣ�48,300��~�B
�B.���i�����i�ϑ��u�A���Ɣ�10,500��~�B
�C.�O���[�f�B���O�}�V�[��1��A���Ɣ�7,980��~�B
�D.�d�ʑ����1��A���Ɣ�1,470��~�B
����14�N4�����݂̏o�����i�P�ʐ�~)
����䒬
����8�N7�� 5,000
����12�N10�� 20,000
����14�N2�� 89,350
����14�N4�� 17,650
�v 132,000
���V�e��
����8�N7�� 5,000
����12�N10�� 20,000
����14�N2�� 89,350
����14�N4�� 18,450
�v 132,800
�܃P����
����8�N7�� 3,000
����13�N01�� 6,000
����14�N2�� 4,650
����14�N4�� 16,250
�v 29,900
���P�n�X�ёg��
����10�N10�� 3,000
�v 3,000
���ގ��Ƌ����g��
����8�N7�� 1,000
�v 1,000
���Y���Ƌ����g��
����8�N7�� 1,000
�v 1,000
�o�������v 299,700
---------------------
2002.7.8�@�{��c
�@�{��c�����ł��B�V�����̎{�����j����������܂����B
�@9�F00�J��A��c�^�����l���w���A�����ĉ����23���܂łƌ��肷��B
�@���ʂ̕Œ�Č��̎�舵���ɂ��ċ��c�A���̂悤�Ɍ��肳�ꂽ�B
�E���y��ʏȑS���ݘJ���g�������s�������o���ꂽ�u�����{�ʂ̌������Ɛ��i�ƒ������Ƃ̎��s�̐��̊g�[�����߂�ӌ����v�͔_�ь��ݏ�C�ψ���֑��t�B
�E�{�茧�c��X�сE�ыƊ��������i�c���A�������o���ꂽ�u�X�сE�ыƁE�؍ފ֘A�Y�Ɛ���ƐV���ȗ\�Z�̊m�ۂ����߂�ӌ����v�ɂ��ẮA�_�ь��ݏ�C�ψ���֑��t�B
�E�{�茧�X�ёg���A������o���ꂽ�u�X�сE�ыƁE�؍ގY�Ǝ{��Ɋւ����v�ɂ��ẮA�_�ь��ݏ�C�ψ���֑��t�B
�E�{�茧�g���b�N���5�g�����Ə�����o���ꂽ�u����218�y��325���ɂ�����ǂ��z���Ԑ��̌��݂����߂��v�ɂ��ẮA�_�ь��ݏ�C�ψ���֑��t�B
�E���{�ٌ�m�����o���ꂽ�u�Z����{�䒠�l�b�g���[�N�V�X�e���Ɋւ���{�s���������߂錈�c�č̑�v�]�v�ɂ��ẮA�����E������C�ψ���֑��t�B
�����āA�����̏��M�\���B�v�|���̂Ƃ���B
�������S�ʂɂ킽���Ă̊�{�I�l�����́A�����哱�ɂ��܂��Â����ڎw���B
�������J�ɂ���
�E�ϋɓI�ɏ����J���s���A�Z���Ə������L����B���̏�ᐧ��̏��������Ă���B
�E�����Ƃ̂܂��Â���g�[�N�𐄐i���Ē����Ƃ̑Θb�ɂ��M�������߂����B
���{��̎w�j�ɂ���
�E��l�����������v����w�j�Ƃ��Ă����B
�E�e�ۂ̏ƔN�x���Ɏ��Ƃ��`�F�b�N����V�X�e�����������Ă���B
�E�܂��Â��萄�i�ψ������Ɍւ�Ǝ��M�����������Â�����������B
�������^�c�ɂ���
�E80���ȏ�ˑ������ɗ����Ă��錵���������̒��Œ����̗����Ȃ���^�c����B
�E�⏕���̂��������������ψ���𗧂��グ�����B
�E�s���]���V�X�e���A�������ƕ]���V�X�e�����������B
���������ɂ���
�E�������͂܂��Â���̎�i�Ƃ��ĔF���B
�E����P���܂��Â����ڎw���B
�E�����ɔ�����C�����͖����B
�E������i�߂闝�R�͌�������Ȃ��B
�E���̃A�C�f���e�B�e�B�A���������ƁB
�E�����v����m���Ɏ��s���邱�ƁB
�E��������@17�N�܂ŗ\�f�������Ȃ��B���̂��Ƃ�O���ɂ����ď����W����B
�E�����Ȃ邱�Ƃɂ��Ή��ł���Ԑ��ŗՂށB
���_�ыƂɂ��āB
�E���S���A�i���ւ̂������A���Y�҂̊炪�����闬�ʁB
�E����ȋC����������i���t�����l�̍������Y�B
�E�܃P���̂�������������茟�����Ēn�Y�n���A�n��z�^�_�ƁA���Y�҂Ƃ̑Θb�ɏd�_��u���B
�����C�i���[�ɂ���
�E���A���A�n���A�����̉�c�A���Y�҂̈ӌ����Ĕ��f�A���ƒ�������肵���B
�E���ۑ�͑������p�m�����W���ď��z�������B
�E�n���ɐ��i���c����ł����B
�E�Ǘ��^�c�̂�����A���ƓW�J�ɂ��ẮA�߂������ɍ\�z���������Ƃ��ł���B
���n�C�����h�̉^�c�ɂ��āB
�E���V�[�Y���́A7��5��l�߂�����҂�����A�ݐϐԎ�����疜�قǂɈ��k�ł����B
�E�{�݂̘V�����ɂ��A�C�U��C���̌o����ꂩ�瑽���Ȃ�A�ۑ���������X�L�[��͒��̕�ł���B
�E�_�C�Ƃ̐M���W�������Ȃ���i�߂�B
�E�����X�L�[�����@�ɐV���Ȍ����̃X�L�[�̏�Ƃ��ē��O�ɃA�s�[������B�{�N�͌��J���Z�ł��邪�������擪�ɂ����Ď��g�ށB
���a�@���ɂ���
�E����15�N8���ɂ͕a���̑I�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�E���S���ĕ�炵�Ă����ɂ́A���a�@�̏[�����K�v�B
�E�ǂ̂悤�ȕa�@��ڎw���̂��������Ă��������B
�E�܂��A�����������o���Ă��Ȃ��B���������B
�����̑��̎���
���̖��ɂ��ẮA���̓s�x�c�_���Ă��������B
�i�_�]�F������胁���̂��߁A���m�ɕ\���ł��Ă��Ȃ����������邩�Ǝv���܂����A�����ĐϋɓI�Ȏ{�����j�ōD����������܂����B���ł��A�����J�A�s���]���A�������ƕ]�����x�̓����͉���I�Ȃ��Ƃł��B
�@���̂悤�ɕ]�����x������A�Ⴆ�q���I�Ȏ��ƂɎ��g��ł��A���̓s�x�]�����Ȃ���Ή��ł���̂ň�ʂɂ͈��S��������܂��B�����A��������s����ɂ͑�����R���͂��łĂ��邱�Ƃł��傤���炱�̌��͂�������Ǝx�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�j
�@�����ď��Č��ɂ��Ē��������ė��R�̐���������A�{���͒�ė��R�̐����݂̂ɂƂǂ߂ĎU����B
--------------------------------
2002.7.17�@�{��c
�@�{���́A��ʎ���̓��ł���B�{��c��10�F30����J�c����A���̋c�����o�d���܂����B
���{�i�c��
�E���������v��̐i���ɂ���
�E�ь��E�É��Ԃ̉ˋ��ɂ���
��{�T�\�c��
�E���C�i���[���݂ɂ��āB
�����t�j�c��
�E�������̈ێ��Ǘ��ɂ��āB
�H�{���c��
�E�s�����v�A�������v�ɂ��āB
�E�W���Z���^�[�̏������x�ɂ��āB
�E�k������n���̑�ɂ��āB
�b�㋁�c��
�E���w�Z���p���ɂ���
�@�M�҂̎���͒��H������Ōߌォ��ƂȂ����B���^���e�͈ȉ��̂Ƃ���B
---------------------
�c���@����ł́A�x�e����ĊJ���܂��B��ʎ���𑱂��܂��B�Q�ԏH�{���N���o�d���肢�܂��B
�H�{�@�Q�ԁ@�H�{ ���ł������܂��B�ʍ��ɏ]�������֎��₵�܂��B����̑��_�́A�s�����v�A�������v�ɂ��Ăł������܂��B
�@����V���W���̖{��c�`���Œ����́A���ꂩ��̒����ɂ��Ċ�{�I�ȍl�������q�ׂ��܂����B���̒��ŏ����J������^�c�ɂ��ĐϋɓI�ɉ��v�����Ă����Ƃ������l����������܂����̂Ŏ��͊������v�������������܂����B
�@�v���C�o�V�[�͂������Ǝ��Ȃ�����A���ׂĂ̏������J���邱�Ƃ��s���ƏZ���ɂ�鋦���W�A�M���W�\�z�ɂƂ��čł��d�v�ȃe�[�}�ł���܂��B�ꍏ�����������J���̐�������҂�����̂ł���܂��B�܂��A��ᐧ���҂܂ł��Ȃ��ϋɓI�ɏ����J�����čs���ƏZ���ɂ�鋦���W�A�M���W�̍\�z���߂������Ƃ��d�v�Ǝv���܂��B
�@�����^�c�ɂ��ẮA�s���]���V�X�e�����̍\�z��ڎw���Ɣ��\����܂����B���ꂩ��̌������������������ď��z����ׂɂ͐���̃v���Z�X����n�܂��Ăo�c�b�`�̃T�C�N�����Ȃ��猘���ȃK�o�i���X��ڎw���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł���܂��B
�@�����������x�́A���łɑS���̑����̎s���������g��ł���܂��āA���ꂼ��Ǝ��ȃV�X�e���𗧂��グ�Ă���܂����Ƃ͂����m�̂Ƃ���ł���܂��B�����������i�K�̕����⎎�s����̕���������܂����A�{���Ǝ��̂��̂悤�Ȑ��x�̊m���������A���ꂩ���X�����߂�o�o�o���_�A�܂�s���ƏZ���̃p�[�g�i�[�V�b�v�̍\�z�ɂƂ��Ă����Ƃ��d�v�ȃe�[�}�ł���܂��B���́A�J���ꂽ�s����ڎw�������̎��������}������̂ł���܂��B
�@�����ŁA�������������J���x��s���]�����x�̂��������g�ݕ��ɂ��čX�ɏڂ��������̏��M���������肢�����Ǝv���܂��B
�@���ɁA�n��W���Z���^�[�̏������x�ɂ��Ăł���܂��B
�@���͂���܂��Â����ڎw���ׂɂ́A�n��Z���̃R�~���j�e�B��������Ϗd�v�ł���܂��B���̃R�~���j�e�B�̊�{�I�ȒP�ʂƂ��ẮA�{���ł�14�̊e�n��ɂ��ꂼ���̌����ق��ݒu���Ă���܂��B
�@���̂P�S�̋�́A�s���̓s���Ő��������ꂽ�s����ł���܂����A�{���̒n��R�~���j�e�B�́A�×����|��ꂽ�`���I�W���ɂ���܂��B
�@���������`���I�W���ɂ́A�n��W���Z���^�[������A������قƂ��Ă����p����A���邢�͂���ȏ�̊��p���Ȃ���Ă���n�悪����������܂��B
�@�������Ȃ��炱���̒n��W���Z���^�[�́A�T�ˏ��a�T�O�N��̐��x���Ƃɂ�茚�����ꂽ�{�݂������A�V�������i��ł���A�܂��o���A�t���[�̊T�O���Ⴂ����̌������̂��ߍ���҂̗��p�ɕs�ւȎ{�݂ƂȂ��Ă���܂��B
�@���������{�݂́A����A����n���̍�����Ԃ��������钆�ł�����n�R���m�Â���͓������ƂȂ�܂����̂ŁA���ꂩ��͂��ꂼ��̒n��W���ŕ�C�A�C�����Ȃ����Ɋ��p���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�Ƃ��낪�A�����̎{�݂�n��Z���݂̂ŕ�C����̂͑��z�̔�p�����݁A�n��݂̂ŕ�C�C�����邱�Ƃ͓���s�\�ɋ߂��ł���܂��B
�@�����������Œn��W���Z���^�[�̕�C�C���ɑ���⏕���ƂƂ��ẮA���Ɣ�300���܂łł��̒��Ŏ��Ɣ��30���A100���~������Ƃ����⏕���x������݂̂ł��B����A��̌����ق́A���Ɣ��50���⏕�̐��x������܂��B
�@�����������Ƃ���A�n��R�~���j�e�B�琬�̂��߂ɒn��̏W���Z���^�[�̕�C��C�����Ƃɂ��ẮA��̌����ٓ��l�̏������x�n�݂��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̂��l���������������������Ƒ����܂��B
���ɁA�k������n���̑�ɂ��Ăł���܂��B
�@�{���̊�Y�ƂƂȂ�_�ыƂɂ��ẮA��������ʖ{��c�`���ŏq�ׂ�ꂽ�悤�Ɍo�ς̃O���[�o�����ɂ�鉿�i�j��A����A�ߑa�����ɂ��A���̎�芪�����͐��Ɍ��������̂�����܂��B�������Ȃ���p�m�����W���Ă���������������Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�����ŁA�e�Y�ƕ��傲�Ƃ̕����Â���ڕW�m�ɂ���K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���킯�ł���܂��B
�@���ɖ{���̔̔��_�Ƃ̍k������n�ɂ��ẮA�܃P�������S���ł��Q���đ������Ă���̂ł���܂��B���v�������̎����ɂ��܂��ƕ���2�N���畽��12�N�܂ł̍k������n�̑������́A�܃P�������_�Ɛ��P�O�X�˂���183�˂�1.68�{�̑����A�ʐς�1,338a����3,266a�ւ�2.44�{�̑����ƂȂ��Ă���܂��B
�@����䒬�ł́A179�˂���289�˂�1.61�{�A�ʐς�2,585a����4,262a�ւ�1.65�{�B���V�e���ł́A141�˂���188�˂�1.33�{�A�ʐς�1,597a����2,490a�ւ�1.56�{�ł���܂��B
�@�{���́A2.44�{�̍����ő������Ă���܂��B���ꂩ����k������n�̑����͂܂��܂���������Ǝv���܂��B
�@���ʁA�{���̔_�Ƃ����O���O�ōk�삷�邢����o�҂��_�Ƃ��������Ă����ɕ����Ă���܂��B���������_�n�̎��p�ƍk������n�Ƃ̖����A�܂����ꂩ�瑝������k������n�̊��p�ɂ��Ăǂ̂悤�ȑ�����l���ł��邩�������������Ƒ����܂��B��낵�����肢���܂��B
�c���@�����B
�����@�����ł��B�����̏H�{ ���c���̂R�_�̂�����ɂ��Ă��������܂��B�悸�����Ď��̎{�����j�ɂ��^�������܂��Ė{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�����������͂Ȃ����͂��x�������肢�\���グ�����B���̂悤�ɖ`���\�����������Ǝv���܂��B
�@�ŏ��̍s�����v�A�������v�ɂ��āA�����J���ꂩ��s���]���V�X�e���ɂ��čX�ɏڂ������M�������Ƃ���������ł���܂����B
�@�悸�A�����ł̏����J���̐���̏ɂ��Ă���\�������܂����A�S�S�s����������34�̎s�����ŏ����J��Ⴊ���肳��Ă���ł��B
�@�{���ɂ����܂��Ă������P�P�N��������J���̌����ɓ����Ă���܂��āA�{�N�Q���ɂ͐��P�n�R���ŁA�{�N�x���{�Ɍ����Ă̋��c���s���Ă���Ƃ���ł���܂��B�����A���V�e�͂��ē��̂Ƃ����ᐧ�肳��Ă���Ƃ����ł���܂��B
�@���͏�ᕶ�ɂ��Ă͂ł��ˁA���������ǂ̎����̂������ɂȂ��Ă���Ǝv���܂�����ǂ��T�˓����ł���܂��B�ł�����A���𐧒肷�邱�Ƃ͂���������Ƃł͂Ȃ��B�Ƃ����ӂ��Ɏ����g�F�����Ă����ł�����ǂ��A�������A��Ԗ��ɂ��Ă���̂́A���̌��J���̈�Ԃ̃|�C���g�́A�Z���̕��X�����J�������s��ꂽ���ɁA�����̉�X�̑Ή���������Ƃł���̂��ǂ����A��������Ԃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B
�@�ł�����A�Z���̊F�����������ɂ��Ă̕��͂��������Ƃ���ꂽ���ɁA���������ł����A����́A�����̂ǂ��̉ۂɂ����āA�ǂ��ǂ��ɂ����ĂƁA�������ł���̂��ǂ����Ƃ����̂����Ɉ�ԑ厖�ȂƂ���ł͂Ȃ��̂��Ȃ��Ƃ����C�����Ă����ł��B�ł�����A�c��������ꂽ�悤�ɏ�ᐧ���҂܂ł��Ȃ��A�����J�͂���Ăق����Ƃ������ƂŎ��������̂���ł���܂��B
�@�ł�����A�����J��Ⴊ�ł������䂦�ɂ����ɂł�����镶���Ƃ������A���܂Ō��Ă�����������Ԃ��������ċt�Ɏ��Ԃ��������Č���Ȃ��Ƃ��ł��ˁB���Ⴀ�ǂ��ɂ���̂��ƁA�����悤�ȕ������F���ۑ����Ă��āA�ǂ��Ƀt�@�C�����O���Ă��邩�킩���Ƃ����悤�ȏ�X�̂��Ƃ���Ԃ��̏�ᐧ��ɂ��Ă͖��ł���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B���ケ�̏�ᐧ��Ɍ����Ă͂ł��ˁB���̓����̉^�p�ɂ��Ă̌����A���̐i������钆�ŁA��ᐧ��̃^�C�~���O�����v�炢�����Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@�ǂ������͐��肳��Ă��܂�����ǂ��^�p���ɂ��ẮA�قƂ�Njc�_���Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ����̂�����ł���܂��̂ŁA�{���̈Ӗ��ł̏����J��ᐧ�肪����ėǂ������ƌ�����悤�ȏ��ɂ��邽�߂ɂ́A�����̕����̌������Ԃ���ԑ厖���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���Ƃ���ł���܂��B
�@�ɂ��ẮA�����������Ƃł��̂ł����������Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�@���ɁA�s���]���V�X�e���ɂ��Ăł���܂����A���̂��Ƃ������\�������܂��������J���Ƃ܂������\����̂̊W�ɂ���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă��܂��B���f�肵�Ă����܂�����ǂ��܂��{�i�I�ɒ����ŋc�_���X�^�[�g���Ă��܂���B
�@�ł�����A���l�̍l�����Ƃ������ƂŔ����������Ē��������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�v�́A�s���]���V�X�e���͋c����������������悤�ɂ����ȂƂ���œ����A�������͎��s�A����������Ă��܂��B
�@�����m�����ɂ����ẮA�s���{���ɂ����ẮA�T�˂P�O�O�p�[�Z���g�������A�������͎��s���n�܂��Ă���B���ꂩ��A�s�A��ɂ����Ă͂W�T�p�[�Z���g�ʂ̏ŁA���炩�̎�g�݂�����Ă���B�����������́A���s���ꂩ�猤������Ă���B
�@�A���A�����̒i�K�ɂȂ�ƁA���̒m�蓾��ł͂ł��ˁA�܂��T�p�[�Z���g��ʂ��������Ă��āA6�����ɂ��Ă͌v�悵�Ă��Ȃ��Ƃ����Ƃ����ӂ��Ɏ��Ƃ��Ă͔F�����Ă���Ƃ���ł��B
�@�ŁA�s���]���V�X�e��������ɓ����Ă��A��͂�ړI�����̂��߂ɓ�������̂��Ƃ������Ƃm�ɂ��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B��ʓI�ɂ��낢��Ƃ��̍s���]���V�X�e���̓����͉��̂��߂ɂ���̂��Ƃ������Ƃ������Ă��܂����A�����g�Ƃ��Ă͏��M�\���ł��\�������܂����悤�ɁA��������邱�Ƃɂ���ďZ���ƍs���Ƃ��������L����Ƃ������Ƃł��B
�@�Q�_�ڂ́A�Z�������̖����x�����シ��Ƃ������̂Q�_���낤�ƍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@�����āA������͂����肢�����܂��ƁA���ɂ́A��������̕]�����x����]���Ώۂ��ǂ����邩�Ƃ������Ƃ����R�o�Ă���킯�ł���܂�����A�����̋c�_�ɂ����ށB���낢�댾���Ă���x���`�}�[�L���O�Ȃ̂��A����Ƃ��������ƕ]�����ǂ������`�ł��̂��Ƃ��A�c���̕����X�ɂ��ڂ����Ǝv���܂����A�����]���Ȃ̂��Ƃ��A�����ȍl�������e�n��ŋc�_����Ă��܂��B
�@�����͂���͐�ʌ������悤�Ɏ����ō���낤�Ƃ��Ă��鑍���v��̐i�s�Ǘ����`�F�b�N����ƁA�s�������ł͂�����Z���̊F������ɂ��������āu�����A�����Ȃ��Ă��܂���v�Ƃ����̂��ЂƂ̍s���]���V�X�e���̃p�^�[�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�@���A���ł��܂��܂Ȋp�x���獡�}�s�b�`�ł��̍s���]���̌������i�߂��Ă��܂��B��ʂ��{��s�̍s���]�����i�ۂ̎�g�݂��Љ��Ă���܂�������ǂ��A�����Ȑ�i�I�Ȏ�����������܂��B
�@�v�͖{���K�͂Ƀ}�b�`�����V�X�e���ɂ��Ȃ���A�₽�獡�ȏ�ɐE���ɕt����������悤�Ȃ��Ƃł͉��̂��߂ɓ��ꂽ������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����C�����Ă��܂�����A���̒����̖͕�ł͂Ȃ��Ď����g���[���[���ł���悤�ȍs���]�����x������Ă��������Ȃ��Ƃ����ӂ��ɍl���Ă��܂��B
�@���ׂ̈ɂ͒����̎��ŁA����͂���Ӗ��ł͂h�s�̊��p���ǂ����邩�Ƃ����̂��A�E���̕��S���y�������̗v�f�ɂ��Ȃ�܂��̂ŁA��蒆�S�ɂ��̖��ɂ��Ă̓`�[����g��ʼn��f�I�Ɍ������Ă����K�v������Ƃ����C�����Ă���Ƃ���ł��B
�@�S���I�ɐ������Ă����ł́A�g�b�v�_�E����������Ԑ������Ă���Ƃ�������ł���܂��B���ƃg�b�v���������A����ɑ��ĊF���Z���Ԃ̂����ɂ�肠����Ƃ������Ƃł����������Ԑ������Ă���Ƃ�������ł���܂��B
�@�������̖��́A�������Ȃ��Ƃ����C�����Ă���܂��̂ŁA��قǂ̏����J���̂�����^�p�̌��������R�h�s�̖�肪�����ł����ł��B�ł�����A�ł����瓯�l�̃`�[���ł��̖����������ĕK����肠�������Ȃ��ƁB���ꂪ�A���ꂩ���̌܃P�����̂���Ӗ��ł͒��̃X�e�[�^�X�����߂镔���ɂȂ��Ȃ����Ȃ��Ƃ����C�����Ă���܂��̂ŁB
�@���Ȃ��J�͂���Ǝv���܂��B���A�s�̃��x���̏���������A��厏��ǂ肵�Ă��A���Ȃ�w�͂����č��グ�Ă��������܂�����A����ɕ����Ȃ��悤�ɕK���������Ă��������ƁB�s���]���V�X�e���͌�������ʏ�͂R�N���炢�������Ă���Ƃ������Ԃ̂悤�ł���܂��B
�@�܁A�܃P�����Ƃ��Ăǂ��������Ƃ�]�����Ă����̂��A�ǂ���������������̂��Ƃ����̂͂��ꂩ��̌����ɂȂ�܂�����ǂ��A���x�������悤�ł�����ǂ��A��͂�A�{���Ƀ}�b�`�������̂��Ⴀ�Ȃ��ƈӖ����Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��̂ł��������l�����̂��ƂɌ�����i�߂Ă��������Ǝv���܂�����c���̊F������ɂ������������̓s�x���ꂱ�����͌��J���ĎQ��܂��̂ł����Ȃ��x���A���m�b�����肽���Ƃ��̂悤�ɍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@���ɏW���Z���^�[�̏������x�ɂ��Ăł���܂����A�m���ɂ��w�E�̂Ƃ��肱�ꂾ���ł͂������܂���ǂ����s���x�ł͎��Ԃɂ�����Ȃ������͂���ƍl���Ă���܂��B
�@���M�\���ł��\�������܂����悤�ɁA���̖�肾���ł͂Ȃ��Ē��P�⏕���Ƃɂ��܂��ẮA�����ψ���𗧂��グ�čēx���Ȃ����A�Ȃ����Ƃ������Ƃ����Ă����ł���܂�����A���̒��ō���[���Ɍ������ĎQ�肽���Ƃ��̂悤�ɍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@�R�_�ڂ̍k������n���̑�ɂ��Ăł���܂�����ǂ��A�T�N���Ƃɍs���Ă���_�ыƃZ���T�X�Ƃ����̂��������܂��B���̌��ʂ����Ă݂܂��Ɛ�قǂ��b������܂����悤�ɕ����P�Q�N�x�̌܃P�������̍k������n�͐��c�A���A�����n�Ȃǂ̍k�n503ha�ɑ��܂��āA42ha�̂ł���܂��B�䗦�ɂ��ĂW�����x�B�O�����̕����Q�N�x��28ha�ł���܂��̂łT�N�Ԃ�14ha�������Ă���ƁA�Z���T�X���猩��Ƃ��̂悤�Ȏ��ԂɂȂ��Ă���܂��B
�@�c�������b������܂����悤�ɁA����ł͋ߗׂ̒��������Ă݂܂��Ɠ��V�e����542ha�̂�����33ha�A�䗦�Ƃ��ĂU���B����䒬�ł�1327ha�̂���60ha�A�䗦�Ƃ������܂��Ă͂S�D�T���ƂȂ��Ă��܂��B�{�����W���A���V�e�����U���A����䒬���S�D�T���ƁA��قǂ��b���������Ƃ���ł���܂��B
�@�܂��A�{�茧�S�̂łǂ����Ƃ����܂���53,499ha�̓���2,959ha�Ŕ䗦�Ƃ��Ă�5.5���Ƃ������Ƃł���܂��̂ŁA�{���̍k������n�́A��r�I�����Ă��̔w�i�Ƃ��ẮA��͂�R�Ԓn���L�̌��������n�����̉e��������Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@���̍k������n����������X���́A�S���̏����s���n��ł���܂����R�Ԓn�ł́A���Ɍ����ł���܂��B�_�ѐ��Y�Ȃɂ����Ă��_�Ɛ��Y������ʂ��čk������n�̔�����h�~����ϓ_���炲�ē��̂Ƃ��蕽���\��N�x��蒆�R�Ԓn�撼�ڎx���⏞���x���n�݂��ꂽ�Ƃ���ł���܂��B
�@�{���ɂ����܂��Ă��W���P�ʂōk������n���o���Ȃ��ׂ̋��������ł��������A��t���̔����͎Q�������_�Ƃ̕��X�ɁA�܂��A�c��̔����ɂ��܂��Ă͒n��̊������̂��߂ɗ��p�����Ă���܂����B����13�N�x��714�˂̔_�Ƃł��̐��x�������p���������Ă���A�����Ō�t�����z�́A66,314��~�Ƒ�ϑ傫�Ȃ��̂ł���܂��B
�@�����s���Ƃ������܂��Ă�����16�N�x�܂ł̎��{���Ԃ����Ƃ������ł���悤�ɍ���A���A���Ȃǂ̊W�@�ւɓ��������Ă����l���ł���܂��B
�@�܂��A����̍k������n��Ƃ������܂��ẮA�k������n�̓��A������_�n�Ƃ��ė��p������Ɨђn�ւ̓]����}����Ƃ��敪����_�n�Đ������Ƃ𐄐i����K�v������ƍl���܂��B
�@���̓��A�_�n�Ƃ��ė��p������ɂ��܂��ẮA�_�Ƃ̗v�]�ɂ��������ߍׂ��Ȋ�Ր������s���A�_��Ƃ̉��P�����Đ��Y���̂���_�n�ɂ��A�����̔_�n�������ɑΉ��ł�����_�n�ɂ���K�v������ƍl���܂��B
�@����A�k������n�ł���V�x�n�����n�ɂ���ďW�ς��邱�Ƃɂ��Ĕ�_�p�n��n�����邱�Ƃɂ��{�ɗp�n���̑��̗p�n�ɂƂ��Ă̗��p���l������Ǝv���܂��B
�@���ɁA���ۂɍk����s���S�����ɂ��܂��ẮA���݂��s���Ă���܂���ϑ��_�ƁA�܂�A�O���w���p�[�ւ̕����I�Ȕ_��ƈϑ����珫���I�ɂ́A���̒����ł�����܂����_�ƌ��Г��̔_�Ɩ@�l�𗧂��グ��p�҂̂��Ȃ��_�n�����ЂŔ������A��]�҂ւ̒��݁A���p�Ȃǂ��s���V�X�e�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����������ӂɗ���̂��Ȃ��ƍl���Ă���Ƃ���ł���܂��B
�@���ɁA���O�A���O�ł̍k�삪�������Ă���Ƃ����_�ɂ��Ăł������܂��B�h�z���̔_�ƈψ���Ɋm�F�������܂������A�܃P��������̒��ݓ��̍k��_�n�ɂ��Ă͊m�F���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���A�K����n��̐��˂̔_�Ƃ̕��X���T�g�C���̐��Y������Ă���悤�ł���܂��B
�@���̔w�i�Ƃ������܂��ẮA�A���Q�h�~�Ɗ�Ր����̈Ⴂ�ɂ��܂��_��Ƃ̌y�������傫�ȗv���Ƃ����ӂ��Ɏ����͍l���Ă���܂��B
�@���݂̔_�Ɛ���Ƃ������܂��Ă��L��_�����͂��߂Ƃ���c�_�A���ʁA�̔��̍L�扻�A���ꂩ��R�X�g�̍팸��������Ă���܂��̂ŁA�K�͊g�哙�ɂ�钬�O�ł̔_�n�̍k��ɂ��܂��ẮA�_�n�@��̖�肪�Ȃ���Ύx��͂Ȃ����̂ƍl���Ă���Ƃ���ł���܂��B�ȏ�A�k������n��̊�{�I�ȍl�����ɂ��ďq�ׂ����Ă��������܂����B
�@�ȏ�łR�_�̓��قɑウ�����Ă��������܂��B
�H�{�@�c��
�c���@�͂��A�H�{ ���N
�H�{�@���肪�Ƃ��������܂����B���ɖ��邢���Ƃ������������̂悤�ɂ������܂����B
�@�Ď���́A���Ԃ��t�ɂȂ�܂�����ǂ��A�k������n�̖��ł��ˁB���ꂩ����ɑ����Ă���A������܂��čk��ł��Ȃ��Ƃ��낪�����Ă���B�����������ɑ��܂��ẮA�i�_�n���j�敪�����芷�n�A����Ƃ������ł́A�����ł��Ȃ���������̂��Ȃ��Ƃ����v��������킯�ł��ˁB
�@�ǂȂ��ł������Ă����ł���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���̐l�̂��̂ɂȂ��ł͂Ȃ����Ƃ����s��������B���ꂪ�傫�ȏ�Q�ɂȂ�Ƃ����C�����܂��B�k��n�̗����������邽�߂ɂ͐M��������Ƃ��낪�ꎞ����āA�����ł��܂��^�p���Ă����B
�@�܂�A���Ȃ��������ӔC�����Z�N�^�[������ĐM����������Ƃ���ł��肵�܂��āA�����ōk������n��݂��o���Ă��܂����p���Ă����B
�@�i�ύ앨�Ƃ����������������ł��ˁB�Ⴆ�A����n��ɓ����čs�������A�r�ꂽ�k������n�����������ɖڂɂ����Ƃ��܂��Ƃł��ˁA�����̃��������ɔ敾���ĕn�����Ƃ�����ۂ���B���ɃO���[���c�[���Y���Ɏ��g�ޏꍇ�́A�����ɔ������_���i�ς�n�o���邩�Ƃ������Ƃł������܂�����A���������k������n��Ⴆ�Όi�ύ앨�Ƃ��Ăm�o�n�Ƃ��{�����e�B�A�̃O���[�v�ł���낵���̂ł����A�����ȃO���[�v��c�̓��ɂ��̒n��ň�Ԃ悭������ꏊ�ɂ͌i�ύ앨�����肢����B
�@���A���ɂ͊G�ɂȂ�悤�ȋG�ߊ����Ȃ��̂ł���B�t�ɂ͍̉Ԃ���ʂɍ炢�Ă���Ƃ��A�H�ɂȂ�ƃ\�o�̉Ԃ��炢�Ă���Ƃ��A�����Ă�����Ƃ��A���������G�߂̉ԂŌi�ς�����Ȃ��珮�����n������Ƃ����悤�ȁA���������i�ύ앨������Ă��������Ƃ��A�����͋G�߂̉Ԃ����ł������Ǝv���܂����A�����������p�́A��͂�s���������֗^�����Ƃ���ŐӔC�������ĉ^�p���A���L�҂��K�v�Ȏ��͂��ł����Ԃ����܂���A�Ƃ����悤�Ȃ��ƂŊ��p���Ă����B�����������x�����邱�Ƃ��厖�ł͂Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@������ɂ��܂��Ă��A���ꂩ����ɍk������n�������Ă��钆�ł��̑�Ƃ����̂͑�Ϗd�v���Ǝv���܂��B���������������B
�@���ꂩ��A�n��W���Z���^�[�̏������x�ɂ��Č����������Ƃ������Ƃő�ς��肪���������܂����V�������i�݁A�}������������܂��̂ʼn�������ړr�Ɍ��_���o����悤���������̂��A�����̂Ƃ����������Ƒ����܂��B
�@���ꂩ������J���x�̎�g�݂ɂ��ẮA���͔��Ɋ����������Ă���܂��āA����������������n�������̈�ԑ厖�ȕ������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B����܂ł̒����͔��ɕ��I�ł���܂��ĉ�X�c���ł��Ȃ��Ȃ���킩��Ȃ�����������B
�@���́A���N�R���̋c��ł����͐X�ь������Ƃɂ��āi�ϑ��j���z�����N�オ�����艺�������肵�Ă���̂ł���͈�́A��ɂȂ�_��͂ǂ��Ȃ��Ă����ł��傤���ƁA�����������̂�����܂��̂ł��傤���Ǝ��₵�܂�����A�������ĕ��܂��Ƃ������Ƃł������ŏI�I�ɂ́A�����J��Ⴊ�Ȃ��Ƃ������ƂŌ����Ă��炦�Ȃ��B
�@�܁A�����������Ƃ͏����ĂȂ��Ǝv������ǂ��A�ł��������牯�����o�Ă��܂��ł��ˁB�����̊�ŐR�c�����邱�ƂɂȂ�̂Ŕ��ɂ܂��������ɍs���Ǝv���̂ł��B
�@�������������̂������ɂ������Ē��������B���J��Ⴊ�Ȃ��Ă��ϋɓI�Ɍ��J���Ă����Ƃ������Ƃł������܂����̂Ŗ{��c�ł������������̂�������Ƃ����������āA�������������̂���ɂ��ĐR�c���Ă��������Ǝv���܂��̂ŁA���ꂪ�ł��邩�ǂ��������������Ǝv���܂��B
�c���@�͂��A�����B
�����@��_�ڂɂ��܂��ẮA���������������Ō������Ē��������Ƃ������Ƃł���܂��̂ŁA���܂��܂Ȏ�@������Ƃ������Ƃ��قǐ\�������܂�������ǂ����������ӂ��Ɏ����͍l���Ă���܂��B
�@�_�щۂ������ȏ������W���Ȃ���ǂ������`�������̂��Ƃ����̂��������͂��߂Ă��܂��̂ň��������A��قǎ������悤�Ȃ��ӌ����܂߂Ă��w���������������ȂƂ����ӂ��ɍl���Ă��܂��B
�@���ꂩ��A�W���Z���^�[�̊W�ł����܂łɂƂ������b�ł���܂����A�W���Z���^�[�Ɍ��炸���P�ƕ⏕���̌������ɂ��ẮA���̐V�N�x�̗\�Z�ɔ��f���Ȃ���Ύ��͈Ӗ����Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@����̗\�Z����ɂ����Ă����ԓI�ȗ]�T���Ȃ��āA�c�_���Ȃ��āA����܂ł͂����������ƂŁA���������オ��ł��낤�⏕���̌����ψ���ɁA���̕⏕���ɂ��Ă͍ڂ��悤�Ƃ����}�[�N�����_�����Ă���܂��B
�@�����������Ƃ�����܂��̂Ŏ��Ƃ��Ă͎����V�N�x�\�Z�ɔ��f�ł��鎞���A���N�����ς��ʂɂ́A�܁A��������킯�ł͂���܂���ǂ��A�l�����ɂ��Đ����������Ǝv���Ă��܂��B
�@�����J�̓_�ɂ��ẮA�]���́A���I�ł������Ƃ����ӂ��ɋc���͂������Ⴂ�܂������A�����͌����ĕς��Ă��Ȃ��ƍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@�܁A�����Ȃ̂��Ȃ��Ƃ����C�����Ă���܂����A�l�����ɂ��Ă͏]�����ς��Ă��Ȃ����A�Z���̊F�����̏����������Ƃ����̂�����ł��ˁB�l�̃v���C�o�V�[�ɊW�Ȃ���Γ��R��������������Ȃ��Ƃ����K�v�͂Ȃ��킯�ł�����B
�@�����������Ƃ�S�ۂ��邽�߂ɂ���͂�����J���Ƃ����̂́A������Ζ������������̂ł��傤����ǂ��A��͂�l���ς�����ǂ��Ȃ̂��ƁB�S���҂��������i�̕����j�֍s�����猩����Ƃ��A�������֍s�����猩���Ȃ��Ƃ��A���ǂ��Ȃ�̂��Ƃ������Ƃł���܂�������Ƃ����͕̂K�v�Ȃ낤�Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@������ɂ���܂����_�ɂ��Ă͂ł��ˁB����͉����B�����Ă���K�v�������Ȃ��āA�_��͌���ł���킯�ł�����K�v��������ł������ɂȂ��č\��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ȃ��Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���Ƃ���ł��B�ȏ�ł��B
�H�{�@���肪�Ƃ��������܂����B�ȏ�ŏI���܂��B
--------------------------------
���i�_�]�F����A�V�������̕�\�Z��R�c����{��c�ɂ����āA�����̐����₤��ԑ厖�Ȉ�ʎ���ł���Ȃ��玿��҂͈�N���c��������ł��������Ƃɕs���������܂����B��������A���C�i���[���A�a�@��X�L�[��A������蓙�傫�Ȗ�����������̎��Ɉ�N���c������ł��B�F����ʂ����Đ^���ɍl���Ă���̂��낤���B�j
----------------------------
2002.7.18�@�S�����c��
�@���C�i���[�\�z�ɂ��ẮA�c��Ƃ��Ă�����������������Ƃ������Ƃ���A���̓��́A��1��c���ɂ����āA�����̑�\��7���̕��������ă��C�i���[�\�z�ɂ��Ĉӌ��������܂����B
�@���̎��̈ӌ��������_���Ƀ�������]�ڂ���Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�E�����܂ł��ĕ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂Ń����b�g�̂���{�݂ɂ��Ăق����B
�E���̎{�݂́A�_�ыƂɂƂ��Ĉ�ԉe���̂���{�݁A�_�Ƃ����������ł���ɓq���Ă���B�_�ƂƊό�����̉����ċύt���钬�����肢�����B
�E�K����n��́A�\�t�g���Ƃ�8�N�Ԋ撣���ăm�E�n�E��~�ς��Ă����B���ꂩ��n�[�h�Ƃ��Ďp�����킷���ł���B
�E�����Œ��l�200���ł����B���ꂩ��2500�l�̑g�D��ڎw���A���̃l�b�g���[�N��S���ɍL���Ď��Ƃ̊�b�Ƃ������B
�E�I���W�i���e�B�Ȏ��Ƃł���̎Z�����Ǝv���B
�E���Y�҂Ƃ͂��������b������������Ȃ������̂ł͂Ȃ����B
�E�Ԃǂ��̉��i�����N�͂܂�����ŕs���B���C����p��́A200�~�̒P���ł͌o�c�ł��Ȃ��B300�~�͍Œቿ�i�ł�����350�~�łȂ���Έ��肵�Ȃ��B
�E���Y�_�Ƃ̍̎Z�x�[�X�Ŏ��[�J�[���p�[�g�i�[�Ƃ��ċ���ł��邾�낤���B
�E�����A�Ԃǂ��̉��i�⏞������Α��̎Y�ƕ���ɂ��y�Ԃ��߁A���E�����Ȃ��Ȃ�B
�E�ӔC�̂�����܂Ŗ��m�ɂ��Ă����肩�����Ē��������B
�E���C�i���[�ׂ̈̂Ԃǂ����Y���A�Ԃǂ����Y�҂̂��߂̃��C�i���[���B
�E���ɂ́A�����ƒő��̓��Y�i������A�Y�n�Ƃ��Ă̊m�����܂��s�[���ł���B����Ȃ̂Ƀ��C�i���[�Ƃ͂Ǝv�����B
�E���i����Ȃ��Ԃ��Ă͂����Ȃ��B
�E�������{���Ƀ��C�����������邾�낤���A�s���ޗ�����������B
�E�Ԃǂ����Y�_�Ƃ��Ȃ������肵�Ȃ��悤�ɂ��Ăق����B
�E�����A�ő������D�ł��������Ă���B���C�i���[���ł��Ă����Ŕ̔�����Γ��D�ɏo���Ȃ��Ă悭�Ȃ�B
�E�Ԃǂ��͔|�����サ�Ă����Ă܂��P�������܂��Ă��Ȃ��B����s���܂����Ƃ����̂������B�ǂ����Đ��Y�҂����̂��Ƃ������_�ōl���Ăق����B
�E�Ԃǂ���������ʈ����ɂ��Ăق����Ȃ��B
�E�e�n��ł����ꂼ��̎��Ƃ�����Ǝv�����A���ꂪ�摗�肳�ꂽ��]���ɂȂ邱�Ƃ����͂�߂Ăق����B
�E�������C����Δ����B�n���ł��o�����Ă�肽���B
�E���C���͐Q������ΐQ������قǒl�i���オ�鏤�i������S�z�Ȃ��B
�E�u���b�N�I�����s�A�́A���i����������Ȃ��B��̗��͌��̉\��������B
�E�O���ɏ��Ȃ������ꍇ�ǂ����ӔC���Ƃ邩�͂����肵�Ăق����B
�@���X�̂����Ȉӌ����o�����ϕ��ɂȂ����S�����c��ł����B
�����̌�A�ߌォ������������S�����c��s�B�������烏�C�i���[�\�z�̐���������܂����B�v��͎��̂Ƃ���B
�E���C�i���[�̑S�̌v��ɂ��ẮA�����������Ԃ�������B
�E���X�g�����ƒ������͕K�{�v���B���̑��C�x���g�L��A�̌��H�[�����邪���e�ɂ��ẮA�c�_���K�v�B
�E�Ǘ��̐��́A�_�C�A�i�`�A���H��A���Y�ҁA�n���n�斯���l���Ă���B
�E��Ђ̎��{���́A���疜����ꉭ�~�K�͂ɂȂ�B�����ߔ��������\��B�_�C�ɑ啔���������Ă��炤�B�ł��邾�����������ɗ����グ��B
�E�Ԃǂ��̔������ꉿ�i��300�~��ړr�ɂ��Ă���B���̉��i�⏞�͍l���Ă��Ȃ��B
�E���X�g�����́A�n�Y�n���Ŕ_�ƃ��X�g�����̋��_�ɂ������B�܃P���̎l�G�̐H���������߂�B
�E���X�g�����̋K�͂�100�Ȓ��x�Œn��̕����ɂӂ����悤�Ȍv��ɂ������B
�E���߂��ȏ�͊m���ɐ��i����B�s���哱�ŐV���Ȃ܂��Â���Ɏ��g�ށB
�����̌�A�����ے����7��8���t�ŕ��ʌ�t�ő����\�����ꂽ�|�������������B
�@����ɂ��Ɩ{���̊�������p�z�́A����13�N�x��\�܉����玵�S���~�ɑ���14�N�x�͓�\�O���Z���S���~�œ��S���̌���-7.8���B
�@����������z�́A����13�N�x���O�����S���ɑ���14�N�x�́A�O���S���B
�@��t��z�́A����13�N�x��\�Z��Z�S���ɑ��ĕ���14�N�x�́A��\���Z�甪�S���Ŗ�~8.7���̌��z�ƂȂ����B
�@���A���Ɣ��̒n�d��60�`70����30���ɂȂ�B�i�K��̌��Ȃ�����3���N�ŕ�B
�i�_�]�F�N��10���~���z�������i�ؓ����ԍρj�������{���ɂƂ��āA��t�ł̌��z�̓{�f�[�u���E�̂悤�ɃY�V���Ɖ����܂��B�j
------------------------------
2002.7.23�{��c�@
�@�{���͍ŏI�c��B�J��ɐ旧���đS�����c��J�Â���A�c�^��胏�C�i���[�֘A�œ��ʈψ����Ґ��\��A�c���Ƃ������A�|�̕�����B
�������Ē�Č���7��8���A���ꂼ���C�ψ���ɑ��t���ꂽ���ɂ��Ĉψ����B
�E���{�ٌ�m�����o���ꂽ�u�Z����{�䒠�l�b�g���[�N�V�X�e���Ɋւ���{�s���������߂錈�c�č̑�v�]�v�ɂ��ẮA�s�̑��B
�E���y��ʏȑS���ݘJ���g�������s�������o���ꂽ�u�����{�ʂ̌������Ɛ��i�ƒ������Ƃ̎��s�̐��̊g�[�����߂�ӌ����v�ɂ��ẮA�s�̑��B
�E�{�茧�c��X�сE�ыƊ��������i�c���A�������o���ꂽ�u�X�сE�ыƁE�؍ފ֘A�Y�Ɛ���ƐV���ȗ\�Z�̊m�ۂ����߂�ӌ����v�ɂ��ẮA�ӌ�����o�B
�E�{�茧�X�ёg���A������o���ꂽ�u�X�сE�ыƁE�؍ގY�Ǝ{��Ɋւ����v�ɂ��ẮA4���Ɠ���̂��ߎ����Ƃ���B
�E�{�茧�g���b�N���5�g�����Ə�����o���ꂽ�u����218�y��325���ɂ�����ǂ��z���Ԑ��̌��݂����߂��v�ɂ��ẮA����������ĉ^�����̂��ߌp���R�c�Ƃ���B
�̕�����B
�@�{��c�́A10:25����J�c����A�M�҂͒n�В����ƃX�L�[��̈ϑ����ɂ��Ď��₵�܂����B����܂ŁA��ʎ���ȊO�̎��^�ɂ��Ă͗v���̂f�ڂ��Ă��܂������A����͈ꎞ���������̂ŔO�̂��ߕM�ҕ����̑S�L�^���f�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B
-------------------
�H�{�@�c���B
�c���@�͂��B2�ԏH�{�N�B
�H�{�@2�ԏH�{�ł������܂��B����14�N�x��ʉ�v��\�Z��31�y�[�W�n�В�����ɂ��āA���ꂩ��36�y�[�W�̐X�ь������Ɓi�X�L�[��j�̈ϑ����ɂ��Ď��₢�����܂��B
�@�܂�31�y�[�W�̒n�В����ɂ��Ăł������܂����A����́A�����\�Z75,512��~�ɑ��ĕ�\�Z�ł�6,718��~���z����Ă���܂��B���̂��Ƃɂ��Ă��q�˒v���܂��B
�@�n�В����́A�K����n�悩��O������E�݂��オ��A�E�݂��I�������獶�݂������ĎO�����여����I���B���ɈƉ��̓���n�悩��܃P����E�݂��オ���ăX�L�[��̕��ɏオ��A�E�݂��I��������g�A����܃P���썶�݂�g�n��܂ʼn���Ȃ��璲������Ƃ�����K�͂ȍ��y�����ł������܂��B
�@���݂́A�O������E�݂̓��̌�����㗬��ɂ����Ē������Ƃ������ƂŁA�{���̖ʐϖ�16,000ha�̓��A�����ς݂̒n�悪��4,733ha�A�������n���11,000ha�ƂȂ��Ă��܂��B�i������30���ɂ������Ȃ��Ƃ���ł��B
�@���N250�`300ha�����Ă���Ƃ����܂����A���̃��x���Ői�߂܂��ƔN250ha�����̏ꍇ�́A���ɂ��ꂩ��44�N�Ԃ��������Ă��܂��܂��B
�@�L��ȎR�іʐς����L����{���ł́A�ыƂ̕s�U�ƍ���ɂ��ђn�̋��E�⏊�L������B���ȕ����������Ȃ����܂��B
�@���̎��Ƃ́A���y�������i���ʑ[�u�@�i���a�R�V�N�@����P�S�R���j���Ɋ�Â����{����Ă��Ă�����̂ŁA��50���C��25���C��25���̎��Ɣ�ōs���Ă��܂��B
�@��B�ɂ�����A�����P�P�N�x�̐i�����ׂĂ݂܂������A����ɂ��ƁA���ꌧ��88���A������69���A��������67���A�F�{��55���A���茧50���A�啪��49���A�{�茧47���ƂȂ��Ă��܂��B�ȏ�̂悤�ɋ�B�ōł��x��Ă���̂͋{�茧�ł����A����ł�47���̐i�����ŁA�s�����ɂ���ẮA���ɒ������I�����Ă���n�������悤�ł��B
�@������ɁA�{���ł́A����13�N�x�Ői������30���ɂ��B���ł��Ă��܂���B���̐������悤�ɕ���11�N�x�ɒu��������Ƃ����ƒႢ�����ƂȂ�܂��B���P�n�S���ł��ł��x��Ă���̂��{���ł������܂��B
�@�Z���̍��Y�����A�X�ьv���n��v��Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ��n�В����ł��B�y�n���L�҂̍���ɔ����Č��n�̋��E�m�F�����łɓ���Ȃ����܂��B����ł́A�������Z���T�[�r�X���ቺ���Ă���Ƃ����v���܂���B
�@�����������Ƃ��l����ƁA�{���Ƃ́A�摗��ł��Ȃ��i�ق̉ۑ�ł���܂��B���������ė\�Z�̌��z�́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł���܂��B�ނ��댸�z���啝�J��グ�ɂ�鑁���B�����߂����ׂ����Ǝv���܂��B
�@�����āA���̍ہA�����܂łɂ��̎��Ƃ�B�����ׂ��ł��邩�A�Z���Ƃ悭���k���Ă��̖ڕW��������Ɛݒ肵�Ă������������B
�@�n�ВS���҂ɐq�˂܂��ƁA�����ɂȂ�����I��邩�킩��܂���Ƃ������Ƃł��B���v��Ȓ����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł���܂��B
�@���ɁA36�y�[�W�̐X�ь������Ƃ̈ϑ����ɂ��Ăł������܂��B
�@����13�N�x�ɖ��������ϑ������{�N�x�i����14�N�x�j�̕��2�疜�~�v�コ��Ă���܂��B����13�N�x�́A���т������Ƃ������Ƃł������܂����A�ǂ��������������ł��Ȃ�����������܂��̂ł����������肢�������Ǝv���܂��B
�Ŗ��ے��@�c���B
�c���@�͂��A�Ŗ��ے��B
�Ŗ��ے��@�Ŗ��ے��ł��B�����A�H�{�c���̎���ɂ��Ă��������܂��B�ɂ��ẮA30���ɂ������Ȃ��Ƃ������Ƃł������܂��B�m���ɁA���a50�N���炱�̎��ƂɎ��g��ł���܂�����ǂ��A�S���ł͈�Ԍ�ɒ��肵�ĂƂ������Ƃł��̂悤�Ȑ����ł���܂��B
�@������A�v��ɂ��܂��ẮA�\���N�v��Ƃ������ƂŌ�����������Đi�����̐i�ߋ�A���Ɣ�̕�ɂ��܂��Ă��A�v��ɂ��܂�����ǂ��A������Ă���ł́A����̐E���ŁA1�ǂŌK����̕����獡�\���������Ƃ����{�̕��i��ł���Ƃ���ł������܂��B
�@�����ŁA�S���ƍ������Ƃ��������d�˂Ă���킯�ł������܂����A���X�A�O���A16�N����O���������1�ǂ�2�ǂ��炢����āA���Ƃ̐i����i�߂悤�Ƃ������ƂŁA���́A�l�����痈���킯�ł�����ǂ��A����܂łɁA���̂悤�Ȍv����l���Ă���悤�ł��B
�@�����������ŁA����16�N�x�Ɛ\���܂�������ǂ������ۂƌ������d�˂āA�����A������ɂ��Ă������I�����������Ƃ����̂͏H�{�c���ƑS���ꏏ�ł������܂��āA�ēx�A���A���̕⏕���𗘗p���Ȃ���1ha�ł������N�x�ɂ����Ď��Ƃ��i�ނ悤�ɑ����I���悤�ɁA1�N�̎��Ɨʂ�350ha�Ȃ�400ha�Ȃ�������ł��Ȃ����ƍl���Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�����������ƂŁA����1�ǂ��ǂ�����n�߂�̂��Ƃ������̂��܂߂܂��Ăł��ˁB��قǂ��b������܂�������ǂ��A�Ɖ��A�O�����A�ł�����1�ǂƂ������Ƃ��l������킯�ł�����ǂ��A�l�߂Ă���Ă�����Ƃł��ˁB�Ȃ��Ȃ��A���ʂ̍Y������ς蔲������ǂ������肵�܂��ƁA�l����悤�ȍ�Ƃł��������܂���B����A�n���҂̋��͑Ԑ����Ȃ��Ƌ��������Ȃ��Ƃ���������܂��̂ŁA�������A�n���̉��������������Ȃ���撣���Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@�\�Z�I�Ȃ��Ƃ��������܂��̂ŁA�����łǂ����܂��Ƃ������Ƃ͂͂�����\���������܂���ǂ�����1�N�ł������I��肽���Ƃ����͓̂����ł������܂��̂ł�낵�����肢���܂��B
�����@�c���B
�c���@�͂��A�����B
�����@�n�В����ɂ��ẮA���Ŗ��ے����\�������܂����Ƃ���A�H�{�c���̂�����̌��ɂ��ẮA���ɓ��ł��S���ۂƂ��Ă͐i������L�������Ƃ������ƂŁA�c�_���Ă��Ă���ł��B
�@�����Ƃ��Ă����R�A��������10�N��܂ł̂��Ƃ������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͓����ӌ��ł���܂��̂ŁA�ǂ��������@�ł���Ώ����ł��O�i�ނ��Ƃ������Ƃŋc�_�����Ă܂��肽���Ǝv���܂��B
�@���܂ł��\�N�������ċc�_�����Ă���Ƃ���Œx�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ����������낤�Ǝv���܂�����ǂ��A�C�����́A�ے����\�������܂����Ƃ���A�����������ς�܂���̂łǂ��x�Ⴊ���邩�Ƃ������Ƃ��������Ă��������ƍl���Ă���܂��̂ʼn��炩�̂��m�b������ΒS���ۂ⎄�̂Ƃ���ł��\���܂���̂ł��w��������������肪�����Ȃ��ƁA�����I�ɒ��ʂ��Ă��錻���̕���������܂��̂Ői�߂ĎQ��܂��̂ł����������Ǝv���܂��B
�@�X�ь����̈ϑ��̌��ł���܂�����ǂ��A�����̎w�E�ɂ��܂��ẮA�ȑO�A�������������܂����S�����c��̒��ŏ����̕����炨�b�͍����グ�Ă���Ƃ����ӂ��Ɏ��͗������Ă���܂����A�ϑ����̍l�����ɂ��܂��ẮA�K�͓I�Ɍ��I�{�݂��3�Z�N�^�[�Ɉϑ����Ă��镔���ɂ��ẮA���̉^�c��ɂ��Ă͊T�˂̎����̂ʼn��������̈ϑ����͌v�サ�ĉ^�c���Ă���Ƃ����ł���܂��B
�@���A�ܐ疜�~�����疜�~�ɍ팸���č�����߂Ē�Ă����Ă���Ƃ���ł���܂�����ǂ��A���̐܂�������̌��ʂ��A��Б�����v��\���o�������܂�ɂ͂ł��ˁA�T��5�N��ɂ́A�o�c�����肵�āA���̎��̎����ɂ��ϑ����̓[���ƌv�サ�āA�����̋c��̊F������ɂ����t�g���̖��ɂ��Ă��c�_�����Ă����������o�܂�����Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B
�@�ϑ����ɂ��Ă���疜�~���b�����z���Ă����Ăł��ˁB�o�c�ɂ���āA���̓����A���̎��̎����ł����5�N��̎��x�v��\�̒��ł̓[���ƁA���킹�āA�ł����玄�������\�������Ă���悤�ɁA���t�g�����y�����Ă��������Ƃ����v��̒��Ń��t�g���A�ϑ����ɂ��Ă̂��c�_�A����������Ƃ���ł���܂��B
�@����́A�����I��������Ƃ������Ƃŕ�\�Z�̒�ĂɂȂ��Ă���܂����A����́A���R�����\�Z�ł̋c�_�ɂȂ�Ǝv���Ă���܂��̂ŁA�c���������܂����悤�ɁA����Ɛт����ɍD�]�v���܂��ėݐϐԎ�����疜���x���k���Ă���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B
�@���������āA����͂ł��ˁB��قǂ����܂����v�揑�ɂ̂��Ƃ��ċc�_���Ă����Ȃ�A�����ꂩ�̎��_�ňϑ����̊z�A�ϑ����̂�����ɂ��Ă���3�Z�N�A��Б��Ƃ̍l�����̎C�肠�킹�͓��R�K�v�ɂȂ��Ă���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B
�@���A�c��̊F������Ƃ��X�L�[��̂�������ʂ����Ăǂ�����ׂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����������Ă��b���Ă��������Ǝv���܂��B
�@���C�i���[�̌��ɂ��Ă���3�Z�N�̂�����ɂ��đS�����c��ő�ϐ^���ɂ����Ȃ��ӌ�������܂����̂ō���A�܃P�����Ƃ��Ă̑�3�Z�N�^�[�̂�����A�Ⴆ�A�܃P���n�C�����h�ł���A���C�i���[�ł���Ƃ������Ƃ��܂߂Ęb�����������Ă�����������肪�����Ȃ��ƁA���̂悤�ɍl���Ă���Ƃ���ł��B�ȏ�ł��B
�H�{�@�c��
�c���@�͂��A�H�{�N�B
�H�{�@�n�В����ɂ��ẮA�ڕW�ݒ肪�厖���낤�Ǝv����ł��B�����́A���ɍs���]�����x�A�������ƕ]�����x���Ƃ�����ƁA���ꂪ���̃X�e�B�^�X���Ƃ����悤�Ȃ��������Ď��͂���ɔ��Ɋ��҂��Ă���Ƃ���ł��ˁB�ł�����A�����������̂ɂ̂��Ƃ��Ēn�В����̂ł��ˁB���N���炢�ɏI���Ƃ����A������o�c�b�`�̃T�C�N���Ń`�F�b�N���Ă����Ƃ������Ƃł��ˁB����𑁋}�Ɏ��g��Œ��������ȂƂ����ӂ��ɑ����܂��B
�@���ꂩ��A�i�X�ь������Ƃ́j�ϑ����ɂ��Ăł����A���A��������5�N��Ƃ����b�����Ă����Ƃ������Ƃł������܂����B���́A�c���^�ׂĂ݂܂����������������Ƃ͓����Ă��Ȃ��̂ł��ˁB
�@����ŁA�S�����c��Ő��������ƁB���킩��ł��傤�ƁB�����炲�������������Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁi�����\��N�x�́j��������ɂȂ��Ă���킯�ł�����ǂ��A���̌o�܂��ڂ������`�����Ȃ��ƕ���Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA����12�N�x�ƕ���13�N�x�i�̌_�j�ׂĂ݂܂����̂ł������������Ǝv���܂��B
�@����R�X�ь����Ǘ��ϑ��_�ŁA����12�N6��16���ɒ������ꂽ���̂��������܂��B����ɂ��܂��ƌ܃P�������@�������M���i�b�j�Ƃ��ć��܃P���n�C�����h�@��\����𒆓��������i���j�Ƃ��Č_��Ă���܂����A���̑���ɂ́A�_��̊��ԁ@�����P�Q�N�S���P�����畽���P�R�N�R���R�P���܂ŁA��Z���@�ϑ����Ƃ��āA�Ǘ��^�c�ϑ����́A�b����������������p���͈͓̔��ōb�����c�̏㌈�肷��B��2���ɂ͑O���̊����̈ϑ����́A50,000��~�Ƃ���B�掵���́A�b�́A�܃P�����g�p���y�ю萔���������i���a�R�U�N�܃P��������P�V���j�Ɋ�Â��������p��������B�A���A�����̎��[�����ɂ��ẮA���Ɉϑ�������̂Ƃ���B���̑��{�ݗ��p���ɂ��ẮA�������p�����Ƃ��Ē�������B��ɉ����������闘�p�����́A�b�̏��F���ĉ�����߂�B�ƂȂ��Ă���܂����A���̕����\��N�x�̈�ʉ�v�ɂ����Ă͂ł��ˁA
�X�ь������Ƃ̍Ώo�́A
����9,100�~�A�X�ь����ϑ���20,000,000�~�A���t�g�_���ϑ���693,000�~�A�X�m�[�}�V���g�p��2,400,000�A���L�юg�p��4,214,700�A�H��������40,371,550�A���S���i�������k�������j480,000�~�A�x����2,007�~�A���v68,313,157�~���x�o����Ă���܂��B
�@�X�ь������Ƃ̍Γ��̂Ƃ���ł́A���H�g�p���i���t�g�j�Ƃ��ē����\�Z��120,000,000�~�オ���Ă���܂�������\�Z��119,609,000�~�����z�ɂȂ��Ă���܂��B
�@���̌_��ł͂ł��ˁB�i���t�g�����́j�b�̎����ɂ���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ł���B����ňϑ����́A50,000��~�Ƃ���A�ƂȂ��Ă���̂ł��ˁB�Ƃ��낪���ۍs���Ă��邱�Ƃ́A�_��ɂȂ����Ƃ���Ă���̂ł���B�ǂ�������͕s�R���ƁA�������Ȃ��Ǝ��͎v���킯�ł��B
�@���ꂩ��ł��ˁB����13�N�x�̌_�i����R�X�ь����Ǘ��ϑ��_�j�ł�����ǂ��A����́A����Ɍ_��̊��ԁ@�����P3�N�S���P�����畽���P4�N�R���R�P���܂ŁA��Z���@�ϑ����́A�Ǘ��^�c��́A�����������闘�p�����������ĉ����x�ق���B�掵���@�{�ݗ��p���ɂ��ẮA�������p�����Ƃ��Ē������A���̎����Ƃ���B�ƂȂ��Ă���܂��B
�@������A�܃P���n�C�����h�����ׂė��p���͎����ɂ���Ƃ������Ƃł��ˁB�����������Ɓi�ϑ����͏o���Ȃ��_��j�ɂȂ��Ă���܂��Ăł��ˁA����̕�i����14�N�x�̕�\�Z�j�Ɂi�ϑ���20,000,000�~�j���o�Ă����Ƃ������Ƃł������܂��B
�@�����́A�Z���̊F������ɐ�������̂ɂ���͔��ɓ���B�Ⴆ�A�i�ϑ����́j20,000,000�~�́A����13�N�x�̗\�Z�ɉ��Ƃ��ł��Ȃ����ƑŐf�������đS�����c��ŋ��c�����o�܁i�ł��Ȃ��Ƃ̌��_�j������̂ł����A����14�N4��24���t�̌܃P���n�C�����h�̎��ƊT�����Ƃ����̂��o���ꂽ��ł����A����ɂ��Ƒ�8���A����14�N5�����̂Ƃ����20,000,000�~�̈ϑ����Ƃ��āi�����̗��Ɂj�v�サ�Ă����ł���ˁB�������Ė{���o�Ă��܂����i�܃P���n�C�����h�́j������ѕ\�ɂ��܂��Ɓi�ϑ������v�コ��āj�Ȃ��B
�@���́i���т́j���e�A���v�v�Z�����݂Ă��ł��ˁB����13�N6�����畽��14�N5�����̑��v�v�Z���ł����A���㍂���X�L�[��374,115,422�~�A�ؒn��106,990,970�~�A���Y�Z���^�[53,918,544�~�ō��v535,024,936�~�ƂȂ��Ă���܂��B
�@�����ŏ��o������������p�O���v�́A�X�L�[�ꂪ101,145,639�~�A�ؒn�����}�C�i�X��4,907,491�~�A���Y�Z���^�[��816,896�~�ō��v97,055,044�~�̗��v�ł������܂��i�������p�͒��̎{�݂̂��ߕs�v�j�B
�@�g�[�^�������97,000��~�̗��v������ƁA�łĂ���킯�ŁA��������قǂ��ƈ�疜������Ƃ��ŗݐό�����������Ƃ������Ƃł���܂����A����1�����̗��v������̂ɁA��N�͈ϑ������o���Ȃ������̂ɁA�Ȃ�ō��N���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����������ł��ˁA�ǂ����i�����ɂ͐������j�ł��Ȃ��B
�@����Ɠ����ɁA�ϑ����Ƃ͈�̂Ȃ낤�ƁB����12�N�x�Ɍ��ꂽ�ϑ��_�Ƃ́A�܂������E�\�i�̂��Ɓj������Ă����ł���ˁB���̂��Ƃɂ��ĕ�łǂ��Ȃ������i�c�_���ꂽ���j�Ƃ������ɁA������Ƌc���^����Ă��邩�Ƃ������ɂł��ˁB���̋c���^�ׂĂ݂܂��ƁB
�@����13�N�N�x��1������l���ڂ̑������^�Ƃ���܂����A�c���͎��i���A����҂����i�@�O�c���A���c���ł���܂����A�X�ь������Ɣ�Ƃ��Ĉϑ����O�疜�~�̌��z�ƃ��t�g���i119,609,000�~�́j���z�ɂ��Ď��₳��Ă���܂��B
�@����ɂ��܂��Ƃł��ˁA�����́A
�@�u���̌��ɂ��܂��ẮA����ƂȂ��c��^�c�ψ���A���邢�͖w�ǂ̊F������������ł��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B
�@�ʏ탊�t�g�����́A���̍Γ��ƂȂ��Ă������킯�ł���܂�����ǂ��A���̗��R�ɂ��܂��ẮA���낢��Əڂ������������Ă����Ԃ̊W������܂����A��قǂ��炲�������Ă���܂����Ƃ���A������ϑ���̊�����Ќ܃P���n�C�����h�̕��̎����Ƃ���Ƃ������Ƃł��傤���A�����������ƂɈꉞ���āA���̂悤�Ȍ��z��������Ƃ���ł���܂����A����ȏ�ɁA�܂����ڂ����������K�v�ł���A�ڂ����������܂����A�����肢�������܂��ł��傤���B���������������܂����ł��傤���B�v
�@�Ɠ��ق�����A�Ď���ɑ��āA�����́A
�@�u���낢�뗝�R������܂����A���ꂼ��̂����������������X�̎�ςɂ����܂��āA�Ȃ��Ȃ����������������Ȃ��Ƃ�������邩�Ǝv���܂�����ǂ��A����R���U���ɂ��������\�������܂������A���A���A�S�����c��̎��ɂ��\�������܂������A���������P�O�N�x�ɍČ��������Ƃ������Ƃɂ��Ă��[�����ē����낤�Ǝ��͎v���Ă���܂����v
�@�]�X�Ƒ����킯�ł����āX����ɑ��Ē�����
�@�u�����A���i�c�����璬���̕��ɗ����̂����������ł��Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���܂�����ǂ��A���͍ĎO�A�Ďl�����������������߂ɑS����������Ă���܂��̂ŁA���̓_�ɂ��ẮA�@���Ȃ闝�R�ł����������ƂɂȂ������Ƃ������Ƃɂ��ẮA�����[�������m�ł��낤�Ǝv���܂����A�ܘ_�A�����̑�\�ł���܂��Ƃ���̋c���̊F������ɒ����̕��ɂނ��낱�̂��Ƃ��w�����Ă������������A���������Ă������������A�Ƃ��̂悤�Ɏv���܂��B�v
�@�Ƃ������Ƃō̌�����Ă����ł��ˁB
�@��y�c���́A���͂܂��c���łȂ��������瓯�Ȃ��Ă��炸�킩��܂���ǂ��A���t�g�������܃P���n�C�����h�ɂ��Έϑ����͂���Ȃ��Ȃ�Ƃ����������i�S�����c��Łj����������ǂ����̂��Ƃ����^�₪�F������łłĂ����ł��ˁB
�@������A�{��c�ł��i�����������Ƃ́j�L�^����Ă��Ȃ��B���A�����̐����́A5�N��Ƃ����ӂ��Ȃ��Ƃł������ƁA�����ł܂��A�H���Ⴂ������B
�@�����A�_��ɉ��������Ƃ������ɂȂ��Ă��Ȃ��B���̂悤�Ȃ����łł��ˁA���A�[���̗��Â���ŐV���ȁi��O�Z�N�^�[�́j���Ƃ�����킯�ł�����ǂ��A���̂܂܂������̕��֍s���킯�ɂ͂�����Ǝv����ł���B
�@�����炱����A����1�c���Ƃ��Ē��������Ȃ��B�c��œ��ʈψ���Ȃ�����Ȃ���Β��������Ȃ��킯�ł��B������A�f�ГI�ȏ��ł������f�ł��Ȃ��B�S�̂��{���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��A������ƌ��������ł��������������Ȃ��Ƃ����邶��Ȃ����ƁA�����������������Ă͂����肵����ŁA�܊p�A�������V�����a�������킯�ł�����A�������Ɖߋ��̂��������ςȂ��Ƃ͂�����Ƃ��āA�����āA�V���ɃX�^�[�g����Ƃ������Ƃł����ɂȂ�Ȃ��ƁA���̉������ł����Ȃ��Ƃ�i�߂Ă����ƁA���͏Z���A�����̊F����ɑ��ĐӔC���ĂȂ��킯�ł��B
�@�܂��Ƃ��Ȏd�������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł�����A����������Ē��������B
�@���A�����ŁA���킩��̂��Ƃ͂����ْ����Č��\�ł������܂�����ǂ��A���͂���ς蒲���ψ��������ďڂ������������āA���ďZ���ɔ[���̂ł���悤�Ȃ��Ƃɂ��Ă���A���̐R�c���̂��A�������Ē����Ȃ��Ɩ�肪����Ⴀ�Ȃ����Ƃ����悤�ȋC�����܂��B�����������Ƃł�낵�������ق������Ǝv���܂��B
�c���@����
�����@�c���A���A�H�{�c������Ď��₪�������܂�������ǂ��A�_���s���������_�ɂ��ẮA�������傭�ɁA���̎��_�ŕύX�_�ׂ��������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B���ꂪ��������Ȃ������킯�ł�����c���̂��������Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�������A�c�_�̌o�߂ɂ��Ă͂ł��ˁA�����������A���������������Ƃ������Ă���킯�ł��Ȃ�ł��Ȃ��āA�����A5�N�ԂłƂ����̂́A�����̂��̎��_�ł̈ϑ������c�_�����ʂŁA��������Б��Ƌ��c���ďo�����v�揑�Ƃ��Ă�5�N�セ���Ȃ�ł��낤�ƁA�����A���̎��_�ƍ����ǂ��ł��邩�Ƃ����̂́A������x���̎�����������x���āA����Ƃ��Ă݂Ȃ�������Ȃ���ł��傤����ǂ��A���̃f�[�^�����R�c���Ă���Ƃ������Ƃł���܂�����A���̍��܂ł̌o�߂ɂ��Ăł��ˁA�ēx�������āA�X�J�b�Ƃ����C�����łƂ���������ł���A�����������A��������܂���Ƃ������C�����͂܂������������܂���B
�@�������Ƃ������āA�X�L�[��͂ǂ�����ׂ����Ɛ�قǎ����\�������܂����悤�ɁA�ǂ�������ꂩ���X�L�[��𖢗��i���Ɏ��B�̒��̕�Ƃ��đ����Ă������Ƃ��ł���̂��ǂ����A���̂��Ƃ��܂߂Ăł��ˁA���ԎQ���A��O�Z�N�^�[�̂�������܂߂Ă��̋@��ɏ[���c�_���Ē������́A���͑�Ȃ��Ƃ��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�@�ł�����A�����������Ƃ��K�v���Ɛݒu������ł���Ύ��͐ϋɓI�ɂ����͂������Ē��������A�t�ɂ��������@��ɂł��ˁA�X�L�[��̍l�����ɂ��Ă������̊F������ɍēx���i���������Ƃ��̂悤�Ɏv���Ă��܂��B
�H�{�@�c���B
�c���@�͂��A�H�{�N�B
�H�{�@���������������ψ���������Ă�����ł�������Ȃ����Ƃ������Ƃł������܂��̂Ő�����ʈψ���ł��̌��́A�������蒲�������Ăł��ˁA�[���̂����悤�Ȍ`�ł����߂Ă������������ȂƎv���܂��B
�@���ꂩ��A���C�i���[�Ƃ͕ʂ��Ƃ������Ⴂ�܂����B����͓��R�ł��ˁB�����ǂ��A�������Ƃ���������߂����Ă���ł����������ǂ��A���̂܂܂ł���ނ�ɂ����Ƃ��ׂĂ��������ӂ��ɂȂ��Ȃ����Ƃ����悤�ȈӖ��Ŏ��͐\�������Ă���킯�łł��ˁB
�@������A���X���̓_�͂������Ƃ��Ă��ꂩ��A���g�ނƂ������Ƃł��ˁB�����āA�ł���s���]�����x�Ƃ������������̂����g�ނƂ������Ƃł�����A�A������A�g���Ă����悤�Ȍ`�ło�c�b�`�̃T�C�N�����܂킵�Ȃ������Ă����Ƃ������Ƃɐi�߂Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�@�c���A�����������Ƃňψ���i�̐ݒu�j�����߂܂��B
�c���@�H�{�N�̂��̈ӌ��ɂ��ẮA���A����S�����c������Č��߂Ă��������Ǝv���Ă���܂��B
�H�{�@�c���B
�c���@�͂��B
�H�{�@�c���A�ł���ł��ˁA�l�͂������̕����悾�Ǝv����ł���B����ς肫�����Ƃ��Ă���i�߂�Ƃ������ƂŁA����ނ�ɂ��Ă����悤�ł���ł��ˁB����́A�Ȃ�ɂ��S�ۂ��Ƃ�Ă��Ȃ����A���̂܂܍s���Ă��܂��킯�ł���B�����Ԃ��̂��Ƃłł���Ǝv���܂�����ł��ˁB����͂����Ƃ���Ă���i�ނׂ��ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B�܁A���̋c�������̈ӌ��������Ă�����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�c���@�͂��B���A���c�Ƃ��ĔF�߂Ȃ���Ύd���Ȃ����ȂƎv���̂ł����A�������ł����F����B�^���҂�����Γ��c�ƔF�߂ăn�C�����h�ɂ��Ă̍���̎�g�ݕ��ɂ��ē��ʈψ����ݒu���Ă�肽���Ƃ������Ƃł���܂��B
�c�ꂩ��@�b���x�e�B
�c���@�b���x�e��v���܂��B
�i���̌�A�c�^���c���Ȃɍs�����c����A�ȉ����c�̍̌��ɂ��Ă̓e�[�v�ɋL�^�Ȃ��A�����ƋL���ɂ��Č�����Ɓj
�m�Č������n�܂�n
�c���@�x�e����܂��B����ł́A�������H�{�c������o���ꂽ�܃P���n�C�����h�������ʈψ���̐ݒu�����߂铮�c�ɂ��Ď^���̕��́B
�c���@�^���҂Ȃ��B����Č܃P���n�C�����h�������ʈψ���̐ݒu�͕s�̑��ƂȂ�܂����B
�m�������I��n
(�ȉ��A�����c���̎��^�Ɉڂ�)--��--
�c���@���^���Ȃ��悤�ł�����A����ɂĎ��^���I�����܂��B���_�͏ȗ����Ă��ꂩ��N���ɂ���č̌����܂��B�c�đ�28���A�����\�B
�H�{�@���́A���ł͂Ȃ��ł����ސȂ����Ă��������܂��B
�c���@������Ƒ҂��Ă��������B���A2�ԏH�{���c������ސȂ̗v�]������܂����̂ŁA����͋c���Ƃ��ĔF�߂����Ǝv���܂��̂ł�낵�����R�c�������Ǝv���܂��B
�c�đ�28���A����14�N�x�܃P������ʉ�v��\�Z��1���ɂ��ẮA���Ă̂Ƃ��茈�肷�邱�ƂɎ^���̕��͋N�����肢�܂��B
�͂��B�N�������ł���܂��B���������Ė{�Ă͌��Ă̂Ƃ��������܂����B
�c�ꂩ��@�����ł͂Ȃ��ł���A�Ȃɂ��Ȃ�����B
�c���@�����A�����ł����B���炵�܂����B�c�đ�28���A����14�N�x�܃P������ʉ�v��\�Z��1���ɂ��ẮA���Ă̂Ƃ��茈�肷��ɐl�Ɏ^���̈ӎv�����܂������A�S���N���ł���܂����̂Ŗ{�ẮA���Ă̂Ƃ��������܂����B
�c���@�����A�H�{���c���̓���������܂����̂ł�낵�����肢���܂��B���ɋc�đ�29���A����14�N�x�܃P�����������N�ی����ʉ�v���Ɗ����\�Z��1���ɂ��ā\�ȉ����\
----------------------
�����^���I����āB
�@�Ȃ��A���̂悤�ȍs���ɂłȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B�܃P�����ƌ܃P���n�C�����h�̊W�ɂ����āA���܂�ɂ���ꍇ���ŋْ����̂Ȃ�������F�߂�ꂽ����ł��B�������S�ʓI�ɏ����J���s���Ɛ錾���ꂽ�̂ŁA�_�_�ƃf�[�^���ȉ����J���܂��B
�@.�����܃P���n�C�����h�ɃX�L�[��A�ؒn���A���Y�Z���^�[�̌��I�{�݂̉^�c���ϑ�����ɓ����ē����̊�{�I�Ȍ_�Ȃ��B
�A�D����12�N4��1�����畽��13�N3��31���܂ł̊Ǘ��^�c�ϑ��_��ł́A���t�g���͒��̎����ƂȂ��Ă��邪�A���ʓI�ɂ́A�܃P���n�C�����h�̎����ɑւ���Ă���B�\�Z�ʂł������\�Z��120,000��~�����Ƃ��ďオ���Ă������r����\�Z��119,609��~���z����Ă���B�܂��A�ϑ����͌_��ł�50,000��~�ƂȂ��Ă��邪��\�Z��20,000��~�Ɍ��z����Ă���B���̕ύX�_�Ȃ��A�����z������\�Z�̐R�c�ߒ��ł��A�ύX���R�̋L�^���c���^�ɂ����݂��Ȃ��B�܂��A���t�g������3�{�̃��t�g�̓��ǂ̕������w���̂����_�ɖ��L����Ă��Ȃ��B
�B.���N�̕���13�N4��1�����畽��14�N3��31���܂ł̊Ǘ��^�c�ϑ��_��ł́A���t�g�����͌܃P���n�C�����h�̎����Ƃ��A�ւ��Ɉϑ����͏o���Ȃ��ƒ�������Ă���̂ɑS�����c��ł͈ϑ������o���Ȃ���Ή�Ђ̓X�L�[�ꂩ���������Ƃ�����Ђ���������X�L�[��͑����ł��Ȃ��Ȃ�Ǝ��s������������ꂽ�B
�C�D���t�g������ύX�������A���t�g�����܃P���n�C�����h�ɓn���Έϑ����͂���Ȃ��Ȃ�Ƃ����������������̂ɂƂ�����������B�i�L�^�ɂ͂Ȃ��j
�D.�O�N�x�P���̒P�N�x�̗��v���������̂ɐV�N�x�c�ƈȑO�Ɉϑ�����20,000��~�o���Ƃ����͍̂������R�����B
�E.�X�L�[��̉^�]�����Ƃ������ڂ��ϑ����̍����ł��邪�A�܃P���n�C�����h�̌o�험�v�Ƃ��̓���͎��\�̂Ƃ���B
�X�L�[�ꕔ��i�P�ʐ�~�j
| �X�L�[�� �i�P��:��~�j |
|||||
| ��S���i10/5�j | ��5���i11/5�j | ��6���i12/5�j | ��7���i13/5�j | ��8���i14/5�j | |
| ���㍂ | 242,328 | 220,230 | 200,902 | 268,999 | 374,115 |
| ���㌴�� | 38,970 | 37,940 | 29,608 | 33,205 | 46,417 |
| ���㑍���v | 203,358 | 182,290 | 171,294 | 235,794 | 327,697 |
| ��ʊǗ��� | 272,794 | 197,444 | 226,940 | 224,233 | 237,086 |
| �c�Ɨ��v | -69,436 | -15,154 | -55,646 | 11,561 | 90,610 |
| �c�ƊO���v | 16,446 | 10,937 | 8,136 | 5,945 | 4,928 |
| �c�ƊO��p | 728 | 894 | 372 | 315 | 540 |
| �o�험�v | -53,718 | -5,111 | -47,882 | 17,191 | 94,998 |
| �i���p�O���v�j | -48,961 | 866 | -41,081 | 23,135 | 101,145 |
�ؒn������
| �ؒn�� �i�P��:��~�j |
|||||
| ��S���i10/5�j | ��5���i11/5�j | ��6���i12/5�j | ��7���i13/5�j | ��8���i14/5�j | |
| ���㍂ | 61,364 | 98,169 | 112,709 | 106,990 | |
| ���㌴�� | 21,196 | 32,943 | 34,709 | 35,726 | |
| ���㑍���v | 40,168 | 65,226 | 78,000 | 71,264 | |
| ��ʊǗ��� | 57,329 | 85,820 | 84,556 | 79,836 | |
| �c�Ɨ��v | -17,161 | -20,594 | -6,556 | -8,571 | |
| �c�ƊO���v | 518 | 940 | 1,129 | 1,643 | |
| �c�ƊO��p | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| �o�험�v | -16,643 | -19,654 | -5,427 | -7,076 | |
| �i���p�O���v�j | -10,553 | -12,699 | -1,312 | -4,907 |
���Y�Z���^�[����
| ���Y�Z���^�[ �i�P��:��~�j |
|||||
| ��S���i10/5�j | ��5���i11/5�j | ��6���i12/5�j | ��7���i13/5�j | ��8���i14/5�j | |
| ���㍂ | 55,667 | 53,918 | |||
| ���㌴�� | 34,185 | 35,058 | |||
| ���㑍���v | 21,482 | 18,860 | |||
| ��ʊǗ��� | 19,730 | 18,804 | |||
| �c�Ɨ��v | 1,752 | 55 | |||
| �c�ƊO���v | 774 | 230 | |||
| �c�ƊO��p | 0 | 0 | |||
| �o�험�v | 2,526 | 286 | |||
| �i���p�O���v�j | 2,881 | 816 |
�@��L�̂悤�ɁA�X�L�[��͂��ł�14�N5�����Ōo�험�v�̗v��5,478��~�̍����A���p�O���v�̗v��35,104��~�̍������v�サ�Ă�����ɐԎ��͉�������Ă���B
�@�܂��A���p�O���v-�o�험�v�͊T�ˌ������p�ƂȂ�̂ł��̒l��29,626��~�͏��p���ς�ŃL���b�V���t���[�Ƃ��ĉ�Ђ͉���ς݁B
�@����āA�ϑ�����20,000��~�̓X�L�[��̋~�Ϙ_�A�^�]�����_�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�䂦�ɁA�X�L�[��̉^�]�����_�͘_�_�̂���ւ��ł͂Ȃ����B
�@���́A�o�푹�v�v-48,800��~�̖ؒn���̐Ԏ��̎����ǂ����邩�Ƃ������Ƃł��邪���̔F���������B
�F.�������p��ɂ��ẮA�_�ł́A�y���ȏC�U�͉�Ђōs���ݔ��͒����s�����ƂɂȂ��Ă���B���̂��Ƃ��画�f����Ɖ�Ђ͏C�U��݂̂ŁA�������p�͔������Ȃ��͂��ł��邪�A11/5������14/5���܂�44,352��~�̐ݔ��������Ȃ���Ă���B�{�ݑS�̂��������ƂȂ�Ȃ����B
�G.�X�L�[�V�[�Y���ł���12������3���܂ł̖ؒn���̏h���q���́A���\�̂Ƃ���2,761�l�ł���B
| 12 | 583 |
| 1 | 755 |
| 2 | 776 |
| 3 | 647 |
�@�{���A�ؒn���̏h���{�݂́A�X�L�[�q�͑Ώۂɂ��Ȃ��Ɩ�������Č��݂��ꂽ�{�݁B�����A���h�E���ٓ��X�L�[�q�����Ă���ł��������Ԏ{�݂͂��̌㌚�݂��ꂽ����t���I�{�݂̖ؒn���ɂ����Ɉ������Ă���B�O���[���V�[�Y���ɂ��A���Ė��Ԏ{�݂𗘗p���Ă����ڋq��U�v���Ă��薯�Ԏ{�ݑ��͎������ƂȂ��Ă���B�f�p�[�N���h�q�̖��Ԏ{�ݗ��p�́A���X������̂ł���S�����b�̂Ȃ��h���{�݂�������B
�H.���Ɍf����u�̔���y�ш�ʊǗ���v���̑��l����176,246��~�Ɋ܂܂��o��S��58,721��~�i�o���Ј��ƃ}�l�W�����g���H�j�͑��l�����33.3���ɏオ���Ă���K�����H�B
| �̔���y�ш�ʊǗ���@��8���i13/6�`14/5�j�@�@�i�P�ʁF�~�j | ||||
| �Ȗ� | �X�L�[�� | �ؒn�� | ���Y�Z���^�[ | ���v |
| ���^���� | 11,642,413 | 3,994,057 | 5,712,345 | 21,348,815 |
| �ܗ^ | 2,428,800 | 404,300 | 1,231,200 | 4,064,300 |
| �G�� | 73,032,603 | 9,726,653 | 3,135,139 | 85,894,395 |
| �ސE�� | 0 | 113,020 | 0 | 113,020 |
| �@�蕟���� | 2,191,855 | 2,031,851 | 1,153,960 | 5,377,666 |
| ���������� | 299,475 | 376,462 | 50,535 | 726,472 |
| �o��S�� | 25,183,723 | 33,177,309 | 360,832 | 58,721,864 |
| �l����v | 114,778,869 | 49,823,652 | 11,644,011 | 176,246,532 |
| ���Օi�� | 11,111,478 | 4,209,365 | 953,131 | 16,273,974 |
| �R���� | 18,517,380 | 4,236,600 | 0 | 22,753,980 |
| �ʐM�^���� | 11,751,802 | 1,683,589 | 369,928 | 13,805,319 |
| �ی��� | 6,702,480 | 53,210 | 95,660 | 6,851,350 |
| �ڑҌ��۔� | 1,479,011 | 783,439 | 539,122 | 2,801,572 |
| �x���萔�� | 695,138 | 468,085 | 78,300 | 1,241,523 |
| �L����`�� | 4,866,619 | 895,366 | 2,858 | 5,764,843 |
| �������M�� | 15,071,008 | 6,267,490 | 3,407,464 | 24,745,962 |
| �}�����C�� | 202,349 | 158,378 | 70,458 | 431,185 |
| ���ޗ��� | 318,539 | 93,198 | 8,800 | 420,537 |
| �ϑ��� | 12,188,740 | 4,110,360 | 255,430 | 16,554,530 |
| �g�p������ؗ� | 24,559,787 | 3,495,794 | 448,581 | 28,504,162 |
| �d�Ō��� | 2,045,338 | 253,087 | 15,663 | 2,314,088 |
| �����ʔ� | 1,649,189 | 90,951 | 273,724 | 2,013,864 |
| �ŗ��m��V | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| �̔����i�� | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ��c�� | 123,151 | 80,080 | 17,520 | 210,751 |
| �C�U�� | 3,180,067 | 850,147 | 14,000 | 4,044,214 |
| �������p�� | 6,146,841 | 2,169,384 | 530,778 | 8,847,003 |
| �G�� | 1,499,196 | 64,183 | 79,063 | 1,642,442 |
| ���v | 237,086,982 | 79,846,358 | 18,804,491 | 335,727,831 |
�@�ȏ�̂悤�ɏ������ׂ������ł��A���̂悤�ɖ����_������܂��B����قǘ_�_������̂ɁA�c�_�����������Ȃ��ŏ����A��O�Z�N�^�[�ɂ�郏�C�i���[���Ƃɓ˓����邱�Ƃ́A�Z���̊F����t�����ċc��ɂ���҂Ƃ��ĐӔC������Ǝv�����̂ł��B
�@�Ȃ����̋c���̊F���^�����Ă���Ȃ������̂��B���̏ꍇ�̓��c�́A�Œ�1�l�̎^���c��������ΐ�������͂��ł��B���̂��߁A�̌��ɂ͎Q�������c�ꂩ��ޏꂷ��ق��Ȃ������̂ł��B
�@�������u��O�Z�N�^�[�̂�������܂߂Ă��̋@��ɏ[���c�_���Ē������́A���͑�Ȃ��Ƃ��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�ł�����A�����������Ƃ��K�v���Ɛݒu������ł���Ύ��͐ϋɓI�ɂ����͂������Ē��������B�v�Ƃ������ق��������̂ł��B�c�O�I�B�����Ǝ��O�̍����K�v�ł����B���ȁB
�@����ɂ��Ă����̌��͂��̂܂ܖ�������Ă��܂��̂ł��傤���B1�c���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B����Ƃ��M�҂̍l�������Ԉ���Ă���̂ł��傤���B
�@�X�L�[��͒����̃X�L�[��A�n�抈�����̂��߂̃X�L�[��łȂ���Ȃ�܂���B���Ƃ́A�Z���̊F����̗ǎ��Ɣ��f�ɂȂ������Ǝv���܂��B
�@�{����4��1�����ŏ������t�����z�u�����Ă̋c�_�Ƃ���̋c�_�v���܂��ɂ�����������悵�Ă���̂ł��B����̋c�_�̏�ł�����c�_���ė����������Ă��L�^����Ȃ��A�S�ۂ���Ȃ��̂Łu���̎��͂ǂ��ł��������v�Ƃ����L���ɗ��邵���Ȃ��B���ꂩ��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
------------------------------
2002�N7��25���@�c�����C��
�@�ߌ�1�����A���P�n�x���̑��c���ɂ����āA���P�n3���̋c����Ώۂɂ����s���������c�����C��������B
�@���n���ۂ̐����̌�A���^�������������B���P�n3���̍����ŘZ���~�̍������ʂ�����Ƃ����B
�@����17�N3����ړr�Ƃ��čl�����鍇�����f���X�P�W���[���́A���L�̂Ƃ���B
1.����14�N3��
����������̐��ʂƂ�܂Ƃ߁E���\�B
2.����14�N�x�̂Ȃ�ׂ����������B
�C�ӂ̍������c��̔����B
�Z���c��̍\�������o�[
�Z���̑��E���A�c�����c���\�ҁA�w���o����
�Z���c��̑g�D�B
�@���c��̉��ɁA������A��啔��y�ѐ�C�̐E���ō\�����鎖���ǂ�ݒu�B
�Z���c����
�E�s�������v��̍쐬
�E�Ő��A�����������̍s�����x�̓��ꋦ�c
�E�����d�v���ڂ̋��c
�@�����̕����A����
�A�V�s�����̎������̈ʒu�A
����
�B�c��̋c���̒萔�y�єC��
�̎戵
�C���Y�̎戵��
�������O�����Ȍ������s���ꍇ�A�@�荇�����c��ֈڍs
�@�����c�s���̏ꍇ�A���U
3.����15�N9���c��
�e�\���s�����Łu�@�荇�����c��̐ݒu�v�ɂ��ċc��
4.����15�N10��
�@�荇�����c��̐ݒu
�E�C�Ӎ������c��Ō��肵���S�Ă̎����𗹏�
�E�s�������v��̒m�����c
�E�������菑����
5.����16�N9���c��
�\���s�����c��ō������c�A�m���ɍ����\��
6.����16�N12���c��
���c��̋c���A�m���̌���y�ё�����b�ւ̓͏o
������b����
7.����17�N3��
�����{�s
�@�ȏ�̂悤�ȃX�P�W���[���Ői�߂���B
�@���P�n����������̒������ʂɂ��ẮA��̍���䒬���ɑւ���ĕ���̓��V�e������嗢�@�O���̖��O�Ŕ��\���ꂽ�B���������ꍇ�̗��_�Ɩ��_���L�ڂ���Ă��镔����v��Ɖ��L�̂Ƃ���ł���B
�@���������ꍇ�̗��_�i�����b�g�j
�C�A�����͂����������K�͂Ȏ��Ƃ��ł���B
���A�s���o��ߖ�ł���B
�n�A�����{�݂̋��p���ł���B
�j�A�s���T�[�r�X�̌��オ���҂ł���B
�z�A�n��̊����������҂ł���B
�A���������ꍇ�̖��_
�C�A�����������Ȃ�s���T�[�r�X�̒ቺ�ɂȂ���B
���A���S���������悭�Ȃ�A���Ӓn�悪���c�����̂ł́B
�n�A�����̂��傫���Ȃ�A�Z���̈ӌ������f����ɂ����Ȃ�̂ł́B
�j�A��������Ɗe���̗��j�A�����A�`���A����������̂ł́B
�z�A��������������荂���Ȃ�̂ł́B
�@�ȏオ�u�����̌��ʁE�ۑ�v�̎�v���ڂƂ��Čf�ڂ���Ă��܂��B
2002�N7��25���@�S�����c��
�@23���̖{��c�ŕs�̑��ƂȂ����܃P���n�C�����h�̒������ʈψ���̐ݒu�����߂铮�c�ɂ��ċc�^�̋��c���ʂ����ꂽ�B���̊T�v�́A
�E�S���ɐ悾���ċc�^���J���ċ��c�������ʁA�������ʈψ���ݒu�Ɏ^���̈ψ��͈�l�����Ȃ��B
�E�S���ŐR�c���Ă������������B
�Ƃ������Ƃł���B
�@������đS���ŐR�c�������A�S���ł����ʈψ���ݒu�̕K�v�Ȃ��ƌ��_���ꂽ�B
�@���̒��ŁA�����ɂǂ��������邩����̂Ő\�����킹����Ȃǂ̈ӌ����o���ꂽ���e�X���ӔC�������Đ������ׂ����ƌ��_���ꂽ�B
�@���ɁA�c��̃��[���ɂ��Ďw�������B
�E�c�ꂩ��ޏ�A���ꂷ��ꍇ�ɂ́A�c���̋��������Ƃōs�����邱�ƁB
�E���c���o���ꍇ�ɂ́A�悸�u���c���o���܂��v�ƌ����Ă����ė��R���������悤�ɁB
�i�_�]�F�������瓮�c���o������͂Ȃ������̂ł����A����̐���s���㌋�ʓI�ɓ��c�ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B���n�ł����I�B���c�ɂ́A1.�Ă�����Ă��铮�c�B2.�Ă�����Ă��Ȃ����c�B��2��ނ���A�Ă�����Ă��Ȃ����c�́i1�j��c�̊J�Ɋւ��铮�c�Ƃ��ć@����������c���J�����Ƃ̓��c�B�A�x�e�A����A�U��A���~�̓��c�B�B�x��̓��c�B������܂��B����ɂ��ƁA�b���x�e�̔��������������Ƃ��A�̋x�e�̓��c�ɓ���A���c�Ƃ��Ē�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�c��[������ł����A�c��ł͂����Ƌc�_���₷�����Â��肪�K�v�ł��傤�B�j
------------------------------
�@7��20���`21���J�Â��܂����攪��E�����z�V���|�W�E���́A50���قǂ̏��l���Ȃ�����_�ˁA���R�A�R���A�啪�A�������S���e�n����Q��������A����̂����ɏI�����܂����B
�@���̑�E�t���[�g�R���T�[�g����̃G�X�e�ƃq�[�����O�̌����A���P�[�g�ł͂ƂĂ������]������܂����B
�@����ڂ̍u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����́A����܂łɂȂ����M�����c�_�ƂȂ�܂����B���̃V���|�W�E���̋L�^�́A���݃e�[�v��������i�߂Ă���A�{���ł������f�ڂ��Ă����\��ł��B


�V���|�W�E���̎������ꕔ�f�ڂ��܂��B
------------------------------
�}�C�i�X�C�I���ɂ��āiPISCO�̃z�[���y�[�W����j
�@�C�I���Ƃ́A���q�╪�q���������蓾���肵�Ăł����A�d�C��тт���Ɍ����Ȃ����q�ł���B�{�����q�̓v���X�ƃ}�C�i�X���ƂȂ��Ē�����ۂ����肵�Ă���̂����A���炩�̃G�l���M�[�i�d���g�E�L�Q�K�X�E�X�g���X�Ȃǁj�������ƁA�}�C�i�X�̓d�q����яo���Ă��܂��B���̔�яo�����d�q�����̕��q�Ȃǂɕ߂܂����āA�d�q�����́A�܂�}�C�i�X�̓d�q��тт����̂��}�C�i�X�C�I���inegative ion�j�Ƃ����B���Ȃ݂ɁA�}�C�i�X�C�I���̑����Ƃ���Ƃ��ẮA�厩�R�̋�C�E��̋ߖT�E�����E�V�����[�̒��E�X�т̒��Ȃǂł���B
�@�v���X�̓d�q��тт����̂��v���X�C�I���ipositive ion�j�Ƃ����B��ɁA�����Ԃ���r�o�����r�C�K�X��H�ꂩ��̔�����ċp���ɏo��_�C�I�L�V���Ȃǂ��v���X�C�I���B�����Ă���B���̂��Ƃ�����A�n�k�Ɗ֘A�����v���X�C�I������C�̉��ꂽ�ꏊ�Ŋϑ����邱�Ƃ͓���B���Ȃ݂ɁA�v���X�C�I���̑����Ƃ���Ƃ��ẮA�ߐ��������E�s�s���E���V��̒��Ȃǂł���B�܂��A����̑�C�̃C�I���o�����X�́A�}�C�i�X�C�I��1�ɑ��A�v���X�C�I��1.2�ł���B
���i�[�h����
�t�̂��}���ɔ���������ۂɉt�̂̕\�ʃG�l���M�[���ω����邽�߂ɉt�H���ѓd����B���Ƃ��ΐ��H������Ƃ��ɁA���H�͐��ɑѓd������̋�C�͕��ɑѓd����B���̌��ۂ����i�[�h���ʂƌĂ�C�݂��ڕt�߂ŕ��C�I���������̂͂��̂��߂ł���B���Ȃ݂ɂ��̕��C�I���́A�̂ɑ�ϗǂ��Ƃ���Ă���B
-------------------
�i��Ë@�탁�[�J�[�i���j�����g�[�^���T�v���C�̃z�[���y�[�W����j
�}�C�i�X�C�I���Ö@�ɂ���
�S���}�C�i�X�C�I����w���@�i���^�����W���]�ځj
��w���m�@�@�x���@��
2002�N2��5���@�Љ�����J���
�@�����ẤA���x�ȉȊw�Z�p�����A�������i�����Ƃ��܂������A���̔��ʁA�Q������V�l��s���ǂ��邢�͐A���l�Ԃ����������ŁA���낢��ȓ��肪�R�ς݂���Ă���A�s���l�܂��������ÂƂ����ĈႢ�Ȃ����̂Ǝv���܂��B
�@�����������ɂƂ��Ă��̌����͔E�ѓ�ߌ��ł���A�����̊��ҕ����Q���߂��݂̗܂𗬂��Ă���̂�����ł��B���ۖ���͂��߂Ƃ��Ă��܂��܂Ȏ��Ö@���{����Ă��܂����A���҂��{���Ɉ��S���Ď��Â��������A���������{�I�����ɓ����Ö@���d�v�ł��B
�@�}�C�i�X�C�I���Ö@�́A����p���Ȃ����{�I�Ɏ��a�������܂��̂ŁA�Q�P���I�̈�Â�i�W�����钍�ڂ��ׂ��Ö@�ƌ����܂��B
�@�}�C�i�X�C�I����Տ���w�ɉ��p���邱�Ƃ��o�������Ƃ́A���ɉ���I�Ȃ��Ƃł���A��Ì��ꂩ�炻�̌��ʂɑ傫�Ȋ��҂����Ă��܂��B���������ĂыN���������͂��߂Ƃ������������}�����A����ɂ����邠����Z�p����g���Ă������̌����݂��Ȃ��悤�Ȋ��҂ɑ��Ă�����߂ėL���ł��邱�Ƃ��A��Ì���Ŏ�����Ă��邩��ł��B
�@���R�E�̃G�l���M�[�A�}�C�i�X�C�I����l�̂ɗ^�����̎���̉́A���R�����͂��������Ď��a����������̂ł��B
�@�Ƃ���Ō��݁A���E�I�Ƀ}�C�i�X�C�I���ɑ���S�����܂�ƂƂ��ɁA�������ɋN�����鐔�����̎��a�����炩�ɂ�����ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȏ��A�}�C�i�X�C�I���ɂ��V�������Ö@�́A����̎����ɑ��Ă܂��܂����̏d�v�x��[�߂Ă��܂��B
�@�}�C�i�X�C�I������L�̑��ɔ]�זE�̊������A�̑������A�S�������A���A�a�A���e���傤�ǁA�C�ǎx�b���A�A�g�s�[���畆���ɋɂ߂ėL�p�ł��邱�Ƃ��A�Տ��f�[�^���疾�炩�ɂ���Ă��܂��B���̂悤�Ɋe�푟��̍P�퐫�̈ێ��ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B
�@�ߔN�A�}�C�i�X�C�I���ɂ�����S����w���܂�A��w�E�ɂ����܂��Ă��A��b�ƗՏ��̗��ʂ���}�C�i�X�C�I����w�̌������i�߂��A���̂ɑ��鐶����p�₻�̎��Ð��ʂ��������\����Ă���܂��B�܂��A���̂ɑ��Ă͑̉t��H�̎�A���J�����A�����_�f�����\�A�Ɖu�@�\�̑����A�����_�o�n���ߍ�p�A�����z�����ʂ̑����A���ÁE���ɍ�p�Ȃǐ��X�̍�p���F�߂��Ă��܂��B
�@��т��̑��̗Ö@�̑�����ʂ����߂鎩�R�̗Ö@�����҂̒ɂ݂��ɂ���苎��A���܂łɂ͍l�����Ȃ������a�����P�����܂��B
�@�����̎��Ö@�����ł͌��E������܂��B���E�����a���A���A���������Ƒ����Ă��܂��B���̍ی��Ȃ��g�̂�I�ޕa���̂��邢�͎��a�̑傫�ȗv���ł��銈���_�f���Ǝ������̐g�̂͒������Ă��܂��B�l�̈ꐶ�͂��̐킢�̘A���Ƃ������܂��B���̐킢�ɏ����������N��z��������S�����邱�Ƃ�������l��l�̊肢�ł���܂��B����ɂ͂ǂ�����������[�[�[�[�[�[�B
�@����͍זE���������������R�����͂����߂邱�Ƃł��B�}�C�i�X�C�I���͒��ڐ��̂ɍ�p���Ă��̍P�퐫�@�\�ƐV��ӂ����߁A�A�����M�[��������K���a�Ȃǂ̗\�h�Ɖ��P�ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂ƌ����܂��B
�@���R�E�̃}�C�i�X�C�I����l�̂ɗ^���āA�����̍���������Ö@�A���Ȃ킿�A���̎��炪�{�������R�����͂��ő���ɍ��߂邱�Ƃɂ��A�g�̂̓�������a�C���������Ƃ��ł��A�a�C�ɂ�����ɂ������x�Ȑg�̂�z�����Ƃ��o���܂��B
�@�����ɂ����āA�͂��߂ė\�h��w�̎��H������A�Ǐ��}���邽�߂̑ΏǗÖ@�łȂ��A�a�C�����{���玡�������Ö@�ւƈ�Â̐i�W���݂���̂ł���܂��B
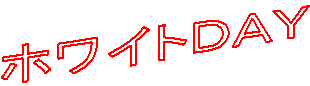
�ҏW������
�@�������̂ŁA�M�҂����̋c��ɐȂ�u���悤�ɂȂ��Ă����N���o���܂����B���䖲���̈�N�������悤�ȋC�����Ă��܂��B�������o�ϊ����ʼn�Ђ̌o�c�Ɨ����ł��邩�Ƃ������O������܂������A�F����̂������ƒg�������x���Ɏx�����ĉ��Ƃ����蔲���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���̂����Łu���v����������邩�ǂ�����Ԃ܂�Ă��܂������A���ł͓��L�����̋M�d�ȋL�^�ƂȂ�܂����B�F�l�̐�������������قǏ��̋��L���������ɑ�ł��邩��Ɋ����Ă���Ƃ���ł��B
�@�������ւ��܂�����2�N�ڂ́A�����������̗͂��Ċ����ł���Ǝv���܂��B�s���͂��Ȃ����Ƃ���ł����A���ꂩ������w��������������܂��悤���肢�\�������܂��B
�@���N�́A���Ƃ̂ق��ҏ��������Ă��܂��B���N�ɗ��ӂ���č����������Ă��������B�܂��܂��̂����������F��v���܂��B�i���j
�@���̂����Łu���v�͖����łǂȂ��ɂł�������ł��܂��B�V���ɍw�ǂ���]�̕��́A������0982-83-2326�܂ł��\�����������B���A�ʓr�X�������K�v�ł��B�܂��A�r���ŕs�p�ɂȂ����������ʓ|�ł������A�����������B