2002年6月1日号 毎月1回1日発行
第17号 発行者 やまめの里 企画編集 秋本 治 五ケ瀬町鞍岡4615 電話0982-83-2326
祝・新しい町の誕生
県内で最も若い飯干辰巳町長の誕生おめでとうございます。22年ぶりといわれる町長選挙は、とても激しい選挙戦となり加熱のあまり誹謗中傷に辛い思いをされた有権者も多かったようですが、ともあれ良い結果となりました。
甲斐賢ニ候補も凄い善戦をされました。甲斐候補の善戦を裏付ける実に象徴的なできごとが飯干辰巳候補の出陣式でありました。飯干候補が挨拶の中で「企業よりの政策はとりません」と述べられた時、集まった多くの群集から突然拍手が湧きあがったのです。選挙の深層を物語っているように思えました。
「田舎では、選挙より一本化のほうがよい」という意見もあります。その方が政策施行上スムーズにいくとする議論です。しかし、これまで無投票で22年間も町政が続いたわけですが、今回のように住民すべての人たちが町政を真剣に考え議論したことがあったでしょうか。また、候補がこれほどまでに政策を語り真剣に住民の中に入ってこられたことがあったでしょうか。身震いするほど感動しました。間違いなく町政は大きく変革することでしょう。
波風なくして政権移譲が行われることは、政策遂行上はスムーズに行きますが、緊張感がなくなり政治の活力は確実に減退しました。当然、選挙の弊害も考えられますが乗り越えなければならない問題でしょう。首長を民主的に選ぶにはやはり選挙しかありませんですものね。問題はフェア―な選挙ができるかどうかにかかっています。強制的、強圧的に行われる選挙は排除しなければなりません。
今回の選挙に筆者は留守がちで申し訳ありませんでした。というのも告示の翌日22日は宮崎県物産振興センターの理事会、夜は宮崎ツーリズムネットワークの報告会、23日帰宅、翌24日は宮崎県マイスター推進会議で再び宮崎へ、翌25日はNHK文化センターのオリエンテーション等以前から組みこまれたスケジュールをこなすのに精一杯で24日延岡で行われた「九州横断自動車道延岡線建設促進沿線議会期成会総会」にも出席できませんでした。
県物産振興センターの事業を通じて、県マイスターの事業を通じて、あるいはグリーン・ツーリズムを通じて本町を含む中山間地の活性化に寄与することも現在与えられた筆者の役割であり義務だと自覚しているからです。
新しい首長の誕生を契機に町が変り、行政と住民の新たなよい関係(PPP‐パブリック・プライベート・パートナーシップ)が構築されることを願っています。
ともあれ、筆者も住民の皆さんから町政の監視役として付託を受けている身です。町政の是は是、非は非として毅然と対応し、そして積極的に政策提言を行って付託に応えていくつもりです。
過疎、高齢化、不況による活力の減退、交付税の減少等、町政の舵取りはこれからますます難しくなるでしょう。清和村の兼瀬村長が言っていました。「首長になって感じることは毎日が49対51の仕事ということ」だと。住民のニーズが多様化するほど首長はその決断に僅差の綱引きで判断を強いられることになる。一部の住民の49対51であってはならない。いかに「明日を読む」か、否「明日が読める」かでしょう。そして、若い町長をいかに支えていくかも重要です。
それにしても、町の防災無線による選挙速報には唖然としました。有権者は固唾をのんで一刻も早い開票速報を待ち望んでいるのですが、テレビの画面に開票結果がテロップで流れてその30分後くらい経ってからようやく放送される始末です。情報が一番至近距離にありながらこれではお粗末としかいいようがありませんでした。
こうしたことも、これからは変ってくれることでしょう。監視も怠れません。
5月2日 五ケ瀬中等教育学校講義
この講義は中等教育学校の「森林文化1」の授業で「五ケ瀬の植生と人々の生活との関連を考察することによって、前期課程での「地域基礎」を総括し、五ケ瀬学からフォレストピア学への導入を行う」に基づいて行われるものです。
標高の低い宮崎平野の自然の森はなぜ冬も青葉が茂り、五ケ瀬の自然の森はなぜ秋に落葉する?、種の保存のための植物の戦略は?、サクラの戦略とブナの戦略の違いは?。霧立越の歴史と自然・狩猟儀礼作法・ヨキの語源、果てはヤマメの野生の退化と都市文明等々。午後1時半から4時までですが、生徒がとても熱心なためについつい時間超過してしまいます。
5月7日 中山間地域総合整備事業鞍岡地区推進会議
兼ねてから計画されていた鞍岡地区の中山間地域総合整備事業が3月28日付で採択されました。総事業費14億3千万の事業が平成14年から平成19年度まで5ヵ年間で実施されます。
この日は、鞍岡中央公民館に鞍岡地区の公民館長、議会議員が召集されて町担当課より事業内容の説明があり事業推進のための鞍岡地区整備促進協議会が設立されることになりました。
事業内容は、
農業生産基盤 7億8千6百万
生活環境基盤 6億2千9百万
交流基盤 1千5百万
で鞍岡地区にとって最後のインフラ整備事業となるかもしれません。事業がスムースに実施できるように住民あげての推進体制がのぞまれています。
5月16日 九州4県スキー選手権大会来年1月5日五ケ瀬で開催決定
鹿児島、熊本、大分、宮崎の4県スキー連盟による九州4県スキー大会は、国体選手選考を兼ねた大会として本年で9回を数え、五ケ瀬ハイランドスキー場における最も大きなスキー大会となっています。
本年は1月6日に開催しましたが、一般スキーヤーやスノーボードのお客様への影響があるということから、通称「地獄谷」と称している第3リフトの下部400m程度のコース使用しか許されなかったので20秒台でタイムを争うという競技になりました。国体コースは、1500~2000mのコースであり、余りにも短いコースでは選手の実力を発揮することができません。
このため、参加選手からの苦情が続出し、大分県スキー連盟から次回は大分の九重森林公園スキー場で開催したい旨の申し入れがありました。九重森林公園スキー場では700mのコースを提供するということです。温泉もあります。
そこで、宮崎県スキー連盟理事長と競技部長と筆者で㈱五ケ瀬ハイランドとの協議を行いました。結果、遅くとも午前9時00分までに競技を終了することという条件のもとに1000mの全コース利用が可能となり再び五ケ瀬開催が実現することになりました。
五ケ瀬のスキー場は、佐賀の天山スキー場、大分の九重森林公園スキー場との立地の違いが、アルペン競技に最も適しているスキー場であるという特長を持っています。1000mの全コースが利用できれば文句なしに五ケ瀬開催が決定されます。選手のエントリーも100人を超える質の高い大会ですので、再び五ケ瀬開催決定に胸をなでおろしているところです。㈱五ケ瀬ハイランド様のご協力に感謝します。
5月22日 宮崎物産振興センター理事会
宮崎県物産振興センターは、新宿にアンテナショップを出店する際に、従来の財団法人宮崎県物産振興協会を改めて財団法人宮崎県物産振興センターとして新たにスタートした商業振興課主管の組織で、県庁東別館に事務所と店舗があります。
センターの事業は、
1.取引促進事業として各種商談会の開催、売り込み・紹介事業
2.商品開発支援事業としてマーケティングリサーチ、一般的開発支援事業、個別的開発支援事業
3.各種物産展開催事業
4.研修・相談事業
5.データ整備・管理事業
6.広報・宣伝事業
7.みやざき物産館、新宿みやざき館、大阪支部、福岡支部等による県産品の委託販売事業等
を行っています。
筆者が特に力を入れていた分野は、「ものづくりネットワーク会議」で県産品の開発や品質向上のため商工農水とそれぞればらばらに縦割り行政で試験場と専門家が配置されているものを物産センターで束ねて総力を発揮しようという企画です。立ち上げ時は座長として進めましたが、不況で会社も多忙を極めるようになった為、設立1年後座長を辞退した経緯があります。
このため「ものづくりネットワーク会議」は気になる存在です。今回も、県央から県南県北各地に出向いて積極的に生産者を支援するよう強く進言しました。また、生産者の顔の見える売り方などいろいろと意見を述べましたが、宮崎は素材大国の商品貧国です。県外の商品に押さえられてなかなか物産が育ちません。おおいに物産センターを活用して頂き地場産業振興で地域に活力を呼びこみたいたいものです。
物産センターの役員構成は次のとおりです。(敬称略資料順)
会 長 松形祐尭 宮崎県知事
副会長 黒木健二 物産振興センタ―
〃 中島勝美 県酒造組合連合
会会長
常 務 河野喜和 商業振興課長
理 事 秋本治 ㈱やまめの里
〃 南崎洋史 南崎茶業㈱
〃 堀之内登 宮崎県伝統工芸
品産業協会会長
〃 坂本益造 ㈲味のくらや
〃 川野幸三 グローバルビレ
ッジ綾代表
〃 佐藤高義 県経済農業協連
合会代表理事
〃 岩切達郎 県商工会議所連
合会会頭
〃 佐藤勇夫 ㈱宮崎銀行頭取
〃 金丸常昭 ㈱宮崎山形屋社
長
〃 岩橋辰也 (財)都城圏域
地場産業振興セ
ンター理事長
〃 工藤 訓 日之影町村興し
総合産業㈱社長
監事 菊地銑一郎 ㈱宮崎太陽銀行
頭取
〃 佐藤道明 佐藤工房代表
〃 尾崎昌樹 ㈲尾崎商店代表
5月24日 地域興しマイスター派遣事業推進会議
地域興しマイスター会議は、宮崎県農業会議・県農政企画課主管の組織です。県農業会議から委嘱を受けたそれぞれの専門分野を持つ16名のマイスターが、特定農山村地域において地域興しに意欲的な団体に対して専門的に指導助言を行うものです。
特定農山村総合支援事業は、毎年5~6地域を指定して支援が行われ平成13年度は、76.500千円の事業が実施されました。五ケ瀬町にも13.191千円が配分され、ぶどう防鳥ネット・サクランボ定植に利用されました。平成14年度は、南那珂郡北諸西諸地域を対象に事業が実施されます。
また、マイスター研修会が年に数回開催されて全国の地域づくりを学んでいます。
平成14年度のマイスターは次のとおりです。(敬称略資料順)
・河内通信 営農活動(南九州大学非常勤講師)
・濱川典昭 地域ネットワークづくり (元宮崎大学非常勤講師)
・永田雅輝 農業情報・農業施設(宮崎大学農学部教授)
・杉田浩一 食品開発(JA食品開発研究所所長)
・有村玄洋 土づくり(綾町有機農業開発センター)
・川野靖一郎 販売マーケツティング(宮崎中央青果㈱相談役)
・永崎収一 観光興し(宮崎県観光協会常務理事)
・土井裕子 景観づくり(A・D建築設計室主宰建築士)
・秋本 治 エコ・ツーリズム(㈱やまめの里)
・森松平 郷土料理(㈱杉の子社長)
・室の園一三 グリーン・ツーリズム(元フェニックスリゾート)
・川口道子 広告宣伝(㈲鉱脈社専務)
・黒岩マサ子 特産品づくり(北郷町特産品加工組合)
・井上博水 漢方・薬膳・薬草(恒心館クリニック院長)
・福原忠俊 薬用植物(森薬品㈱DI部長)
・井原満明 コミュニティづくり(地域計画研究所社長 東京)
夜の懇親会は、会費6千円負担で杉の子で開催されました。実践活動家の懇親会はとても盛りあがります。
この席で、筆者は立体農業として素晴らしい可能性のある地域について提案しました。それは、小川岳の北斜面です。町有林から国有林にかけて標高1100~1200mの尾根に数ヘクタールに及ぶ台地が広がっています。谷川の水も充分あります。道路もすぐ下まで出来ています。霧が立ち込める超冷涼な季候の台地で花卉等の生産を始めたら面白いと思うのです。西米良の天包山で佐土原新富付近の農家の方が蘭の立体農業を展開していましたが、狭いし水も不充分でした。
九州には小川岳のような条件を備えた地形は珍しいのではないかと思います。農業でなくとも例えばその付近は山椒が自生していますので山椒の苗木を植栽して山椒の葉の佃煮製造などもコミュニティビジネスとしてこれから将来性があります。
そこで、前記のマイスターの先生方に現地を見ていただき、薬草や山菜、花卉類、超高冷地野菜等の立体園芸などそれぞれの専門的立場から活用の仕方を提案頂いて、地元で生産組合なりを設立して取り組んだら素晴らしいと・・・。五ケ瀬にマイスターツァーを計画しましょうと呼びかけたところ皆さん強い興味を示されました。
新町長さんのご支援を頂いて、ここは1つ農業会議とマイスターの活用をして見ようではありませんか。きっと新しい何かが展開できる可能性を感じます。
5月27日 五ケ瀬町議会全員協議会開催
午後1時30分から議員控室において、全員協議会が開催されました。
協議案件は、㈱五ケ瀬ハイランドに対する委託金の件及びワイナリー建設の件について助役及び担当課長から説明がありました。
〇㈱五ケ瀬ハイランドについて
㈱五ケ瀬ハイランドに対する委託金については、平成13年度は計上してありません。平成14年度の予算にも計上してありません。スキー場がらみで計上してあるものは、森林公園事業としてスキー場の施設整備費や修繕費及び国有林の借地料などのみです。
運営委託料が計上されていない理由は、リフト収入を従来町の収入としていたものを㈱五ケ瀬ハイランドの収入として変更した時、委託料を出さないこととして議会も了承したという経緯があるようです。
ところが㈱五ケ瀬ハイランドとしては、運営に支障をきたすとして委託料2千万円を未収金として本年度の決算に計上したい旨の申し入れがあり、5月決算のため早急に決定するよう要求があったということです。
また、委託料2千万円を町が出さなければスキー場から撤退するといわれているということです。㈱五ケ瀬ハイランドは町長が会長であり、議長が監査役でもありますが、現議長はまだ1度も監査に立ち会ったことはないということです。
ちなみに、㈱五ケ瀬ハイランドの収支状況で経常利益は、昨年がスキー場17.191千円、木地屋△5.427千円、特産センター2.526千円。総合では単年度経常利益14.290千円。
本年の予測として㈱五ケ瀬ハイランドから出された資料によると経常利益は、スキー場117.330千円、木地屋△6.200千円、特産センター1.070千円。総合では単年度経常利益112.200千円、前年対比785.2%の伸びとなっています。
これに対していろいろな考え方が出されました。
①赤字であれば支援しなければならないが黒字が大きく計上されるのに委託金を出すことは町民の理解が得られるか。
②赤字会社をここまで高収益体質の会社に育ててもらったのだから委託金は出すべきである。
③町の収入としていたリフト料を㈱五ケ瀬ハイランドの収入に変更する時、委託金は出さなくて良いという説明でリフト料を渡したことに対してその責任はどうなるのか。
④スキー場の存続を第1義に考えれば今回委託料を出してその後のあり方をきちんと契約すべきではないか。
⑤これからスキー場の施設老朽化に伴い大幅な再投資が予想される。町は減価償却して積み立て金を用意していないので、これから町単で支出しなければならない。今後どうなるのか。
等々の考え方がそれぞれ示され、結論には至りませんでした。
もちろん全員協議会で意思の統一ができても本会議で議決できなければ決定したことになりません。町や地元住民でスキー場の運営が引き受けられるような体制ができれば一番いいのですが、町が引き受けるということはスキー場が存続できないことを意味するという意見が圧倒的です。
公が造った施設は、公の力を借りずに運営できることを目指すべきですが、運営企業の利益追求のみの手段となっても弊害がでてきます。公の施設運営では、地域の活性化にどう貢献するかの視点こそが大切です。スキー場経営において「地産地消」(その土地で採れた物をその土地で消費する)を実現して地域活性化を行うには、町や地域主導で取り組むのが一番いいのですが難しい問題です。
けれども、ノウハウはすでに従業員の中にある程度は出来ています。後はマネジメントのできる人を探すだけですのでそういうことも視野に入れて検討すべきではないでしょうか。できないはずはありません。そのような努力をすることが五ケ瀬の真の自立の姿ではないかと思います。新町長が誕生したばかりです。新町長の判断のもとでよい議案が議会に提案されるものと思います。
〇ワイナリ―の件
夕日の里ふれあい交流空間整備事業の進捗状況について説明がありました。その中で経営構造対策事業は、連絡道路とワイナリーの施設。レストラン等は、第三セクターを設立後実施するという計画です。
この中で4月24日農政局から「かなり厳しい指摘」があったと報告されました。連絡道幅員は車道3.5m、ワイナリーは、開発許可不要とされる1ha未満で事業を実施するというもので事業規模の縮小です。
現在は、農政局の指摘どおりで事業認定を受け、経営構造対策事業はこの連絡道とワイナリー整備に限定して事業実施を目指しているということでありました。
ともあれ、この事業はかわら版議会特集号で掲載した通り、これを通さなければ鞍岡地区の中山間地総合整備事業も駄目になると脅されて3月当初予算でレールが敷かれました。これからは前向きで検討しなければなりませんが、これからの問題は第三セクターのあり方です。
ワイナリーを作れば大きな観光客が流れ込んでくるという幻想から脱却しなければなりません。ワイナリーは副次的なものとしてもっと根本的なビジョンと地域を巻き込んだ新たな切り口での知恵が求められます。そうしなければ際限なく予算を継ぎ込む体質から脱却できなくなるでしょう。
現在この計画を推進しているコンサルタントは「都市と山村の交流による五ケ瀬町の活性化」として夕日の里をテーマに交流人口流入のもと地域内市場形成・余暇空間の創出・地域イメージの浸透・地域の独自性・地域の魅力等をうたっていますが、これはどこの町村地域にでも共通する事項で、それができないからどこの町村でも悩みが大きいわけです。
ワイナリーがなくても、その地域に感動を求めて都市住民が入り込んでくるような地域の魅力や仕掛けを創出しなければなりません。夕日の里を標榜するだけでは、残念ながら今のところ都市から人々が押し寄せる力はありません。行政が予算を組んでイベントを仕掛けた時だけです。
もともと、桑野内地区に夕日をテーマに地域計画を最初に書いたのは、実は筆者です。それまでは大阿蘇展望の里とされていました。確かに阿蘇の展望も良いですが、阿蘇展望の魅力だけで勝負するなら九住高原から見る阿蘇五岳の絶景にはかないません。
平成4年3月に策定された「五ケ瀬町観光振興計画」は、策定委員長に任命されたので各地域毎に持ち回り座談会を開催しました。その時桑野内地区に対して浮かんだのが「夕日の美しいむらづくり」でした。
この地域には阿蘇の遠望を背景に起伏の美しい地形の中に農村の原風景を見る事ができる。日本の原風景ともいえる農村風景は日本の心の故郷となる。そのイメージを増幅させるキーワードを「夕日の美しいむら」としたのです。農村の原風景を思わせる童謡の世界としてもイメージは広がります。童話や童謡を掲げて村おこしに取り組む地域さえあります。
そして、埋蔵する旧蹟群、芝原又三郎に関する伝説、桑野内神楽、古戸野神楽、戸田流棒術、団七踊り、升形山・かばき岳の展望。こうした自然と歴史と生活文化が織り成す風景を風光へと高めるために「クオリティ(品位風格)・アメニティ(快適空間)・ホスピタリティ(もてなしの心)」を掲げ、九州で一番美しいむらづくりを目指すとしたのです。
こうした魅力により都市と山村の交流が芽生え、そこに新たな産業を生み出していく。
具体的には、例えば、八十八箇所巡りにちなむおだいっさんの接待がある。現在は消滅した小屋も多いと聞きますが、町内で最も接待小屋(とよんでいいものかわかりませんが)の多い地域と聞いています。これを修復又は復元してお祭りの接待日をイベントにつなげる。サイクリングロードとして変化する阿蘇の遠望を楽しみながら自転車で八十八箇所めぐりができれば、まさに都市から訪れた人々への最高のホスピタリティ(もてなしの心)となるでしょう。お接待の日にこうしたツァーを組むのも面白い。
また、農村風景を美しく見せているものにお茶の畠があります。阿蘇遠望の背景の中うねうねとした地形に沿って整然としたお茶の列が並ぶ。ここで都市住民が我家の一年分のお茶を摘茶体験して持ち帰る。或いは茶園を区切って貸し農園として作業の指導をしてもいい。単なる体験農園ではなくて我家の美味しい無農薬のお茶を獲得できるのです。それだけのお金はきちんと頂く。
こうした美しいお茶畠風景のポイントにはなるべくビニールハウスを造らないほうが地域の風景は活きてくる。桑野内地区から長年積み上げてきたお茶をなくしたら何も残らないような気がします。
これらは思いつきのほんの一部ですから、もっと新たな知恵と切り口を見つけ地域の皆さんと詰めていかなければならないでしょう。そのためには、それぞれの立場から専門家をお呼びして地域ぐるみでシンポジウムを行うとかして、外部からの知恵の導入をはからなければなりません。
今年4月24日虎ノ門パストラルで行われた地域開発研究懇談会で早稲田大学理工学部教授後藤春彦先生の講演録があります。景観づくりについて「景観とは何か」「場所の力とは」など大変参考になることが述べられていますので後のページに掲載します。
先生は、地域づくりにおいて時としてその地域特有の力を感じることがあるといわれ「地霊」という言葉さえ使われます。筆者も何度か五ケ瀬にお呼びして霧立越シンポジウムを開いています。本町の観光振興計画策定の折りにも策定委員として関わって頂いたのですが、本ができたらそれでおしまいとなりました。
5月28日 長野県分杭峠視察
長野県の伊那地方、南アルプスの断層地帯であらたな地域づくりが胎動しています。長谷村は「気の里」づくりとして生涯学習センターを建設しました。「気の里」の「気」とは気功の「気」です。このことについては、前号で静岡県・グリーンツーリズム研究所主任研究員 溝口久さんからのリポートを紹介しました。
それを確かめる為にリポートにある「中央構造線の謎を探る会」会長の後藤琢磨さんと長谷村の「気の里」づくり担当の教育次長 池上直彦さんに会ってきました。
夕食をともにしながらお話を伺いましたが、お二人はもう学者です。考えてもみなかった世界があります。五ケ瀬町は中央構造線と仏像構造線に挟まれた特種な地帯ですのでこれを霧立越シンポジウムにつなげたいと思っています。詳細は、後のページ「シンポジウム企画」の欄でご紹介します。
5月29日 国土交通省地域振興アドバイザー受入市町村との打ち合せ会
この組織は、以前国土庁が地方振興アドバイザーとして各地に派遣していたものを国土交通省が継承したもので、依頼された市町村に国の費用で出かけ地域づくりのお手伝いをする制度です。通常アドバイザー3人を一チームとして派遣されます。
この日は、依頼された市町村とアドバイザーの打ち合せが経済産業省の別館で行われました。今年筆者は、前記マイスターでもある東京の井原満明さん、熊本大学の徳野貞雄先生と3人チームで佐賀県鳥栖市のまちづくりを手伝います。
だいたい年に3回ほど現地を訪れます。新たな切り口で助言指導を行うわけで、そのリポートを書くのは億劫ではありますが、嬉しいのは全国の地域づくりの達人たちと情報交換できて学べることです。今回も先輩友人知己のアドバイザーが並んでいます。
本年のアドバイザー派遣計画は次のとおりです。(敬称略、資料順)
・福島県柳津町 前田博(岐阜県立森林アカデミー教授)、麦屋弥生(日本交通公社地域調査室長)
・埼玉県行田市 飯田正明(日本開発構想研究所参与)、今枝忠彦(都市計画設計研究所室長)、熊倉浩靖(NPOぐんま代表理事)
・山梨県忍野村 安藤周治(中国・地域づくり交流会副会長)、井出建(環境計画機構会長)、黍島久好(愛知県豊根村経済課長)
・三重県伊勢市 富田宏(漁村計画研究所所長)、林泰義(計画技術研究所社長)、松田猛司(クラブノアグループ代表)
・滋賀県彦根市 伊藤雅春(大久手計画工房)
・岡山県大原町 菅原由美子(菅原由美子観光計画研究所主宰)、松井郁夫(松井郁夫建築設計事務所代表)、光多長温(鳥取大学教育地域科学部教授)
・山口県豊浦町 内田文雄(山口大学工学部教授)
・徳島県山城町 大川信行(東日本国際大学経済学部教授)、野口秀行(日本インテリジェントトラスト常務)、若井康彦(地域計画研究所代表取締役)
・高知県ごめん・なはり線活性化協議会 鈴木輝隆(江戸川大学社会学部助教授)、羽田耕治(横浜商科大学商学部教授)、望月真一(アトリエUDI都市設計研究所代表取締役)
・佐賀県鳥栖市 秋本 治(やまめの里)、井原満明(地域計画研究所代表)、徳野貞雄(熊本大学文学部教授)
・長崎県江迎町 寺川重俊(寺川ムラまち研究所代表取締役)、橋立達夫(作新学院大学地域発展学部教授)、本田節(人吉ひまわり亭代表取締役)
・大分県直川村 市村次夫(長野県小布施堂代表取締役)、浦野秀一(あしコミュニティ研究所代表取締役)、松場登美(石見銀山生活文化研究所)
・鹿児島県牧園町 後藤春彦(早稲田大学理工学部教授)
・鹿児島県世論町 小河原孝夫(生態計画研究所代表取締役)
以上で今年は取組みます。まあ、会社も大変、五ケ瀬の地域づくりも大変の立場にあってと思われるでしょうが、ま、指名されればしょうがありません。精一杯努力するのみです。お許しください。
だけどこんな組織をわが町でも活用しませんか。筆者を除けば、皆その道の一流どころの凄いメンバーですよ。夕日の里づくりで外部の知恵を導入するには一番ではないでしょうか。国のお金でコンサルが使えます。前述のマイスター制度と共に有効に使ってほしいものです。内輪だけで議論していても道は開けません。
5月30日 国保運営協議会
五ケ瀬町国民健康保健税条例を一部改正したいと説明がありました。税率100分の1.30を100分の1.40に改めるなど税率アップの提案で6月5日の臨時議会で専決処分として報告承認を求められる予定です。
シンポジウムの企画
今年の霧立越シンポジウムは、ちょっと趣向をこらして異次元の世界?へ切り込みたいと思います。まだ、企画書全体は完全に固まっていませんが、取り敢えず現在押さえている部分を掲載します。
------------------------------
第八回・霧立越シンポジウム(案)
ミステリースポット
―幻の滝と構造線の謎を探る―
日本列島には、中央構造線という大地を真っ二つにした大断層がある。その断層は紀伊半島から四国山中を通り、九州では大分の臼杵から熊本の八代にかけて存在する。その南側には仏像構造線が並ぶ。こうした構造線上の地域には、地域特有の現象が存在する。私たちは、これまで霧立山地をテーマに民俗歴史や自然をテーマにシンポジウムを展開してきたが、構造線上には地域特有の植生があることを学んだ。例えば「襲早紀要素」を持った植物群である。その代表的なものが霧立山地のキレンゲショウマだ。キレンゲショウマは、学名と和名を同じ呼称にした特異な植物で九州山地から四国山地、紀伊半島にかけて構造線に沿ってのみ植生する。世界でこの地域にしか生育しない種である。
この構造線上にはこのような植生の特異性のほか未知のミステリースポットがある。長野県の分杭峠には磁場ゼロ地帯が存在し、そこから大地の「気」を発してヒトの免疫力を高めるマイナスイオンが多いことが解ったという。構造線は謎のエネルギーを秘めた地帯である。「磁場ゼロ」とか「気」とか「マイナスイオン」という言葉は、目で見ることができないので何となく胡散臭いが気になる存在ではある。今回のシンポジウムは、こうした構造線や地質を学びミステリースポットの謎を探りたい。
日程
7月20日(土)(第1日目)
滝開きとフィールドワーク
「滝ヒーリング体験班」と「断層と構造線探険班」に分けて受付
〇「滝ヒーリング体験班」
08:30~09:00 受付(ホテルフォレストピア)
09:00 ホテル発(マイクロバス)
09:50 木浦林道滝入り口着
09:50~10:00 オリエンテーション
10:00 木浦林道滝入り口発(徒歩)
10:50 滝到着
11:00~11:40 神事及テープカット
11:45~12:15 昼食
12:20~14:20 滝ヒーリング(healing)体験
14:30 滝発(徒歩)
15:30 林道滝入り口(マイクロバス)
16:30 ホテル着
〇「断層と構造線探険班」
08:30~09:00 受付(ホテルフォレストピア)
09:00 ホテル発(マイクロバス)
09:50 木浦林道滝入り口着
09:50~10:00 オリエンテーション
10:00 木浦林道滝入り口発(徒歩)
10:50 滝到着
11:00~11:40 神事及びテープカット
11:45~12:15 昼食
12:20~15:30 滝より遡行して上流のもう1つの滝を探険。林道に上がって白岩山衝上断層を学びます。
15:30 林道滝入り口(マイクロバス)
16:30 ホテル着
7月21日(日)(第2日目)
ミステリースポット
―幻の滝と構造線の謎を探る―
開会行事(09:00~09:20)講師紹介、来賓紹介
セッション1(09:30~10:30)
構造線の謎を探る ―脊梁山地の構造線と地質―
講師 (未定)
◆秩父帯の中・古生界
◆仏像構造線と臼杵八代構造線
◆黒瀬川帯と三宝山帯
◆白岩山衝上断層等
セッション2(10:35~11:05)
〇滝学 ―幻の滝の謎―
講師 小林伸行氏
◆滝の定義と分類
◆九州の滝・宮崎の滝
◆滝から読み取れるもの
セッション3(11:10~12:10)
〇構造線の謎
講師 後藤琢磨氏(中央構造線の謎を探る会代表・長野県)
・構造線の七不思議
・分杭峠の謎
・磁場ゼロ地帯と大地の気
セッション4(13:00~15:30)
パネルディスカッション
・構造線の謎とミステリースポットを探る
パネリスト
上記講師+1~2名
コーディネーター 秋本 治
閉会 16:50
---------------------------
シンポジウム関連リポート
「幻の滝と中央構造線の謎を探る」
2002.05
秋本 治
溝口リポート
静岡の溝口久氏からリポートがmailで届いた。巨漢で優しい目が魅力の溝口氏は、かつて湯布院の観光協会事務局長公募に応募して静岡県庁から出向した経歴を持つ活動家である。現在は、静岡県・グリーンツーリズム研究所主任研究員として活躍、時々筆者にもリポートが届いている。
2002年4月24日のリポートは、静岡の天竜川流域で行われたイベント参加の模様が記されていた。そのリポートに目を通していると、《…「ホウジ峠の中央構造線」は県指定の天然記念物であり、花崗岩主体の領家帯と結晶片岩類の三波川帯の接触面を見ることができる。ここで「地のエステ体験」をしようと言う。何のこっちゃと思いつつ資料に目をやる。中国から気功の専門家を招き中央構造線上を歩いてもらったところ長野県長谷村と大鹿村の境にある分杭(ぶんぐい)峠で「気の場」を見つけたと言う。「大地の気」は断層上の特異点にあり、このような場所はゼロ地場であることが多く、マイナスイオンが流れ込み疲れやストレスを取り除き免疫力を高めるとの説明がある。うーん???。…》
ここまで読んだ時、「?まさか」と思ったが次に「もしかして」と、はっと閃くものがはしった。それは、昨年発見した「幻の滝」である。
発見以来テレビ局の取材などで滝つぼに案内した。落下してくるしぶきが引き起こす爽やかな風とさらさらざーざーと周りの岩壁に響く滝の音がとてもここちよい。するとリポーターやクルーの表情が優しく変るのである。「気持ちがいい」「ストレス解消になる」などの言葉が聞えてくる。全身が笑っているように見える。先日も霧雨模様の日ご案内したグループから「嬉しくて涙が出ました」という声を聞いた。
「何となく不思議だ。他と雰囲気が違う。この滝には何かあるのではないか」。そんな突拍子もない思いが浮かんでいた時に溝口氏のリポートである。「もしかして、あの滝付近は断層ではないか。『気』があるんではないか」などと空想がふくらんだ。その滝つぼ横の岩盤の中から湧き出る岩清水はとてもまろやかで美味しい。「滝ヒーリングなんてのはどうだろう」そんな発想が湧き出たのである。
さらにリポートは続く。《この断層上には諏訪大社、山住神社、鳳来寺、伊勢神宮、高野山、四国に渡り石鎚山、最後九州阿蘇の元伊勢とも言われる幣立神宮に繋がっていく。山岳信仰、霊場が連なっているのである。これらの聖地と中央構造線の位置関係は単なる偶然でしょうか?と「中央構造線の謎を探る会」代表の後藤琢磨氏はその話を締めた。その断層上で目を閉じ腕を広げゆっくりと腹式呼吸をすると「大地の気」を感じる、これが「地のエステ」という訳である。》と。
中央構造線の謎を探る
そこで、溝口氏に「中央構造線の謎を探る会」代表の後藤琢磨氏を是非紹介してください。とmailを打った。折り返し後藤琢磨氏からmailが入った。《小生、地質の専門家では、ありません。また、氣の専門家では、ありません。地質(中央構造線の成り立ち、鉱物資源も含む)と、「氣」などを切り口として、
中央構造線を調査・研究しております。ずいぶん前から、金属資源を切り口に中央構造線のなぞに迫りたいと思っておりましたが、5、6年前から、そこに「氣」の話(中央構造線上に素晴らしい「気の場」がある・・・)が加わり、かつては、夢のようだった調査旅行が、いっきょに現実のものになりました。》とある。後藤琢磨氏はこれらの調査のために地元新聞社を辞めて取り組んでいるという。現在は、有限会社ヒューマネットの取締役社長であり、長野県飯伊地域メディア振興協会事務局長など地域づくりにも精力的に活動されているようだ。そして後藤琢磨氏のホームページには以下のように謎が提示されている。
◇「気の場」の謎。
数年前から、この巨大断層上にある、「気の場」(一種のパワースポット)が話題になっています。長谷村(はせむら=長野県上伊那郡)と大鹿村(おおしかむら=同下伊那郡)の境にある分杭峠(ぶんぐいとうげ=標高1400m)がそうだというのです。そこからは、気功師が出すよりもはるかにレベルの高い、天然のよい気が、発生しているといわれます。癒しのエネルギーと呼ぶ人もいます。気の場とは、いったいなんでしょう? なぜ、断層上から「気」が発生するのでしょう?
◇南朝方ルートの謎。
日本列島が北朝と南朝に分裂。ふたりの天皇を立て、抗争した南北朝時代(1336~1392年)は、中学校の歴史の時間にも勉強します。建武(けんむ)の新政を行った、後醍醐(ごだいご)天皇は、中央構造線上にある奈良の吉野を拠点として、その沿線上に皇子(みこ)たちを配置し、北朝方に対抗しました。後醍醐天皇は、なぜ、中央構造線を選んだのでしょう? そこには、どんな勢力がいたのでしょう?
◇渡り鳥の、南下の謎。
猛禽類(もうきんるい)の、サシバという鳥をごぞんじでしょうか?サシバは、秋になると、東北地方から長野県の伊那谷上空に集結してきます。そして、中央構造線に沿って、四国、九州、沖縄と南下し、さらに東南アジアの諸島に渡り、そこで越冬するのです。渥美半島(愛知県)の伊良湖(いらこ)岬は、サシバが集結する半島として、有名です。いったいサシバは、中央構造線の何に反応して渡るのでしょうか?
◇聖地(霊場)の謎。
中央構造線という巨大断層の真上に、あるいは近辺に、昔から聖地と呼ばれてきた山や神社、お寺が集中してあります。まず、諏訪大社(長野県)、その上社前宮の霊山・守屋山(もりやさん)。狼(おおかみ)信仰のメッカとなった山住神社(やまずみじんじゃ=静岡県磐田郡水窪町)、修験道の霊場・鳳来寺山(ほうらいじさん=愛知県南設楽郡鳳来町)。三河湾を渡れば、わが国最大の聖地とされる伊勢神宮。さらに奈良・吉野を越えて、紀州・高野山(こうやさん)と、根来(ねごろ)寺。四国に渡れば、霊場・石鎚山(いしづちさん)、そして九州は阿蘇の元伊勢ともいわれる幣立神宮(へいたてじんぐう)。これらの聖地と中央構造線の位置関係は、たんなる偶然でしょうか?
とある。
「うむ、そういえば、秋になるとホテルの裏山の通称『サキヤンタニ』の上空に弧を描いてサシバが集まり、揃って南下しているなあ」と頷く。ここは多分、中央構造線の延長線にあたる「臼杵-八代構造帯」の上になるのではないか。
「聖地(霊場)の謎」では次のことを思い出した。当地の東方、北郷村に宇納間地蔵尊が鎮座している。ここの地蔵尊の例祭には県内外から多くの参詣者があり各地に代参の講が数多く受け継がれていて歴史のある有名な地蔵尊である。けれどもなぜ北郷の地蔵尊だけがこれほど有名なのか。力があるのか。そういうことを議論したことがある。その時考えたのは、宇納間地蔵尊近くの川原の中には、帯状になった岩盤が斜めに川底から異様に突き出している。あれは断層だ。断層地帯には何か不思議なエネルギーがあるのではないかと考えたことを思い出した。これは、早稲田大学の後藤春彦教授の地霊論から発想した。先生は地域づくりの話で「地霊」と言う言葉を使われる。地域には時として地域特有のエネルギーが存在するという話である。
山伏伝説
更に、想いは連想ゲームのように広がる。幻の滝は「近くの村人たちや猟師さえ行ったことが無い」という。険しさもあるが恐れて近づくことをきらったのではないか。これは滝伝説からの想像である。
滝の下流の村人から聞いた伝説とは、「その昔、ある男がこの谷に迷い込んだ。すると滝の近くに間口が5間もある大きな家があった。その家に上がり込んだら床の間に高御膳でご馳走が準備してあった。男は恐ろしくなって逃げ帰ってきたげな」という。その時、その御膳を食べてこなかったので男には福が授からなかったと伝えられているそうである。
また、「ある時、谷に迷い込んだら、一面にソバやキビが実っていた。そのキビを一房摘んで帰り、明くる日再び奥さんと連れだって行ったらソバもキビもなく一面にスズタケが広がっていた。そして、そのスズタケは首がみんな折れていたげな」という。また「遠くから見ると白い衣のような布がかかっており、近づくと消えてしまう」とか「谷に入り込むと鶏の鳴き声が聞えたげな」或いは「滝つぼには鴛(おしどり)がいて近くから矢を射かけても当たらない」などという話もある。
人跡未踏の深山幽谷の地にこのような伝説があるとは、村人が近寄りがたい何かがあったのではないか。それは、修験者「山伏」が修業していたのかも知れない。そして、その修験者は、修行により滝の「気」を感じていたのかも知れない。実は、滝の近くに丸く石積みした塚のようなものがあるのだ。どうも自然のものではないような感じがしてならない。素人が発掘してはならないと誰にも言わないことにしている。
更に、想いは飛躍する。「ガゴが岩屋」である。昭和40年代に、白岩山の西側山中に「ガゴが岩屋」を訪ねたことがある。地元の猟師さんたちと日肥峠から耳川源流にでてたどりついた。その岩屋は6畳か8畳位の広さがあり、床や天井も平らな岩石で壁は出口の方が狭くなっており、大きな炭窯の中にいるような気がした。
子供のころ悪さをすれば、「カゴがくるぞ」と脅されていたものだ。そのガゴとは一体何者なのか誰も知らない。椎葉の方々にもガゴの話しを聞いたところ、高齢の皆さんは一様にガゴの話を知っている。「悪さをすればガゴが出てくるという」。その「ガゴが岩屋」付近には昔、炭や鍋釜茶碗類のかけらがあったというのだ。
過日、単独行で「ガゴが岩屋」を探しに出かけたが見つけることができなかった。「ガゴが岩屋」を訪ねてから三十年近い歳月が経ち、原生林は伐採され付近の自然は大きく変わっているので記憶の場所が定かではない。今、「ガゴが岩屋」の場所を知る人はもうほとんどいなくなった。再度本格的に探険しなければならない。
ガゴの伝説に似たような話は、京都の元興寺にある。インターネットで検索すると、《元興寺は、蘇我馬子が飛鳥の地に創建した飛鳥寺がその前身で718年に寺籍を移して現在地に新造された。その寺の梵鐘に鬼がいたという伝説がある。弘仁年間(810~824)に成立した「日本霊異記」に「ココラニモ、チノミ子ガツヨウナクニ、ココエ、ガガウゼガクルト云テヲソラカセバナキヤムゾ」》とある。これは「ガゴ」ではなくて「ガガウゼ」であるが訛ったとも考えられる。京都の伝説がなぜ九州山地の奥深くに残るのか。
もしかすると「ガゴ」は修験者の山伏ではないか。白岩山を挟んで東側の幻の滝と西側の「ガゴが岩屋」が活動の拠点と思えば節が合う。山伏が断層による「気」の場を修業により見つけてその場所で精神世界を高めようとしたかも知れないのだ。
山伏が脊梁山地で活躍していたと思われるいくつかの手がかりがある。鞍岡に伝承されている古武術「タイシャ流」は、祇園神社の夏祭りのメインだ。六尺棒を持った「棒使い」がお神輿を警護して行列をつくる。お神輿が終わると神殿横の広場で「白刃」(しらは)と称して真剣と6尺3尺棒で闘陣の型を演武するのである。タイシャ流と呼ばれるこの古武術には、巻物と呼ぶ神格化された秘伝書がある。門外不出、他言無用とされる秘伝書には、巻頭に天狗が闘陣の型を見守っている絵が描かれおり、闘いの極意が記されている。
巻末には傳尾判として伝授者の名前とその年号が列記されているが肥雲働山・一能院友貞から柏村十介に渡されたことが書かれており、山や院がついていることから、山伏系統の武術ではないかと思われるのである。その後の伝授者は正保二年山村四兵衛から始まり嘉永や安政年代まで白岩山を越えて椎葉と鞍岡の人物に渡ったことが伝授者名から読み取れる。タイシャ流は、人吉出身の丸目蔵人が開眼した武術であるが、鞍岡のタイシャ流は山伏の武術となって受け継がれたものと思われる。
また、鞍岡の秋のくんち祭りに臼太鼓踊りが演じられ、その中に山伏装束の二人が山伏問答を行う場面がある。その問答は、
問 そうれに見えし山法師は、何山法師にて候(そうろう)
答 たあだ山法師にて候
問 まこと本山の山法師ならば、御身の体(たい)のいわれを御開かれ候
答 体(たい)は父の体内より血を丸め、母の体内に九月の宿を借り阿吽という二字をうけ、生まれ出でたるがまこと本山の山法師にて候
問 まこと本山の山法師ならば、御身のかぶったるトキンのいわれを御開かれ候
答 トキンは、峯七つ谷七つ須弥山(しゅみせん)の山を表ぜたるものにて候
問 まこと本山の山法師ならば、御身の肩にかけたる袈裟のいわれを御開かれ候
答 袈裟は、今日天照皇大神を表ぜたるものにて候
問 まこと本山の山法師ならば、御身の手についたる杖のいわれを御開かれ候
答 杖はつく日の形と申す
問 形とはいかに
答 形とは、良きところにも悪しきところにも杖はつく日のいわれをもって形とは申す
問 まこと本山の山法師ならば、御身の腰に下げたる貝のいわれを御開かれ候
答 貝は法螺貝にて候
問 音はいかに
答 音は、ぽーぽーと聞こえ次第のものにて候
問 まこと本山の山法師ならば、御身の足に履いたるわらんじのいわれを御開かれ候
答 わらんじは神の前でも仏の前でもこれは礼なしのものにて候
問 にせではない。とうざいとうざい。皆を御尋ね御開かれそうろう。仲直りに遊び踊りを一度つかまろうやと若い衆を進めいで、早く急いで急いで
答 さあきから心得ておる
こうした問答が行われる郷土芸能の伝承文化を見ると山伏はこの山のどこかに拠点を持っていたに違いないと思うのである。
巨樹の会を主宰する平岡忠夫氏は、霧立越シンポジウムで「修験道は明治維新になった時に消されているんです。歴史上からですね。それは、なぜかっていうと、新しい明治政府が一番恐れたのが、修験道だったんですね。消されて今残ってるのは名前だけなんですよ、土地の。」と説明している。
平家落人の里として知られる椎葉であるが、椎葉の古老たちは労働歌などの歌も上手いが、唱えごとが実に素晴らしい、そらんじている。「コンニチノ、キクガミ、ゲクニューノカミ、テンニイチガミ、ヤマノカミノオンマエデ、カブフタオシムケ、オシユルギャアテ、ジョウブツサセモウスゾヤ、ナムアミダブツ」。などと狩の作法でもすらすらと唱えごとがでてくるのである。また神楽の中でも長々と出てきて実にすらすらと唱えられる。こうした唱えごとは口伝である。このような能力は山伏の影響を受けているのではないかと思う。
不気味な地底
筆者が断層に興味を持つようになったのは、昭和四十年代のことである。ヤマメの孵化場を本屋敷上流の松が平に建設しようと考え、孵化用水探査のため大学の地質学の先生や電気探査の業者を招いて地下水探査を行った。その結果、凝灰岩(阿蘇の火山でできた石―俗に言う「はい石」)の層を掘削して横穴を開けると古生層の石灰岩に突きあたり、そこに湧水があるという調査結果を得た。そこで業者に依頼して凝灰岩に直径1mほどの坑道掘削を始めた。
50mほど入ったところで粘土状の被溶結凝灰岩(「はい石」が固まっていない部分)の層が現れ、その中に溶岩で炭化したと思われる木の年輪を付けた炭が見つかった。そして、その奥に石灰岩の古生層はあった。そこから、まさに大量の湧水が噴出しその水は被溶結凝灰岩の層に消えていた。
掘削した坑道奥の闇の中で耳をすますとまるで地下に滝と湖があるかのようにドロンドロンという不気味な音が地底深くから聞えてきた。「地下はなんと不思議な構造をしているんだ」と、地下構造の凄さ不思議さに感動したものである。
五ケ瀬町鞍岡から椎葉一帯にかけては、仏像構造線と中央構造線につながる臼杵八代構造線に挟まれた秩父累帯である。その中の黒瀬川構造帯と三宝山帯について「日本の地質9 九州地方(共立出版社)」には次のように記してある。《この地域のおもな三宝山帯は宮崎県五ケ瀬町鞍岡の南方の国見峠を中心とした地域で、五ケ瀬町本屋敷から椎葉村仲塔まで幅約8km、長さ25km以上にわたる帯状の地域にある。北限は、本屋敷―戸根川上流を結ぶ構造線で、黒瀬川構造帯と接する。南限は仏像構造線に相当する構造線で南側の四万十累帯と接する(神戸 1957)》とある。この断層の白岩山衝上層近くと思われる場所に幻の滝はあった。その滝付近を地形図で見ると、とても険しい地形であることがわかる。谷や尾根がどの方向へ曲がっているのかよくわからないほど等高線が左右上下に振れていて密である。九州脊梁山地の地形図全体を読んでもこのように等高線が深い皺をつくり複雑に絡み合っている地域は他にはない。
脊梁山地が造山活動を行う時、巨大な岩盤のぶつかり合いや摩擦が想像を絶するエネルギーを引き起し、その力がこの地点に集中し凝縮されてできた地形ではないかと思った。大地の巨大な岩盤のずれは、その摩擦で生じた電気が雷雲を呼び起こし、岩盤のぶつかり合う轟音と雷鳴が宇宙まで轟いたであろうことは想像にがたくない。その岩盤から生じた電磁波などのエネルギーが固い岩石の中にも閉じ込められているのではないかと思うと面白くなる。
シンポジウムへ
これまで「気」とか「マイナスイオン」などと聞きなれない言葉が多く出た。それらはインターネットで検索すると膨大な情報をヒットするが、どうも理解しがたいものが多い。中にはオカルト的なにおいのするものもある。だが、《今回の分杭峠の「気場」を発見する過程で活動に携わった「東海大学の佐々木茂美教授(工学博士)」の学会論文や著書には,詳しい内容が記載されています。》とある。また《マイナスイオンが滝壷や噴水の周辺のような水が流れるところや飛び散るところに多く発生することは、今世紀初頭に、物理学者のフィリップ・レナード博士によって発見され「レナード効果」と名付けられました。レナード博士はこの功績によって、ノーベル物理学賞を受賞しています。日本では、マイナスイオン研究の第一人者、東京大学 山野井昇博士がイオンと医学の分野で活躍されており、先生の著書「イオン体内革命」(廣済堂)は現代の「マイナスイオンバイブル」といっても過言ではありません。》などとあるので、これは改めて学ばなければならないと思った。
市場でもマイナスイオンヘアドライヤーだとかイオン水などイオン〇〇とするイオングッズのオンパレードである。今、宮崎市は「イオン」で揺れている。大規模店舗の進出は既存の商業施設を揺さぶるが、これもあの「イオン」からつけられた社名なのだろうか。
いつもの虫が騒ぎ出し「中央構造線の謎を探る会」代表の後藤琢磨氏に「シンポジウムの講師に来て頂けませんか」とお願いのmailを打った。初対面からmailでのお願いは失礼千万であるが、地域づくりで活躍されている仲間であれば許されるであろうと。すると、5月14日待望のmailが届いた。mailには《せっかくのお誘いでもありますし・・・・(高千穂や、幣立神宮行きは、以前からの課題でありましたから)おうかがいさせていただきたいと思っております。》とある。そして、分杭峠の磁場発見の隠されたエピソードもちらっと情報を開示された。これは素晴らしいイベントになる。待望の「気」の場は見つからないにしても、学ぶことは大きい。なにより「中央構造線の謎を探る会」の九州支部でも設立できれば日本列島縦断のネットワーク・交流軸ができることになる。(終り)
まちづく講座
夕日の里づくりのページで述べた後藤春彦先生の講演録の一部を掲載します。じっくり読んで見ると面白いです。
---------------------------
自治体シンクタンクからドゥタンクへの試み
後藤春彦(早稲田大学理工学部教授)
―小田原市政策総合研究所の取り組む新しいガバナンスのかたち―
(1)「景観」とは何か
私は「景観」を研究テーマの中心に置いて、これまで研究活動等を行ってきました。学生時代に景観の定義として最もシンプルで最も印象的だったのは、イギリスのゴ-ドン.カレン(Gordon Cullen)による「1つの建物は建築であり、2つの建物はタウンスケープである」という非常に有名な言葉です。「単体の建物は建築であり複数集まると景観となる」というこの言葉は私の景観研究の端緒となる概念でしたが、ある意味でこれにはたいへん悩まされました。ゴードン・カレン自身深い考えがあって、景観をこうした単純な言葉で表現してのだと思います。しかし、当時の学生からしますと、建物の連続するような街並みをどうしても景観という概念でくるんでしまおうと思いがちであったのではないかと考えいています。
それでは、「景観」とは何か。「景観」とは、明治時代に三好 学という生物学者がランドシャフト(Landschaft)というドイツ語にあてた造語です。今では中国でも韓国でもこの「景観」という言葉を使っていますが、これは日本から逆輸入した言葉です。では、そのランドシャフトとはどういう意味なのか。景観像という言い方をされる先生もいますが、分かりやすく言えば、眺めと、もう1つは地域的な広がり、景域という2つの概念が実はそのランドシャフトの中に入っています。生物学や地理学では地域、景域といった空間的な広がりを景観と呼んでいるのに対し、造園、土木、建築分野では眺めの方を重視して景観と呼んでいます。ですから、たとえば黒い屋根瓦の景観というと、地理学では黒い屋根瓦の分布するエリアをいうのに対し、建築では黒い家並みの連続する風景を指します。このように景観という概念は、2つに分けてとらえられてきましたが、もともと眺めと地域という2つの意味系列を持っているものをもう1度統合してとらえなくてはいけません。ですから、景観とは美醜の対象ではなく、ある意味では社会的規範、パブリック・ヒストリーの表現だととらえてみたいのです。ドロレス・ハイデンは「みんなの歴史が表われているもの、それが景観なのだ」と言っています。ですから、たとえば2つの建物の眺めは、実はそれを下支えしているその地域、あるいはその地域の歴史をも含めて、景観と考えなくてはいけないのです。
ランドシャフトという言葉には実は可視的現象と地域単元という2つの意味系列があり、研究としては景観の特性やその構造がどうなっているかをつかもうとしますが、基本的に風景、景色、眺めといった可視的現象と、場の景観、場所、景域といった地域単元の2つの意味系列を統合して、景観・地域デザインといった概念でもう一度再構成できないものかと私自身は思っています。
(2)景観の仕組み
では、その景観とはどんな仕組みでできているのでしょうか。それを少し解きほぐそうと思って書いたのがテトラモデルと名づけている図です。
実は景観とはある資源からできており、その資源をわれわれは評価し、それを総合化・体系化することによって何かの主題を与え、さらにそれの実現に向けて計画を行います。すなわち、景観形成には「資源」「評価」「主題」「計画」という4つのステージがあるのではないかと思っています。その景観の資源は、「自然」「人口」「人間」という3つのカテゴリーから成ります。そして、それをいろいろなかたちで評価しますが、それには「本能的な評価」「習慣的な評価「論理的な評価」の3つがあります。さらにそれは、「風土性」「社会性」「歴史性」といったテーマで読み解くことができます。あるいは主題に即して進める計画を「保存・保全、守ろう」、「育成・修復、育てよう」、「創造・開発、つくろう」といった3つに分類し、計画の三角形の各頂点に位置づけます。
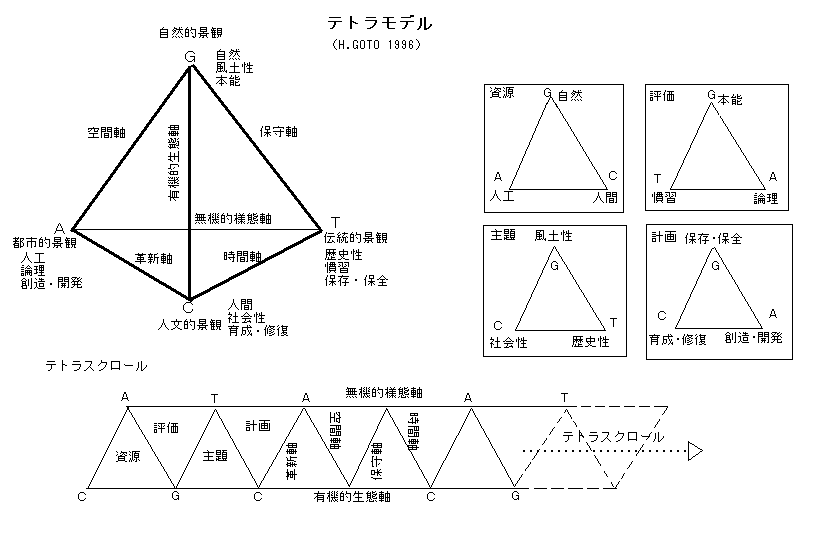
その4つの三角形をもとに正三角錐(テトラモデル)を構成しますと、先程の三角形の頂点にあったキーワードが集まってきます。たとえば「自然」「風土性」「本能」、「人工」「論理」「創造」、「人間」「社会性」「育成」、「歴史性」「慣習」「保存」といった、比較的似たような言葉が集まってきます。また、各頂点について景観を考えるならば「自然的景観」「都市的景観」「人文的景観」「伝統的景観」といった4つのカテゴリーがつくりだせます。面に意味を持たせ、頂点に意味をもたせたので、線や辺にも意味があるかなとじっと眺めてみますと、たとえば都市的景観や自然的景観はある種空間を扱うのに対し、人文的景観、伝統的景観は時間を扱います。あるいは、自然的景観と伝統的景観には保守的な意味合いがあるのに対し、都市的景観、人文的景観には革新的な意味合いがあるのかもしれません。あるいは、自然的景観や人文的景観はどちらも生物の生態を表す軸であるのに対し、伝統的景観や都市的景観は無機的な様態を表す軸になります。このように、ねじれの位置にある関係にはそれぞれ対の意味が読み取れます。
実は景観でもそうなのですが、例えば地域づくりでも今、私はこの「テトラモデル」と呼んでいる三角錐の中でどこの仕事をしているのか、自分がどの辺りにいるのか、これからどちらに向けて仕事をしていかなくてはいけないのかといったことを考えながら取り組んでいるのです。次の一手をどちらに進めていくか。それを実はこのモデル上で私は考えているのです。さらに、たとえば、砂浜の上にこのモデルを転がすと軌跡がつきますが、この正三角錐をころころと転がしますと、ちゃんと「資源」「評価」「主題」「計画」の順に砂の上にプリントされていきます。これをバックミンスター・フラー(R.Buckminster Fuller)という人は「テトラスクロール」と名づけています。このように、一つの環境の中で資源から計画に至る各ステージが繰り返しあらわれてくることも表現されるのはとても面白いなと思います。これが私の景観に対する基本的な考え方です。
(1)「場所の力」とは何か
『場所の力』という本が非常に魅力的なのは、都市景観を美醜の対象ではなく、ある意味では社会的規範、しかもそれがみんなの歴史を表現するパブリック・ヒストリーの表現だととらえているところです。この本の著者ドロレス・ハイデンは、場所が持つ社会的記憶をまちづくりに活かすことを試みています。特にその中の重要な手法が、オーラル・ヒストリー(口伝の歴史)です。市井(しせい)の人々の口から語られるものを拾い集めることによって、市民のサイドから歴史を編み出していき、それを景観として表現することに意図的に取り組んでいます。ドロレス・ハイデンは著書『場所の力』の中で、「場所の力」について、「それはごく普通の都市景観に秘められた力である。共有された土地の中に共有された時間を封じ込み、市民の社会的な記憶を育む力である」と定義しています。
さらに彼女は「社会的な記憶とは労働者の歴史であり、民族や女性の歴史を意味し、特に地域社会における悲痛な体験や敗北した闘争の歴史を含むものである。そして、こうした歴史は、書物に記されたり、公園や広場の銅像となって表象される、強者や勝者の、すなはちメジャーの歴史とは明らかに異なるもので、人々の口伝や街角の何気ない景観などによってのみ伝えられる市井の人々のアイデンティティとも言えるものだろう」と述べています。
このように、彼女は教科書や銅像となって表れるような勝利者の歴史ではなく、その場所に生きてきた人々の口伝えの歴史を表出していくことに意図的に取り組んでいます。
この『場所の力』という本の中には、多くの写真が登場します。たとえば鉄道の建設史もこの本の中では労働者の歴史として編み直しています。第2次世界大戦中のロングビーチの造船所で働く労働者たちです。労働者たちは、多様な民族グループの女性そして男性から成っていました。またニューヨークの中国人の洗濯屋です。こうした労働者の視点から、ニューヨークの形成史をもう一度編み直しています。バナキュラーな家あるいは街並みの中にパブリック・ヒストリーの種や人々の場所に対する記憶が残っているのだというのがハイデンの考え方です。
当然、一つの都市にはいろいろなテリトリーが生じます。ちょつとどきりとさせられますが、「日本人は出ていけ!」という、日系アメリカ人を排斥する大きな看板が掲げられています。ある大学の講義風景では男性と女性の座る場所が明確に分かれていると同時に、黒人の学生は最後列で、また数も一人二人ぐらいしかいません。このようにそれぞれのテリトリーが形成されています。こうしたものも場所の記憶として語り継いでいく必要があるとドロレス・ハイデンは言っています。
(2)生活の営みは空間を場所化する行動
空間と場所という、ちょつと似たような言葉について少し考えてみます。生活の営みはその空間を場所化する行動です。空間は、数学で習うようなXYZという3次元の、ある種均質なものものです。そこに人間が暮らし、住み込んで、いろいろな記億を蓄積していくことによって、そこに場所性が表れてきます。換言すれば、空間に手を入れ、使い込む事により、さまざまな意味が発生し、そこに記憶が蓄積され、場所と呼ぶべきものとなります。場所とは社会的な記憶の源泉であり、記憶の糸が紡がれた織物のような存在です。そしてその力は再び人間の五感へと働きかけてくるものです。したがって、私たちはいつも「場所の力」を感じて生きています。
もう少し付言しますと、都市の景観はどんな言葉表現よりもはるかに饒舌に場所の社会的な記憶を語る力を持っています。私たちは場所を通して過去に生きていた先人たちと対話する事も出来ます。場所は人々にモラルや教訓を伝える「教育力」をも内在しています。この「教育力」が非常に重要だと私は思います。歴史的に見れば、場所の概念には、個人が一定の規模の土地を所有する、あるいはコミュニティーの構成員になるという社会経済的な意味合いも込められています。
「場所の力」は、現代に生きる多様な人々や地域社会を相互に結びつけることを可能にします。つまり、場所はさまざまな人種や国籍、あるいは所得階層といったものを相互に結びつける力も持っています。今日、社会の絆としての都市生活の意味や可能性を市民自らが発見できる場所、さらにその「場所の力」を顕在化するための仕事が、歴史家や芸術家も巻き込んだ、より多くの分野の専門家と市民の参加によるコラボレーションに求められています。特にこの本の著者ドロレス・ハイデンは、ロサンゼルスを中心に単に建築、都市の専門家だけではなく、歴史家や芸術家、あるいは環境保全活動家とか、いろいろな専門家をあつめて、その場所の力を顕在化するプロジェクトに取り組んでいます。
少し整理しますと、数年前に「ゲニウス・ロキ(Genius Loci)という言葉が日本でもかなり使われました。ゲニウス・ロキとはラテン語ですが、英語に直すと「Genius of location」です。場所が何かを生み出す力、神様のような見えない力、それがゲニウス・ロキです。
「場所の力」とはゲニウス・ロキにも通低する概念です。しかし、「場所の力」は現代に生きる私たち市民一人ひとりの生活に密着した記憶に根ざしたものであり、かつそれらの総体としてより広範な社会性を帯びた概念でもあります。
ですから、市民一人ひとりの記憶の蓄積、パブリック・ヒストリーをみんなの歴史という言い方をしましたが、その方がゲニウス・ロキよりもより社会性を持っている概念ではないかと私自身は解釈しています。
そして、パブリック・ヒストリーの解釈では、可視的表現のプロセスに市民や専門家の参加と協働といった外へ向かって運動していく力が込められている点が大きな特徴てぜす。ここがゲニウス・ロキとは少し異なる点ではないかと思います。ドロレス・ハイデンは、こうしたプロセスを実は「公共事業」と呼び、「場所の力」が顕在化された空間を「公共空間」と位置づけています。
(3)『場所の力』から学んだこと
① 「場所の力」によるデザイン領域の拡大
私なりにこの『場所の力』という本から学びとったことを大きく3つにまとめてみました。まず「場所の力」はデザイン領域を拡大してくれました。先ほど「場所の力」を顕在化する仕事には、歴史家も環境保存運動の活動家もいろいろなかたちで参画するという話をしましたが、それと同様に、従来、景観はどちらかといえば、「図」でかたられる事が多かったと思います。ゴードン・カレンが「1つの建築は、建築だが、2つの建築はタウンスケープである」と言いました。でも、それは「図」なのです。実はその2つの建築の背後に「地」があってこそはじめての1つの景観になります。安定した「地」と洗練された「図」の間の良好な関係こそが「場所の力」に求められるものです。建築学をバックグラウンドとするハイデンは、「図」にのみ目がいきがちな建築分野に対して厳しいスタンスをとりながらも、建築と社会の良好な関係のあるべき姿を思索していたのです。
「図」の保存、あるいは「図」のデザインの巧拙だけではなく、この安定した「地」をどのように保全していくかが、実はこの「場所の力」という考え方において重要なのです。
もう1点、「場所の力」によって関係づけられたものとして、都市の社会的経済的文脈の存在を示唆しています。ちょつと分かりにくい表現ですから、説明が必要かもしれません。今、ある有名な建築を保存しょうとします。具体的には大富豪の邸宅を想像してもらうといいかもしれませんが、有名な建築家がつくって、芸術的価値も非常に高いものを保存しようとします。まさにここでいう「図」の保存です。でも、そうした中での邸宅を建設した大工の腕、あるいは石を組んだ石工の技術、あるいは維持管理していた庭師の職人技なども、実は非常に重要なのです。単に脱け殻としての有名建築を保存するのではなく、それをつくり上げてきた、地域の文化、技術といったものも併せて保存していくことによって、はじめて保存建築の中に社会的経済的文脈が読み取れるようになるのです。
ハイデンは「都市労働者階層の歴史とランドマーク的建築作品は、それらを建設した石工や大工の技術や、それらを維持管理していた庭師の技術の側面からも解釈されうる」と述べています。「あるいは解釈されなくてはならないのではないか」とも彼女は言っているのです。
見慣れた「地」としての日常の風景も、最近では生活景ということで、保存・保全の対象になり始めました。何も「図」としてのランドマークだけが私たちの暮らしの中で重要なのではなく、普段は見慣れてしまった「地」も実は重要だったのです。通勤途中で見慣れていた、どうということのない石垣が壊れた事によって、日常の風景がとてもかけがえのないものであったことに気づいたと、阪神淡路大地震の被災者が証言しています。こうした生活景、あるいは「地」の風景もデザインの対象、保存・保全の対象なのだということがこの本から読み取れます。
② 「場所の力」を顕在化する都市景観
都市景観とは、場所にまつわる社会的な記憶(パブリック・ヒストリー)、つまり「場所の力」を顕在化するものです。都市景観にこうした位置づけを与えた事は非常に意味深いものがあると思います。このような都市景観に対するアプローチは、特に多様な都市社会において、共通の文化的帰属意識の内から形成される一種のアイアンティティとしての「文化的市民権」を構築していく上で見過ごすことはできない重要なものです。
この「文化的市民権」とは、ちょっと耳新しい言葉かと思いますが、人種も宗教も国籍も階層も多様なアメリカの場合、自分のへその緒がどこにつながっているかは非常に重要なことなのです。日本においても、昨今ではそうした都市における自分の居場所探しみたいなものがはじまりつつあります。そうした中で、実は市民権と呼んでもいいようなへその緒を求め、それを構築することがこれからもっと声高に進んでいくのではないでしようか。『場所の力』という本はその辺りを少し先取りして見せてくれるのではないかと思います。
さらに前世紀末は、かなり都市改造や再開発により、都市景観が損傷を受け、多くの市民が共同体についての重要な記憶を消し去られてしまいました。しかし、そうした場所でさえ、共有する社会的意味、あるいは共同体の記憶を修復することが可能だとこの本は勇気づけてくれます。すなわち、この本は、もう建築が残っていなくても、あるいは木が1本も残っておらず、全くの更地にされてしまった状態でも、実は共同体の記憶を修復する方法はまだあるのだと言っています。都市に積層する有形無形の多様な遺産に配慮しながら都市空間の社会的意味を高めることは可能であり、それは場所の文化的重要性を認識する社会的プロセスを伴ったまちづくりの展開に他ならないと言っているのです。そして、具体的にはこの著者は先程もお話したように、オーラル・ヒストリーを多用することが有用であると言っています。
市民の社会的記憶を育み、過去と未来をも共有できるような「場所の力」を模索する実験的なこころみが近年爆発的に進んでいます。この本は、そうした「文化的市民権」を追求する、日本の新しいまちづくりのムーブメントに対して学術的な論拠をあたえるものでもあります。
(2)自治体シンクタンクーの期待
自治体シンクタンクとは何か。それは、自治体の政策形成機能を補完・支援する組織であり、また市民、企業、行政とのネットワークを活かした研究を進め,市民の立場からの政策形成を目指すようなコミュニティ・シンクタンクと呼べるようなものではないかと思います。
(3)自治体シンクタンク/コミュニティ・シンクタンクの変遷
こうした自治体シンクタンク/コミュニティ・シンクタンクがこれまでどういう変遷をしてきたか。ここでは大きく4期に分けて眺めてみます。
①模索期――70年代から80年代半ば
実は、1970年代から、自治体シンクタンクは誕生しています。ただ、この時は大阪、神戸、北九州などという政令指定都市レベルの自治体で研究所が作られています。研究体制としては行政と学識経験者によるもので、そこに市民や企業の参加は全く見られません。研究機関としての活動が重視されたもので、市民や企業が参加することはありませんでした。
②財団法人化、市民、企業参加期――80年代後半から90年代前半
1980年代後半から90年代前半にかけては、ほとんどの組織形態が財団法人でした。また、半分以上のシンクタンクで市民や企業の参加が見られるようになっています。この辺りから、パートナーシップがかなり強調され始めたことが見てとれます。
③任意団体移行期――90年代後半
90年代後半には、組織形態がこれまでの財団法人から任意団体に移行します。1つには財団法人の認可が厳しくなったことがありますが、もうに1つにはバブル崩壊後の第三セクターの財政破綻などに対する嫌悪感や設立運営のための資金繰りが強く影響していることが読み取れます。
④行政内部設置期――2000年代。
2000年に入り、地方分権一括法の施行を受けて、自治体自らが独立政策形成を進めていくために、これまで行政内部、財団法人、任意団体と移ってきた流れが再度行政に逆戻りするような動きが小田原と上越市で誕生しました。
研究所設立のアドバイス
最初、市長から私のところに連絡あり、「政策総合研究所といったものをつくってみたいからちょっと知恵を貸せ」と言われました。その時、私が申しあげたアドバイスをいくつかご紹介します。
①アドバイス1 知恵袋というよりも…ガバナンスのかたちの模索
当初、市長からは自分の知恵袋が欲しいというお話でしたが、私は「知恵袋というよりもガバナンスのかたちを模索していくような組織がのぞましいのではないか」と言いました。具体的には、それは市民と行政の間を橋渡しする「中間セクター」として育っていくような組織です。できれば、そこには独立した財源と専門スタッフを配置し、何かを研究するというより、まちづくりを支援するスタイルの組織として成長していけないものかというお話をしました。つまり、これまではきちんと敷かれた線路の上を高性能で走る列車をつくることが重要でした。まさにそれがガバナンスのあり方だったのかも知れません。しかし、これからはそうではなく、「船頭多くして船山に上る」では困ってしまいますが、多様な主体が参画して、右に行ったり左に行ったり、いろいろと蛇行しながらも、船の本来の進むべき方向をみんなで模索していく必要があるのではないかと考えたのです。この政策総合研究所でガバナンスのかたちを少し実験的に行えないものかとのイメージを私は最初に持っていました。
②アドバイス2 ある程度の試行錯誤が許されるべき
行政としての市役所の仕事はどうしても誤りがあってはいけないのですが,政策総合研究所という枠組みの中ではある程度の試行錯誤は認められるべきではないか。その中ではいくつかの社会実験ができるようにしたいというお話もしました。
③アドバイス3 大学研究室、学生とのコラボレーション
どうしても1年目、2年目ぐらいまでは力がありますが、だんだん皆疲れてきてしまい、研究を持続することが難しくなってきます。ですから、そうした時には外からのパワーをどんどん引き寄せてこなくてはいけません。職員や市民の稼動にも限りがあります。そこで、大学研究室や学生とのコラボレーションをしようという提案をしました。「オープン・ユニバーシティ・ラボ」などという言いかたもしていますが、ここで、いろいろな大学の学生に、修士論文や博士論文を書いてもらえるようなことも行えないかといったことも話しました。
④アドバイス4 中心市街地にまちづくりの実験拠点
ワークショップや研究成果が発表できるような、まちづくりの実験拠点を市役所の中ではなく、中心市街地のどこかに欲しいといったこともお話させていただきました。
こうした4点ほどのアドバイスを市長にお聞きいただき、ちょうど2年前の2000年4月に小田原市政策総合研究所が設立されました。この研究所は、政策形成やその実施を目指すものであり、研究員は公募の職員研究員、指名の職員研究員、それと公募の市民研究員からなる組織です。更に、外からの力として大学や民間研究所からも研究員を招聘するかたちでスタートしています。
具体的にこの政策研究所の機能には、先ず調査研究機能があります。その内容は、基礎的な調査研究に基づく将来の政策立案に向けた提言(政策提言)、市政の横断的かつ重要な事項に関する専門的な研究(政策研究)、政策アドバイザーの各部局への派遣(政策形成支援)外部調査機関への委託調査等です。研究所の調査研究機能以外の機能としては、研究フォーラム、研究紀要の発行、インターネット等の研究情報交流機能、派遣職員の活用等といった人材活用・育成機能があります。
研究所の組織は、所長以下、副所長、研究顧問、上席研究員(大学の教員・教官クラス)、研究員(市職員、大学の助手、博士クラスの研究員)、市民研究員、職員研究員といったスタッフからなります。それの大きなボードを握っているのが市長、助役、収入役、企画部部長、所長からなる運営会議であり、そこで基本的な重要事項を決定します。
小田原市政策総合研究所は、行政、学識、市民の協働による政策形成能力を有し毎年「小田原スタディ」と称する研究紀要を作っています。それから社会実験やさまざまなワークショップ、講演会などを市民が企画開催します。もうひとつ総合政策研究所は、市民まちづくり活動の傘/母体となることを目指しています。NPO、いろいろなまちづくり運動・クラブにたいして、ある種、傘の役割を果たして、たとえばそこに活動助成や研究助成を与えることができないか。あるいは、更に何か新しいまちづくり活動のグループを生み出していく母体となることを考えられないかということで運営しています。具体的に今、「角吉倶楽部」という名前のまちづくり活動がここを中心に育っています。さらにもう1つ、まちづくり応援団(仮称)なるものが近々誕生する予定です。
-------------------------------
あとがき
早いものでもう6月となりました。養魚場の開放的な事務所でパソコンに向っていますが、最近ホトトギスとジュウイチが盛んに鳴いています。
夜中までジュウイチ、ジュウイチとなくあの鳥です。どちらもカッコウ科の渡り鳥でウグイスなどが巣づくりをした頃渡ってきてその巣の中に卵を産み付けてウグイスなどに育てさせるという託卵をする鳥です。自然界も厳しい掟がありますねえ。
シンポジウムの件で山伏なと調べていましたら、これまでの誤りに気づきました。それは、鞍岡のお祭りで臼太鼓踊りが行われ山伏問答をやりますね。「トキンは、峯七つ谷七つ須弥山の山を表ぜたるものにて候」と。これは文書に「須弥山」とあったため「すややま」と読んでおりますが正しくは「しゅみせん」と読むようです。恥ずかしい!。
須弥山は古代インドの世界観で世界の中心に須弥山(しゅみせん)があり、月日の運行の中心であるとされた山のことだそうです。別名:カイラス山のことを指しこの山は東経81・20度の位置にあり、ヒマラヤ山系の西半を構成する標高6714メートルの大雪山。チベット仏教の大聖地としても名高く、須弥山詣では、全教徒の念願として今もなお伝えられている。―ということです。
凄いですね。この山中のお祭りにおいて古代仏教の世界観、宇宙観を語っていたわけなんです。保存会の皆さんこれからは、「須弥山」を「しゅみせん」と読みましょう。
このかわら版は、14区の皆さんに配布していますが、どなたにでもお届けできます。ご希望の方は郵送料として年会費千円を添えてお申し込みください。(治)