2002年5月1日号 毎月1回1日発行
第16号 発行者 やまめの里 企画編集 秋本 治 五ケ瀬町鞍岡4615 電話0982-83-2326
今年のサクラ情報
1.サキヤンタニのサクラ
「サキヤンタニの大幹線林道下に変ったサクラが咲いているので調べてみて」と秋山光義氏から情報を頂いていたので4月4日午後、調査に出かけました。この季節、山のあちこちに開花しているサクラはエドヒガンです。説明された場所に近づくと確かに遠目にも他のサクラとは違う色合いや咲き方をしている樹が目にとまりました。標高千m付近です。
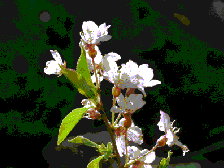
このサクラの特長は
①総花柄がない。…ヤマザクラには総花柄があり、エドヒガンには総花柄がない。故にこのサクラはエドヒガン系である。
②花柄からガク筒にかけて毛がある。…ヤマザクラには毛がなくエドヒガンには毛がある。故にこのサクラはエドヒガン系である。
以上の特長でエドヒガン系とわかります。しかし、次の点が普通のエドヒガンとは異なる点です。
③ガク筒が丸く膨らんでいる。…エドヒガンは、このように丸く膨らまない。
④若葉が出ている…エドヒガンは、若葉が出る前に花が開くので若葉はこのように伸びていないはず。
⑤花の経がエドヒガンの半分くらいで極めて小さい。
⑥花柄が曲がらずピンと立っている。
⑦花弁が曲がらずピンと立っている。
以上がエドヒガンと異なる点です。
①と②はエドヒガンの特長そのままですが、③~⑦までは、エドヒガンと異なります。特に⑤の花の経がエドヒガンの半分くらいで極めて小さい。⑥の花柄が曲がらずピンと立っている。⑦の花弁が曲がらずピンと立っている。この3つの違いが遠目にも「変ったサクラ」と見えるのです。それでは、このサクラは一体何者でしょうか。
エドヒガンは交雑により実生ではいろんな変種ができやすい樹です。例えばシダレザクラもエドヒガンから変じてできたサクラです。
そこで、シダレザクラとエドヒガンを比較した写真を撮影しましたのでご覧ください。
 写真の左が調査のサクラ、中央がシダレザクラ、右はエドヒガンです。比較してわかるように、花の大きさとガク筒の丸み、若葉の出具合はシダレサクラによく似ています。ただシダレザクラとの違いは、地球の重力に強いのでしょうか、花柄や花弁がしだれずにピンと立っていることがわかります。シダレザクラは地球の重力に弱いから枝がしおれるようになったと考えられます。
写真の左が調査のサクラ、中央がシダレザクラ、右はエドヒガンです。比較してわかるように、花の大きさとガク筒の丸み、若葉の出具合はシダレサクラによく似ています。ただシダレザクラとの違いは、地球の重力に強いのでしょうか、花柄や花弁がしだれずにピンと立っていることがわかります。シダレザクラは地球の重力に弱いから枝がしおれるようになったと考えられます。このことから、サキヤンタニのサクラは、エドヒガンが変じてシダレザクラに近い種として突然変異が起ったのではないかと考えられます。
日本にある数百種にも及ぶサクラは、このように突然変異種を接木で増やしたり交配して作ったものです。
周辺にもこれと同じサクラは見つかりませんので新しい種ではなくエドヒガンの突然変異といえるでしょう。仮の名前をサキヤンタニザクラとしておきましょう。
2.不土野の八重咲きサクラ ?

 椎葉の黒木勝実氏から、珍しいサクラがあるとの情報が入りました。不土野の椎葉照毅氏がヤマザクラの八重咲きがあるというので見てほしいということです。エドヒガンの季節が終わった4月10日の午後4時頃から出かけました。現地は、不土野の村から林道、作業路を数キロ入り込んだ標高1200m付近で写真のように作業路の法面上にありました。樹齢も100年以上ありそうで人為的に植えたものではなさそうです。
椎葉の黒木勝実氏から、珍しいサクラがあるとの情報が入りました。不土野の椎葉照毅氏がヤマザクラの八重咲きがあるというので見てほしいということです。エドヒガンの季節が終わった4月10日の午後4時頃から出かけました。現地は、不土野の村から林道、作業路を数キロ入り込んだ標高1200m付近で写真のように作業路の法面上にありました。樹齢も100年以上ありそうで人為的に植えたものではなさそうです。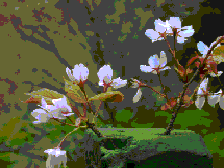
写真左が不土野のサクラ、右はヤマザクラです。
写真でおわかりのように、サクラは5枚の花弁があるのに対して不土野のサクラは、9~10枚ありますのであきらかに八重咲きです。
このサクラの特長は
①総花柄がある。
②花柄からガク筒にかけて毛がない。
以上はヤマザクラの特長と共通する。故にこのサクラはヤマザクラ系。けれども次の点がヤマザクラと異なっている。
③ガク筒がガク裂片に向かって大きく膨らんでいる。…ヤマザクラは、ガク筒が細く、このように膨らまない。
④ガク裂片が短くて厚い。またヤマザクラのように反り返らない。このためか、花が開き切れずにしぼんだようにして咲く。
⑤花弁が9~10枚。
以上③④⑤がヤマザクラと異なる点です。
栽培種のヤエザクラは、花弁が数十から数百枚あります。
疑問は「なぜ八重咲きのサクラがこの山中こにあるか」です。
①鳥が種を運んできた。
②人為的に昔植えた。
③ヤマザクラが突然変異を起こした。
以上3点しか考えられません。
この中で
①は、他の山中で同種が見つからない限り否定される。
②は、この山奥までわざわざこの種のサクラを植えに昔の人が来る意味が考えられない。
一方、新たな「種」を形成しているのではないかということについては、付近に同種のサクラがないということなので種としては否定できます。サクラは一本の木では受粉できないので種として存在するには群落を形成していることが必要です。
そうするとやはり③の突然変異説ではないかと思われます。開花期もヤマザクラと同じです。このため仮の名前をフドノサクラにしておきましょう。いずれにしても専門家の調査に待ちたいと思います。
また、実が大きくなっていましたので、実生の実験をすると面白い。サクランボが成熟したら果肉を取り去り冷蔵庫に入れておきます。11月頃取り出して鹿沼土の上に蒔き、その上に石苔をかぶせておくと翌年の春3月上旬に芽を出します。これはキリタチヤマザクラで実験済みです。発芽率は100%近いです。
その実生から同じような八重咲きのサクラができるか、それともただのヤマザクラになるか興味のあるところです。
次になぜ突然変異を起こしたのでしょうか。これは不明です。前記1.のサキヤンタニザクラも、この八重咲きのフドノザクラも、他のサクラと違うところは、とても幼樹の時から傷めつけられているように見えました。
サキヤンタニサクラは、同じような大きさの他の樹木と根元近くで競り合い、樹と樹が擦れ合ってサクラの木は、幹の半径ほど削れて片側しか皮もついていません。フドノザクラも根元部分にそのような傷みがあり、二本に分かれていますが、一本の樹なのか、二本の樹であったのか確認できないほどです。突然変異には、外部の刺激が必要だと思いますが、まさか育つ過程で傷めつけられて変化するものでしょうか。考えすぎですかね。これはやはり受粉の時何らかの刺激があったものでしょう。
いずれにしても、この突然変異らしきサクラを接木で増やすのは楽しみがあります。接木の方法をキリタチヤマザクラの体験からご紹介しましょう。
先ず、3月の早い時期に天気の良い日を見計らって枝を採ります。枝は徒長したように大きな枝先がよい。採集した枝は、ポリ袋に入れて密閉状態にし、光の入らない冷暗所に10日~2週間入れておきます。この場合水に浸けるのは厳禁です。接ぎ穂には、光りが欲しい、水が欲しいという飢餓状態にしておく必要があるそうです。
次に台樹を準備します。この台樹はヤマザクラの1~2年もの、高さ1~2m位のものがよいようです。台樹を植えて準備していない場合は、植えると同時にそれに接木しても大丈夫です。
接木は、先ず台樹を地上10センチくらいの高さから剪定鋏で切断します。接ぎ穂は、新芽を2個付けた部分10センチほどにして後は切り捨てます。
次に台樹の皮目にナイフを入れて形成層ぎりぎりのところを縦に切り裂きます。接ぎ穂は、切り裂いた台樹の長さと合うように、接ぎ穂の経の中心部まで切取ります。更に縦に切取った接ぎ穂の裏からもナイフを入れて先をV字状にします。
こうして接ぎ穂を台樹に合わせ双方の形成層部分を出きるだけ広い面積で合わせるようにし、台樹の切り裂いた皮の部分を接ぎ穂にかぶせます。
こうしてから接木用のテープで上から巻きつけてしっかり密着させます。この場合、台樹の切り口から雨水が入らないようにテープをしっかり巻きつけなければなりません。その後接ぎ穂の頭の切断面に接木用の薬剤を塗布します。
以上で数週間後には接ぎ穂から新芽がぐんぐん伸び出し、やがて急速に成長します。是非読者の皆さんも珍しいサクラがあったら接木体験してください。
新しい町の誕生を!
今月は、数十年ぶりに町長選挙が行われます。
筆者も、何かにつけてこれまで行政不審などで対立や批判しあったりすることが多かったのですが、選挙を契機に町が変り、新しい首長のもとで行政と住民の新たなよい関係が構築できることを願っています。
振り返ってみるとこれまでいろんなことがありました。筆者は、なぜ行政とうまくいかなかったのか、以前エッセイ風にまとめた未発表の原稿ですが当時を振り返ってご紹介します。筆者の議会不審、行政不審の捻れ現象が始まったのはこの時からです。
------------------------------
行政は誰の為にあるのか
―スキー場による被災―
苦しみもがくヤマメ
1990年8月12日、私はヘアートニックの香りが漂う散髪屋さんの椅子の上にいた。倒した椅子に寝そべり、蒸しタオルを顔に当てられているとやがて睡魔が襲う。テレビの音声もしだいに遠くなり心地よくなってうたた寝の世界へ吸い込まれていった。と突然「お電話です」という声に目を覚ました。
椅子の上で渡された受話器を耳に当てると「養魚場が濁りで大変です」と職員のうわずった声が飛び込んできた。「そんなにひどい雨でもないのになあ」と小雨模様の窓の外を覗いてみたが受話器の向うの息遣いが慌しく聞える。「少しぐらいの濁りに慌てることはないよ」と言ったがどうも変だ。何だか只ならぬ予感がしてあわてて養魚場へと車を走らせた。
やがて養魚場の見える坂道を上ると、いつも見慣れた緑の中の谷川が茶褐色の布を引いたように異様な光景に変っているのが視界に飛び込んだ。「大雨でもないのになぜだ」。思い当たることがないまま養魚場に到着すると職員達は呆然となって池の縁に突っ立っていた。
水路から池に落下する水は赤茶色でドロドロしている。粘っこくて白い泡も立たない。苦しみもがくヤマメたちは水面高く飛び上がったり、水際をツツツーと頭だけを出してパクパクしながら跳ねまわる。死魚をすくい上げてみるとエラの中には粘土のような泥が詰まっている。
「これは全滅になるぞ」そう思った途端足がすくんでしまった。背中に冷たいものが走り頭までジーンと突き上げてきた。なすすべもなく職員達と呆然として池の縁に並んで見つめていた。
「そうだ。原因を確かめなければ」。ようやく気がついて上流へ車を走らせた。谷川沿いにくねくねと上る林道から見え隠れする谷川の水はどこまで上がっても赤く染まっている。「一体どうしたというのだ。」不審に思いながら林道を上がりきると、そこはブナの巨木が茂る天然林で五ケ瀬川の水源地帯だ。
その一角の標高1,600m付近にスキー場の造成工事現場がある。緑の中の山が削り取られて赤土が剥き出しになった斜面が見える。その端に重機が数台並んでいた。その中に入って下を覗くと天然ワサビの自生地がある。山椒魚たちが無数に生息している湧き水地帯である。
削られた斜面を夢中になって湧き水のある方向へ駆け下りた。するとその湧き水地帯はなんとドロドロとした赤い沼に変っていた。中へ入って行こうとするとずぶずぶと膝まで赤土の中に沈んでしまう。引き返して端の方に出て廻り込んで下流側に出た。
原因がわかった。そこから赤くドロドロと化した泥水が谷川を埋めつくし下流に向かって流れていた。こともあろうにこの湧水場所に山を削り取った土砂を埋め立てたのだ。このため地下水の逃げ場がなくなりやがて一気に噴き出して埋め土を沼のようにドロドロにし、その泥水が谷川に流れ出したのだ。
この濁流で池のヤマメ30トンはほぼ全滅した。そして翌日もまたその翌日も泥流は続き、かろうじて生き残ったヤマメもしだいに弱り果て水生菌などに冒されて2次感染が広がりやがて次々と死んでいった。毎日トラックで死魚を運び出す。ポリ袋に詰めた死魚の山が増えていった。
池に入ると池底は30cmもの泥が堆積しておりその泥の中にも死魚が無数にあった。濁流は農家の水田にも入って稲に被害を与えた。濁りは延々と延岡まで続いたと後で聞いた。
川の魚類も上流域ではほぼ全滅した。あの生命力の強いアブラメさえ姿を見せない。初夏になると無数に飛び交っていた蛍も消えてしまった。この時、無秩序な開発の恐ろしさ、ブナ林破壊による自然の逆襲をまざまざと見せつけられた。
それにしても、なぜこのような工事をしたのだ。当初スキー場開発計画では、コンサルタントと何度も現地へ同行してこの湧水地帯の処理について説明を求めた。コンサルタント氏も開発の最大の課題はこの湧水の処理だ言い、いくつかの工法を説明してくれた。
もっとも安上がりの工法は、ゲレンデ予定地の樹木を伐採してゲレンデ内の沢や湧水地帯にその木材を積み上げて並べ、その上に土を盛る工法だという。そうすると水が増水しても木材の隙間から流れ出すので濁ることはない。そして時間の経過と共に木材が腐っていき、埋立地が地盤沈下しても水の通る道は確保されて安定してくるという。
「こういう工法は、多くのスキー場で実験済みであるが、ご当地の場合はこのような安易な工法はとらずもっときちんとした水処理をするので心配しないように」と説明を受けていたのだ。
困難を極めた交渉
死魚を運び出していると役場から100万円の見舞い金を持って挨拶に見えた。その後の補償交渉は困難を極めた。「秋本君がスキー場スキー場というから町は工事をしたのだ。今度はそのスキー場を作ることによって被害が出たからと補償を言われても秋本君のいうそれは困難だ。議会の同意も取り付けにくい」。町長からそう言い渡された時、目の前が真っ暗になった。どこから出た数字なのか真意のほどはわからないが、議会では3トンの被害ではないかと言われたという。
新聞社やテレビ局も濁流事件を聞きつけ取材に来るという。すると「補償交渉の大切な時期に外に漏らせばできることもできなくなる」と言われる。
当時の生産形態は毎年400~500万尾の稚魚を孵化させてこの季節は常時百数十万尾、30トン程のやまめを在庫させているのだ。活魚価格で単純計算しても7500万以上になる。
在庫管理実績などの詳しい数字をあげて被害の実態を説明しても聞き入れて貰えない。調査にさえ来てくれない。ならば公平に第3者の判断を仰ぎたいと裁判による決着を申し出た。すると「裁判になると相当長引くことが予想される。決着がつくまで数年かかるだろう。それまで会社は持ちこたえられるだろうか」といわれる。
「とにかく議会対策をしてくれ」といわれるので、一升瓶を下げて近くの各議員宅にお願いのご挨拶をして回った。なぜ議員宅にこのようなことをしなければならないのか。憤まんやるかたなく四面楚歌のままでとうとう提示された2400万と100万円の見舞い金合計2500万円で補償交渉は涙をのんだ。
これから向かう1年間売上がなくなるのだ。会社はどうやって生きていくのか。大きな累積赤字を将来に向けて背負い込むことになった。
養魚場の移転
そうしたある日、県土木課から「上流域での開発に支障があるから養魚場は移転してくれないか」という申し込みがあった。「スキー場開発により養魚場の上流に砂防堰堤をつくらなければならない」というのだ。「養魚場が支障になって事業ができない」という。
「このような立地条件は他にはありません。移転費用はどうなりますか」と聞くと「それは無い」という。「町の事業で造るべきだ」と県は言った。ところが役場に相談に行くと「それはできない」という。すっかり困り果てて再び県に相談に出かけた。
そうして知恵を授かり国の制度事業にのせて補助金を直接受けられる漁業生産組合を設立することにした。こうして国50%、県14.5%、町10.5%、事業主25%負担のもとに1億3千5百万円で別水系への移転事業は進められた。
移転の問題で一番困難なことは、移転場所である。とても養魚場ができる場所とは考えられない土地に1500mにもなる長い導水路を引くことになった。崖地に350ミリの導水管を通すため約六千万ほどの事業費が必要となったがこれは補助事業の対象外という。
そこで養魚場跡地を町が買収することにしてその資金と一部導水路移転補償費を積み上げてもらって別途事業として長い導水路工事を建設した。導水路と制度事業などを合わせると総額2億に達する一大事業である。
こうしてようやく1993年6月18日、竣工式を迎えた。もとより、受益者負担の25%や移転先の土地取得や造成事業など補助対象外事業については、大きな赤字を背負った会社に負担する資金はない。またもや借金を重ね大きな負債を二重に背負い込むことになったのである。
町とのねじれ現象
こうした間にもさまざまな困難に遭遇し、悔し涙を流す日々が幾度となくあった。その涙のしみ跡が残るメモがダイアリーに貼りつけてある。
1992年10月7日、8時30分から相談したいことがあるので役場会議室に来て欲しいと電話があった。どんな相談だろうかと気軽に会議室に出向いたら、町の幹部クラスや議員の皆さんがずらりと勢ぞろいしていた。
相談とは「マスコミの対応について」ということである。当時のメモには町側の発言として以下のようなことを記している。
・熊本のテレビ局が、スキー場からの濁りにより養魚場に被害があったと放送した。知り合いからの知らせでそのビデオを取り寄せて見た。
・放送では、スキー場は秋本が開発したと報道したがスキー場は町がつくった。
・片方ではスキー場を作ったとマスコミにしゃべり、片方ではスキー場に被害を受けたとスキー場を否定することをしゃべっている。
・スキー場の被害のことをしゃべるが町の援助のことは放送されない。なんにも言わない。
・町は、養魚場にはできるだけの取組みを行っている。援助をしてきたつもりだ。
・このことは、今、九州でブナ林の保存運動が起きているがスキー場をターゲットにされかねない。
・この運動に加担しいるのではないか。
・一連の発言はスキー場に悪いイメージを与える。
・こうした放送により国有林が保安林解除などの協力がとれなくなる可能性がある。
・町は国や県からの援助が受けられなくなる。
・秋本と町は一枚岩となってマスコミに対応しなければならない。
等々である。このようにして町長はじめ数人の方から厳しく詰問されたのである。県内のマスコミには、釘を刺されていたので取材には断っていたが県外のテレビ局のためつい気を許してしまったのがことの発端となった。一人で反論を試みるが、何しろ多勢に無勢である。スキー場は「ふるさとづくり特別対策事業」通称「ふる特事業」として町が取り組んだことは周知の事実であり、いまさら何をと思うがどうしょうもない。
また、秋には「地域の光りの創造と発信」と題してシンポジウムの計画を立ちあげていた。養魚場はなんとか移転が決まってほっとしたが、これまでの夢は養魚場を公園化し、周辺にレストランやホテルを配置した理想の園を建設したいとの思いでこれまでの人生を賭けて取り組んだ仕事である。
滋賀県の醒ヶ井養鱒場や静岡の井之頭養鱒場などを目標にそれをやまめで実現したかったのである。それがやまめの里のビジョンであった。
ところが養魚場とレストランは水系を分けて分断されてしまった。もはや一体的な公園化は図れない。やまめの里がやまめの里ではなくなったのだ。人生を賭けたやまめの里構想が頓挫したのである。そこでブナ帯文化圏みたいなカオスがふつふつと湧いてきて人生の仕切り直しがせまられていた。
そのため、当時の長銀総合研究所の理事長でエコノミストとして活躍中の竹内宏氏などを講師にお願いしてこれからの地域づくりを学びたいとシンポジウムを計画していたのである。
町側の詰問は今度はこのシンポジウムに向けられた。再び当時のメモに目を移すと
・シンポジウムでは、スキー場の問題をとりあげるべきではない。スキー場に悪いイメージを与えることになる。
・九州ブナ文化圏構想などと言っているがこれは山村の現実をとらえていない。
・ブナは金にならないので経済林として人工林にしたのだ。国の方針に反することになる。
・そのようなことは、これから町の事業に対して国や県からの援助協力が受けられないことになる。
・シンポジウムでは、原生林伐採のことをしゃべるべきではない。それは町の利益にならない。
等々である。日本のブナ帯には日本特有の生活文化が存在し、これが地域づくりの基本となり得ることも、何もわかっていない行政がとても悔しかった。
湧き水地帯を埋めたのは工事中に山が崩れてきたため埋まったのだという。ホタルがいなくなったのも農薬のせいであるという。もっともらしい言い訳がまかり通る。あれだけの被害を住民に与えておいて誰にも責任がないとする。このような町はもう信頼できない。行政は一体誰の為にあるのだろうか。
終り
------------------------------
発表できなくてお蔵入りになった原稿ですが、今、読み返してみて「おまえもようやったなあ」と自分自身を感心しているところです。
以来、これはバチが当ったのだと思うようになりました。最初にスキー場の予定地をヘリコプターで探して見つけた時は随分悩んだものです。これを開発したら養魚場が危ないと。
しかし、養魚場だけがよくてもそれは自分の人生ではないだろう。過疎化して人も住めないような疲弊した村になるより、皆と元気に住める村にすることにロマンを感じたのです。「スキー場ができると生産は何割か落ちる。だが付加価値は高まる。」これが結論でした。
そのために、企画書もスキー場計画ではなくて環境を前面に出した森林公園計画とし、冬はスキーができるというリポートにまとめたものでした。そして行政が動くまでの気の遠くなるような年月の苦闘が続く。
ところが行政は制度事業に採択された時から一部の関係者以外事業内容が見えなくなる。ビジョンもなくなるということに気が付かなかったのです。今、残っているのは森林公園事業という歳出の項目名だけです。そして事業は施設業者と職員の贈収賄疑惑にまで発展した。
結果としては、ブナの原生林に手をつけたことが原因であることには間違いないという事実です。その責任は筆者にあります。このためにバチがあたった。そう思う以外収まるところがありません。
もう1つ古い原稿があります。西日本新聞社の依頼を受けて24回連載したもので、ご覧になった方も多いと思いますがその内の17回から21回まではスキー場開発の初期の頃を記録したものです。読み返してみると感慨深いものがあります。その部分を再度掲載します。
-------------------------------
九州ブナ帯文化圏
17.最適の環境をもたらす
ブナの森に軽快な音楽が流れ、樹氷をぬって滑るスキーヤーの歓声がこだまする。過疎の町、五ケ瀬町が開業した五ケ瀬ハイランドスキー場は雄大なロケーションとすばらしい雪質に恵まれ、連日多くのスキーヤーでにぎわった。
今シーズンは四月十一日まで営業、八万人の入場者があった。二十八日からは装いを新たに夏スキーが始まる。夏スキーはゲレンデにスノーマットを敷いて冬と同じようにスキー板で滑る。
スキーは楽しい。白銀の斜面をダイナミックに滑降する快感や、恐怖とたたかいながら急斜面を征服できた満足感、思う存分大地に転ぶ愉快さは人間に潜んでいる本能を呼びさますのかもしれない。雪面をギュッギュッと踏んでターンし、振り子のように身をゆだねながら滑り降りるのはスキーならではのだいご味だ。
スキーは健康によい、風邪で少しくらい発熱していてもスキーに出掛けると治ってしまう。雪山の純度の高い空気を胸いっぱいに吸い込みながら楽しく全身運動をするからだろう。だが、あまり無理をしてはならない。疲れは重大事故につながる。
日本のスキーヤーは一回でも多く滑ろうとガツガツした滑りをする人が多い。一日六十回以上も滑る人がいると聞いた。欧米のスキーヤーは適度に滑ってアフタスキーを存分に楽しむ。自然の中でデッキチェアに寝そべり、日なたぼっこをしてボケーッとした時間を過ごす。仲間とのふれあいもアフタスキーの魅力である。
日本には約七百カ所ものスキー場があり千二百万人もの人々がスキーを楽しんでいるという。スキーはブナ林の活用によるものだ。温度、湿潤、多雪がブナ林を育てた。ブナ林はスキー場に最適の環境をもたらしているのである。
スキー場開設により過疎の五ケ瀬にも変化がみられるようになった。これまで冬になると雪にとざされ仕事もなかった寒村が、正月休みも返上して、朝まだ暗いうちからスキー場のリフトにレストランにショップに出かけていく。
出稼ぎの人も帰り、都会に就職していた青年たちも故郷に帰るケースが目立つようになった。旅館や民宿、レンタルスキーなど地元の人々の事業参加も始まった。村の婦人会の皆さんが生き生きとあかぬけて見える。
スキーもまだ三シーズンを迎えたばかりで問題も多く、越えなければならないハードルも高いけれど、きっと克服できるだろう。
18.初め二の足踏んだ行政・最南のスキー場(1)
過疎の九州山地で大きい反響を巻き起こしたスキー場だが、これには十数年に及ぶ年月と関係者の血のにじむような努力があった。
波帰地区では昭和四十六年、地域の活性化を図ろうと『えのは振興会』を結成した。波帰川に区画漁業権を設定し、ヤマメの有料釣り場を開設したのである。
昭和五十年にはやまめの里構想のもとにカヤぶき屋根の炉辺を囲むレストランがオープンした。五十四年には宮崎国体の山岳競技が開催され、これを機に、ヤマメ釣りをベースにした民宿が五軒できた。
婦人会による山菜の加工場もできた。ほとんど都会から人の入り込みのなかった寒村に少しずつ観光客らしいものが芽生えてきた。その取り組みの中からスキー場の発想は生まれた。
他地域にできないものを探そうとして浮かんだのが雪であった。雪が多いのは子供の時から体験的に知っていた。雪が多ければどこかにスキー場ができるような場所があるに違いない。
スキー場の情報収集の傍ら町役場に陳情を始めた。『どこかにスキー場ができる場所があると思うから調査してみたください』。五十二年ごろのことである。ところが答えはいつも『何とも知れないものに大事な町費を使うわけにはいかない』。それでも辛抱強くお願いを続けた。
五十四年の暮れか五十五年の正月だったと思う。当時の町長から『そこまで言うのなら地元でもっと調査してみたらどうか、可能性があれば町も取り組んでもよい』というような返事をもらった。
『なるほど、自信のないことを陳情してはいかんのだな』と思ったが、ではどのようして広大な山地を調査していいかわからない。
途方にくれていた時、ヘリコプターが低空飛行を繰り返しているのが見えた。直観的に『そうだ、山を空から見てみよう』と思った。
当時は拡大造林政策がピークを迎え、標高千メートル以上の高地まで植林事業が進められていた。苗木を背負い、歩いて一時間半とか二時間かかって運ぶところもある。そこでヘリコプターで苗木を運ぶ方法がとられた。
毎年雪解けのころになるとヘリコプターで苗木を運んでいたのである。最初に飛んだのが五十五年三月三日であった。カメラをしっかりと握りしめ、ヘリコプターに乗った。深い山ひだが連なる九州の尾根、脊粱(せきりょう)の山並みを追って飛んだ。北斜面に雪がびっしり残っていて、スキーができそうな場所を二箇所確認した。その一つが向坂山だった。
19.南国イメージ壊さぬか?・最南のスキー場(2)
標高一、六八四メートルの向坂山山頂付近は、深いブナの原生林だ。波帰から歩いて三時間半、スズタケをかきわけながら上空から確認した地点を目指す。
目標へ近付くにつれて次第に根雪が姿を現し始めた。三月上旬というのに六十~八十センチの根雪が横たわっている。これならスキーができる。もっと詳しく地形を調べよう。二万五千分の一の地図で等高線を読みながらさらに山歩きを続ける。
春の息吹が感じられるようになると最初にマンサクが黄色いリボンの花を付けた。バイケイソウが落ち葉を持ち上げながら、みずみずしい芽を伸ばしてくる。イチイやナナカマド、ナツツバキやヒメシャラなど北国の木がブナの森に混生している。神秘的な森のたたずまいであった。
これは素晴らしい。スキー場だけでは、もったいない。森林公園にすべきだ。そう思いながら調査を続けた。
昭和五十五年五月、リポートを書いて町長に提出した。町長は『これは素晴らしい、あの辺には雪が深いとは知っていたが、これほどとは思わなかった』と言われ『やってみようじゃないか』ということになった。
かくてスキー場は五ケ瀬町の計画となったのである。だが、実は、ここからが大変だった。町にも議会にもスキー場の専門的知識を持つ人はいない。まして行政で取り組んだ事例を知らない。先例のない事業はとても難しい。
最初にスキー場の情報をもたらしたのは当時の営林署長である。スキー場予定地は国有林にある。営林署にも足繁く通ってお願いしていた。署長はスキー場に大変関心を持たれた。
まず現地を見ようということになりスキー板を持ってみえた。目指す予定地までは雪が深くて登れなかったが途中でテスト滑走された。『これはいいねえ、雪質も長野辺りの雪に似ている』五ケ瀬ハイランドスキー場で最初に滑った人とは営林署長であった。
五十五年十一月、営林署長の案内でスキー場視察に出発した。町長、財政課長、経済課長、そしてレンタカーの運転手として私、総勢五人のメンバーだ。四泊五日で群馬県や新潟県の主要スキー場を回った。特に前橋営林局では国有林を活用したスキー場の研修がよかった。
署長は上京の折り、林野庁でスキー場の計画を話した。すると『南国宮崎でスキー?』ということになったらしい。『特に中央から見た場合、宮崎は南国イメージが強い』という。そこで『きちんとしたデータがないと役所は動かない』とアドバイスを受けた。
20.熊本の計画にあわてる・最南のスキー場(3)
昭和五十五年十二月二十一日、気象観測機材を背負って運び、向坂山に百葉箱と風向風速計を設置した。初めて町が百五十万円の調査費を計上したのである。以後六十年まで、気の長い年月をかけた気象観測が始まる。
五十六年春、再び植林地の苗木運搬にヘリコプターが来た。三月十日、五ケ瀬町長もヘリコプターに乗り上空からスキー場予定地を視察した。この年も向坂山には雪が、びっしり残っていた。
町長は積極的に営林局や宮崎県へスキー場建設の陳情を始めた。町長から声が掛かる度に雪山の写真や積雪データーを持参する。議会や担当課も四国や本州のスキー場視察に出かけた。関係機関からの現地視察も相次ぐ。
やがて、県地域振興課でスキー場の調査費が計上されたというニユースが飛び込んだ。いよいよスキー場の夢が実現する。期待に胸を踊らせた。
五十七年、委託を受けたコンサルタント会社がスキー場の調査に来た。やがて報告書が提出された。建設費は二十数億円。町の年間予算に等しい数字である。だれもスキー場を口にしなくなった。
精力的に陳情を続け、奮闘していた町長が突然、病魔に倒れた。スキー場は、もうだめだよと、だれもが言う。五十九年八月十七日地、新町長が誕生した。新体制もスキー場は県が事業主体とならなければ町財政では無理との見解。
県は町が主体性を持って進めなければ支援できないと言い、事態は前進しない。そんな時『熊本県にスキー場建設』のニュースが駆け抜けた。
当時の熊本県の細川知事がスキー場の計画を発表したのである。場所は五ケ瀬町で計画を進めている向坂山だ。ここは熊本県境で、両県にまたがった地形にある。
「困った」。関係者は頭を抱え込んで町長室に集まった。その時、隣接する清和村の村長があいさつに見えた。「突然ですが、知事がスキー場を建設するというので、ごあいさつに来ました。そちらの町が先に計画を進められていたのですが、よろしくご協力を」ということである。
これが発端となり計画が再燃する。町長はスキー場建設に腹をくくり、町民の理解を得るために地区ごとに座談会を開いた。議会では長い年月をかけたスキー場の案件が、ようやく全会一致で決定、改めて県へ陳情に向かった。
熊本県と宮崎県ではトップレベルで話し合われ方針が決まった。こうして昭和六十年、一気にスキー場建設に向けて行政が動き出した。
21.しり上がりの支援体制・最南端のスキー場(4)
気象観測は困難をきわめた。標高八百㍍の波帰から標高千六百㍍の観測点まで高低差八百㍍を毎週一回登る。片道三時間半の行程だ。
大雪になると観測点までたどりつけず途中から引き返し、また翌日挑戦する。そこでスノーモービルを買い入れた。スノーモービルで登山道を登り、尾根伝いにたどれば観測点に着くかもしれないと考えた。ところが新雪は軟らかくて登れない。
東北地方のスキー場を回った時、青森でカンジキを買った。これはよかった。日当たりのよい斜面は雪が固まっている。この斜面をたどれば深い雪でも平気で歩けた。
恐い思いもした。北向きの斜面でかん木を埋めつくした軟らかい雪にはまった。もがけばもがくほど落ちていく。雪面へ上がることができない。助けてくれる人はいない。「気を付けてくださいよ、あなとほどの雪山装備を持った人は消防団にも警察にもいないから。」と役場の担当者は言った。
宮崎県スキー連盟が「五ケ瀬にスキー場を成功させよう」のキャンペーンを始めた。大淀川河畔で行われる"まつり宮崎"に発泡スチロールの粒をまき、スノーモービルやスキー用品、スキーウェアを着けたマネキンを設置し、雪山の写真やビデオを紹介した。
地元の青年たちも高山植物の盗採盗堀防止に森林パトロールを続けた。テレビ局と雪上プロレスなどの番組を仕組んだり、発泡スチロールの雪だるまに雪を詰めて宅配したりして雪山キャンペーンを続けた。
名称も「森林公園協力会」から「雪の五ケ瀬むらおこしグループ」へ、そして「むらおこしカンパニー」へと発展した。
昭和六十年からの行政の取り組みには、めざましいものがあった。スキー場開発基本計画の策定、道路の開設、保安林解除、国定公園の利用許可、運輸局の索道事業の申請、送電の協議など矢継ぎ早に進めていった。
県も観光振興課、地域振興課、地方課、環境保全課、造林課、林業振興課、林政課など、関係課による支援体制を敷いた。
スキー事業は自治省のふるさとづくり特別対策事業に採択され、平成二年十二月二十一日、オープンのテープは切って落とされた。
長年の夢が実現し、むらおこしの大きな起爆剤となった。リスクを背負って決断した町長や町議会には言葉に表せないものがあったに違いない。
--------------------------------
こうして、以前書いた原稿を読み直してみると懐かしくもあり、ほろにがいものがあります。
そうして更に、行政不審の極に達したのが森林教育の森整備事業でした。
好調のスキー事業に気をよくした行政は、更にスポーツ合宿施設を30億を投じて計画するというのです。問題は宿泊施設にありました。スキー客を当て込んで民宿や旅館が次々と建設されたり増改築が行われ、町の新しい産業としてスタートしたばかりです。
観光地でもない町で、産声を上げたばかりの軌道にも乗っていない民間施設群は、町営の大型宿泊施設ができれば潰されるのではないかという不安がありました。
もとより競争は必要で、競争が発展の原動力となるのですが、公金で建設した大型施設と民間の借金で建設した施設は競争とは言えないわけです。
そこで、スポーツ合宿施設の宿泊部門は民間施設に任せて欲しいとお願いし、何度も宿泊業組合や地元地域住民と行政の対話集会が開かれました。
今、公民館の書記簿の記録、或いは旅館組合の書記の議事録等で対話集会の模様を開いてみれば、当初行政の説明は要約すれば下記のようなものでした。
1.スポーツ合宿のための森林教育の森整備事業は、夏のシーズンのための事業である。
2.スキー場は夏場が仕事が無い。このため冬はスキー場、夏はスポーツ合宿施設で働けるようにする。
3.したがってスポーツ合宿施設は、スキー客を受け入れる施設ではない。
むしろスポーツ合宿施設により民間の宿泊客が大幅に増えることが見込まれる。
こうして、行政は住民をごり押しで説得されたのです。今、当時の行政関係者に聞くと「当時は皆んなそのように思い込んでいた」といわれます。
ところが現実的には、この宿泊施設は赤字部門のためスキーと温泉をセットにしてスキー客を積極的に誘致はじめました。スポーツ合宿以外の民間で開発したグリーンシーズンの誘客まで行わなければ成立しなくなったのです。民間はいよいよピンチを迎えました。
住民がだまされたと思うのは理解されるでしょうか。仕方ないことでしょうか。何か変です。この他にも、似たようなケースはもっとありますがこういうことを書くと疲れます。
それでも敢えて書かなければと思ったのは、これまでの行政不審、議会不審、行政との捻れ現象等を払拭したいからです。また、行政の考え方は、人が変れば考え方も変わるという現実を確認したかったからです。
町よ変ってくれ。新しい町の誕生を夢見て。
あとがき
今号は、「新しい町の誕生を願って」の特集号にしました。個人的な文章が多くてごめんなさい。皆さんのご意見をお待ちしています。
溝口さんのリポート―「大地の気は断層上の特異点にあり、このような場所はゼロ磁場であることが多く、マイナスイオンが流れ込み疲れやストレスを取り除き免疫力を高める。」というのは面白い。九州脊梁山地は、臼杵八代構造線と南側の仏像構造線上にあります。幻の滝はどうでしょうか。「中央構造線の謎を探る会」代表の後藤琢磨氏を紹介してもらいました。何か新しい発見がありましたらお知らせします。
このかわら版は、14区の皆さんに配布していますが、どなたにでもお届けできます。ご希望の方は郵送料として年会費千円を添えてお申し込みください。(治)